~「全世代型社会保障」のあるべき姿
井手英策(慶応義塾大学経済学部教授)
Imidasオピニオン2023/06/14
自己責任が前提の「勤労国家」
政治の世界で「全世代型社会保障」という言葉を耳にするようになった。政府の説明によれば、人生100年時代の到来を見すえ、高齢者だけでなく、子ども、子育て世代、さらには現役世代全体を射程に収めた、持続可能な制度改革をめざす、とされる。
なぜこうした裾野の広い改革が必要なのか。まずはその背景を探ることから始めよう。
私は日本の福祉国家を「勤労国家(Industrious State)」と定義してきた。勤労国家の前提にあるのは、勤勉に働き、倹約、貯蓄を行うことで将来不安に備えるという「自己責任」である。子育てや教育、病気や老後の備えに関して、日本における政府の保障は十分でなく、とりわけ現役世代への給付は、先進国最低の水準に甘んじてきた。
想像してほしい。大学の授業料、医療費、介護費のいずれも自己負担が求められる。これらのサービスが無償化ないし低負担化されている他の先進国との差は明白だ。また、義務教育でさえ、修学旅行費、給食費、学用品費といった負担が重くのしかかり、貧困層には生活保護、低所得層には就学援助をつうじて財政支援が行われている。
この勤労国家が、近年、〈逆機能〉し始めている。逆機能とはどういうことか。それは、自己責任で生きていくための前提条件である経済成長、所得の増大が困難になり、自己責任の美徳が社会に深刻な分断を生みだしている、ということだ。
平成元年(1989年)と平成31年(2019年)を比較しつつ、日本の経済データを追跡してみよう。
一人あたりGDPは世界4位から26位へと順位を落とした。企業時価総額トップ50社のうち32社を日本企業が占めていたが、平成の終わりにはわずか1社になった。勤労者世帯の実収入は平成9年(1997年)がピークであり、平成31年には世帯収入300万円未満の世帯が全体の約33%、400万円未満が約45%を占めた。この比率は平成元年とほぼ同じである。また、あるデータでは、2人以上世帯の3割、単身世帯の5割が「貯蓄なし」と回答している。
自己責任が前提の勤労国家では、経済的に自立できない人たちは〈道徳的失敗者〉とみなされる。
アジア通貨危機が直撃した1997年から98年にかけ、失業者が約50万人増加した。自己責任という社会的責務を果たせなくなった人たちの一部は、失業給付を利用するでも、生活保護を利用するでもなく、命を絶つという決断をした。1年で自殺者の数は8000人以上増え、14年にわたって3万人を越えた。中心は住宅ローンや家族の暮らしを背負わされた40〜60代の男性労働者だった。
所得が少なく生活保護を利用できる人たちのうち、スウェーデンでは8割、フランスでは9割が制度を利用するが、日本では2割程度しか利用しない。他者に頼るのを恥ずべきことと考え、生活が困窮しても社会的責務から逃れられない人びと。通俗道徳の根深さがハッキリと浮かびあがる。
「弱者」への関心が低い〈分断社会〉の誕生
平成をつうじて晩婚化と少子化が進んだことは周知の通りである。くわえて、外食や旅行、衣類や履物の購入が控えられ、持ち家率も大きく低下した。私たちは貧しくなった。ところが、生活を切り詰め、自己責任をまっとうしようと努力する労働者たちは、自分たちが依然として中間層に踏みとどまっていると感じている。
内閣府の「国民生活に関する世論調査(令和元年6月調査)」によると、自らの生活水準を下流とみなす人は4%しかおらず、93%が中流と考えている。さらに、「国際社会調査プログラム(2019年)」では、「中の下」と考える日本の回答者の割合は、28の調査国の中で1位である。
貧しくなっても、生活を切り詰め、歯を食いしばって働き続けなければならない社会。その裏返しとして、弱い立場に置かれた人たち=「弱者」への関心が薄れつつある。
「国際社会調査プログラム(2016年)」のなかに、政府の責任を問う質問がある。以下の施策を政府の責任とみなさなかった日本の回答者割合を見てみると、
・「病人が病院に行けるようにすること」35カ国中1位
・「高齢者の生活を支援すること」35カ国中1位
・「失業者の暮らしを維持すること」34カ国中2位
・「所得格差を是正すること」35カ国中6位
・「貧困世帯の大学生への支援」35カ国中1位
・「家を持てない人にそれなりの家を与えること」35カ国中1位
である。他国と比べ、日本の「弱者」への関心の低さは際立っている。
寛容さをなくした社会は財政の再分配機能も弱い。OECDの調査(2008年)によると、低所得層への給付による格差是正効果、富裕層への課税による格差是正効果は、調査対象21カ国のなかでそれぞれ19位、最下位である。かつては北欧とならんで平等主義国家と呼ばれた日本だが、OECDデータ(2018年)によると、相対的貧困率は調査対象国のなかで9番目に高く、所得格差の大きさを示すジニ係数の大きさも11位という状況だ。
勤労国家では、経済が衰退し、所得水準が低下すれば、多数者が自らの生活防衛を優先するほかない。「弱者」の苦しみを他人事とみなす〈分断社会〉の誕生である。現役世代は自己責任、就労を終えた高齢者と貧困層の生活に限定して保障するという勤労国家は逆機能し、自己責任の痛みが社会の分断を加速させている。
分断と対立を生む「全世代型社会保障」構想
最初の問いに戻ろう。現役世代の受益の乏しさ。深まる生活苦。これらの事実を念頭におけば、保障の範囲を現役世代や子どもにまで拡充し、自己責任の領域を縮小する全世代型社会保障が構想されたのは、もっともなことだといえよう。
だが、現段階の政府の構想によって、人びとの将来不安が払拭され、社会的な分断が緩和するか、と問われれば、答えはNOである。
まず、全世代型社会保障では、1)子ども・子育て支援、2)働きかたに中立的な社会保障、3)医療・介護の制度改革という3本の大きな柱が立てられている。政策のリストは広範にわたる。だが、令和5年度(2023年度)の改正で、現実に具体的な制度改革に結びついたのは、出産育児一時金の増額やかかりつけ医の法制化支援など、ごく一部だ。
むしろ議論の焦点は、現役世代の受益を大胆に拡大することよりも、高齢者の負担を増大させ、現役世代の不満を和らげることにあった。事実、介護サービスの利用時負担の引きあげ、国民年金の保険料納付期間の延長、75歳以上の後期高齢者医療の保険料の引きあげ等、財源問題は陰に陽に議論の俎上に載せられた。
統一地方選挙前という事情もあって、実現したのは、後期高齢者医療の保険料引きあげだけだった。乏しい財源を高齢者に求め、出産を控えた世帯に現金を配る、現役世代の保険料負担を軽減するというこぢんまりとした政策パッケージが選択された。
この現実を見て、全世代型社会保障といわれても、誇張の感をぬぐえないのは私だけではないだろう。政府は、出産育児一時金が42万円から50万円に大幅に増えた、というが、子どもにかかる膨大な教育費の前では焼け石に水である。かかりつけ医の法制化も欧米で実施されている本格的な制度には程遠い。
さらにいえば、負担者=高齢者、受益者=子育て世代という線引きは世代間の分断を生む。同世代の間でも、出産する世帯とそうでない世帯との間に対立の芽が生まれる。社会的分断の緩和という視点からすれば、むしろ反対のベクトルを持つ制度設計なのである。
ベーシックサービスで人間の尊厳を平等に
社会の分断状況を打破するカギは、限られた財源のなかで世代間のバランスをとるのではなく、すべての人たちの生活を保障し、世代間の対立、そして所得階層間の対立を無効化することである。
私はこうした視点に立って、税を財源として、すべての人びとに、教育、医療、介護、子育て、障がい者福祉等の「ベーシックサービス」を提供することを提案してきた(『どうせ社会は変えられないなんてだれが言った?』小学館、『幸福の増税論』岩波書店)。
ベーシックサービスとは、誰もが必要とする/必要としうる基礎的なサービスである。ILOが「GDPの2〜3割を要する」と警告を発したベーシックインカムとは異なり、ベーシックサービスは必要な人しか使わないため、財源を大幅に節約できる。私たちは、現実主義に立脚し、病を抱えても、失業しても、長生きしても、子どもをもうけても、貧乏な家庭に生まれても、誰もが人間らしく生活できる社会をめざすのである。
もちろん、無年金の高齢者、シングルマザー、障がい者など、就労が困難な人たちは現金を必要とする。それゆえ、私は、ベーシックサービスとあわせて、「品位ある最低保障(Decent Minimum)」を提案する。
すでに指摘したように、日本社会では、「弱者」に対する配慮が成立しにくく、「弱者」もまた、施しをきらう。そこで、政治戦術として二つのステップが必要となる。
まず、ベーシックサービスの無償化で中間層の将来不安を解消し、低所得層への財政支援に対する嫌悪感を緩和する。自分たちの生活が守られるのであれば、生活扶助、失業給付の拡充、住宅手当の創設等、どうしても働けず、財政支援に頼らざるをえない人たちへの生存保障(=品位ある最低保障)は許容されやすくなる。
もう一点、ベーシックサービスをすべての人たちに保障していくことで、「助けられる領域」を大胆に縮小させる。医療や介護、教育が無償化されれば、生活保護の医療扶助、介護扶助、教育扶助、さらには修学援助も大幅に削減されることとなる。
確認しておきたいことがある。勤労国家のもとでは、中間層であっても、運が悪ければ将来不安に直撃される。共稼ぎで年収1000万円の世帯であっても、一方が病に倒れ、職を失えば、将来不安はたちまち現実になる。
品位ある最低保障は低所得層への施しではない。あらゆる人びとが直面しうるリスクに対する最低保障、すべての人たちのセーフティネットだ。すべての人びとの生存・生活保障が徹底されれば、中間層の低所得層に対する疑念、嫉妬、低所得層の後ろめたさも解消される。所得だけでなく人間の尊厳を平等にできる。全世代型社会保障は、パッチワークではなく、真に包括的な制度改革として構想されねばならない。
6%の消費税増税でかなう、自己と他者の幸福が調和する社会
大胆な改革には財源が必要であるが、ここでも分断社会の解消がめざされる。
私は消費税を財源の中心に据え、これに所得税の累進性強化、減税の続いた法人税率の回復、金融資産や相続財産への課税強化、逆進性の強すぎる社会保険料の改正等をセットで議論すべきだと考えている。
なぜ、逆進性のある消費税が財源の中心なのか。それは、低所得層も含めすべての人たちが納税者となることで、給付を「施し」から「権利」に変えたいからである。納税という責務を果たせば、社会の一員としての自尊心が育まれる。同時に、納税者としてサービスを利用するのは当然だ、という社会規範も生まれる。
たしかに消費税を柱とすることへの批判は強い。だが、税の累進度の強いアメリカは所得格差が大きく、累進度の弱いスウェーデンは所得格差が小さい事実をどう考えるか。逆進的であっても、貧しい人も負担するがゆえに豊富な税収をうむ消費税を利用し、手厚い給付を行えば、所得格差は小さくできる。
医療、介護、大学教育、障がい者福祉を無償化する。また、義務教育で必要となる給食費、学用品費等も無償化し、さらには保育士や介護士等の給与も引きあげていく。これに品位ある最低保障である、生活扶助・失業給付の3割拡充、住宅手当の創設がくわわる。
以上の財源として、消費税なら6%の増税、つまり16%への引きあげが必要となる。大増税に聞こえるが、じつは主要先進国の平均程度の税負担でしかない。そして、住宅手当を全体の2割に相当する低所得層に月額2万円給付するから、6%の増税でも、低所得層は年間で約15万円も得をする計算になる。それだけではない。社会的分断は緩和され、すべての人びとの生活が楽になり、施しは権利に変わる。
哲学者イマヌエル・カントは、『道徳形而上学原論』のなかで、人間が互いを同等な存在とみなし、人間自身を手段ではなく、目的として扱うことで尊厳が守られる、と論じた。
所得や年齢で人間の扱いを変えるのではなく、〈あらゆる人間にとってのニーズ〉を基準に人間の扱いを変えないからこそ、社会的分断は緩和される。全世代型社会保障はゴールではない。人間の尊厳を重んじ、自己と他者の幸福が調和する社会への変革こそがゴールだ。社会保障改革はその手段に過ぎない。
園のようす。





咲いた咲いた チャイブ
チャイブ

 メドウアネモネ
メドウアネモネ

 バラ
バラ
色づき始めたハスカップ



























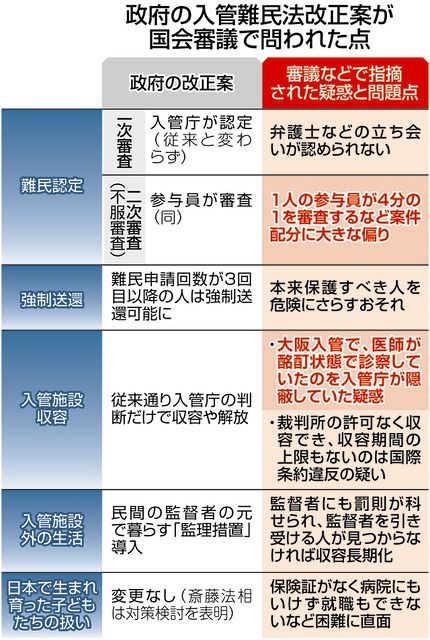
















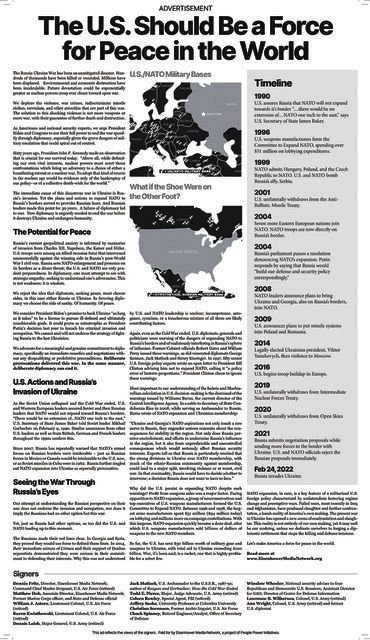








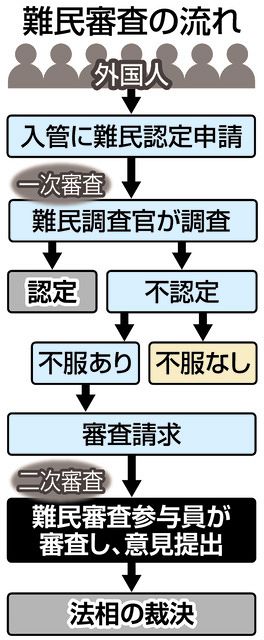


 アマドコロ
アマドコロ