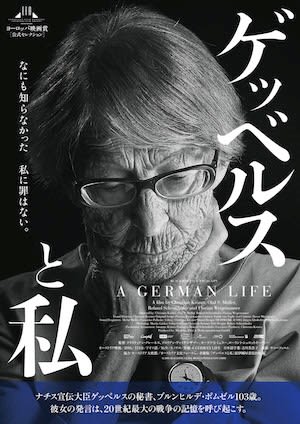今日3本目の記事です。長いですがぜひ読んでほしい記事です。
***
女児虐待死事件から感じた危険な空気
情報・知識&オピニオンimidas連載コラム > 仁藤夢乃の“ここがおかしい”第26回
2018/06/27 仁藤夢乃 (社会活動家)
(1)子どもたちが助けを求められなくなる
児童相談所と警察の情報共有に懸念
2018年3月に東京・目黒で起きた女児虐待死事件。児童相談所が関与していたにも関わらず、5歳の少女の命を守れなかったこの事件を受けて、児童相談所の虐待情報を警察と全件共有することを求める声が大きくなった。しかし、私はそのことに危機感を抱く。例えばハイティーンの子どもたち――特に虐待や困窮から生き延びるために万引きや性売買、犯罪に関わった少年少女は、警察による取り締まりやけん責を恐れて、ますます助けを求められなくなるからだ。
朝日新聞の報道では「厚生労働省によると、虐待が疑われるとして全国の児相(筆者注 : 児童相談所)が2016年度に対応したのは12万2575件に上る。一方、08~15年度の8年間で心中以外の虐待で亡くなった子は408人。うち約4人に1人は、児相が関わったことがある子どもだった。どの段階で警察へ連絡するかなどの基準は、自治体によってまちまちだ。子どもの支援に関わる自治体職員は『子どもを長い期間見守るためには、親との信頼関係を築くのが一番大切。警察と訪問した途端、態度を硬くする親も多い』と話す」とある(朝日新聞デジタル、18年6月16日)。
都内のある児童相談所では、親が子どもに会わせることを拒否したため警察に援助要請して住居へ立ち入り、未就学の女児を保護した事例がある。茨城県や愛知県では、今年(18年)から児童相談所が把握した全ての虐待情報を警察と共有している。埼玉県や岐阜県でも、児童相談所と警察間で「情報の全件共有」を行う方針が発表された。
3日間で8万人以上の署名を集めた「もう、一人も虐待で死なせたくない。総力をあげた児童虐待対策を求めます!」という署名サイト(https://www.change.org)のキャンペーンで掲げられた「児童虐待八策」にも「児相の虐待情報を警察と全件共有をすること」が挙げられている。
児童虐待については、これまで市民の関心が高まらず、重点政策にならなかった。現場の支援者の多くも、危機的状況にある目の前の子どもたちに関わるのに精一杯で、政策提言には力を入れる余裕なく過ごしてきた。私もその一人だと思う。児童福祉に関わり、現場で悲惨な現実と向き合い続けている人たちが、政治家や市民の意識を喚起するような動きを十分に作れずにきた結果、体制も制度も変わらないまま弱い立場の人にしわ寄せがいってしまっているのも事実だ。
そんな中、目黒の女児虐待死事件から始まったこの署名サイトのキャンペーンは、影響力のある人々が声を上げ、タレントなど著名人も賛同して注目を浴びている。いち早く立ち上げたことでインパクトもあったろうし、待ったなしの現実がある中で、世間の関心が高まっていることはうれしく思う。「支援に詳しくない自分にもできる」「今すぐにできること」と考えて、賛同した人も多いのではないだろうか。
キャンペーンに賛同する人にはさまざまな立場や考え方の人がいて、多くが虐待対応の現場を知らない人たちだろう。そうした人たちがまとまり、声を上げ始めたことは確かに喜ばしい。しかし一方で、影響力のある人々が問題の背景などをよく理解しないまま声を上げていることや、署名に賛同する一人ひとりがどこまで問題を理解しようとしているのか、という点に不安も感じている。例えば冒頭に書いたようなことだ。
今回は現場からの声を聞いてほしくて、その問題について書くことにした。
警察組織は子どもに寄り添えるか?
私は日々、虐待などによって家にいられない、もしくは家にいたくなくて街やSNSをさまよううちに犯罪に巻き込まれたり、日銭を得るため性売買や万引き、振り込め詐欺の受け子などに関わったりした少女たちと出会っている。非行や家出に走る子どもたちは指導や矯正の前に、家庭などの背景へと介入し、福祉、医療、教育的なケアにつなげるべきだ。が、そうした子を理解できる大人は少なく、当事者たちは学校でも排除され、児童養護施設や自立援助ホームなどの児童福祉施設などでも「問題行動がある」として受け入れてくれれないことが多い。福祉の現場でさえそんな状況なのだから、警察がケアの視点を持って保護に関わってくれたことはほとんどない。
警察では、非行に関わった子は取り調べの対象となり、犯罪者扱いされる。少年院に入院する子の多くも家族関係に悩みを抱えているように(家に戻せない、しかし他に受け入れ先がないことから、少年院しか行き場がないという子もいる)、そういう子たちは大人から裏切られたり、「非行」されたりした経験がある子がほとんどだ。しかし、警察に児童相談所の情報が流れるなら、そういう子は家に居場所がなくても、ますます児童相談所には頼れなくなるだろう。
保護のニーズが高まる夜間や土日祝日、年末年始に駆け込める公的機関は警察だけなので、「長期休暇の時や土日、夜間には『危険を感じたら警察に駆け込むんだよ』と子どもに言うしかない」といった学校教員などの声も聞く。実際には明らかな虐待があり、本人も保護を求めていて、学校から児童相談所に何度も虐待通告しても保護してもらえない中高生のケースはよくあるのだ。しかし警察は福祉施設ではなく、不適切な対応をされることが多い。
例えば、父親に殴られて交番に駆け込んだ中高生に、警察官が「お巡りさんがお父さんに言ってあげるから」と言って親を呼んで叱り、親子とも家に帰すようなケースに私は何件も関わっている。そのことで虐待が更に悪化し、子どもはそれ以来、他人に相談ができなくなり警察も恐れるようになった。
虐待を背景に家出や性売買に関わった少女が警察に駆け込み、「家に帰りたくない」「親にも迎えに来てほしくない」ということで私たちが呼ばれて行ったら、「ふらふらしているのが好きな子なんでしょう」「これだけ売春を繰り返しているんだからまずは鑑別所。親にも連絡したけど無関心だったので、その後は少年院しかないでしょうね」なんて軽々しく言われたこともある。彼女は虐待の影響から精神障害も抱え、躁状態になって「親に振り向いてほしい」という気持ちで、この日、衝動的に警察に駆け込んだ。迎えに来てくれると思った親は来てくれず、深夜だったこともあって補導され、取り調べられるうちに性売買に関わっていることが発覚したのだ。
彼女に弁護士を付けたいと言うと警察はなぜかそれを渋った。他にも18歳未満ではなかったが、性虐待から逃れるため地方から逃げてきた女の子と一緒に警察へ行ったら、事件が起きた場所はここじゃないので、今から新幹線で地元へ帰り、家の近くの警察に相談しなさいと言われたこともある。彼女は地元で頼れる人がいなくて東京の支援団体を頼って逃げて来たのに、警察は「シェルターなら地元にもあるでしょう」などと執拗(しつよう)に諭し、レイプキットによる検査もせず帰そうとした。
公的機関で唯一、街やSNS上で積極的に家出や性売買に関わる子どもを発見し、つながる活動をしているのも警察だが、それは「補導」という形になる。補導された子は生活態度を注意され、親や学校に連絡され、家に連れ戻され、家庭裁判所によって少年鑑別所や少年院に送られることもある。だから私自身も家を飛び出て繁華街をさまよった中高生時代、「警察は見かけたら逃げるものだ」と思っていた。
全ての子どもに弁護士を付けたい
私は女子高校生サポートセンターColabo(コラボ)の活動を行う中で、子どもの気持ちに寄り添おうとする警察関係者とも出会っているが、中には「個人的には『それでいいのか?』と思っていても、警察官として動く以上、警察組織の役割の中で対応をせざるを得ず心苦しいこともある」と話す人もいた。
また虐待を受けている中高生の中には、家族が犯罪に関わっていることを知っている子もいる。児童相談所に相談して警察から家族に手が伸びてしまうことを嫌う子は、助けを求めることができなくなる。「情報の全件共有」は幼い子にとっては救いになることもあるかもしれないが、思春期以降の子たちにとっては脅威にもなる。虐待を背景に万引きや性売買に関わる、ハイティーンの子どもたちをどう守るかを考えていきたい。
子どもが児童相談所に保護を求めた際、家を出てギリギリの生活を続ける中で盗みや性売買に関わったことが分かった途端、その子を警察に任せてしまおうとする児童福祉司もいる。その瞬間から、彼女は保護を求める虐待被害者ではなく、取り締まりの対象である非行少女として扱われてしまう。
あるハイティーンの少女は、虐待によって児童相談所に一時保護されていた時、過去の犯罪行為が発覚して鑑別所へ行くことになった。彼女はその後、少年院に入ったが出院時に家に帰されてしまった。家では虐待が続いたため、彼女には居場所がない。
けれど出院後の保護観察中なので「◯日以上の無断外泊はしない」とか「夜◯時までには家に帰る」といった順守事項が課せられ、それらを守らなかったり、保護観察所が指定した居住地にいなかったりすると少年院に戻される可能性があり、「どうしたらよいか?」とColaboに相談してきた。
そこで私たちは彼女を保護し、児童相談所と保護観察所の担当者を集めて話し合うことにした。両者はそこで名刺交換を行った後、児相の担当者が「私たちとしては、一時保護の時点で彼女はもう家に返せないと判断していたんです」と切り出した。その後、彼女が安心して暮らせる場所をどう探すかで、児童相談所と保護観察所が互いに押し付け合おうとするようなことが起きた。児童相談所は厚生労働省、保護観察所は法務省と管轄が違うために連携が難しいのだそうだが、彼女のようなケースは本当に多いので、帰住先探しや出院後の支援などでの連携を強く求めたい。
警察と情報共有をすべきケースについては、各児童相談所の判断に任せるのではなく、過去の事件や今の状況を検証・調査し、よく議論して基準を作ってほしい。また、警察は福祉機関ではないが、現状で児童相談所の閉所時間に頼れる唯一の公的機関なのだから、虐待被害児に対し「取り締まり」ではなく「ケア=保護」の視点を持って関われるよう、全ての警官に継続的な研修を早急に行うべきだ。私は、そういう問題意識もなく「情報の全件共有」を語る人が増えることが怖い。警察には、むしろ補導した子を支援につなぐなど、必要なケアを受けられるよう積極的に動いてほしいと思う。
児童相談所と警察の情報共有を叫ぶ人たちには、「全ての子どもに弁護士を付ける」ことへの賛同も同時に求めていきたい。虐待されている子どもの中には「親と離れて生活したい」「親と縁を切りたい」と思っている子も、そうでない子もいる。しかし公的機関の対応には、そうした子どもの気持ちや意思が尊重されているとは感じられなかったり、子どもの権利が守られていないと思われたりすることが多々ある。
大きな権力に自分の人生や生活が左右されてしまうこと、決め付けられてしまうことを子どもたちは恐れている。虐待の事実が発覚したことからそういう経験をしたり、家族とのいい距離感を求めていたのに、介入があだになって関係が悪化したと感じたりした子どもは相談をしなくなる。だから警察と情報共有をするかしないかに関わらず、「子どもの味方」になる人を子どもたち一人ひとりに付けてほしい。「児童相談所の弁護士」ではなくて、「子どもの代理人」として活動できる専門家が必要だろう。
(2)短絡的な親批判では何も解決しない!
必要なのは児相や保護所の見直し
目黒の女児虐待死事件について言えば、問題の本質が果たして児童相談所と警察との情報共有ができていなかったことなのだろうか? それよりも虐待防止のためにまず必要なのは、児童相談所の体制を見直すことだと私は思う。
虐待を受けた子どもはさまざまなトラウマを抱えており、その影響から身を守るために嘘をついたり、甘えたり、大人を試したり、暴力的・反抗的・無関心な態度を取ったりすることがある。それらへの対応には知識と経験が必要だが、児童相談所には事務職として採用された公務員が児童福祉司として働いていることがあり、そういう人はトラウマへの理解やケアの視点を持って関わるための専門性が身に着いていないことがある。
更に人員不足で職員に余裕がなければ、子どもや他機関支援者との関係作りに時間を掛けることも難しい。知識と経験のある人を児童福祉司として採用し、専門性を磨きながら長く勤務し続けてもらう仕組みや、一つひとつのケースに丁寧に対応し、学校や医療、民間支援団体などとの連携ができる時間的、精神的な余裕を確保することが必要だ。
現在、1人の児童福祉司が100ケース以上を抱えている児童相談所もあり、そこの職員から「すぐに命に関わる低年齢の子を優先せざるを得ず、中高生は後回しになる」と言われたこともある。私は、今関わっている子どもに適切に対応できるようにするためだけでも職員数は最低5倍、支援を求めながら対応されていない子どもたちのことを考えると10倍以上に増やすべきだと思う。0〜18歳と幅広い年齢の子を同じ児童相談所職員・施設で見るのにも無理がある。乳幼児と中高生では対応の仕方や必要なスキルも違うため、10代の子どもたちに対応する専門チームを作るべきだ。
現状で児童福祉司は子どもだけでなく、家庭を支援するため親の問題にも関わっている。同じ担当者が子どもと親の両方から話を聞いて関わるので、児童福祉司と親との対立が生じやすく、子どもからの信頼も得にくい。客観的な判断のためにも、親と子で関わる担当者は分けるべきであり、「子どもの話」を子どもの気持ちに寄り添って聞けたり、親を支えられたりする民間支援者などとの役割分担、連携も必要だ。
そして、子どもの人権が守られない一時保護所の在り方も変えるべきだ。これは憲法学者である木村草太氏の編著『子どもの人権をまもるために』(2018年、晶文社)に共著者の一人として書いたが、ここでも述べておきたい。
児童相談所に保護されると多くの場合、まずは一時保護所に入所し、その間に家庭の状況の調査をしたり子どもの生活場所を探したりする。一時保護の期間は2週間〜2カ月程度が基本となっているが、次の受け入れ先が見つからないなどの理由から最長1年以上入所していた少女を私は知っている。その間、彼女は何カ月間も学校に通わせてもらえなかった。
一時保護期間中は学校での授業だけでなく、クラブ活動や定期試験、文化祭、体育祭、卒業式などの行事にもほとんど参加できない。そのため子ども自身が保護を拒み、虐待の事実はなかったと嘘の「撤回」をすることもある。
また、一時保護期間中は外部との連絡を絶たなければならず、友人や先輩、アルバイト先などに「今から保護されるからしばらく連絡できません」などと知らせることも許されないままに保護され、人間関係が壊れてしまうこともある。外部との接触が断たれ、精神的に追い詰められる子どももいる。多くの場合、教員や民間支援者との連絡や面会も許されず、一時保護所内で不安を感じたり不当な扱いを受けたりした時も、誰かに相談するなど声を上げにくい状況となっている。
せめて身を隠す必要のない子どもだけでも、通学や外部との連絡は許されるべきだ。一時保護所の中にも、状況に応じて登校や、教員、支援者などとの面会を許可している施設もある。そうした施設を参考に体制の見直しが必要だろう。
子どもが安心できる一時保護所を
一時保護所の中では、不可解な禁止事項やルールが存在していることもある。例えば、私語禁止、鉛筆回し禁止、髪の毛の黒染め強要、お絵描きなどで1日に使える紙の枚数が1人1枚までなどと決まっている、貸し出される下着や衣類に番号が付いている、自傷行為の傷跡は包帯を巻いて隠させる、トイレは許可制で職員が付いてくる、歯磨き粉を自分で付けるのはダメ(職員がつける)、兄弟姉妹であっても会話や所内での接見は許されない、など。
入所時の荷物検査も厳しく、「学校で配布されたプリントやテスト用紙、友人からの手紙などプライバシーに関わる物まで1枚ずつ確認された」と話す高校生がいた。入所中の衣類について「親が持ってきてくれない中高生は、みんな上下黒のスウェットを着させられ、刑務所のようだった」「ピアスの穴が塞がらないように透明のプラスチック製ピアスを付けたかったが許されず、穴が塞がってしまった」と言う子もいた。ある少女からは「居室に行くまでに何重もの鍵付き扉を開けて進まなければならず、脱走できないように窓も開かず、外の空気が吸えない環境の一時保護所もある」という話を聞いた。
ルールに違反した罰として体育館を100周走らせたり、態度や目付きが悪いなどと職員が怒鳴ったり、虐待のトラウマから男性職員におびえて面接で黙り込んだ少女に「大人との上手な付き合い方」をテーマにした課題図書を読ませて反省文を書かせたり、衝立で仕切った学習机で5時間も漢字の書き取りをさせたり、学習レベルに合わない計算ドリルをひたすら解かせたりなどを「内省」の名目で行ったりする所もあるらしい。
「自分が悪いことをしたからここに来たわけじゃない。親が暴力を振るったから来たのに囚人になったみたい」「刑務所みたいな場所だった」「虐待があっても家にいたほうがましだと思って、家に帰りたいと言った」「もう二度と行きたくない」と話す子たちと私は出会っている。そうした子どものおびえを知った親や児童養護施設の職員が、「言うことを聞かないとまた保護所に入れる」と、脅し文句として使うこともある。このように、今の一時保護所の在り方は、子どもの学ぶ権利や自由を奪うようなものになっている。
現在、少年院などでも施設見学ができるが、一時保護所については、特に居住スペースは弁護士や支援者などでも多くの場合見学させてもらえず、中で起きている事は子どもたちから聞いた話でしか分からない。先に挙げたような現状や、保護所ごとのルール(制度化されているものだけでなく、暗黙のうちに「私語禁止」などが慣例になってしまっているものを含めて)を調査し、見直すことが必要だ。
しかも一時保護所は、年齢や性別(性的マイノリティーの子どもへの配慮も含む)などに応じた個室整備も十分ではなく、スペース不足の問題もある。より家庭的な環境で保護できるよう、児童養護施設を含む開放施設や、里親などの活用を積極的に行ってほしい。それでもキャパシティーが足りないなら、民間支援者を一時保護委託先として認めるなどの運用も必要だ。いずれにせよ、子どもが「脱走したい」と思わないで済むような、「ここに来て良かった」と思えるような場所で一時保護を行えるようになってほしい。
自分ごととして考える姿勢を持つ
もう一つ、今回の目黒女児虐待死事件では5歳の少女が書いた文章がセンセーショナルに報じられ、虐待に関心が向いて親への批判が強まっていることにも危機感を覚える。
SNS上でも「そんなことする親は許せない!!」「どうして自分の子どもにそんなことができるのか分からない」「人間じゃない!」「そんな親は犯罪者だ」「死刑にしろ」「虐待する親の親権は停止すべき」「これまで同じような事件があるたび悲しむだけで何もできなかったから、その罰として今回の事件が起きた。今回こそ国を動かそう!」などという書き込みが目に付く。が、多くの場合は虐待した親も孤立・困窮していたり、障害や病気、その他の困難を抱えていたりする。
そのことを一番近くで見ていて感じ取り、理解しているのは子どもたちであり、たとえ自分に暴力を振るう親であっても他人に悪く言われることを嫌がる子も多く、私もその一人だった。親が自分を大切に思っていないわけではないと知って、虐待を受けてもなお「親のことが好き」という子どもも少なくない。容易に親権停止を叫んだり、親を犯罪者扱いしたりすることは当事者を更に孤立させ、追い詰めかねない。
「夫から妻へのDVなどと違い、親からの虐待では小さい子は逆らえないし、逃げる術も知らない」という人もいるが、虐待はDVのある家庭で起きることが多い。DVの被害者も子どもを気にするあまり加害者と別れられなかったり、暴力に支配されて逃げられなかったりすることが多い。より弱い立場にある子どもは絶対的に守られるべき存在ではあるが、他の暴力の被害者が助けを求められない状況があることも自己責任ではないし、ケアから排除する理由にはならない。
今回の虐待死事件で亡くなった女児の母親についても、行政が若年出産として把握していながら支援の必要性を認識していなかったという報道もある。子どもの親たちにも、ケアが必要だったのではないだろうか?
これまで虐待問題に関わってこなかった人たちが声を上げ、多くの人に届くことは大切だが、だからこそどんな表現をするかには気を遣い、問題の本質を見失わないよう学んでほしい。この事件を通して感情的になった人々が振りかざす正義によって子どもを虐待する親が責められ、家庭の問題、個人的な問題とされ、自己責任論が助長されないように気を付けたい。これを契機として虐待問題にどう対策していくか、当事者も含めて議論していけたらいいと思うが、正直、今は当事者を追い詰めるような雰囲気になっていると感じる。
虐待は、「一部の悪人」によって行われるのではない。特別問題を抱えている家庭でのみ起きるのではない。イライラして子どもを怒鳴ったり、言い過ぎてしまったり、叩いてしまったりしたことのある人は多いのではないだろうか。虐待は、私たちの生活と地続きにあるもの、すぐそこにあるものだ。自分もちょっとしたきっかけで加害者になるかもしれない。だからこそ、親も子も孤立せず、疲れた時には弱音を吐いたり、助けを求めたりできる環境が必要だ。それは、制度の中だけで実現することではない。虐待をしそうな、または現にしている親に対してもその気持ちや背景を想像し、理解を示し、励まし、支える雰囲気があることが、必要な時に必要な支援を利用することにつながる。
虐待のある家庭では、「このことを誰かに言ったら許さない」「人に言えば、お前は家族を壊すことになる」などと親が周りの目を気にして子どもを脅していたり、子どもも「大ごと」になるのを恐れていたりする。今の世間には、いっぱいいっぱいいで悩んでいる親が「子どものこと、イライラして叩いちゃったんだよね」と、友人に相談することもできなくなるような空気が充満していないか。子育てに関する悩みを児童相談所に相談するハードルはそもそも高いのに、全件警察に共有となれば、気軽に相談できなくなる親もいるだろう。
親を責めることよりも、「子育てや家族との関係は誰しもが悩むもの」という当たり前のことを共有し、「相談していいんだ」と思える雰囲気を作ってほしい。
子どもが関わる問題は「児童相談所や警察が保護すれば終わり」というものではない。保護された後、子どもたちが何を聞かれ、どんな手続きを踏み、どんな所でどんな生活を送ることになるのか――。先に挙げた一時保護所の実態や、児童福祉施設内での虐待の問題、里親の不足、非行に関わりやすいハイティーンの子どもたち(若年妊娠のリスクも高い)の行き場がないこと、子どもたちが人権や暴力、対等な関係性について学ぶ機会がないことなどにも目を向けるべきではないか。
問題はあり過ぎるほどに、ある。今回の女児虐待死事件をきっかけに「自分にもできることはないか?」と思った人には、まず知ろうとしてほしい。虐待のある家庭に対する想像力を持つためにも、今後議論されていくであろう虐待対策が、根本的な問題を置き去りにすることのないように、その見極めをするためにも。誰かにとって家庭が安心できる場所でないのだとしても、家庭の他に、地域の中に、いくつも「ホーム」に感じられる場所があったらいいと私は思う。
どんな立場にある人も、誰もが自分が無知であることや見えていないことがあるかもしれないことを意識し、問題が起きた時に誰かのせいにするのではなく、背景を理解しようとする姿勢と、自分ごととして考える姿勢を持つことが大切だと、自戒を込めて伝えたい。
「これだ!」という解決策なんてない。現実に向き合い、考え続けることは時に苦しい。自分の無力さに落胆することもあるかもしれない。だからこそ、さまざまな立場にある人が共に考え、虐待を生まない社会に向けて、家庭を、子どもを孤立させずに地域で支えていくことを始めてほしい。




















 クロガキの茶道具・棗。(提供・吉井恒仁)
クロガキの茶道具・棗。(提供・吉井恒仁)
 木材市場の片隅に摘まれた広葉樹材(筆者撮影)
木材市場の片隅に摘まれた広葉樹材(筆者撮影)