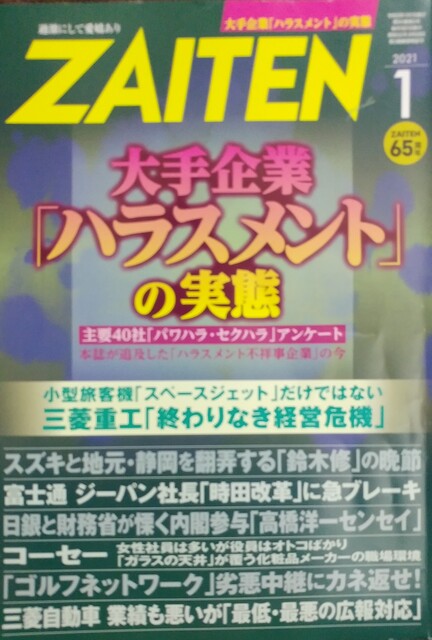堺・工場爆発:常務ら書類送検 労働安全衛生法違反容疑で
毎日新聞 2013年12月03日 20時43分
堺市堺区の金属製品製造業「日本伸銅」本社工場で溶解炉が爆発し、4人が死傷した事故で、堺労働基準監督署は3日、危険防止措置を講じていなかったとして、同社と工場長の男性常務(62)を労働安全衛生法違反の疑いで大阪地検に書類送検した。送検容疑は、合金を安全に作る作業手順を定めていなかった上、防護壁を設置せず、作業員に耐火服も着用させないなど、危険防止策を取らなかった、としている。
事故は、同社本社工場で今年4月9日、銅3トンを溶解炉で溶かした後、亜鉛1.6トンなど別の金属を入れたところ、亜鉛などが急激に溶けて爆発。西谷龍治さん(当時37歳)ら男性社員2人が熱傷で死亡し、別の男性社員2人も軽傷を負った。
同監督署によると、亜鉛は907度で気化するため、通常は、銅や亜鉛などを溶解炉に一緒に入れてから加熱していたが、この日は、溶解炉内の銅が既に1085度以上の高温になってから亜鉛を入れたため、爆発した。亜鉛は半径10メートルの範囲に飛び散ったという。【田所柳子】
毎日新聞 2013年12月03日 20時43分
堺市堺区の金属製品製造業「日本伸銅」本社工場で溶解炉が爆発し、4人が死傷した事故で、堺労働基準監督署は3日、危険防止措置を講じていなかったとして、同社と工場長の男性常務(62)を労働安全衛生法違反の疑いで大阪地検に書類送検した。送検容疑は、合金を安全に作る作業手順を定めていなかった上、防護壁を設置せず、作業員に耐火服も着用させないなど、危険防止策を取らなかった、としている。
事故は、同社本社工場で今年4月9日、銅3トンを溶解炉で溶かした後、亜鉛1.6トンなど別の金属を入れたところ、亜鉛などが急激に溶けて爆発。西谷龍治さん(当時37歳)ら男性社員2人が熱傷で死亡し、別の男性社員2人も軽傷を負った。
同監督署によると、亜鉛は907度で気化するため、通常は、銅や亜鉛などを溶解炉に一緒に入れてから加熱していたが、この日は、溶解炉内の銅が既に1085度以上の高温になってから亜鉛を入れたため、爆発した。亜鉛は半径10メートルの範囲に飛び散ったという。【田所柳子】