おはようございます。
言葉を追いかけて、結局、夜を明かしてしまいました。
早朝よりの更新で失礼します。
前フリばかりが長くて、いつまでかかるねん!・・・って感じのお話が、ようやく出来上がりました。
書きはじめた時に妄想してたものとは、思いもかけず、違う方向に行ってしまいました。
主人公たちが勝手に動きはじめるのは、いつものことで、
私は、それらを追いかけて言葉に直すんですけれど、
今回は、思ってもいなかったセリフを彼が言ってしまったおかげで、
作者の私自身が落ち込んでしまって、執筆放棄に近い状態で、身動きがとれなくなりました。
なんとか、いつものように立て直そうと思ったんですが、
こういった結末にするのが精一杯。
思い描いた桜のイメージも、上手くつたわるのかどうか・・・
考えていても仕方ありませんので、
百聞は一見に如かず、
とりあえず、お読みくださると嬉しいです。
今回も、少々長めにはなっておりますので、携帯からですと無駄にページ数が増えるやもしれません。
なお、ページの切り変わりで、文章が途切れてしまうことを御承知置きください。
それと、私、生粋の三河人ですので、関西弁には精通しておりません。
関西弁が変なのは、御容赦ください。
それでは。
あ。いつものことですが、小説の最後にランキングのリンクを貼りました。
普段は忘れておりますが、
ま、これも、
小説をUPした時の、半ばお約束のようなものですので、
よろしければ御協力くださいませ。
TORY.35 桜、サクラ、さくら
携帯電話が、メールの着信を告げた。
消せなかったアドレスから届いた、本文のない写メに導かれるように、
彼は、ハンドルを握ったまま、夜の高速をひた走る。
闇を裂いて、星を飛ばして。
仕事終わり。
出来るなら、一分でも、一秒でも早く、彼女のもとへ。
彼女を、この腕に抱きたいと、その思いだけで走り続ける道。
何度この道を通ったんだろう、と彼は思った。
この景色を、この夜空を、
何度眺めて、彼女のもとへと車を走らせたことだろう。
どれだけ仕事が遅く終わっても、
逢える時間がごくわずかでも、
彼女に逢うためだったら、こうして後先を考えずにひた走ることさえ、
いつも、
決して無理なことでも無茶なことでもなかった。
それまでに消えていった恋のいくつかは、
逢えない不安や寂しさや、
無理を承知で作る時間の不自由さの前に、無力すぎた。
―――― 彼女とだったら・・・大丈夫やと思ってたんや、ずっと
ただひとつ、彼に架せられた十字架さえ、背負い続けていられたら。
「もう・・・、お願い、・・・」
彼の腕の中で、彼女が懇願する。
彼女の頬を撫で、柔らかな髪を撫で、
いつくしむように、愛しむように、そのなだらかな曲線をたどり、
彼の細い指が奏でる音楽は、
彼女の途切れる声と、
彼の息遣いと、
揺れる空気、
軋む金属。
軽やかなリズムに、跳ねる身体。
いつしか訪れるまばゆいばかりの閃光に射抜かれて、
二人は、
深い闇の底へ、その身を横たえた。
「もう、終わりにしましょう・・・」
現実に戻って来ないまどろみのなかで、彼は、彼女の言葉をつかみ損ねた。
「終わり・・・って、なに?」
その単語だけが、彼の中に入り込んだ。
「そのまま、の意味ね」
身体を横たえたまま、彼を見ることもせず、彼女が言った。
「いつまでも、こんな不自然なこと、続かないわ」
「どこが、不自然なん?」
「なにもかも」
「ただの、男と女やろ? 出会って惹かれあって、こうして一緒におることの、どこが?」
「君は、忘れてるわ」
彼女は身体を起こして、横たわった彼の顔を、見下ろした。
彼女にまとわりついたささやかな香りが、闇に揺れる。
「何を?」
たじろぎもせず、彼は彼女を見上げる。
薄暗い間接照明の影になって、彼女の表情は読めなかった。
「私は・・・私には」
言い淀んだ彼女が、
自らの左手の薬指にはめられた細いプラチナの指輪に、視線を落とす。
「外さへんの?」
「・・・・・・」
「いつもは、それ、外してるやろ? 見張られてるみたいでイヤやって、言うてたやん」
「外したら、自由になれると思ったから。でも、ダメだったわ」
彼女の指から繋がる赤い糸。
結ばれた先の、
小さくからんだ結び目をほどくこともできずに、
いつしか、もつれて絡まって、彼女自身ががんじがらめになってしまった。
始まりは、ほんのささいなすれ違いだった。
どんな夫婦にだって、必ずあるような、行き違った想い。
ちょっとした頑固な意思のぶつかりあい。
冷静になるために離れたはずだったのに、
それが却って、夫婦の溝を深くした。
やり直せたはずだった。
埋めようと思えば、埋まるはずだった。
互いに向かい合って、
許し許され、笑顔になるはずだった。
それまでの二人なら、そう出来たはずだった。
でも出来なかった。
お互いに感じた居心地の悪さが、なお強くなるだけだった。
逃げ出したかった。
抜けだしたかった。
自分を受け止めて、煩わしさから守ってくれる腕が欲しかった。
少し考えれば分かったはずだったのに。
自分の息苦しさも、つらさも、せつなさも。
すべては、まだ、相手を求めているからにほかならない。
なのに、彼女は目を閉じた。
目を閉じて、夢の中に入り込んでいった。
夢の先で、また、苦しみがやってくることなど思いもせずに。
出会ったばかりの、若くてしなやかな腕。
彼女を救ったのは、
まっすぐに、自分を求めてくる瞳と、飾らない言葉。
嘘のない、邪気のない、あふれんばかりのエネルギー。
「めっちゃ好き!」
後先を考えない、その自由さがまばゆかった。
愛しい、と、思った。
彼女の指の証に気づいて、それでもなお、求めてくる素直さも。
彼女の名を呼ぶ、その小さなためらいさえも。
『まだ、愛してるの? あんなに裏切られたのに?』
言うたらアカン、彼は、そう思った。
―――― 口に出した言葉は、取り消すことは出来んのやから、
言うたら、アカン。
―――― 飲み込め、飲み込まなアカン。
「無理に外さんでも、ええんと違う? 」
ギリギリのところで、彼は言葉をすり替えた。
「それごと全部ひっくるめて、貴女なんやから。自然にしてるほうが、ラクやろ」
「君が、嫌がるんじゃないかと思って」
「なんで? 知ってて、それでも付き合って、言うたん、俺やで? 今更・・・」
「気にしない?」
「気にせえへんよ、そんなん」
―――― ただの、指輪やん。
続く言葉を、彼は飲み込んだ。
「せやって、そんなんがあるからって、好きって気持ちは止められへんもん」
彼は、彼女に問いかける。
「貴女は、そうじゃないの?」
「止められない・・・わね、私も」
「その気持ちだけあったら、ええのに。他には、なんもいらんで?」
彼は、身体を起こして、彼女の肩を抱いた。
女性の身体が、柔らかくて温かくて、
こんなにも優しいものだと教えてくれたのは彼女だった。
決して頑丈とはいえない自分の胸に、すがりついてくる肩を、
なにより愛しいと思ったのは、彼女が初めてだった。
甘えられるのは苦手だった。
泣かれるのは、もっと苦手だった。
お互いが自立して支え合うのが理想だと、信じている。
それは今でも変わらないのに。
彼女だけは、放ってはおかれへん。
こんな細い俺の腕で、彼女を守れるとは思ってへんけど、
この肩の震えが治まるのを待つくらいの時間は、
彼女に与えてやりたい、と、心底思っていた。
―――― せやのに、今、彼女は、何を言いだしてるんやろう。
「私といても、未来は、ない・・・でしょ?」
「未来・・・って? ・・・たとえば?」
彼は、確かめるように彼女を見る。
「・・・結婚・・・とか、子供、とか?」
「俺、そんなん、欲しがってるように見える?」
「時々、口にするでしょう? 子供、可愛いなあって」
「そら、周りがちょっとずつ結婚してけばなぁ、そんなこと思う時もあるけど」
彼の脳裏には、地元の友人や仕事先の友人らのニヤけた顔や、
ミルク臭い赤ん坊の、柔らかい肌の感触がよみがえっていた。
「私には、それを叶えてあげられないじゃない」
「え。なに、それ。なんでそんなことになるん?」
「重要なことでしょ? 私には君の子供を産めないもの」
「うわ、露骨やな。なんなん? 今日、なんでそんな絡んでくるん」
彼は彼女の顔を覗き込んだ。
「なんか、あった?」
―――― 彼女は俺を怒らせようとしてる。
彼は、とっさにそう感じた。
「なあ、さっきの、本気ちゃうやんな?」
「・・・」
言葉のない空間。
それに耐えられないのは、彼の方だ。
「黙るん、止めようや。こんなん、イヤやわ。本気なん?」
彼女が小さくかぶりを振った。
「嘘じゃないわ。終わりにしたいのよ」
「でも、そう思った理由が・・・ほんまの理由があるやろ?」
彼女は、言葉の代わりに、小さく息を吐いた。
「言いたくないんか」
彼女の戸惑いが、手に取るように彼に伝わる。
――――言いたくないんじゃない。
言えないもどかしさが、彼女にあるんや。
――――『好き』って気持ちだけで突き進むには、ここが限界なんか?
彼女を、今、惑わせてるもんは、なんや?
「・・・苦しいのよ」
絞り出すように、彼女が答えた。
「どうしたら、いいのか、分からない。自分でもわからないのよ。
自分が、真っ二つに引き裂かれる感じがするの」
彼女は、震えだす自分の身体を抱くように、両の腕を抱えた。
「君から好きだっていってもらえることが、嬉しい。
君を好きだと思う自分がいて、
君に逢いたいと願う私がいて、
君に逢えなかったら寂しくて、
こんなふうに過ごす時間が待ち遠しくて仕方ないの。
逢えたら嬉しくて、
君に抱かれると、愛されてるって実感するの」
こぼれ出した言葉が、闇に溶けて消えてゆく。
「そんでええやん。俺やって、おんなじやで?」
彼女に言い聞かせるように、彼は言葉をつなぐ。
「俺やって、貴女がこうして俺の傍にいてくれる時間があるから、ほかで頑張れんねん。
べたべた愛してるって言うん、気恥かしいから、
そんなん、よう言われへんけど。
でも、ちゃんと貴女には伝えてきたつもりやったで?
好き、って何度も何度も。
伝わらんかったん?」
「違う、違うの。そうじゃない」
「何が、違うん?」
「伝わるから。君の気持が痛いほど私に流れ込んでくるから。
どんどん君を好きになる自分がいて、手放せなくなる自分がいて、
壊れそうになるの」
「壊れるって・・・」
彼女の言葉の意味を、彼は推し量り損なっていた。
「どういう・・・こと?」
ためらいつつ、彼女は一気に吐き出してゆく。
「君を好きになればなるほど、
私は・・・まだ、自分が夫を好きだってことに気付かされるの。
君に愛されるたび、抱かれるたび、
夫にも、同じように愛されたいって思う自分を見つけるのよ」
「それ・・・って、俺は身代わりってこと?」
「違うわ、違う、そんなんじゃない」
「でも、そう聞こえるやん」
「ごめん、違う、信じて。違うの」
自分を見上げた彼女の瞳を見た時、
彼は、
不用意に放った自分の言葉が、彼女を追い詰めていくような気がした。
「君を夫の代わりだって思ったことなんか、ないわ。
それだったら、こんなふうに迷ったりしない。
そう思えたら、どれほど自由だったか・・・」
―――― 全部、彼女の中にあるもの全部、吐き出させた方がラクになるんかもしれん。
彼は、彼女の肩に回した手で、そっと髪を撫でた。
「君と一緒の時間を過ごしたい。
もっともっと、一緒にいたい。
これから先も、君と笑いたい。
でも、私はまだ、夫と過ごす時間を諦めたくなくて。
心のどこかで、夫に優しくされたい私がいるの。
身体がひとつなのに、心がふたつあるのよ。
自分がどこにいるのか、分からなくなってくる」
髪を撫でる手をはずし、彼は、彼女の方を向いた。
「不器用やな・・・」
彼よりも、はるかに年上なはずなのに、
とても幼い、
まるで、小さな子供のような、
不安げな表情の彼女が、そこにいた。
―――― こんな顔させたくて、彼女を好きになったんと違うのになぁ。
「俺と別れたら、苦しくなくなるん?」
「・・・・・・」
「まだ、振り向いてはもらわれへんのやろ?」
「・・・・・・」
「そんでも、戻りたいん?」
「・・・・・・」
「一人ぽっちが辛くて寂しくて泣いてたやん」
「・・・・・・」
「あんな思い、また、一人で繰り返すつもりなん?」
「・・・・・・」
「俺の胸では、もう頼りにならんか?」
彼女は、激しく首を横に振る。
「さっき、言うたよな。自分といても未来はない、って」
黙ったままの彼女が、うなづいた。
「未来が、そんなに大事なんか?
人間、いつなんどき、どうなるかなんてわからんもんやで?」
「それは、そうだけど・・・」
少しずつ、言葉を選びながら、彼は続けた。
「未来ばっかり考えて、今を踏みつけにするんか。
俺は、そんなん、イヤやわ。
今があってこその、未来やぞ。大切なんは、今やろ。
後悔なんか、したくないやん。
貴女に出会って、貴女を好きになってしまったんやから、
どうしてもこの手に抱きたいと思うんは、俺にとっては自然なことやってん。
言わへんかったら後悔するって思うたから、隠しもせず、告白もした。
言ったあとで、他のヤツのもんやって分かったからって、
突っ走った気持ち、止められへんわ。
貴女が俺のこと受け入れてくれて、
嬉しかったんやで?
貴女が、何かから逃げたがってる、忘れたがってるってこと、
分かったから、
まるごと全部受け止めよう、と決めたんや。
貴女が逢える時に、
俺を必要と思ってくれるときに、無理をせずに逢えるだけでええ、って。
ちょっとずつでも、哀しいこと辛いこと、分け合って、
二人で笑っていたい、って、そう思ってたんは、俺だけか?
そら、俺の腕なんか頼りないもんや。
貴女を守りきることなんて出来んかもしらんけど、
ほんのちょっとでも、わずかな時間でも、煩わしいことから隠してあげたかった。
このままの関係が、いつまでも続くもんやなんて、
俺やって思ってへんよ、
思ってへんけど・・・」
彼は、言葉を切った。
「苦しんでる貴女を見るんは、俺の本意とちゃうねん」
一旦下を向いて、彼は、彼女から目を逸らした。
大きく息を吸って、吐き出して、
意を決したように、ふたたび、彼女をまっすぐに見据えた。
そして強い口調で、言い切った。
「俺と別れることが、貴女をラクにすることなら、そうしたる。
終わりに、したる!!」
ひとひら、またひとひら。
薄紅の影が舞う。
見上げた空には、まだ、かすかな輝きで星が瞬く。
春と呼ぶにはまだ冷たい風が、時折、枝を揺らすように彼の横をすぎてゆく。
車を降りた彼の足は、次第にその歩みを速めていく。
彼は腕の時計をちらりと確かめた。
―――― こんな時間や。もう、おらん。おるはずはない。
両脇に続く桜並木。
誰ひとり通る人のない遊歩道を、彼は、まっすぐに駆けてゆく。
遊歩道の先、小さな公園に辿り着いた彼は、あたりを見回した。
彼の瞳が探すのは、たった一つのシルエット。
忘れられない、忘れるはずのない人の姿だ。
―――― あの桜は、絶対にここのヤツや。
桜のたたずまいも、映りこむ空も、
この季節だったら、どこにいたって見られる景色だ。
際立った特徴があるわけではない。
彼女が一番好きだった花。
好きだった場所。
好きだった時間。
好きだった言葉。
好きだった色。
好きだった匂い。
彼女が彼に残した記憶のカケラは、すべて、ここに戻ってくる。
―――― 桜、見たいなぁ・・・
不意に彼女の声が、蘇った。
―――― 季節がちゃうやん
そう答えた自分に、『そうね・・・』と微笑った彼女。
―――― 夜が明ける瞬間の空に、花びらの色が溶け込んでいくの。
光が広がるのと同時に、
波が打ち寄せるように、桜のピンクが押し寄せてくるのよ。
君に、見せてあげたかったわ。
彼女が、彼の想いを受け入れた場所。
―――― あれから何度も春は巡ったのに、
結局、ここの桜を二人で眺めることなど出来んかったな。
彼は、近くのベンチに腰掛け、空を見上げた。
散るにはまだ早い桜が、花ごと一輪、彼の足もとに落ちてくる。
くるり、くるり、舞うように。
―――― リズムのいい音楽でも、鳴ってるようやな。
桜を眺めているうちに、
やがて空が、次第に明るさを取り戻してきた。
闇に紛れていた桜の紅が、
光に浮かび上がり、紫の空に、鮮やかな波を立てていく。
押し寄せるような、迫ってくるような、
空ごと落ちてくるのではないかと思えるような、波、波、波。
昼間には気づかない桜の、ほのかな香りが彼にまとわりついて、
窒息しそうなほどだ。
―――― 生まれ変われる気がするの。
風が、彼の耳元で囁きながら通り過ぎてゆく。
―――― 夜明けの、あの桜の下にいると、きっと生まれ変われる。
そう思えるのよ。
遠い記憶の彼女の声をなぞりながら、彼は、桜に向かって手を差し出した。
―――― 届かん、な。
なかなか、難しいわ。
手が届きそうで、いっつも、すり抜けてく感じがする。
指に触れそうで、つかみきれない花びらを、追い求めてる自分に気づいて、彼は苦笑った。
―――― そういうことか・・・。
やりたい仕事をやりきれない現状、自分の力の及ばない事情。
そんなものにぶつかるたび、
落ち込んで、苦しんで、考え過ぎるほど考えこんでしまう自分。
それを飲み込んで消化するのに、いやというほど時間がかかる自分。
―――― なんで、あのヒトにはわかんねん。
見透かされてるやん。
―――― 俺も、生まれ変われる・・・か?
空を見上げて大きく息を吸う。
桜からあふれ出している力が、彼の身体に流れ込んでくる。
―――― 離れてても、見ててくれるんやな。
そばに、おってくれてるんやな。
彼は、携帯を取り出すと、空に向かってカメラを向ける。
カシャッ・・・・・・
乾いたシャッター音が、冷たい空気に響いた。
♪♪♪・・・♪♪♪・・・♪♪♪
携帯を開いた彼女の顔に、安堵の笑みが浮かぶ。
闇と光が交差する空を埋め尽くす、桜、桜、桜。
まばゆいばかりの、薄紅。
離れても、
離れたからこそ、なお愛しい彼の声が、そこから聞こえるようだった。
―――― 伝わった・・・んだね。
ッくしゅん。
彼は大きなくしゃみをひとつ。
―――― あかんわ。次の仕事に間に合わんようになる。
名残惜しそうに、もう一度空を見上げ、
彼は、足早に歩き出す。
彼の背を押すように、始まりを告げる光が一面に広がっていった。
FIN.
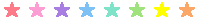
お気に召しましたら、
関ジャニWEBランキング
にほんブログ村ランキング
ぽちんっと押して頂けると、とっても嬉しいです。
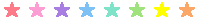
言葉を追いかけて、結局、夜を明かしてしまいました。
早朝よりの更新で失礼します。
前フリばかりが長くて、いつまでかかるねん!・・・って感じのお話が、ようやく出来上がりました。
書きはじめた時に妄想してたものとは、思いもかけず、違う方向に行ってしまいました。
主人公たちが勝手に動きはじめるのは、いつものことで、
私は、それらを追いかけて言葉に直すんですけれど、
今回は、思ってもいなかったセリフを彼が言ってしまったおかげで、
作者の私自身が落ち込んでしまって、執筆放棄に近い状態で、身動きがとれなくなりました。
なんとか、いつものように立て直そうと思ったんですが、
こういった結末にするのが精一杯。
思い描いた桜のイメージも、上手くつたわるのかどうか・・・
考えていても仕方ありませんので、
百聞は一見に如かず、
とりあえず、お読みくださると嬉しいです。
今回も、少々長めにはなっておりますので、携帯からですと無駄にページ数が増えるやもしれません。
なお、ページの切り変わりで、文章が途切れてしまうことを御承知置きください。
それと、私、生粋の三河人ですので、関西弁には精通しておりません。
関西弁が変なのは、御容赦ください。
それでは。
あ。いつものことですが、小説の最後にランキングのリンクを貼りました。
普段は忘れておりますが、
ま、これも、
小説をUPした時の、半ばお約束のようなものですので、
よろしければ御協力くださいませ。
TORY.35 桜、サクラ、さくら
携帯電話が、メールの着信を告げた。
消せなかったアドレスから届いた、本文のない写メに導かれるように、
彼は、ハンドルを握ったまま、夜の高速をひた走る。
闇を裂いて、星を飛ばして。
仕事終わり。
出来るなら、一分でも、一秒でも早く、彼女のもとへ。
彼女を、この腕に抱きたいと、その思いだけで走り続ける道。
何度この道を通ったんだろう、と彼は思った。
この景色を、この夜空を、
何度眺めて、彼女のもとへと車を走らせたことだろう。
どれだけ仕事が遅く終わっても、
逢える時間がごくわずかでも、
彼女に逢うためだったら、こうして後先を考えずにひた走ることさえ、
いつも、
決して無理なことでも無茶なことでもなかった。
それまでに消えていった恋のいくつかは、
逢えない不安や寂しさや、
無理を承知で作る時間の不自由さの前に、無力すぎた。
―――― 彼女とだったら・・・大丈夫やと思ってたんや、ずっと
ただひとつ、彼に架せられた十字架さえ、背負い続けていられたら。
「もう・・・、お願い、・・・」
彼の腕の中で、彼女が懇願する。
彼女の頬を撫で、柔らかな髪を撫で、
いつくしむように、愛しむように、そのなだらかな曲線をたどり、
彼の細い指が奏でる音楽は、
彼女の途切れる声と、
彼の息遣いと、
揺れる空気、
軋む金属。
軽やかなリズムに、跳ねる身体。
いつしか訪れるまばゆいばかりの閃光に射抜かれて、
二人は、
深い闇の底へ、その身を横たえた。
「もう、終わりにしましょう・・・」
現実に戻って来ないまどろみのなかで、彼は、彼女の言葉をつかみ損ねた。
「終わり・・・って、なに?」
その単語だけが、彼の中に入り込んだ。
「そのまま、の意味ね」
身体を横たえたまま、彼を見ることもせず、彼女が言った。
「いつまでも、こんな不自然なこと、続かないわ」
「どこが、不自然なん?」
「なにもかも」
「ただの、男と女やろ? 出会って惹かれあって、こうして一緒におることの、どこが?」
「君は、忘れてるわ」
彼女は身体を起こして、横たわった彼の顔を、見下ろした。
彼女にまとわりついたささやかな香りが、闇に揺れる。
「何を?」
たじろぎもせず、彼は彼女を見上げる。
薄暗い間接照明の影になって、彼女の表情は読めなかった。
「私は・・・私には」
言い淀んだ彼女が、
自らの左手の薬指にはめられた細いプラチナの指輪に、視線を落とす。
「外さへんの?」
「・・・・・・」
「いつもは、それ、外してるやろ? 見張られてるみたいでイヤやって、言うてたやん」
「外したら、自由になれると思ったから。でも、ダメだったわ」
彼女の指から繋がる赤い糸。
結ばれた先の、
小さくからんだ結び目をほどくこともできずに、
いつしか、もつれて絡まって、彼女自身ががんじがらめになってしまった。
始まりは、ほんのささいなすれ違いだった。
どんな夫婦にだって、必ずあるような、行き違った想い。
ちょっとした頑固な意思のぶつかりあい。
冷静になるために離れたはずだったのに、
それが却って、夫婦の溝を深くした。
やり直せたはずだった。
埋めようと思えば、埋まるはずだった。
互いに向かい合って、
許し許され、笑顔になるはずだった。
それまでの二人なら、そう出来たはずだった。
でも出来なかった。
お互いに感じた居心地の悪さが、なお強くなるだけだった。
逃げ出したかった。
抜けだしたかった。
自分を受け止めて、煩わしさから守ってくれる腕が欲しかった。
少し考えれば分かったはずだったのに。
自分の息苦しさも、つらさも、せつなさも。
すべては、まだ、相手を求めているからにほかならない。
なのに、彼女は目を閉じた。
目を閉じて、夢の中に入り込んでいった。
夢の先で、また、苦しみがやってくることなど思いもせずに。
出会ったばかりの、若くてしなやかな腕。
彼女を救ったのは、
まっすぐに、自分を求めてくる瞳と、飾らない言葉。
嘘のない、邪気のない、あふれんばかりのエネルギー。
「めっちゃ好き!」
後先を考えない、その自由さがまばゆかった。
愛しい、と、思った。
彼女の指の証に気づいて、それでもなお、求めてくる素直さも。
彼女の名を呼ぶ、その小さなためらいさえも。
『まだ、愛してるの? あんなに裏切られたのに?』
言うたらアカン、彼は、そう思った。
―――― 口に出した言葉は、取り消すことは出来んのやから、
言うたら、アカン。
―――― 飲み込め、飲み込まなアカン。
「無理に外さんでも、ええんと違う? 」
ギリギリのところで、彼は言葉をすり替えた。
「それごと全部ひっくるめて、貴女なんやから。自然にしてるほうが、ラクやろ」
「君が、嫌がるんじゃないかと思って」
「なんで? 知ってて、それでも付き合って、言うたん、俺やで? 今更・・・」
「気にしない?」
「気にせえへんよ、そんなん」
―――― ただの、指輪やん。
続く言葉を、彼は飲み込んだ。
「せやって、そんなんがあるからって、好きって気持ちは止められへんもん」
彼は、彼女に問いかける。
「貴女は、そうじゃないの?」
「止められない・・・わね、私も」
「その気持ちだけあったら、ええのに。他には、なんもいらんで?」
彼は、身体を起こして、彼女の肩を抱いた。
女性の身体が、柔らかくて温かくて、
こんなにも優しいものだと教えてくれたのは彼女だった。
決して頑丈とはいえない自分の胸に、すがりついてくる肩を、
なにより愛しいと思ったのは、彼女が初めてだった。
甘えられるのは苦手だった。
泣かれるのは、もっと苦手だった。
お互いが自立して支え合うのが理想だと、信じている。
それは今でも変わらないのに。
彼女だけは、放ってはおかれへん。
こんな細い俺の腕で、彼女を守れるとは思ってへんけど、
この肩の震えが治まるのを待つくらいの時間は、
彼女に与えてやりたい、と、心底思っていた。
―――― せやのに、今、彼女は、何を言いだしてるんやろう。
「私といても、未来は、ない・・・でしょ?」
「未来・・・って? ・・・たとえば?」
彼は、確かめるように彼女を見る。
「・・・結婚・・・とか、子供、とか?」
「俺、そんなん、欲しがってるように見える?」
「時々、口にするでしょう? 子供、可愛いなあって」
「そら、周りがちょっとずつ結婚してけばなぁ、そんなこと思う時もあるけど」
彼の脳裏には、地元の友人や仕事先の友人らのニヤけた顔や、
ミルク臭い赤ん坊の、柔らかい肌の感触がよみがえっていた。
「私には、それを叶えてあげられないじゃない」
「え。なに、それ。なんでそんなことになるん?」
「重要なことでしょ? 私には君の子供を産めないもの」
「うわ、露骨やな。なんなん? 今日、なんでそんな絡んでくるん」
彼は彼女の顔を覗き込んだ。
「なんか、あった?」
―――― 彼女は俺を怒らせようとしてる。
彼は、とっさにそう感じた。
「なあ、さっきの、本気ちゃうやんな?」
「・・・」
言葉のない空間。
それに耐えられないのは、彼の方だ。
「黙るん、止めようや。こんなん、イヤやわ。本気なん?」
彼女が小さくかぶりを振った。
「嘘じゃないわ。終わりにしたいのよ」
「でも、そう思った理由が・・・ほんまの理由があるやろ?」
彼女は、言葉の代わりに、小さく息を吐いた。
「言いたくないんか」
彼女の戸惑いが、手に取るように彼に伝わる。
――――言いたくないんじゃない。
言えないもどかしさが、彼女にあるんや。
――――『好き』って気持ちだけで突き進むには、ここが限界なんか?
彼女を、今、惑わせてるもんは、なんや?
「・・・苦しいのよ」
絞り出すように、彼女が答えた。
「どうしたら、いいのか、分からない。自分でもわからないのよ。
自分が、真っ二つに引き裂かれる感じがするの」
彼女は、震えだす自分の身体を抱くように、両の腕を抱えた。
「君から好きだっていってもらえることが、嬉しい。
君を好きだと思う自分がいて、
君に逢いたいと願う私がいて、
君に逢えなかったら寂しくて、
こんなふうに過ごす時間が待ち遠しくて仕方ないの。
逢えたら嬉しくて、
君に抱かれると、愛されてるって実感するの」
こぼれ出した言葉が、闇に溶けて消えてゆく。
「そんでええやん。俺やって、おんなじやで?」
彼女に言い聞かせるように、彼は言葉をつなぐ。
「俺やって、貴女がこうして俺の傍にいてくれる時間があるから、ほかで頑張れんねん。
べたべた愛してるって言うん、気恥かしいから、
そんなん、よう言われへんけど。
でも、ちゃんと貴女には伝えてきたつもりやったで?
好き、って何度も何度も。
伝わらんかったん?」
「違う、違うの。そうじゃない」
「何が、違うん?」
「伝わるから。君の気持が痛いほど私に流れ込んでくるから。
どんどん君を好きになる自分がいて、手放せなくなる自分がいて、
壊れそうになるの」
「壊れるって・・・」
彼女の言葉の意味を、彼は推し量り損なっていた。
「どういう・・・こと?」
ためらいつつ、彼女は一気に吐き出してゆく。
「君を好きになればなるほど、
私は・・・まだ、自分が夫を好きだってことに気付かされるの。
君に愛されるたび、抱かれるたび、
夫にも、同じように愛されたいって思う自分を見つけるのよ」
「それ・・・って、俺は身代わりってこと?」
「違うわ、違う、そんなんじゃない」
「でも、そう聞こえるやん」
「ごめん、違う、信じて。違うの」
自分を見上げた彼女の瞳を見た時、
彼は、
不用意に放った自分の言葉が、彼女を追い詰めていくような気がした。
「君を夫の代わりだって思ったことなんか、ないわ。
それだったら、こんなふうに迷ったりしない。
そう思えたら、どれほど自由だったか・・・」
―――― 全部、彼女の中にあるもの全部、吐き出させた方がラクになるんかもしれん。
彼は、彼女の肩に回した手で、そっと髪を撫でた。
「君と一緒の時間を過ごしたい。
もっともっと、一緒にいたい。
これから先も、君と笑いたい。
でも、私はまだ、夫と過ごす時間を諦めたくなくて。
心のどこかで、夫に優しくされたい私がいるの。
身体がひとつなのに、心がふたつあるのよ。
自分がどこにいるのか、分からなくなってくる」
髪を撫でる手をはずし、彼は、彼女の方を向いた。
「不器用やな・・・」
彼よりも、はるかに年上なはずなのに、
とても幼い、
まるで、小さな子供のような、
不安げな表情の彼女が、そこにいた。
―――― こんな顔させたくて、彼女を好きになったんと違うのになぁ。
「俺と別れたら、苦しくなくなるん?」
「・・・・・・」
「まだ、振り向いてはもらわれへんのやろ?」
「・・・・・・」
「そんでも、戻りたいん?」
「・・・・・・」
「一人ぽっちが辛くて寂しくて泣いてたやん」
「・・・・・・」
「あんな思い、また、一人で繰り返すつもりなん?」
「・・・・・・」
「俺の胸では、もう頼りにならんか?」
彼女は、激しく首を横に振る。
「さっき、言うたよな。自分といても未来はない、って」
黙ったままの彼女が、うなづいた。
「未来が、そんなに大事なんか?
人間、いつなんどき、どうなるかなんてわからんもんやで?」
「それは、そうだけど・・・」
少しずつ、言葉を選びながら、彼は続けた。
「未来ばっかり考えて、今を踏みつけにするんか。
俺は、そんなん、イヤやわ。
今があってこその、未来やぞ。大切なんは、今やろ。
後悔なんか、したくないやん。
貴女に出会って、貴女を好きになってしまったんやから、
どうしてもこの手に抱きたいと思うんは、俺にとっては自然なことやってん。
言わへんかったら後悔するって思うたから、隠しもせず、告白もした。
言ったあとで、他のヤツのもんやって分かったからって、
突っ走った気持ち、止められへんわ。
貴女が俺のこと受け入れてくれて、
嬉しかったんやで?
貴女が、何かから逃げたがってる、忘れたがってるってこと、
分かったから、
まるごと全部受け止めよう、と決めたんや。
貴女が逢える時に、
俺を必要と思ってくれるときに、無理をせずに逢えるだけでええ、って。
ちょっとずつでも、哀しいこと辛いこと、分け合って、
二人で笑っていたい、って、そう思ってたんは、俺だけか?
そら、俺の腕なんか頼りないもんや。
貴女を守りきることなんて出来んかもしらんけど、
ほんのちょっとでも、わずかな時間でも、煩わしいことから隠してあげたかった。
このままの関係が、いつまでも続くもんやなんて、
俺やって思ってへんよ、
思ってへんけど・・・」
彼は、言葉を切った。
「苦しんでる貴女を見るんは、俺の本意とちゃうねん」
一旦下を向いて、彼は、彼女から目を逸らした。
大きく息を吸って、吐き出して、
意を決したように、ふたたび、彼女をまっすぐに見据えた。
そして強い口調で、言い切った。
「俺と別れることが、貴女をラクにすることなら、そうしたる。
終わりに、したる!!」
ひとひら、またひとひら。
薄紅の影が舞う。
見上げた空には、まだ、かすかな輝きで星が瞬く。
春と呼ぶにはまだ冷たい風が、時折、枝を揺らすように彼の横をすぎてゆく。
車を降りた彼の足は、次第にその歩みを速めていく。
彼は腕の時計をちらりと確かめた。
―――― こんな時間や。もう、おらん。おるはずはない。
両脇に続く桜並木。
誰ひとり通る人のない遊歩道を、彼は、まっすぐに駆けてゆく。
遊歩道の先、小さな公園に辿り着いた彼は、あたりを見回した。
彼の瞳が探すのは、たった一つのシルエット。
忘れられない、忘れるはずのない人の姿だ。
―――― あの桜は、絶対にここのヤツや。
桜のたたずまいも、映りこむ空も、
この季節だったら、どこにいたって見られる景色だ。
際立った特徴があるわけではない。
彼女が一番好きだった花。
好きだった場所。
好きだった時間。
好きだった言葉。
好きだった色。
好きだった匂い。
彼女が彼に残した記憶のカケラは、すべて、ここに戻ってくる。
―――― 桜、見たいなぁ・・・
不意に彼女の声が、蘇った。
―――― 季節がちゃうやん
そう答えた自分に、『そうね・・・』と微笑った彼女。
―――― 夜が明ける瞬間の空に、花びらの色が溶け込んでいくの。
光が広がるのと同時に、
波が打ち寄せるように、桜のピンクが押し寄せてくるのよ。
君に、見せてあげたかったわ。
彼女が、彼の想いを受け入れた場所。
―――― あれから何度も春は巡ったのに、
結局、ここの桜を二人で眺めることなど出来んかったな。
彼は、近くのベンチに腰掛け、空を見上げた。
散るにはまだ早い桜が、花ごと一輪、彼の足もとに落ちてくる。
くるり、くるり、舞うように。
―――― リズムのいい音楽でも、鳴ってるようやな。
桜を眺めているうちに、
やがて空が、次第に明るさを取り戻してきた。
闇に紛れていた桜の紅が、
光に浮かび上がり、紫の空に、鮮やかな波を立てていく。
押し寄せるような、迫ってくるような、
空ごと落ちてくるのではないかと思えるような、波、波、波。
昼間には気づかない桜の、ほのかな香りが彼にまとわりついて、
窒息しそうなほどだ。
―――― 生まれ変われる気がするの。
風が、彼の耳元で囁きながら通り過ぎてゆく。
―――― 夜明けの、あの桜の下にいると、きっと生まれ変われる。
そう思えるのよ。
遠い記憶の彼女の声をなぞりながら、彼は、桜に向かって手を差し出した。
―――― 届かん、な。
なかなか、難しいわ。
手が届きそうで、いっつも、すり抜けてく感じがする。
指に触れそうで、つかみきれない花びらを、追い求めてる自分に気づいて、彼は苦笑った。
―――― そういうことか・・・。
やりたい仕事をやりきれない現状、自分の力の及ばない事情。
そんなものにぶつかるたび、
落ち込んで、苦しんで、考え過ぎるほど考えこんでしまう自分。
それを飲み込んで消化するのに、いやというほど時間がかかる自分。
―――― なんで、あのヒトにはわかんねん。
見透かされてるやん。
―――― 俺も、生まれ変われる・・・か?
空を見上げて大きく息を吸う。
桜からあふれ出している力が、彼の身体に流れ込んでくる。
―――― 離れてても、見ててくれるんやな。
そばに、おってくれてるんやな。
彼は、携帯を取り出すと、空に向かってカメラを向ける。
カシャッ・・・・・・
乾いたシャッター音が、冷たい空気に響いた。
♪♪♪・・・♪♪♪・・・♪♪♪
携帯を開いた彼女の顔に、安堵の笑みが浮かぶ。
闇と光が交差する空を埋め尽くす、桜、桜、桜。
まばゆいばかりの、薄紅。
離れても、
離れたからこそ、なお愛しい彼の声が、そこから聞こえるようだった。
―――― 伝わった・・・んだね。
ッくしゅん。
彼は大きなくしゃみをひとつ。
―――― あかんわ。次の仕事に間に合わんようになる。
名残惜しそうに、もう一度空を見上げ、
彼は、足早に歩き出す。
彼の背を押すように、始まりを告げる光が一面に広がっていった。
FIN.
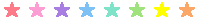
お気に召しましたら、
関ジャニWEBランキング
にほんブログ村ランキング
ぽちんっと押して頂けると、とっても嬉しいです。
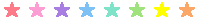










大人ですね~!
私は腐って(笑)るのでこういうのは書けません(汗)
楽しかったです。
私も、一時期、腐ってましたよ。
・・・今でも、素質は残ってますが((笑 隠してます。
コメント、ありがとうございます。
すばるへの愛が似ている方がいてくださるのは、とてもうれしいです。
あまりにも夢を見過ぎて、こんなふうに小説にまでしてしまいました。
これからも、よろしくお付き合いくださいね。
今回のはちょっと長めでじっくりのゆさんの桜の世界を堪能させていただきました。
お昼ご飯後にコーヒー飲みながら。
あれからもう1年経ったんですね~。早いですね。
私のゆさんの桜が主題の小説がとても好きです(*^_^*)
小説を書く時は、いつも自分がそこに入り込んでるんですけど、
今回は入り込み過ぎて、途中、物凄くリアルに凹んでしまいました((苦笑
次は、もうちょっと彼と幸せな時間を過ごしたくて、
舞音ちゃんに登場してもらおうかな、と思ってます。