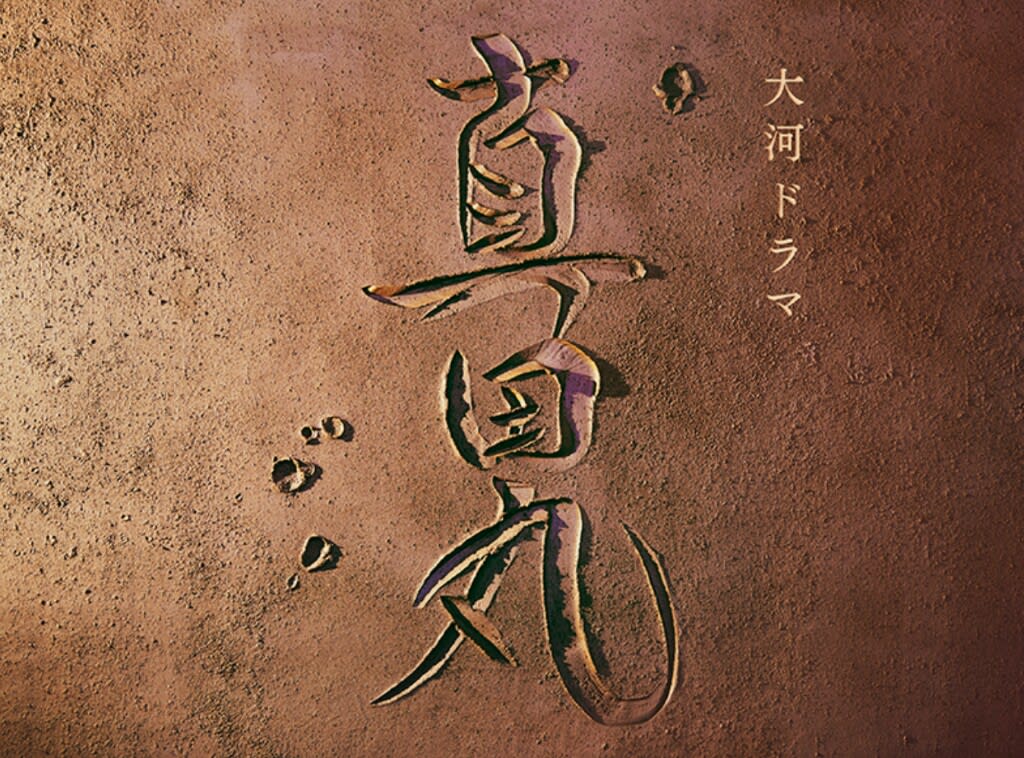
幸村誕生に至る暗い決意の夜から一変、真田家は喜ばしい雰囲気。内記も「大殿が聞いたらお喜びになります」と大坂行きに大賛成。反対を押しきって抜け出すのだろうなと思っていたので意外だった。
幸村「皆には苦労を掛ける」
きり「苦労大好きですから!」
その脱出は酒宴での雁金踊りを利用。踊りながら一人ずつ舞台袖に消えていき(なぜか佐助だけ隠し扉から)、最後は幸村ときりだけになったのが象徴的だった。やはりきりは幸村と対なのだ。
長兵衛さんが監視のリーダーをのらりくらりと騙すのが良かった。九度山の人たちと最終的には仲良くなれたのが良かった。
なんで女子供まで大坂に連れていくのだろうと思ったが、残しておいても徳川に殺されるだけだろうからだな。
九度山の若者が近道を知ってるといって仲間になったが、その近道で助かったとか、思いの外使える奴だとかいったシーンはなし。大坂城に入ったかどうかも不明。
それより佐助が二代目服部半蔵と一騎討ち。殺陣はイマイチだった。幸村と内記も駆けつけて包囲したが、針を多数構えて強引に突破する技で逃げられた。この忍者対決はスペシャルエフェクツ多用で若干おふざけが入っていた。
前回信之が手紙を取り落としたのは病気だったらしい。大坂にはいかず、息子達を派遣する模様。その息子二人のうちどちらを嫡男にするか。
稲の子の信政が、武芸の稽古でこうの子、信吉に圧勝。だけでなく、信吉が落とした木刀をさらに遠くへ弾いた。実際の戦闘では有効だと思うが、人としては美しくない行為。それで我が子に器量なしと見切ったか、稲は自分から信吉を嫡男に、と言い出した。台詞的には信吉の居場所がなくなるからということにしておいて、実はその器ではないと匂わせる脚本が冴えていた。
大坂城に牢人が集まっていると聞き、家康が真田のことを気にする。実力よりも徳川を二度負かしたイメージの方が重要だという。真田が大坂入りしたと聞いて恐怖でガタガタ震えだし、箸を取り落とすという伝説のシーンは無し。予告でそれっぽいのが流れたので、来週かも。
服部を退けたらあとは何もなく大坂入り。老人に化けたから徳川の目をごまかせたとかも無し。老人の変装は、牢人達に「老けたな」と思わせておいて、トイレで変装を解き、颯爽と現れるサプライズを狙ったものらしい。服も比較的派手な柄だった。
受付で、今後は真田左衛門佐幸村と名乗ると宣言。「信繁」に取り消し線を引いて、横に「幸村」と書いた。芸名とかではなく、マジな本名として使用するらしい。
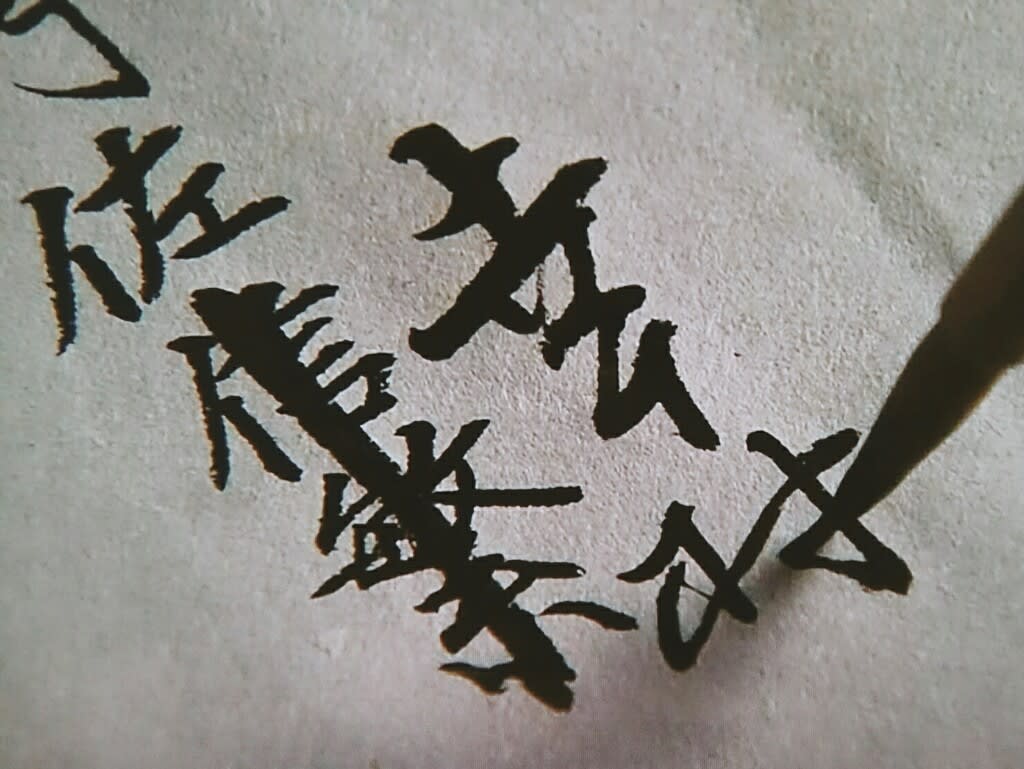
真田幸村という名前の響きはかっこいい。しかし、冷静に考えると「村」はあんまり名前に使う文字ではない。村には「田舎のむら里」という意味しかなく、人の性質を表す文字ではないからだ。荒木村重という例はあるけど。
そんな、響きはいいけど意味がいいとは言えない文字を使った理由として、前回の漢字くじ引きは上手いアイディアだったと思うのだ。脚本家の。
で、秀頼と再会。秀頼は幸村を覚えていたし、頼りににしている様子。なにげに無名の幸村なので、割りと相手にされないかもと思っていたが、そうでもなかった。だが、二度の上田合戦で戦ったのは父安房守ではなく自分だと大嘘をついた。段々お父さんみたいになってきた。
秀頼はぼんやりした木偶の坊みたいなイメージが昔からあったと思うが、このドラマでは容姿端麗(いわゆる花のやうなる秀頼さま)で有能な若者という最近の解釈?になっている。有能かどうかはともかく、よく考えたら戦国一の美女・お市の方の孫なんだから、美男子だった可能性はあるわけで。秀吉の遺伝子が引っ込んでればの話だが。
そして、茶々と再会。
幸村「茶々様…」
茶々「源次郎、また会えましたね」
あの不吉な予言の前半が当たったわけで、茶々のほうは一瞬「あっ」「やはり…」的な反応があっても良かった気もするがが、ここでは特に劇的な演出はなし。
大蔵卿局が幸村を本心から頼りにしている風だった。常に裏では人を疑う、あるいはバカにしている彼女なのに。
大蔵卿局は、大野治長の母である。治長は既に幸村を嫌い始めている。だが、母は幸村に期待している。そのへん、今後どうなるのか注目。















