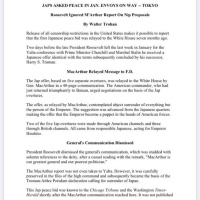地元では原田康子の『挽歌』は口にすることが大人のタブーだった。後日知ったが、原田康子の小説『海霧』に挿絵を描いた画家、羽生輝画伯は私の中学校の美術部担当で技術家庭教諭だった。
その頃の釧路といえば、確かにこの人、もうひとりの釧路有名人であった彼平原 徹男 →彼女平原 麻紀の言うように、景気が良く。夜はカネをばら撒く酔客だらけだった。
その頃の釧路といえば、確かにこの人、もうひとりの釧路有名人であった彼平原 徹男 →彼女平原 麻紀の言うように、景気が良く。夜はカネをばら撒く酔客だらけだった。
つまり船を降りた漁師が昼酒をあおる今だけを謳歌して歩く天国でした。
当時の釧路デパートの屋上 噴水ジュースが懐かしい。飲みたかった。
カルーセル麻紀 「繁華街の栄町をウロウロしていると、紙くずがいっぱい落ちていたの。それは全部おカネなんです。酔っぱらった漁師の腹巻きからこぼれてしまうんです。だから栄町公園に行ったら上を見ないで、下を見ながら歩く。たまに、なぜかイヤリングなどの宝石類まで落ちていたこともありました。漁師たちは、長靴を履いて、鱗がついたまま繁華街に繰り出し、すごく華やかな雰囲気でした。」ザイザツ 桜木紫乃との対談より
『緋の河』
【ノブヨの父は駅裏で飲み屋をひらいているという。秀男が住む幣舞橋界隈とはまた少し気配の違う夜の街である。線路の北と南では、客層も働く女たちもみな違うと聞いたことがあった。秀男は大人たちの、ほんの少し見下したような話しぶりを思い出した。】
駅裏とは原田康子が『挽歌』で描いた山の上のブルジョアや高級公務員の住む釧路から見れば平原 徹男の住む幣舞橋界隈よりもさらに一段下の貧乏人向け歓楽街であり
さらに私の暮らしたトンケシ側は一時雇いの労務者が流れすむさらに貧乏なところ、新釧路川の土手までは三階級下の下層の街だった。
女性は気が強くなければ生きて行けない。仲の良い姉という設定の章子の離婚後の行動の意外な割り切りもよくわかるような気がする。

『緋の河』 あとがき (釧路の風情が凝縮されているので失礼を承知で引用します)
人生の舵を自分で切り続けたひと、自分の居場所を自分で作ったひと──
本書主人公のモデルとなっていただいたカルーセル麻紀さんに持った第一印象は、書き終えた今もなにひとつ変わりません。 初めてお目にかかった際つよく感じたのは、パイオニアの孤独でした。
そのとき釧路湿原の話に寄せて交わしたやりとりをよく覚えています。 「アフリカに行ったとき、この景色どこかで見たことがあると思ったら、釧路湿原だったの」 「わたしは毎日釧路湿原を見ながら、サバンナってこんな感じなのかなと思っていました」
お互い、原風景はモノクロの荒野に沈む、そこだけくっきりと緋い夕日でした。
あの日、炭鉱と漁業とパルプ生産で賑わう街の片隅に生まれた少女が、終戦後にどんな人生を送ることになるのか、どうしても書いてみたくなりました。
釧路の街のことは、どこから太陽が昇りどこへ沈むのか、いつどんな花が咲くのか、雪の音も街のにおいも、冷たい風も、「カルーセル麻紀」の名が大きく世に出たときの騒ぎも、みな記憶にあります。
ほかの誰にも書かせたくなかった、というのが正直な気持ちでした。
問題は、芸歴五十年を超える彼女には山ほどインタビュー記事があるのだけれど、どんな赤裸々なインタビューでも語られなかったことを書かなければ、小説にはならないということでした。
長く芸能界で暮らしているひとに、小説を書くからといって思い出話をさせるのは何かが違う。思い出話ならば、麻紀さんが語ったほうが百倍面白いのです。
人生の修羅場をくぐり抜けてきたひとに思い切って頭を下げる際、恐怖感の隣にあったのは書き手の幸福感でした。 「カルーセル麻紀さんの、少女時代を書かせてください。今まで、どんなインタビューにも答えて来なかった部分を、想像で書かせてくださいませんか。虚構に宿る真実が見てみたくて小説を書いています」 「いいわよ」のあと麻紀さんからは「あたしをとことん汚く書いて」という注文がつきました。そのあとつくづく不思議そうに「あたしまだ生きてるのに、小説にするなんてあんた不思議な子ねえ」とも。
生きることの答えが、生きてそこにあるのだから、たどり着きたい── ひとつの時代を作り上げたひとは、無意識にひとの心を動かしてしまうようでした。
小説を書く者の欲望で、家族構成と登場人物、出来事のほとんどは虚構です。
この物語を最後まで引っ張ったのは、いつか麻紀さんが何気なくつぶやいたひとことでした。 「ちいさいときに弟が死んだの。でもちっとも悲しくなかった。母親がまたあたしのところに戻ってくると思ったから」
パイオニアの孤独は、物語を走らせるなによりの燃料でした。
新聞連載が中盤にさしかかった頃、いちど麻紀さんに訊ねたことがあります。 「ヒデ坊が書き手の想像を超えて前向きで、どんどん悲愴感から遠ざかってゆくのが不思議で仕方ないんですよ」
返ってきた答えは簡明率直。 「あんた、そんな暇なかったわよ」
小説「緋の河」執筆にあたり、カルーセル麻紀さん、そしてご家族や関係者のみなさん、マネージャーの宇治田武士さんにはひとかたならぬご協力をいただきました。小説家の我儘を見守り、ご理解いただけましたこと、ほんとうにありがとうございます。 執筆中は絶え間なく幸福でした。
連載中、毎日美しいイラストで支え続けてくれた赤津ミワコさん、新聞三社連合、新潮社文芸のみなさん、ありがとうございます。 関わってくださったすべてのみなさまへ、心から感謝申し上げます。
令和元年五月 桜木紫乃
ここが一番心に残る文次との本当の別れ
『流れた時間の長さを測るより、今をしっかり演じきることが大切だった。自分は、誰の庇護も必要とせず生きる方法を見つけてしまったのだ。ここに来てひとつくらい手に入らないものがあったところで、それがいったい何だというのか。 「お怪我、早く治りますように。同郷のひとりとして、これからも応援していますね」 「そちらこそお元気で。今日はお立ち寄りありがとうございました」 下げ慣れた頭、艶やかな髷に向かってちいさく手を振った。これからお互いが向かう場所のために、文次の拒絶は必要な手形だったと思うことにした。』