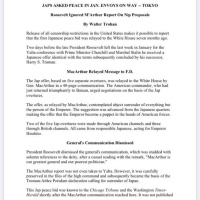1968年10月23日、日本武道館で政府主催の「明治百年記念式典」で『天皇陛下万歳』を発声した人物
以下、『歴史の十字路に立って 戦後七十年の回顧』(石原慎太郎、2015年6月Kindle版より)
「テンノー、ヘイカッ、バンザアーイッ!」
などなど、つまりは父祖の苦闘の歴史を重ね合わせてあの明治百年の行事を今また思い返してみると、日本人としての真っ当な主張を誰憚ることなく、しかし、けっして声高に叫ぶのではなくそれぞれの胸に深く刻むことの意味を、平成の今こそ取り戻さなければならぬという気が強くするのだが、明治という大いなる父祖の時代を思えば思うほど、私たちはそこから切り離されてはなるまいと思う。 さて明治百年の行事には、私は都合で少し遅れてしまい、国会議員の席としては後ろ側の野党議員たち、主に社会党の議員たちの席に座っていたものだった。 式典が進んでいき、最後に体育大学の学生たちによる立体的なマスゲームが行われ、その後、佐藤総理の音頭で日本国万歳が三唱されて式は終わった。やがて司会のNHKアナウンサーが、「天皇、皇后両陛下がご退席になります」と報せ、参加した全員がまた立ち上がって両陛下をお見送りした。 そして、あのことが起こった。それが起こった瞬間に、私だけではあるまい、出席していたほとんどがこの式典に実は何が一つだけ足りなかったかを知らされたと思う。 壇上から下手に降りられた両陛下が私たちの前の舞台下の床を横切って前へ進まれ、ちょうど舞台の真ん中にかかられた時、二階の正面から高く澄んだ声が、 「テンノー、ヘイカッ」 叫んでかかった。 その瞬間陛下はぴたと足を止め、心もちかがめられていた背をすっくと伸ばされ、はっきりと声に向かって立ち直されたのだった。そしてその陛下に向かって声は見事な間をとって、「バンザアーイッ!」と叫んだ。
次の瞬間、会場にいた者たちすべてが、実に自然に、晴れ晴れとその声に合わせて万歳を三唱していたものだった。私の周りにいた社会党の議員たちもまったく同じだった。そして誰よりも最前列にいた佐藤総理がなんとも嬉しそうな、満足しきった顔で高々と両手を掲げ万歳を絶叫していた。 あれは、つくづく見事な「天皇陛下万歳」だったと思う。あの席にいながらなお、あれに唱和出来なかった日本人がいたかも知れぬなどとはとても思えない。あれは単なる昭和天皇への言寿ではなしに、私たちを突然見舞った熱い回顧であり確認だった。それを唱えながら私たちは忘れかけていたものを突然思い出し、静かに、密かに熱狂していたものだった。 あの瞬間ただひたすら、 “ああ、かつて私たちはこうだった。なんだろうと、こういう連帯があったのだった” と誰しもがしみじみ感じ直していたに違いない。 あれはなんと言おう、国家や民族というものの実在への、瞬間的ではあったが狂おしいほど激しい再確認だったと思う。
あの瞬間の後、ある者は反省して、あの「万歳」のもとで多くの者たちが死に、歴史は歪んだ軌跡を辿っていったなどと思い直したかも知れない。 しかし何であろうと、私たちはあの瞬間、この戦後二十余年の推移の中でますます希薄になり、それを思うことが禁忌にまでなりかねないある種の分裂ある種の混乱の中で、失いかけていたものの実感を、瞬時とはいえ取り戻していたのだと思う。 そして、あの瞬間を平成の今思い直してみると、あの時感知し確認させられたものがさらにますます消滅していこうとしている予感に苛まれるのは果たして私一人だろうか。 あの時二階席からかかった「天皇陛下っ」の声に、見事というか本能的にというか、誰よりも早くそれを聞き届けて立ち止まり、すっくと立ち向かわれた昭和天皇はもはや言寿を受ける天皇個人ではなしに、正しく私たちの国柄、歴史の象徴たり得ていたと思う。
「末次一郎氏が何も答えなかったことの意味」
後年私は思いがけぬ形であの時の見事な「天皇陛下万歳」の秘密について知らされた。佐藤総理が引退してしまってからのことだ。
ある縁で知り合った青年運動の指導者末次一郎氏と、この国が失いつつあるもの、いきなり愛国心とか天皇とかいったことではなしに、戦後蔓延しつつあるさまざまなアパシー(無関心、無感動)に抗して取り戻さなくてはならぬもの一般について話し合っていた時、私は自分の今の思いのよすがとして何年か前の明治百年の記念式典の折の、思いがけなくも唱和した天皇陛下万歳の印象について話した。 誰が行ったのか未だに知れぬ、あの見事な「天皇陛下万歳」に凝縮象徴されていたものについて、そろそろ本気で考え直さないと、我々は致命的な喪失を味わわされるのではないか。それにしてもあの見事な万歳を発声したのは一体誰だったのか。陛下も見事にそれに応えられたものだが、あの絶妙なタイミングといい、声の張りとその抑揚の素晴らしさは、と言ったら、目の前の末次氏が、「いやあっ」と頭をかいて、「実はあの声の主は僕なんだよ」と告白したのだった。
「あの式典に若者たちの動員も含めていろいろ協力しろと佐藤さんに言われてね、それに異存はないが、ならば一つ条件があります。式の段取りの中に天皇陛下への万歳がありませんが、どこかで必ず入れてください。
そう言ったら、佐藤さんが暫く考えて、いや、それを事前にプログラムに載せると必ずつまらん文句がつく、それが話題になるだけでも陛下にはご迷惑をかけることになるからな、とね。さすが臣吉田茂の弟子だと思った。 そしたら、それは君がやれ、是非やってくれ。誰かが番外でやったなら、文句のつけようもあるまい。万が一問題になったら、その時は必ず俺が責任をとるからどうか頼む、ということになっちまったのよ」
他のすべての手配が済んだ後、残された日々に、プログラムを眺めながら、いつにしようかと考えに考えたがわからない。ならばその日その場の雰囲気を眺めて、現場で決心して行おうと決めたという。 「だから当日はもう他の事はまったく頭に入らず、万歳のタイミングだけを考えて式を眺めていたな。しかし式典はどんどん進められていく。これでもしし損なったら、佐藤さんへの面子だけじゃなしに、何かもっと大きなものへの言い訳が立たないと思ったね。失敗したらこれは切腹ものだなと思いだしたら汗が流れてきたよ」 そして、あの絶妙なタイミングとなったのだった。 「僕の第一声に陛下がぴたっと足を止め、二階のこちらに向き直ってくださった瞬間には、感動というより、ああこれで死んでもいいなと思った」
言うと末次氏は静かに破顔してみせた。「あれはたぶん日本で最後の本物の天皇陛下万歳でしたよね。今になればなるほどそんな気がしますよ」 私は言ったが、氏はそれには黙ったまま何も答えはしなかった。あれもはるか昭和の時代の話である。末次氏は平成十三年に身罷ったが、今になってみればなおさら、あの時末次氏が何も答えなかった意味がこの国の現状に照らして察せられる。
末次 一郎(すえつぐ いちろう、1922年(大正11年)10月1日 - 2001年(平成13年)7月11日)は、安全保障問題研究会の主宰者。沖縄返還の功労者として知られ、晩年は日ソ専門家会議を主催して北方領土返還運動にも取り組み、「ミスター北方領土」の異名をとった。中曽根康弘首相ら歴代政府首相・首脳のアドバイザーとしても知られる。
経歴
佐賀県出身。佐賀商業学校・豊橋第一陸軍予備士官学校・陸軍中野学校二俣分校卒
経歴
佐賀県出身。佐賀商業学校・豊橋第一陸軍予備士官学校・陸軍中野学校二俣分校卒