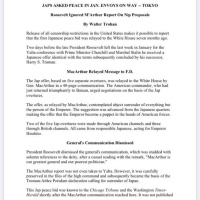『敬太郎は森本のこの言葉を、失意のようにもまた得意のようにも聞いた。 そうして腹の中で、なるほど常調以上の変った生活は、普通の学士などには送れないかも知れないと考えた。』 夏目漱石 彼岸過迄ヨリ
『この、一年有余の長い(山本周五郎の)取材旅行が、昭和三十五年の『青べか物語』となって結実することを多くの人が知っている。失意の時ではなく、作家の幸福とはこれだろうと私などは思う。したたかなものを感じないわけにはいかない。山口瞳(やまぐち ひとみ、本名同じ、1926年(大正15年)11月3日 - 1995年(平成7年)8月30日)『酔いどれ紀行』ヨリ
池波正太郎も自分文体が硬すぎると言って、歴史上の長谷川平蔵を発見してから10年寝かしたと書いていた。
次は映画で見ているが、『青べか物語』から大正昭和をのぞいてみようか。

『老人は舟べりや舳先を 、大事そうに撫でたり叩いたりした 。私はそれを眺めながら 、老人が舟をひき起こすときのすばやい動作には二つの意図があった 、ということに気づいた 。一つは私を捉えること 、他の一つは去年の枯れ草が覗いていた舟底の穴を私から隠そうとしたのだ 、ということである 。 ― ―もう一つ 、これを書いては人が信じなくなるだろうと思って 、書かないことにするつもりであるが 、老人が舳先を掴んでゆすぶったとき 、舳先の尖ったところが折れてしまった 。すると老人は自分の手にある折れた舳先の 、折れたところへ唾をつけて 、元の部分と合わせ 、そこを片手で押えたまま 、いっそう高ごえになって喚きたてるのであった 。事実はこのとおりだったのだが 、これを文字にすると 、おそらく人は筆者が調子づいてふざけていると思うにちがいない 。 「事実を書く 」ということがいかに困難なしごとであるかは 、こんな些細な点でも思い知らされるのである 。 「よし 、そんなら三と五十にすべえ 」と老人は云った 、 「これ以上は鐚一文負からねえだ 、三と五十 、これで話はきまっただ 」』
事実であるから、浦安と言うのが憚られるらしい。まんまと老人の計略にはまる先生。ロシナンテ記号論が出てくる。悪ガキには効力なし。ここの先の浜百万坪が夢の国ディズニーランドに変貌する。生きていれば山本周五郎はどれほど慷慨したことだろう。
山本 周五郎(やまもと しゅうごろう、1903年(明治36年)6月22日 - 1967年(昭和42年)2月14日)は、日本の小説家。本名、清水 三十六(しみず さとむ)。
『幸山船長は船長の席にあがって腰を掛け 、両手で舵輪を握って 、ちょっと左右へ廻してみた 。それから 、すぐ右にある打金の紐を引いて 、ちん 、と鳴らし 、ちんちん 、と鳴らし 、一つ鳴らして次にすぐ二つ鳴らしてみた 。 「ゴ ースタン 、これが合図だっただよ 」と船長は云った 、 「永島へ船が近くなると 、こう鳴らしてゴ ースタンとどなる 、それからスロ ーアヘ ーとどなってこう鳴らすだ 、 ― ―おらが二十九号の船長になってからだがね 」』
まるでニューギニアの裸族を取材するかのように、活写された一時代前を残す浦安のこういう描写は、人間の吐く息まで取材スケッチする徹底があってできること。浅田次郎ならこの数行だけで一冊できる含蓄がある。今さら私が言うべきことでは無いが、どれも名作のスケッチである。なぜ引退した老年の幸山船長が周五郎に語るのか。泣けてくる。
『 文科大学へ行って、ここで一番人格の高い教授は誰だと聞いたら、百人の学生が九十人までは、数ある日本の教授の名を口にする前に、まずフォン・ケーベルと答えるだろう。かほどに多くの学生から尊敬される先生は、日本の学生に対して終始渝らざる興味を抱いて、十八年の長い間哲学の講義を続けている。先生が疾くに索寞たる日本を去るべくして、いまだに去らないのは、実にこの愛すべき学生あるがためである。』夏目漱石 ケーベル先生ヨリ
6歳より母方の祖母にピアノを学び1867年にモスクワ音楽院へ入学、ピョートル・チャイコフスキーとニコライ・ルビンシテインとカール・クリントヴォルトに師事し1872年に卒業した。しかし内気さ故に演奏家の道を断念し、音楽院ピアノ科同級の親友ミハイル・ダヴィドフ(ロシア語版)[4]とともに1873年からドイツのイェーナ大学で博物学を学んだ。エルンスト・ヘッケルの講義を熱心に聞いたが、のち哲学に転じ、ルドルフ・クリストフ・オイケン、カール・フォルトラーゲ(英語版)、オットー・プフライデラー(英語版)、フリッツ・シュルツェ(英語版)らに師事。クーノ・フィッシャーに学ぶためにハイデルベルク大学に移り、1881年にアルトゥル・ショーペンハウアーに関する論文により博士号を得た後、ベルリン大学、ハイデルベルク大学、ミュンヘン大学で音楽史と音楽美学を講じた[5][6]。
その後、友人のエドゥアルト・フォン・ハルトマンの勧めに従って日本へ渡り、1893年(明治26年)6月11日に神戸に到着した[7]。同年から1914年(大正3年)まで21年間東京帝国大学に在職し、イマヌエル・カントなどのドイツ哲学を中心に、哲学史、ギリシア哲学など西洋古典学も教えた。美学・美術史も、ケーベルが初めて講義を行った。学生たちからは「ケーベル先生」と呼ばれ敬愛された。
1898年5月、東京音楽学校(現・東京藝術大学)に出講し、ピアノと音楽史を教えていた(1909年9月まで)。
1903年、日本におけるオペラの初演の際には、指揮を担当したノエル・ペリ(フランス語版)とともに学生を指導し、ピアノ伴奏を行った。クリストフ・ヴィリバルト・グルック作曲「オルフォイス(オルフェオとエウリディーチェ)」が上演されたが、学生の自主公演だったためオーケストラは使えなかった。この際に訳詩を担当したのが教え子の一人である石倉小三郎その他のチーム、背景その他のデザインを担当したのが東京美術学校教授の和田英作であり、上演資金を農学者・実業家の渡部朔が提供、弟で音楽学校学生の渡部康三、柴田環(エウリディーチェ役、後の三浦環)、鈴木乃婦、外山国彦、東儀哲三郎、山本正夫などが出演した[8][9]。
室内楽奏者としては、当初、ルドルフ・ディットリヒのヴァイオリンとの合奏が最高水準と言われた。
ディットリヒの帰国後、1899(明治31)年に、横浜でアウグスト・ユンケルのヴァイオリンを聴いて彼を東京音楽学校に推挙する。ユンケルはベルリン・フィルやシカゴ交響楽団の要職を歴任するも、風来坊的な性格から長続きせず、日本で役不足の仕事をしていたが、ケーベルに認められて日本楽壇を指導し、太平洋戦争中に生涯を終えるまで日本に永住した。ケーベルとユンケルの合奏も当時の日本で最先端の音楽であった。
1904年(明治37年)の日露戦争開戦の折にはロシアへの帰国を拒否したが[10]、1914年になって退職し、ミュンヘンに戻る計画を立てていた。しかし1914年8月12日に横浜から船に乗り込む直前に第一次世界大戦が勃発し、帰国の機会を逸した。その後は1923年(大正12年)に死去するまで、友人のロシア総領事アルトゥール・ヴィーリム(ロシア語版)の横浜の官邸の一室に暮らした[11]。墓地は雑司ヶ谷霊園にあるが[12][13]、ロシア正教からカトリックに改宗して[14]生涯を終えた。
失意泰然という言葉があるが、<失意のようにもまた得意のようにも>というのは作家のある種の幸福状態だろう。山口瞳は山本周五郎のエピソードを切り抜いてこう表現している。
『この、一年有余の長い(山本周五郎の)取材旅行が、昭和三十五年の『青べか物語』となって結実することを多くの人が知っている。失意の時ではなく、作家の幸福とはこれだろうと私などは思う。したたかなものを感じないわけにはいかない。山口瞳(やまぐち ひとみ、本名同じ、1926年(大正15年)11月3日 - 1995年(平成7年)8月30日)『酔いどれ紀行』ヨリ
池波正太郎も自分文体が硬すぎると言って、歴史上の長谷川平蔵を発見してから10年寝かしたと書いていた。
次は映画で見ているが、『青べか物語』から大正昭和をのぞいてみようか。

『老人は舟べりや舳先を 、大事そうに撫でたり叩いたりした 。私はそれを眺めながら 、老人が舟をひき起こすときのすばやい動作には二つの意図があった 、ということに気づいた 。一つは私を捉えること 、他の一つは去年の枯れ草が覗いていた舟底の穴を私から隠そうとしたのだ 、ということである 。 ― ―もう一つ 、これを書いては人が信じなくなるだろうと思って 、書かないことにするつもりであるが 、老人が舳先を掴んでゆすぶったとき 、舳先の尖ったところが折れてしまった 。すると老人は自分の手にある折れた舳先の 、折れたところへ唾をつけて 、元の部分と合わせ 、そこを片手で押えたまま 、いっそう高ごえになって喚きたてるのであった 。事実はこのとおりだったのだが 、これを文字にすると 、おそらく人は筆者が調子づいてふざけていると思うにちがいない 。 「事実を書く 」ということがいかに困難なしごとであるかは 、こんな些細な点でも思い知らされるのである 。 「よし 、そんなら三と五十にすべえ 」と老人は云った 、 「これ以上は鐚一文負からねえだ 、三と五十 、これで話はきまっただ 」』
事実であるから、浦安と言うのが憚られるらしい。まんまと老人の計略にはまる先生。ロシナンテ記号論が出てくる。悪ガキには効力なし。ここの先の浜百万坪が夢の国ディズニーランドに変貌する。生きていれば山本周五郎はどれほど慷慨したことだろう。
山本 周五郎(やまもと しゅうごろう、1903年(明治36年)6月22日 - 1967年(昭和42年)2月14日)は、日本の小説家。本名、清水 三十六(しみず さとむ)。
『幸山船長は船長の席にあがって腰を掛け 、両手で舵輪を握って 、ちょっと左右へ廻してみた 。それから 、すぐ右にある打金の紐を引いて 、ちん 、と鳴らし 、ちんちん 、と鳴らし 、一つ鳴らして次にすぐ二つ鳴らしてみた 。 「ゴ ースタン 、これが合図だっただよ 」と船長は云った 、 「永島へ船が近くなると 、こう鳴らしてゴ ースタンとどなる 、それからスロ ーアヘ ーとどなってこう鳴らすだ 、 ― ―おらが二十九号の船長になってからだがね 」』
まるでニューギニアの裸族を取材するかのように、活写された一時代前を残す浦安のこういう描写は、人間の吐く息まで取材スケッチする徹底があってできること。浅田次郎ならこの数行だけで一冊できる含蓄がある。今さら私が言うべきことでは無いが、どれも名作のスケッチである。なぜ引退した老年の幸山船長が周五郎に語るのか。泣けてくる。