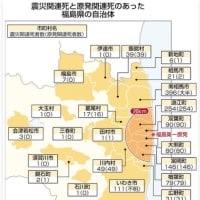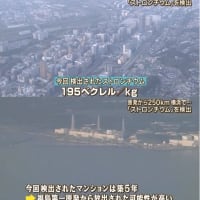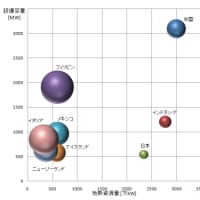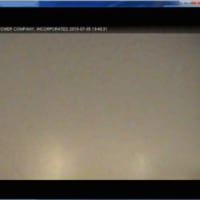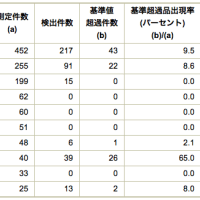最近言葉の語源とか成り立ちについて興味を持ち様々な本を読んでいるのですが、特に働くという言葉の意味について引っかかることがあり、広辞苑で調べてみたら、〈①うごく。②精神が活動する。③精出して仕事をする。④他人のために奔走する。⑤効果をあらわす。作用する。〉のようになっていました。僕の尊敬する斎藤一人さんは自分が働けば「はたの人が楽ができる」ということが働くという言葉の語源です、とある本で述べています。ずーっと本気で自分は斎藤一人さんのかなりの信者としていろいろな著書を読ませてもらっているのですが、最近読んだ韓国の金容雲さんという方が『日本語の正体」三五館発行 という本の中で「働き」は『畑』が動詞化したもので、初め『働く』は畑仕事を意味していたけれども後世になって広い意味で一般の仕事について使われるようになった、と述べられています。
ということは、冷静に考えてみて、斎藤さんと金さんとの間では働くことの意味がかなり違っていてどちらが正しいか、という判断だったら金さんのほうに軍配が上がるのではないでしょうか。斎藤さん一流の半分冗談が活字になっているというのはちょっと問題があるかもしれませんね。斎藤さんの本は、人に安心してもらったり、人の心を明るく勇気づけてくれる、そういう本だと割り切って読むのもいいかもしれないですね。
真夏で頭も十分回転しないし、いまいち働く意欲が増さない自分がちょっと情けないですが、アート業界もそろそろ夏休みになるみたいです。僕は夏休みもなるべく休まないで、銀座で「働く」ことの意味についてぼんやり考える日々ですかね。


僕の「働く」というイメージはこんな感じです。(ミレーの落ち穂拾い)
102853 働くことってどういうことなのか?
働くと仕事という漢字の語源を調べてみました。そこから働くってなんだろう?にアプローチしてみました。
■「働く」とは、「人が動く、人を動かす、人のために動く」と書きます。
「働」は「人」+「動=(重(=人+東+土)+力)」と分解されるようですね。
・「働」くの「動」の「重」は「人」と「東」と「土」で出来ているらしいです。「東」は、突き抜けるという意味があるそうです。「人」が「地面=土」をつきぬくような様を示し、「重」いという漢字になりました。そこに「力」を加えて、「人」の「足=地面=土」がうごいていく様を「動」として、「動」くという漢字が出来たそうです。
・何が「動く」か?というと「人」が「動く」のです。それが、「働く」という意味だそうです。「働」くという字は、国字で、国字とは、日本で作られた漢字です。「畑」や「辻」「峠」などが日本産の漢字です。二文字以上の漢字の字形・意味を合せて作られた会意文字なので上記の言葉の意味も日本人の感覚を示しているようです。
■仕事は「事に仕える」と書きます。
・「仕」は「人」+「士」に区分できるようです。
「士」とは男子。学問と道徳を修めた男子と言われるが、「士」はもともと、地面からまっすぐ十字に立つその人の様を表している。大切な「人」の横に、まっすぐ十字にたってささえている「士」の様を「仕」えると表現しています。
・「事」は、占い棒の入った筒を手で持っている様で、信仰催事を行う様を示します。
*この意味からして、「仕事」の語源をたどると、大切な催事に携わる人々を支えること=携わることのようですね。
近藤文人 ( 41 東京 建築士 ) 05/12/19 PM09 の記事、引用しました。
ということは、冷静に考えてみて、斎藤さんと金さんとの間では働くことの意味がかなり違っていてどちらが正しいか、という判断だったら金さんのほうに軍配が上がるのではないでしょうか。斎藤さん一流の半分冗談が活字になっているというのはちょっと問題があるかもしれませんね。斎藤さんの本は、人に安心してもらったり、人の心を明るく勇気づけてくれる、そういう本だと割り切って読むのもいいかもしれないですね。
真夏で頭も十分回転しないし、いまいち働く意欲が増さない自分がちょっと情けないですが、アート業界もそろそろ夏休みになるみたいです。僕は夏休みもなるべく休まないで、銀座で「働く」ことの意味についてぼんやり考える日々ですかね。


僕の「働く」というイメージはこんな感じです。(ミレーの落ち穂拾い)
102853 働くことってどういうことなのか?
働くと仕事という漢字の語源を調べてみました。そこから働くってなんだろう?にアプローチしてみました。
■「働く」とは、「人が動く、人を動かす、人のために動く」と書きます。
「働」は「人」+「動=(重(=人+東+土)+力)」と分解されるようですね。
・「働」くの「動」の「重」は「人」と「東」と「土」で出来ているらしいです。「東」は、突き抜けるという意味があるそうです。「人」が「地面=土」をつきぬくような様を示し、「重」いという漢字になりました。そこに「力」を加えて、「人」の「足=地面=土」がうごいていく様を「動」として、「動」くという漢字が出来たそうです。
・何が「動く」か?というと「人」が「動く」のです。それが、「働く」という意味だそうです。「働」くという字は、国字で、国字とは、日本で作られた漢字です。「畑」や「辻」「峠」などが日本産の漢字です。二文字以上の漢字の字形・意味を合せて作られた会意文字なので上記の言葉の意味も日本人の感覚を示しているようです。
■仕事は「事に仕える」と書きます。
・「仕」は「人」+「士」に区分できるようです。
「士」とは男子。学問と道徳を修めた男子と言われるが、「士」はもともと、地面からまっすぐ十字に立つその人の様を表している。大切な「人」の横に、まっすぐ十字にたってささえている「士」の様を「仕」えると表現しています。
・「事」は、占い棒の入った筒を手で持っている様で、信仰催事を行う様を示します。
*この意味からして、「仕事」の語源をたどると、大切な催事に携わる人々を支えること=携わることのようですね。
近藤文人 ( 41 東京 建築士 ) 05/12/19 PM09 の記事、引用しました。