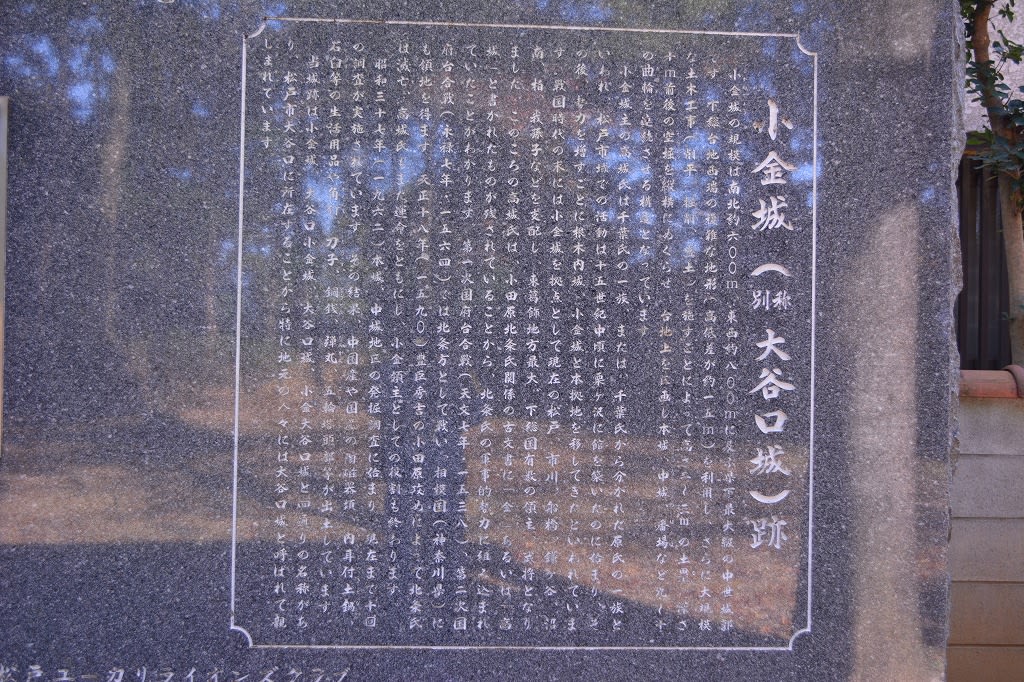滋賀 湖東三山百済寺 紅葉 大阪夜景
琵琶湖東岸に湖東三山があります。
北から西明寺、金剛輪寺、そして百済寺(ひゃくさいじ)。いずれも天台寺院です。
これに禅宗(臨済宗)の永源寺を連ねて紅葉を狩りまくる人出が多いですね。
途中、不謹慎。 運転席からパチリ・・・ベタどまりです。
交通情報はここまでなかったのに・・・ ちなみに道の先のとんがりが近江富士、新幹線からも良く見えます。

百済寺は、聖徳太子の創建とも・・・すると百済はずばり”くだら”でしょうね。
ごったがえすといっても人は京都ほどのことはありません。しかし、車はなかなか停められません。
ともあれ山門。

百済寺には石段に沿って多数のテラス状平面があります。
完全に人工的な”削平”です。
その各段にかつて数多の堂宇がひしめいていたとか・・・
なにも残っていないのは・・・そう、あの”うつけ殿”が完全破壊されたとか・・・おそろしい人だね~(^^;
そんな過去など置いといて・・二人して来し方を語れるというのは美しいことだね。





庭園を拝見しましょうか。



紅葉は障子によく映えます。










今年もいい色になりました。



ここからの眺めは天下を眺めるものだそうです。
超巨大城郭観音寺城、その琵琶湖側ふもとに安土城・・天下・・・ふむふむ・・


本堂です。



生命を感じますね。


ご本尊は十一面観音です。

”かえるまた”にほのかに彩色が残ります。



鐘の音は仏の声、多くの人が鐘をついて祈りを捧げます。
私は並びません。
”世界が平和でありますように” ”家族が健康でありますように” そこまでなら並んでもいいんだけども・・・
やっぱ祈っちゃうもんね。 ”◯億円当たりますように!” ご~ん(^^;

弥勒菩薩。 ご表情が・・・





今はあちこちにあって珍しくない・・とご参拝のご婦人がおっしゃってました。 あんたのために植えたんじゃ・・・また要らんことを・・




桐の意味はなんでしょうね? 経の巻にお止まりのご婦人も早く産卵しないと・・名前はチサ◯というんじゃ・・・時の人だもんね。



”あんたなにやってんのよ~” ということでもないような・・


秋が深いですね。
好天が続きました。新幹線で隣だった横浜からのお嬢さん、今の時期京都を訪れる何万、何十万という中の1人に過ぎないんだろうけど楽しめただろうね。きっと・・
帰りの渋滞が心配で太郎坊へは遠慮しました。
黒丸パーキングから正面に見えているんですね。

参道からは完全にピラミッド型に見えます。
ローマにはうそつきが手を入れるとはさまれてしまう顔があるようですが、ここはもっとすごいです。
狭い岩の割れ目を抜けて参拝するのですが、うそつきが通るとその割れ目が閉まってしまうのだとか・・・
・・・通っちゃいかんね・・
帰ってから大阪の夜景を撮りに行ってみます。
cx3 もう売ってないカメラですがお気に入りです。
腕も棚にあげてだけど、やはり光が少ないときには表現力足りないかな・・・



もうクリスマスですね。