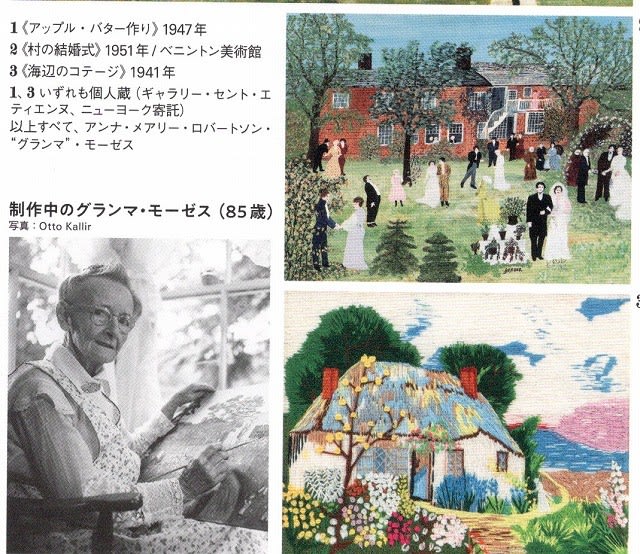先日、おべべを着せた、出来上がりの辰をお見せいたしましたが、20日と、今日22日がその木目込みの講習会でした。15年を超える長寿人気講座です。
木目込みを始めた頃は、ちゃんとした資格を持った先生をお招きしておりましたが、ご老人の介護が始まり引き受けられないと断られ、結局、コミュニティ―委員で研究しながら、教えようということになりました。一番年長者の私、委員はすでに退いておりますが頼まれて、烏滸がましくもしゃしゃり出て、2日間講師を務めてまいりました。中一日、家庭での作業を挟んで、今日、大体の方が、仕上げることが出来ました。
自分の体力の衰えをつくづく感じました。一日3時間、立ちん坊で、教えながら机間巡視すると正直なところ座り込みたくなります。まあどうにかこなしましたが。
講座を受講なさる方の、ちょっとした言動に、びっくりし、表には現しませんでしたが、腹を立ててしまいました。修行が足りません。
1日目の9時始まりの5分ほど前です。私の隣に席を取った方が、何の挨拶もなく
「これどうするのですか。早く教えてほしいのですけど・・・」
「はい、今時間が来ましたら始めます。もう5分足らずお待ちください」
「早くやりたいのですが、始めましょうよ」
「区民センターの方のご挨拶もありますし、もう少し待ってください」
「楽しみに来たのです。早くやりたいのですよ」
「ご出席ありがとうございますが、30人近くの方にお教えするのです。初めの基本の説明などは、皆さんで聴いてほしいのです。お待ちくださいませんか」
「せっかく早く来たのに・・・」
修行の足りないおせっちゃん、とうとう厳しく言いました。「お一人別行動でなさりたいのなら、ご自分で始めてくださっていいですよ。どうぞ」
唾を3回でしたかしら、それ以上はぐっと黙りましたが、それでもいい気分での発車オーライの気分は壊れました。
爆発する前に、事務長さんのご挨拶が始まり、私と他の委員の方の紹介があり、委員会で話し合った順序で、授業がスタートしました。その方も、作業に打ち込んでいらっしゃるようで、ほっとしましたが。
こうした、昭和時代の化石人間には受け入れられない言動があります。私の腹立ち、修行の足りない私が悪いのでしょうか。今の時代、人より一歩速くやること、これが大事なことなのでしょうか。
まあ兎に角皆さん、ご自分の作品にご満足のご様子。良かった良かった。
留守番の夫に昼食を作り、食べていると、玄関でピンポ~ン。出て見るとセンターの方が、私の忘れ物、ブレザーを持って来てくださっていました。ああ~。