先日、台所片づけをやり始め、棚の上面がびっくりするほど汚れていることに気が付いたことはお話しました。あぶなっかしい体勢に気を配りながら整理から始めました。それほどだらしなくしているとは思っていませんでしたが、奥の方にはあることも忘れているものがあり、廃棄処分に。
その一つに、すり鉢。
ああ、こんなものもあったか。20年ほども前になったでしょうか、お茶のお稽古をしてもらっていた先生から、「すり胡麻」というものがありますよ。煎って擂り潰した状態のものです。私はこれを発見してから、ホーレンソウの胡麻和えが苦にならなくなりました、と教えていただきました。すぐにその知識は取り込みました。
それまでは、小さなミルクパンで煎って、擂鉢へ、小さな擂粉木でゴリゴリ、結構手間がかかったものでした。「摺りごま」が主婦の味方として登場してから、擂鉢は棚の奥へ置き去りにされ、埃だらけで放られてていたのでした。
そんな自分の記憶に重なって、実家にいた幼い時から、嫁ぐまでの思い出も湧いてきました。母の時代は、まず生産から始まります。畑で栽培して採取していたのです。それを見ていた私は、子育て中の時、旅先で、胡麻栽培の畑を見た時、こどもたちに、「これは胡麻の花」と教えて株をあげたことがありました。
ゴマを煎るのは「ほうろく」という、素焼きのフライパン型をしたものがありました。母は「ゴマはすぐに焦げるから、三粒跳ねたらもう火を止めてね」と教えていました。
煎れたら、擂鉢へ。擂粉木も大家族だったわが家のはかなり大きいものでした。母がごりごり始めると出番が来ます。両手で擂鉢を押さえるのです。妹のらい太が、負けまいと手を出します。お互い有利に押さえようと肘を張って相手をけん制して争うのでした。今、その幼子二人が80越えの婆さん二人になっています。
もう擂鉢を使うこともあるまいと、不燃ごみに出すことにしました。台所の隅で、忘れられていたがために、辛うじて命を保っていたものを、見つけられるや廃棄、ちょっとかわいそうですね。
まあ、この世の中の移り変わりというか進歩というか、速いのよ。ネットだ、リモートだ、スマホだと、人間の古物も見捨てられそうなこと多多。同類ですよ。
、


















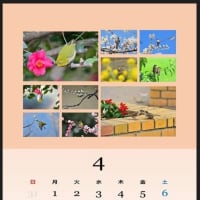


すりばち一つでここまで話せますか!
胡麻の畑には、太った6,7cmもある緑色のウジ虫がいたんだよねえ。蛾になるのだとか。嫌だった。
ネタ探しに苦労しながらも、15年間毎日のように文を書いていると、少しは進歩するのでしょうか。
学生時代には、同じ研究室の男どもに「1+1=2」という文だねえと貶された悪文家でしたからねえ。
土を彫れば芋虫が転がり出ていましたね。でもあれは都会ではデパートで売られるカブトムシの幼虫ですからね。
思い切りましたね。
(大きなすり鉢を実家から持って来て、使わなくなったので玄関に飾ってあります。
いい感じな風情をかもしだしています)