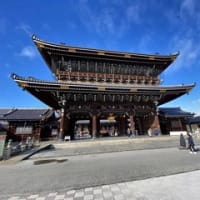名古屋市博物館 名古屋開府400年記念特別展「変革のとき 桃山」
「尾張名古屋400年の礎となった桃山時代におきた変革を、三英傑の城郭や御殿、漆器、茶陶によってたどります。幻の城である聚楽第(じゅらくだい)を描いた貴重な屏風や、高台寺蒔絵の優品、桃山茶陶の名碗が一堂に会します。」(公式解説より)との事で前期と後期で展示替えがあり2度見に行きましたが、個人的には後期が良かったです。
楽市楽座制札
重文。織田信長が加納の楽市場に発給した制札。有名な楽市楽座政策の資料だがかなり限定的なものだったらしい。
長篠合戦図屏風(犬山城白帝文庫)
織田・徳川連合と武田軍の争いを描いた作品。信長・秀吉・家康の三英傑が描かれている。
織田信長所用 白地紗綾形雲文綸子陣羽織
熱田の西加藤家に伝わる。信長より拝領の品。
豊臣秀吉所用 茶地唐草模様ビロードマント
茶のビロードに金糸で模様を刺繍している。ポルトガルもしくは中国製。
輝元公御上洛日記
この日記は毛利輝元が天正16年初上洛の際の旅日記で家臣が記したもの。失われた秀吉の城である聚楽第や大坂城に出仕した際の記述がある。
大坂冬の陣図屏風(東京国立博物館)
六曲一双の屏風だが元は未表装で大正14年に屏風に仕立てられた。粉本で完成品は見つかっていない。徳川家康や秀忠本陣に徳川方の軍勢、大阪城内の豊臣秀頼に淀殿、真田幸村が築いた真田丸が描かれている。
醍醐花見図屏風(国立歴史民俗博物館)
慶長3年3月15日に醍醐寺にて催された豊臣秀吉主催の花見。盛大に行われたこの宴の5ヵ月後に秀吉は亡くなっている。描かれた秀吉は老いの色が強く出ており、まさに朽ちる巨木の最後の一花といえる。
書籍でもよく見る作品ですが、初めて本物を見ました。思ったより人物が大きく描かれていますね。
聚楽第図屏風(三井記念美術館)
聚楽第がまだ存在していた頃に描かれた作品だそうです。6曲1隻の作品で御殿や天守が描かれています。
洛中洛外図屏風(尼崎市教育委員会)
こちらも聚楽第が描かれています。しかしながら同時代には存在しない二条城まで描かれています。
洛中洛外図屏風(個人)
八曲一隻の作品で伏見城が詳細に描かれています。1592年に建設された最初の伏見城は地震で倒壊。この屏風に描かれている城は1597年再建された二代目だそうです。