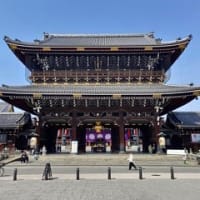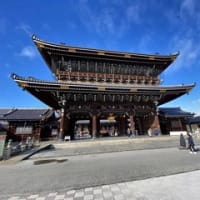新潟県立歴史博物館
2000年開館。常設展示では新潟県の歴史や縄文人の世界や文化を紹介しています。

夏季企画展「越後の大名」
期間:7月30日(土)~9月11日(日)
「慶長3年(1598)に上杉氏が会津に移封した後しばらくして、越後は「小藩分立」の時代となりました。江戸時代の越後を支配した大名家やその変遷などをゆかりの資料から紹介します。」

堀直寄寿像
直寄が還暦のときの姿を描いたもの。
堀直寄は直江兼続・小早川隆景と共に天下の三陪臣と呼ばれた堀直政の子で越後で長岡藩・村上藩主を務めた。
堀直寄所用 銀箔押鯰尾形兜
宝仙寺所蔵。小田原城で観た兜とほぼ同形のもので、こちらが若干古いものであるらしい。直寄の兜は古くから有名であったらしく「銀の鯰尾の甲」として記録が残る。
紅糸釘抜紋柄威二枚胴具足
欧州産の輸入兜で製作された南蛮兜、胸板や脇板には唐獅子の金蒔絵が描かれ胴と佩楯には白糸で釘抜紋を表す。
所用者は不明ながら釘抜紋から直政・直寄等の堀一族が用いたと推定されています。
村上頼勝 肖像画
頼勝は元丹羽長秀の家臣。長秀死後は越前北庄に代わって入った堀秀政の与力大名となります。1598年堀秀政の子秀治が越後へ転封になるとそれに従い村上城主となります。
溝口秀勝 肖像画
秀勝も村上頼勝と同じく丹羽長秀家臣から堀氏与力大名となり越後入国時には新発田城主となります。よく似た経歴ですが村上氏が2代改易になったの比べて溝口氏は1598年の入国より幕末まで12代にわたって新発田藩主として継続しています。これは改易・転封が多い越後国の藩主では唯一だそうです。
溝口宣勝所用 紫糸縅甲冑
兜に家紋の掻摺菱の前立。この甲冑は初陣の際に母方の父である長井源七郎から贈られた。
市橋長勝所用 伊予札腰取二枚胴具足
金箔押しの烏帽子形兜に二枚貝の脇立が付く。この具足は長勝が関ヶ原合戦で着用したものと伝わっているそう。
長勝は信長・秀吉に仕え関ヶ原合戦では東軍についた。大坂の陣での戦功により越後三条藩主となる。
榊原康政所用 陣羽織
長篠の合戦で康政が着用したと伝わるもので背中に榊原家紋である源氏車があしらわれています。
康政の子孫である榊原政永が1741年に越後国高田藩主となり以降幕末まで続きます。
牧野忠成木像
牧野家の菩提寺である長岡市の栄涼寺にある木像。
牧野忠成は徳川家家臣。大坂の陣の戦功により越後国長峰藩主となり1618年長岡へ加増のうえ転封となります。
井伊直政所用 孔雀尾具足陣羽織
全体に孔雀の尾羽を縫いつけた陣羽織。本能寺の変の際、堺にいた徳川家康と家臣は苦難の末三河に帰還しています。この陣羽織は帰還に尽力した功により直政が家康より拝領したもので、その後直政の嫡男直継に贈られた。
与板藩井伊家はその井伊直継を祖とし1706年に与板藩主となり10代170年続きます。
内藤信成所用 六十間筋兜
内藤信成所用 頬当
頬当は徳川家康より拝領の品と伝わる。
内藤信成の子孫である内藤弌信が1720年に駿河田中より越後村上に移封され以後幕末まで9代150年藩主として統治した。
その他各藩の絵図や領地目録等の展示がありました。
沢山の藩に分かれていた越後なので、新潟県中(県外も)から資料を集めたのは大変だっと思われます。関係者的には上杉家がそのまま統治してれば楽だったのにw、って感じでしょうか。
ともあれ県(旧国)単位での展示というアプローチは藩が分立していた他県でも見てみたいと思わせる手法でした。
次の場所へ
大移動!