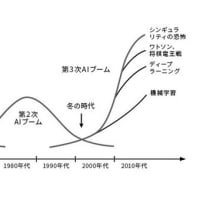「千年に1度」の巨大地震はどのようにして起きたのか――。2011年に未曽有の被害をもたらした東日本大震災の発生メカニズムを探る国際共同プロジェクトが9月に始まった。
海洋研究開発機構(JAMSTEC)の地球深部探査船「ちきゅう」で震源域の海底を掘削調査し、採取した試料や得られたデータから、12年前の前回調査で残った巨大地震の謎に迫る。

24年9月、宮城県沖約200キロメートルの調査地点を目指して、ちきゅうが清水港(静岡市)を出港した。
調査航海は日米欧が主導する「国際深海科学掘削計画(IODP)」の一環で、世界10カ国から地震学や地質学など計56人の研究者が参加する。12月20日までの3カ月超に及ぶ一大プロジェクトだ。
今回の航海は震災翌年の12年に同じ海域で行われた掘削調査の「続編」にあたる。
最大の目的は、巨大地震と津波を起こした断層が震災直後からどのように変化したのかを確かめることにある。断層の物理的な特徴を調べることで、前回調査でたどり着けなかった発生メカニズムの解明を目指すとともに、次の巨大地震に向けた準備が始まっているかどうかを確認する。
「研究者の間でも意見が分かれる2つの仮説を検証する絶好の機会になる」。調査の共同首席研究者であるJAMSTECの小平秀一理事は掘削調査への期待をこう語る。
東日本大震災では、海側の太平洋プレートが陸側の北米プレートの下に潜り込む日本海溝の付近で、プレート境界の浅い部分が50メートル以上にわたってすべったことが確認された。その影響で大量の海水が押し上げられて、巨大津波の発生につながった。
ただ、この現象は研究者にとっては想定外だったという。東日本大震災が分類される「海溝型地震」では、海底深くの2つのプレートがくっついた固着域で蓄積したひずみが一気に解放され、断層がすべることで地震が起きる。一方、「境界の浅い部分は固着が弱く断層すべりを起こさない」というのが従来の考えだった。

「境界の浅い部分も固着してひずみがたまり、それが解放されることですべった」のか、それとも「固着せずに深部の破壊が伝わって一緒にすべった」のか――。「固着説」と「非固着説」と呼ばれる相反する2つの説は、現在、断層に加わる力を調べることで「どちらが正しいか決着させられる」(小平理事)。
12年の歳月を経て、ちきゅうは日本海溝を再訪し、日本海溝を挟んだ2地点での掘削調査を始めた。探査船からドリルパイプを水深約7000メートルの海底に下ろし、前回と同じプレート境界の浅い部分に加えて、沈み込む前の太平洋プレート上をそれぞれ海底下約950メートルと約450メートルへと掘り進めている。
前回調査では、海底下約850メートルを掘削し、プレート境界の浅い部分から断層の試料を採取した。分析結果から地震前に蓄積されていたひずみがほぼすべて解放されたことや、断層が主に粒の細かい粘土からなり、その中に含まれた水が地震による摩擦熱で膨張し、すべりを加速させたことなどを突き止めた。
今回も掘削と同時に地質の様々なデータを計測するほか試料採取をする。断層に働く力や強度がこの12年間でどのように変わったのか、断層を構成する物質が沈み込む前後でどのように変わるのか、といった時空間変化を調べながら、プレート境界の浅い部分の実態解明に挑む。

調査を通じて得られた知見は今後の地震研究に活用される。
「プレート境界の浅い部分が力を蓄えられる特徴を持っているのか否かを理解することは、地震発生帯のモデルを検討する上で基礎的なデータになる」と小平理事は強調する。
将来は、南海トラフなどさまざまな海溝型地震に応用できるモデルづくりに生かしたい考えだ。
11月8日の経過報告で共同首席研究者で筑波大学の氏家恒太郎教授は掘削調査が順調に進捗しており「断層への力のかかり具合や、粘土層からなる断層の分布を明らかにする上で必要なデータが得られている」と明かした。
巨大地震の全貌にどこまで迫れるのか、目が離せない。(桑村大)
ちきゅう
JAMSTECが保有する世界最大級の海底掘削船で全長210メートル、約5万6000トンある。
船中央部のやぐら(高さ約70メートル)の下にある開口部からドリルパイプを海中に下ろし海底を掘削する。
世界中の深海底を掘削し、地震のメカニズムや生命の謎の解明を目的とする国際共同研究プロジェクト「国際深海科学掘削計画(IODP)」の主力船で、これまで地震の巣とされる南海トラフでの掘削などを手掛けた。
今回の掘削調査で海面から穴底までのドリルパイプの長さが計7877.5メートルに達し、2012年に自らが樹立した海洋科学掘削の世界最深記録7753メートルを更新した。
東日本大震災から13年となった被災地。インフラ整備や原発、防災、そして地域に生きる人々の現在とこれからをテーマにした記事をお届けします。
日経記事2024.11.16より引用
<picture class="picture_p166dhyf"><source srcset="https://article-image-ix.nikkei.com/https%3A%2F%2Fimgix-proxy.n8s.jp%2FDSXZQO5597100008112024000000-4.jpg?ixlib=js-3.8.0&w=638&h=533&auto=format%2Ccompress&fit=crop&bg=FFFFFF&s=6173f70e04d63adeb6137ecb2439f771 1x, https://article-image-ix.nikkei.com/https%3A%2F%2Fimgix-proxy.n8s.jp%2FDSXZQO5597100008112024000000-4.jpg?ixlib=js-3.8.0&w=1276&h=1066&auto=format%2Ccompress&fit=crop&bg=FFFFFF&s=e0bb89beb6016235fb17077d06b4d95c 2x" media="(min-width: 1232px)" /><source srcset="https://article-image-ix.nikkei.com/https%3A%2F%2Fimgix-proxy.n8s.jp%2FDSXZQO5597100008112024000000-4.jpg?ixlib=js-3.8.0&w=638&h=533&auto=format%2Ccompress&fit=crop&bg=FFFFFF&s=6173f70e04d63adeb6137ecb2439f771 1x, https://article-image-ix.nikkei.com/https%3A%2F%2Fimgix-proxy.n8s.jp%2FDSXZQO5597100008112024000000-4.jpg?ixlib=js-3.8.0&w=1276&h=1066&auto=format%2Ccompress&fit=crop&bg=FFFFFF&s=e0bb89beb6016235fb17077d06b4d95c 2x" media="(min-width: 992px)" /><source srcset="https://article-image-ix.nikkei.com/https%3A%2F%2Fimgix-proxy.n8s.jp%2FDSXZQO5597100008112024000000-4.jpg?ixlib=js-3.8.0&w=600&h=501&auto=format%2Ccompress&fit=crop&bg=FFFFFF&s=a6eb4972363987bf91b06bf3623cf595 1x, https://article-image-ix.nikkei.com/https%3A%2F%2Fimgix-proxy.n8s.jp%2FDSXZQO5597100008112024000000-4.jpg?ixlib=js-3.8.0&w=1200&h=1002&auto=format%2Ccompress&fit=crop&bg=FFFFFF&s=6e3a284afb84b42f7e1cbfa176211c6b 2x" media="(min-width: 752px)" /><source srcset="https://article-image-ix.nikkei.com/https%3A%2F%2Fimgix-proxy.n8s.jp%2FDSXZQO5597100008112024000000-4.jpg?ixlib=js-3.8.0&w=600&h=501&auto=format%2Ccompress&fit=crop&bg=FFFFFF&s=a6eb4972363987bf91b06bf3623cf595 1x, https://article-image-ix.nikkei.com/https%3A%2F%2Fimgix-proxy.n8s.jp%2FDSXZQO5597100008112024000000-4.jpg?ixlib=js-3.8.0&w=1200&h=1002&auto=format%2Ccompress&fit=crop&bg=FFFFFF&s=6e3a284afb84b42f7e1cbfa176211c6b 2x" media="(min-width: 316px)" /><source srcset="https://article-image-ix.nikkei.com/https%3A%2F%2Fimgix-proxy.n8s.jp%2FDSXZQO5597100008112024000000-4.jpg?ixlib=js-3.8.0&w=600&h=501&auto=format%2Ccompress&fit=crop&bg=FFFFFF&s=a6eb4972363987bf91b06bf3623cf595 1x, https://article-image-ix.nikkei.com/https%3A%2F%2Fimgix-proxy.n8s.jp%2FDSXZQO5597100008112024000000-4.jpg?ixlib=js-3.8.0&w=1200&h=1002&auto=format%2Ccompress&fit=crop&bg=FFFFFF&s=6e3a284afb84b42f7e1cbfa176211c6b 2x" media="(min-width: 0px)" /></picture>