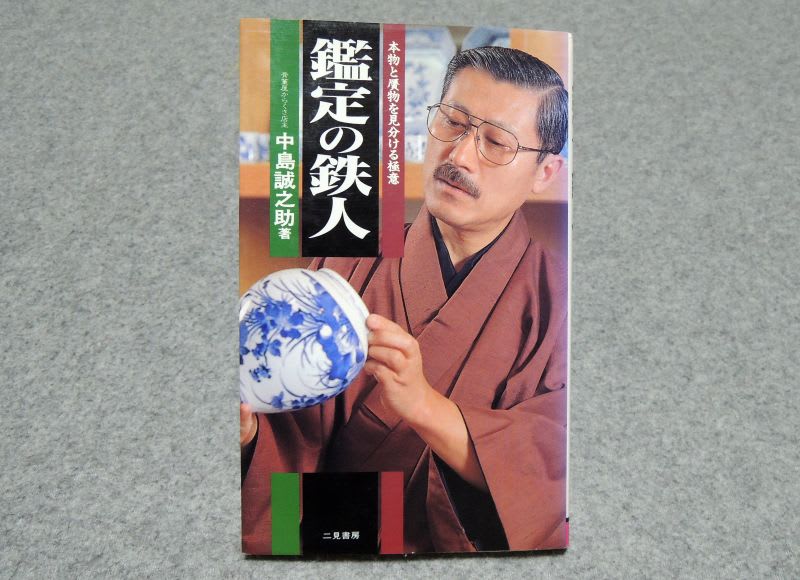ヤフオクを見ていたら、藍九谷の名品として図録には必ずと言っていいほど掲載されている「竹虎文皿」が出品されていました。
この捻じり縁の超有名品はときどき出品されており、去年の9月に出品された時は70万円を超える高額で落札されていました。
前回の品の真贋はともかく、今回の品は捻りが甘く、さらに絵柄が微妙に違い時代色が感じられないようには見えます
ちなみに、とても判りやすい写し物はコチラで確認できます。
ワタシは17年前の東京ドームプリズム骨董祭でガラスケース越しにこの品の現物を見たことがありますが、
70万円オーバーで落札された品の真贋はわかりません。(当時は300万円のプライスが付いていた)
こちらの東京の一流業者のHPに掲載されている品は間違いなく本物ですが、古くより名品として知られた品ですので
贋作や写し物が登場するのは名品の証と言えなくもないような・・・。