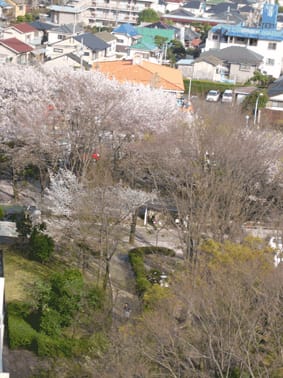<iframe src="http://rcm-jp.amazon.co.jp/e/cm?t=sakitablog-22&o=9&p=8&l=as1&asins=4062749831&fc1=000000&IS2=1<1=_blank&lc1=0000ff&bc1=000000&bg1=ffffff&f=ifr" style="width:120px;height:240px;" scrolling="no" marginwidth="0" marginheight="0" frameborder="0"></iframe>
友人が清水義範と言う人の本が面白いよ、と勧めてくれたので、まず「おもしくても理科」と言う本を読んだ。感想は「最近読んだ本」リスト参照。(右下の方)
この「いやでも楽しめる算数」は、その「おもしろくても理科」「もっとおもしろくても理科」に続く3作目のおもしろ勉強エッセイシリーズ。この後も、社会とか国語とか続くみたいである。おもしろ勉強エッセイというけど、全然お勉強という感じはしません。くっだらないことや親父ギャグみたいなのも出てきて、はっきり言って脱力系。西原画伯のイラストがなにより脱力です。全然本文と関係ないんだもん、、、。
理科がそんなに面白くなかったのに、(期待が大きすぎた?)またまたブックオフで算数を買ってしまった訳です。
んがっ!!これは面白かった。ていうか、もともとこういう算数の謎みたいなのが好きなのです。算数は苦手だったんですよ。前にも書いてるけど。でも、算数の不思議は好きなんです。で、さらに言えば、この脱力系の無駄話と無駄イラストはいらんから、もっとたくさんの算数の謎を書いてほしかった。清水先生は、算数の話ばっかり書くと、算数アレルギーの文系人間が逃げて行っちゃうということを、極度におそれるあまり、文系がにたりにたりと読めるような話をはさみつつ、算数の話を展開している訳だけど、算数についてもっと知りたい時にはこれが邪魔なんだなぁ、、、。まあ、たしかに、電車の中で脱力して読むには、そういう方がありがたいんだけどね、、、。
算数ブーム、きてますね?「博士の愛した数式」からですか?
先週の「誰でもピカソ」ご覧になりましたか?面白かったですねぇ。よくデンジロウ先生が理科マジックをやっていて、面白いなぁ、と思うけれど、算数マジックでしたね!
12345679×好きな数×9=好きな数の連続
というのと、数字のピラミッドというのをやっていました。
1×1 =1
11×11 =121
111×111 =12321
1111×1111=1234321
絶対に、自分の手で解明しちゃる!と思って見ていたのですが、この本に全部ネタが書いてありました。
他にも、九九の表という文章を書いた時に友人が9の段の九九は面白い。全部足すと9になる数字でできている、というコメントをよこして、ああ、なんでそうなるのか、今度考えてみよう、と思っていたのですが、そのネタも書いてあります。
その他に7の不思議も。それは「伊東家の食卓」でやっていたらしい。
ちなみに12345679×…の方は19世紀のリュカという数学者の「数学遊戯」という本に紹介されている、とこの本にある。
また数字のピラミッドの方はフォーリーという数学者の「算術遊戯」という本に紹介されている、とこの本にある。
元ネタ本を読みたくなるでしょう?ならない?あれ????
最後に3大数学者とは誰か、について書いてあった。これは数の不思議ではないが、偉人伝みたいでそれなりに面白かった。3大数学者とはアルキメデス、ニュートン、ガウスなんですって。3人とも物理の方だと思っていました。てっきり。そして3人ともかなりの変人であったようです。
子どもが変人でも悲観しないこと。もしかしたら後世に残る偉人になるかもしれませんよ?!
さて、算数パズルの方ですが、この本を読みたくないけど、ちょっと教えてよ!という方はリクエストして下され。もしかすると著作権法に抵触するかもしれないけど、私なりに噛み砕いてご紹介いたしましょう♪
でも、その他にも円の面積の求め方はなぜπr2(パイアールジジョウ)なのか、とか、前にメールで盛り上がっていた分数の割り算はなぜひっくり返してかけるのか?そもそも割り算とは何か?といった、明日子どもに聞かれた時にたじろがずに「それはね、、、」と話せるような内容もたっぷりですので、お母さんは是非購入されてみては???
友人が清水義範と言う人の本が面白いよ、と勧めてくれたので、まず「おもしくても理科」と言う本を読んだ。感想は「最近読んだ本」リスト参照。(右下の方)
この「いやでも楽しめる算数」は、その「おもしろくても理科」「もっとおもしろくても理科」に続く3作目のおもしろ勉強エッセイシリーズ。この後も、社会とか国語とか続くみたいである。おもしろ勉強エッセイというけど、全然お勉強という感じはしません。くっだらないことや親父ギャグみたいなのも出てきて、はっきり言って脱力系。西原画伯のイラストがなにより脱力です。全然本文と関係ないんだもん、、、。
理科がそんなに面白くなかったのに、(期待が大きすぎた?)またまたブックオフで算数を買ってしまった訳です。
んがっ!!これは面白かった。ていうか、もともとこういう算数の謎みたいなのが好きなのです。算数は苦手だったんですよ。前にも書いてるけど。でも、算数の不思議は好きなんです。で、さらに言えば、この脱力系の無駄話と無駄イラストはいらんから、もっとたくさんの算数の謎を書いてほしかった。清水先生は、算数の話ばっかり書くと、算数アレルギーの文系人間が逃げて行っちゃうということを、極度におそれるあまり、文系がにたりにたりと読めるような話をはさみつつ、算数の話を展開している訳だけど、算数についてもっと知りたい時にはこれが邪魔なんだなぁ、、、。まあ、たしかに、電車の中で脱力して読むには、そういう方がありがたいんだけどね、、、。
算数ブーム、きてますね?「博士の愛した数式」からですか?
先週の「誰でもピカソ」ご覧になりましたか?面白かったですねぇ。よくデンジロウ先生が理科マジックをやっていて、面白いなぁ、と思うけれど、算数マジックでしたね!
12345679×好きな数×9=好きな数の連続
というのと、数字のピラミッドというのをやっていました。
1×1 =1
11×11 =121
111×111 =12321
1111×1111=1234321
絶対に、自分の手で解明しちゃる!と思って見ていたのですが、この本に全部ネタが書いてありました。
他にも、九九の表という文章を書いた時に友人が9の段の九九は面白い。全部足すと9になる数字でできている、というコメントをよこして、ああ、なんでそうなるのか、今度考えてみよう、と思っていたのですが、そのネタも書いてあります。
その他に7の不思議も。それは「伊東家の食卓」でやっていたらしい。
ちなみに12345679×…の方は19世紀のリュカという数学者の「数学遊戯」という本に紹介されている、とこの本にある。
また数字のピラミッドの方はフォーリーという数学者の「算術遊戯」という本に紹介されている、とこの本にある。
元ネタ本を読みたくなるでしょう?ならない?あれ????
最後に3大数学者とは誰か、について書いてあった。これは数の不思議ではないが、偉人伝みたいでそれなりに面白かった。3大数学者とはアルキメデス、ニュートン、ガウスなんですって。3人とも物理の方だと思っていました。てっきり。そして3人ともかなりの変人であったようです。
子どもが変人でも悲観しないこと。もしかしたら後世に残る偉人になるかもしれませんよ?!
さて、算数パズルの方ですが、この本を読みたくないけど、ちょっと教えてよ!という方はリクエストして下され。もしかすると著作権法に抵触するかもしれないけど、私なりに噛み砕いてご紹介いたしましょう♪
でも、その他にも円の面積の求め方はなぜπr2(パイアールジジョウ)なのか、とか、前にメールで盛り上がっていた分数の割り算はなぜひっくり返してかけるのか?そもそも割り算とは何か?といった、明日子どもに聞かれた時にたじろがずに「それはね、、、」と話せるような内容もたっぷりですので、お母さんは是非購入されてみては???