歩 い て 世 界 一 周 2月11日(日月) 雪
|
日 数「日」 |
総歩数(歩) |
総距離(m) |
平均歩数(歩) |
|
|
今 日 |
1 |
16,140 |
11,298 |
|
|
今 月 |
11 |
183,855 |
128,699 |
16,714 |
|
今 年 |
42 |
694,400 |
486,080 |
16,533 |
|
2005年から |
2,973 |
41,013,119 |
29,407,183 |
14,132 |
|
70歳の誕生日から |
6,505 |
123,963,255 |
86,774,279 |
19,057 |
ドイツ・オランダ、ベルギー.、フランス.イギリスを経てアイスランドのレイキャビックに向かう、後 533,680m
今日は建国の日、昔は紀元節。昔は小学校で「雲に聳ゆる 高千穂の 高根おろしに草も木も なびきふしけん 大御世を 仰ぐ今日こそ たのしけれ」と歌い紀元節を祝って、紅白の饅頭を貰って帰った。街には何処の家にも日の丸の旗が立てられていて日本に生まれた誇で楽しい一日だった。今は、街中歩いても国旗を掲げている家を見ることは稀だ。ただの休日だ。連休だといって遊びに行くか、朝寝坊でもして一日中リラックスして過ごすのが関の山だ。情けない。落ちぶれたものだ。
戦後、日本の日本の骨抜きを考えてGHQによって紀元節は廃止された。1951年(昭和26年)ころから復活の動きが出て1857年(昭和32年)以降議案提出・廃案を経て、1996年(昭和41年)やっと国民の祝日に追加された。それも【建国記念日】ではなく「建国記念の日」だ。神武天皇が歴史上確かに居たか?何時即位したか?確たるものが無い以上、建国記念日と言う訳には行かないと云うものだ。
2月11日を「建国記念の日」とすることについても【内閣の建国記念日審議会】で審議して、神武天皇即位の日が日本書紀に【辛酉年春正月の康辰の朔とあるのを根拠に、逆算すると、神武元年が西暦前660年になり、陰暦の1月1日を太陽暦に換算して2月11日と決めたという。
西暦前660年で計算すれば、今年は皇紀2673年に当たると云うが、私が15歳の時、紀元2600年の祝展が盛大に行われた記憶がある。その年の8月、私は台君・岡田君と3人で富士山に登頂した。雨に降られて茣蓙を着て登った。ご来光も拝まれず、びしょ濡れになって震えていた思い出があるが、それでも亜細亜から欧米の白人を駆逐して、大日本帝国が亜細亜の盟主として大東亜の新秩序を建設するという夢を持って居た。
日本書紀が採用している暦法を知らなくても、干支を利用すると、神武天皇が即位した辛酉年春正月の庚辰の朔が、太陽暦では紀元前660年2月11日になることが分ります。
まず、日本書紀の年表をつくり、逆算すれば、神武元年が紀元前660年に当ることが分ります。(年表が作れなければ、それが分からないことを銘記してください。)
日本書紀による神武天皇即位の日・紀元前660年1月1日を新暦(グレゴリオ暦)に換算した2月11日を祝日と定めた。当初は1月29日だったが、翌年から2月11日に変更された。戦後、日本国憲法の精神にそぐわないとして廃止されたが、昭和41年に「建国記念の日」として復活した。
1873(明治5)年11月15日、紀元前660年を元年として「皇紀○年」という年の数えかたが作られたが、現在ではほとんど使われていない。
この日はかつて「紀元節」という祝日だったが、戦後になってこの祝日は廃止された。1951(昭和26)年頃から復活の動きが見られ、1957(昭和32)年以降9回の議案提出・廃案を経て、1966(昭和41)年に、日附は政令で定めるものとして国民の祝日に追加された。
建国記念の日の日附については内閣の建国記念日審議会でも揉めたが、10人の委員のうち7人の賛成により、2月11日にするとの答申が1966(昭和41)年12月8日に提出され、翌日政令が公布された。
「建国記念日」ではなく「記念の日」なのは、建国された日とは関係なく、単に建国されたということを記念する日であるという考えによるものである。


















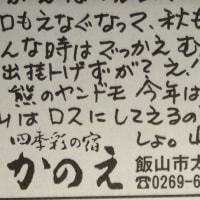

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます