*二十番鷲峯山長安寺 千手観世音菩薩(愛称岩井堂観音) 真言宗智山派 松本市会田四賀
長安寺は廃寺となり、かつて岩井堂はこの寺のお堂だったそうだ 。お堂の周囲は岩山で数十体の石仏群・岩壁には大小の
磨崖仏や、弘法大師が刻んだとされる爪彫り(魔崖浮き彫りの)大黒天があった。
*二十六番栗尾山満願寺 千手観世音菩薩 真言宗智山派 安曇野市穂高
725年頃、裏山の奥にある長者ヶ池から出現した一寸八分の黄金仏像を、聖武天皇の勅願によって堂宇を建て安置したの
が始まりと伝わる、「信濃高野」の異称もある古刹だそうだ。
信濃三十三番札所の中で三番目に急勾配の長い参道だそうだ。確かに年配者にっとってはきつかった。参道の入口にある
「微妙橋」は、欄干屋根付きの太鼓橋で極楽浄土への結界を表しているという。
本堂には、亡くなった後の四十九日の苦しみを現す、「地獄極楽変相之図」が飾られている。 血の池地獄、針山地獄、
閻魔大王の裁判所などの地獄の絵だが、お寺ならではの妙な説得力がありそうだ。


参 道 入 り 口 微 妙 橋


満 願 寺 本 堂 山 門
*二十五番天陽山盛泉山 千寿手観世音菩薩(愛称水沢観音) 曹洞宗 波田町
ここから1.5キロほど山へ入った水沢山に「通称水沢観音」とよばれる若沢寺があった。江戸時代には「信濃日光」と呼ばれた
ほどで、全山に素晴らしい建築物が数多くあり栄えていたそうです。明治の廃仏毀釈により、お堂等の建物は取り壊されて廃
寺となり、再建されたのは明治20年代で、この寺の住職と村の有志の努力によるものだそうです。


盛泉寺 本 堂 山 門 大慈閣(水沢観音堂)



盛泉寺本尊 釈迦牟仏 若沢寺からっ移された仏像の1部 
独特の光背がある不動明王
wikipedia百科事典によれば。
水沢観音堂は、廃仏毀釈により取り壊された若沢寺にあった救世殿を盛泉寺に移し、観音堂として1895年(明治20年代後半)ころ再建したもので、銅造菩薩半跏像、銅造伝薬師如来坐像御正体残闕、銅造菩薩立像、木像(不動明王立像)、真言宗祖師像(木像弘法大師坐像・木像興教大師坐像)2体、絹本不動明王掛軸などを収納している。建物は1984年(昭和59年)に改築された。子授け、アカギレ、イボ等にご利益があるとされる。若沢寺は、長野県内でも有数の古刹で、江戸時代後期には信濃日光と称されるほどの規模を持ったが、明治初年の廃仏毀釈で取り壊されて廃寺となった。当寺が信濃三十三観音霊場の第25番札所であるのも、若沢寺からの継承である。山門前の六地蔵も、もとは若沢寺にあったもの。




















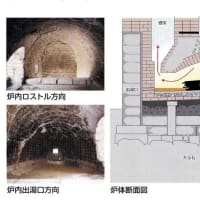
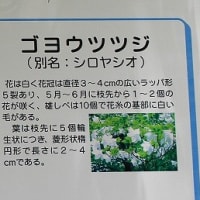
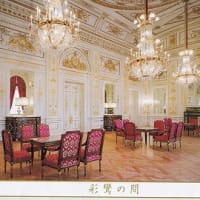

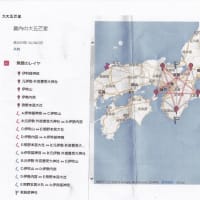





※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます