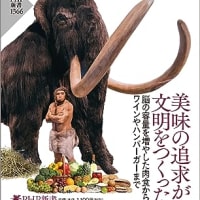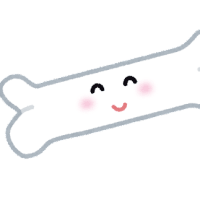香辛料と砂糖-古代インド(5)
インドを中心に生産された香辛料と砂糖は重要な貿易品としてメソポタミアやエジプトなどの西アジアやヨーロッパに運ばれた。香辛料と砂糖はいつの時代でもとても魅力的な食品であり商品であり続けたことから、現在に至るまで様々な時代で人類史に大きな影響力を発揮することになる。まさしく、香辛料と砂糖は食が歴史を変えた典型的な例だと言える。
少し繰り返しになるところもあるが、ここで古代における香辛料と砂糖についてまとめておきたいと思う。なお、香辛料についてはシナモンとコショウについて取り上げる。
シナモン
シナモンは世界でもっとも古くから知られている香辛料で、ほのかな甘みある独特の香りと多少の辛みが特徴だ。シナモンは、クスノキの仲間のセイロンニッケイやシナニッケイなどの樹皮の内側部分を乾燥させて作られる。現代では、シナモンはシナモンロールのようにお菓子や料理に入れたり、紅茶やコーヒーなどの飲料に入れたりして食べられる。

紀元前2000年より以前のエジプトのパピルスやシュメールの粘土板に香辛料の「シナモン」について記載がある。エジプトでは神へのお供え物を清めたりミイラを清めたりなど宗教儀式で主に使用されていた。また、医薬品としても使われていたようだ。インダス文明とメソポタミア文明の間には紀元前2000年より以前から海上貿易が行われており、インドのシナモンがメソポタミアを経由してエジプトに運ばれた可能性が高い。
その後のヨーロッパではシナモンは長い間薬として使用された。強心剤や媚薬としての効能があると考えられていたようだ。ちなみに中国でもシナモンは不老不死の薬とされ、仙人の食べ物とされた。
インドでは有史以前からシナモンが料理に使われていたと考えられているが、ヨーロッパでシナモンが料理に使用されるようになるのはローマ帝国末期の3~4世紀のことである。とにかく、シナモンはヨーロッパではとても貴重で、そして産地がどこなのかずっと謎だった。記録にもアフリカが原産地であるなどの不正確な記述ばかりで、なぜ真実が明らかにされなかったのかが現在では歴史上の謎となっている。
やがて16世紀初めにポルトガルのヴァスコ・ダ・ガマが喜望峰を回ってインドに至る道を開拓すると、ポルトガル人は大量のシナモンを独占して本国に送るようになる。
(いわゆる大航海時代の幕開けだが、そのあたりの楽しいお話しはまだ先になります。)
コショウ
香辛料の中でもっともよく利用されてきたのがコショウだ。そのため「スパイスの王」と呼ばれることが多い。

コショウの木はつる性の20年以上生きる熱帯性の植物で、1本の木から約2キログラムのコショウの実が採れる。実を収穫する時期やその後の処理の違いによって、黒コショウ(ブラックペッパー)、白コショウ(ホワイトペッパー)、青コショウ(グリーンペッパー)、赤コショウ(ピンクペッパー)になる。
この中で代表的な黒コショウは、赤く色づきはじめる直前の緑色の実を果皮ごと天日に干して黒くなるまで乾燥させたものだ。また白コショウは、赤く熟した果実を1週間程水につけて外皮を柔らかくしてはがし、白色の実のみにして乾燥させたものだ。黒コショウは肉料理に合い、白コショウは魚料理に合うと言われている。
一方、青コショウは黒コショウのように緑色の実で収穫するが、そのまま塩漬けにしたもので、赤コショウは白コショウのように完熟してから収穫するが、ホワイトペッパーと異なり外皮をはがさずにそのまま使用するものだ。
コショウの原産地はインドの南西部とされている。そして、古くからインドはコショウの一大産地だった。アーリヤ人はコショウのことを「Pippeli」と呼んだが、ヨーロッパに伝わると、これが変化してラテン語の「piper」や英語の「pepper」が生まれたとされている。
コショウがインド南西部で栽培されたことから、西アジアやヨーロッパに伝わったのはシナモンよりも遅かった。紀元前4世紀のヒポクラテスの著作にはコショウのことが記されているので、この頃までにはエジプトを介して地中海にもコショウが伝えられていたと考えられている。ヒポクラテスはコショウを調味料ではなく薬として記していることから、ヨーロッパに入った当初は薬として認識されていたようだ。
しかし、その後しばらくしてコショウは主に料理に使用されるようになった。特にローマ時代には料理に大量のコショウが使われていた。西暦1世紀になるとローマ帝国はエジプトやメソポタミアを含む広大な支配地を獲得するが、その結果として得られたインドとの交易路を用いてコショウなどの香辛料、香料、真珠、宝石や中国製のシルク製品などを輸入したのだ。
一方、ローマ帝国はその引き換えに大量の金貨をインドに渡した。金貨以外にインドに渡せるものをローマ帝国は作っていなかったのだ。今でもインドの古代遺跡からはローマの金貨が見つかるという。
砂糖
「古代アーリヤ人の食生活-古代インド(2)」でお話ししたように、サトウキビは現在のニューギニア島付近が原産地とされており、紀元前6000年前後にインドや東南アジアに広まったと考えられている。そしてインドで砂糖の精製法が発明されたと言われている。
サトウキビの茎を適当な長さに切ってしぼると、糖を含んだ樹液が取れる。これを集めて貝殻などの石灰性の物質を入れると、夾雑物が沈殿してくる。この夾雑物を除いて煮詰めたものが糖蜜だ。さらに糖蜜を煮詰めて糖分濃度を高くし、ここに粉砂糖のような細かい砂糖の粒を加えて加熱すると、その粒を核にして砂糖の結晶が出来る。こうしてできた砂糖の結晶をすくって乾燥させると出来上がりだ。
インドの人々は砂糖のことを「砂利(じゃり)」を意味する「sarkara」と呼んだ。このsarkaraからラテン語の「saccharon」という言葉が生まれ、やがて英語の「sugar」となる。
古代の人々はサトウキビと出会って、とても素晴らしいものと思ったようだ。ヒンドゥー教の儀式では、火にミルク・チーズ・バター・蜂蜜・サトウキビをくべて神へのお供え物とするようになった。また、紀元前510年にアケメネス朝ペルシア王のダレイオス1世がインドに攻め入った時に、ミツバチの助けなしに甘い汁を出す葦(サトウキビ)を見つけたのだが、彼はそれをペルシアに持ち帰り、他国に知られないように大事に育てたらしい。
ペルシア帝国で大事に育てられたサトウキビは、帝国の衰退とともに西アジア(中東)全体に広がって行った。そして、世界が古代から中世に移り行く時に、この西アジア地域が歴史の上で大きな役割を果たして行くことになる。
なお、古代ギリシア人と古代ローマ人は砂糖の存在を知っていたという記録はあるが、輸入されていたとしてもごく少量で、薬として認識されていただけであった。ヨーロッパ人が砂糖を食品として消費するようになるのは中世になってからである。
サトウキビや砂糖の精製法は7世紀に中国に伝えられたとされている。唐朝の第2代皇帝太宗が647年にインドへ技術者を送って「熬糖法」(糖液を煮詰める方法)を習得させたということだ。日本へは奈良時代に鑑真が唐から渡来した時に持参したという説がある。正倉院の記録『種々薬帳』には砂糖という意味の「蔗糖(しょとう)」という言葉が残されている。古代日本でも砂糖は薬とみなされていたのである。