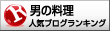(写真)サルビア・メキシカナ‘ライムライト’の花

「サルビア・メキシカナ‘ライムライト’」は、やさしい黄緑の萼(がく)、青紫の口唇状の花で、 この組み合わせがすっきりしているところに、光沢があるライム色の葉が花序を支えるのでキリッとしたすがすがしさが漂う。
この「ライムライト」は、メキシコ中部原産の「サルビア・メキシカナ(Salvia mexicana)」を親にした園芸品種であり、メキシコの中部にあるQuerétaro州から1978年に愛称ボブ(Robert Ornduff 1932-2000)によってバークレーにあるカリフォルニア大学植物園に持ち出されたという。
ボブは、カルフォルニア大学バークレー校で30年間も務め、学部長、大学付属植物園長などを務めたカルフォルニア植物相の権威でもあった。
「サルビア・メキシカナ‘ライムライト’」の親
「ライムライト」の親である「サルビア・メキシカナ(Salvia mexicana)」は、森の端、ふちに生息し、「サルビア・イエローマジェスティ」の場合は、森の中に入りちょっとした空白地での木洩れ日で大きく成長する生き方をするが、
「サルビア・メキシカナ」は、森の中に入っていかないので、森に守られない代わりに草丈をあまり大きくさせずに森の周辺で光りを吸収する草丈などを形成したのだろう。
この「サルビア・メキシカナ」を採取したのは、1833年にアンドリュー(Andrieux, G)がメキシコで採取したという記録が残っている。
彼は、208もの新種をメキシコなどで1834年頃に集中して採取しているが、略歴を調べたが良くわからない謎の人物だ。
「サルビア・メキシカナ」の命名者Sessé y
また、この「サルビア・メキシカナ(Salvia mexicana Sessé & Moc.)(1893年登録)」の命名者は二人いるが、
Sessé y Lacasta, Martín (1751-1808)は、スペインの医者・植物学者で、彼が29歳の時の1780年に軍医としてメキシコに到着し、1785年にニューメキシコの王立植物園のコミッショナーに任命された。
1786年には、時のスペイン国王チャールズ三世(1716 – 1788)にスペインの新大陸植民地の大規模な植物・動物などの資源を調査する提案を行い、その中心メンバーとして探検で活躍した。
このときの探検隊の同僚がもう一人の命名者Mociño, José Mariano (1757-1820)だった。
スペインより遅れて新大陸に進出したイギリスでは、植物の重要性を早くから認識し、既に海外にプラントハンターを送り出していたが、新大陸の金・銀・財宝にしか興味がなかったスペインも遅れて植物探索をすることになる。
Sessé yとMociñoは、16年間に亘る探検の結果をまとめるために1803年にスペインに戻ったが、Sessé yは完成する前の1808年に亡くなり、この成果が発表されたのは何と約80年後の1887年だった。
こんなに時間がかかったのにはSessé yの死亡も原因となるが、スペイン王室の秘密主義も影響していたようだ。
イギリスでは、キュー王立植物園を初めとして情報を公開しているからこそ情報が集まるという流れをつかまえたのに対して、スペインは、情報の流れをせき止めるダムを作り秘匿したがゆえにイギリスに取って代られる凋落の原因を作ったのだろう。
「ライムライト」は、スポットライトを意味し転じて“栄光”をも意味する。
スペインが“栄光”の座から滑り落ちたのも納得が行くし、「サルビア・メキシカナ」にスペインの植物学者Sessé yが命名者となったことも皮肉なことだ。
(写真)サルビア・メキシカナ‘ライムライト’の葉と花

サルビア・メキシカナ‘ライムライト’(Salvia mexicana 'Limelight')
・ シソ科アキギリ属の常緑小低木で耐寒性がある多年小木。
・ 学名は、Salvia mexicana Sessé & Moc. 'Limelight'。英名は Mexican sage 'Limelight'。
・ 原産地は中部メキシコの森の明るい端に自生。
・ 草丈1m以上となるので、夏までに摘心をして丈をつめる。
・ 開花期は、9~11月。淡いライムイエローの顎に濃いブルーの唇形の花が咲く。
・ 耐暑性は強い。
・ 冬場は陽のあたるところで、多湿を控える。
・
・ コレクターは、Andrieux, G. で、彼自身の正体が良くわからないが1833年にメキシコで採取し、スイスの植物学者ドゥ・キャンドール(Candolle, Augustin Pyramus de 1778-1841)に標本を送ったようだ。

ライムライトといえば・・・
『ライムライト』は、電気というものがない時代に舞台で使われていた照明器具で、転じて“栄光”の代名詞として使われたという。
確かにスポットライトを浴びるヒトと場に必要なものであり、 “栄光”に欠かせない舞台装置だ。
チャールズチャップリンの『ライムライト』は、
この“栄光”と“挫折”と“愛”をテーマに、赤狩り旋風が吹きまくった狂気の時代のアメリカとの、チャップリンの決別の映画でもあった。
灯りは希望の象徴でもあるが、その隣には影があり、そこには人生の味がある。
『ライムライト』は、異性との激しい愛ではなく包み込む父の愛であったような気がする。
狂気を包み込める愛は、神か父母しかなかったのだろう。
さよならの愛は、先に死ぬ父母の愛なのだろう。
“ライムライト”という言葉には、こんな感傷的な前置きが欲しくなる。
それにしても、チャップリンの『ライムライト』は良かったな~

「サルビア・メキシカナ‘ライムライト’」は、やさしい黄緑の萼(がく)、青紫の口唇状の花で、 この組み合わせがすっきりしているところに、光沢があるライム色の葉が花序を支えるのでキリッとしたすがすがしさが漂う。
この「ライムライト」は、メキシコ中部原産の「サルビア・メキシカナ(Salvia mexicana)」を親にした園芸品種であり、メキシコの中部にあるQuerétaro州から1978年に愛称ボブ(Robert Ornduff 1932-2000)によってバークレーにあるカリフォルニア大学植物園に持ち出されたという。
ボブは、カルフォルニア大学バークレー校で30年間も務め、学部長、大学付属植物園長などを務めたカルフォルニア植物相の権威でもあった。
「サルビア・メキシカナ‘ライムライト’」の親
「ライムライト」の親である「サルビア・メキシカナ(Salvia mexicana)」は、森の端、ふちに生息し、「サルビア・イエローマジェスティ」の場合は、森の中に入りちょっとした空白地での木洩れ日で大きく成長する生き方をするが、
「サルビア・メキシカナ」は、森の中に入っていかないので、森に守られない代わりに草丈をあまり大きくさせずに森の周辺で光りを吸収する草丈などを形成したのだろう。
この「サルビア・メキシカナ」を採取したのは、1833年にアンドリュー(Andrieux, G)がメキシコで採取したという記録が残っている。
彼は、208もの新種をメキシコなどで1834年頃に集中して採取しているが、略歴を調べたが良くわからない謎の人物だ。
「サルビア・メキシカナ」の命名者Sessé y
また、この「サルビア・メキシカナ(Salvia mexicana Sessé & Moc.)(1893年登録)」の命名者は二人いるが、
Sessé y Lacasta, Martín (1751-1808)は、スペインの医者・植物学者で、彼が29歳の時の1780年に軍医としてメキシコに到着し、1785年にニューメキシコの王立植物園のコミッショナーに任命された。
1786年には、時のスペイン国王チャールズ三世(1716 – 1788)にスペインの新大陸植民地の大規模な植物・動物などの資源を調査する提案を行い、その中心メンバーとして探検で活躍した。
このときの探検隊の同僚がもう一人の命名者Mociño, José Mariano (1757-1820)だった。
スペインより遅れて新大陸に進出したイギリスでは、植物の重要性を早くから認識し、既に海外にプラントハンターを送り出していたが、新大陸の金・銀・財宝にしか興味がなかったスペインも遅れて植物探索をすることになる。
Sessé yとMociñoは、16年間に亘る探検の結果をまとめるために1803年にスペインに戻ったが、Sessé yは完成する前の1808年に亡くなり、この成果が発表されたのは何と約80年後の1887年だった。
こんなに時間がかかったのにはSessé yの死亡も原因となるが、スペイン王室の秘密主義も影響していたようだ。
イギリスでは、キュー王立植物園を初めとして情報を公開しているからこそ情報が集まるという流れをつかまえたのに対して、スペインは、情報の流れをせき止めるダムを作り秘匿したがゆえにイギリスに取って代られる凋落の原因を作ったのだろう。
「ライムライト」は、スポットライトを意味し転じて“栄光”をも意味する。
スペインが“栄光”の座から滑り落ちたのも納得が行くし、「サルビア・メキシカナ」にスペインの植物学者Sessé yが命名者となったことも皮肉なことだ。
(写真)サルビア・メキシカナ‘ライムライト’の葉と花

サルビア・メキシカナ‘ライムライト’(Salvia mexicana 'Limelight')
・ シソ科アキギリ属の常緑小低木で耐寒性がある多年小木。
・ 学名は、Salvia mexicana Sessé & Moc. 'Limelight'。英名は Mexican sage 'Limelight'。
・ 原産地は中部メキシコの森の明るい端に自生。
・ 草丈1m以上となるので、夏までに摘心をして丈をつめる。
・ 開花期は、9~11月。淡いライムイエローの顎に濃いブルーの唇形の花が咲く。
・ 耐暑性は強い。
・ 冬場は陽のあたるところで、多湿を控える。
・
・ コレクターは、Andrieux, G. で、彼自身の正体が良くわからないが1833年にメキシコで採取し、スイスの植物学者ドゥ・キャンドール(Candolle, Augustin Pyramus de 1778-1841)に標本を送ったようだ。

ライムライトといえば・・・
『ライムライト』は、電気というものがない時代に舞台で使われていた照明器具で、転じて“栄光”の代名詞として使われたという。
確かにスポットライトを浴びるヒトと場に必要なものであり、 “栄光”に欠かせない舞台装置だ。
チャールズチャップリンの『ライムライト』は、
この“栄光”と“挫折”と“愛”をテーマに、赤狩り旋風が吹きまくった狂気の時代のアメリカとの、チャップリンの決別の映画でもあった。
灯りは希望の象徴でもあるが、その隣には影があり、そこには人生の味がある。
『ライムライト』は、異性との激しい愛ではなく包み込む父の愛であったような気がする。
狂気を包み込める愛は、神か父母しかなかったのだろう。
さよならの愛は、先に死ぬ父母の愛なのだろう。
“ライムライト”という言葉には、こんな感傷的な前置きが欲しくなる。
それにしても、チャップリンの『ライムライト』は良かったな~