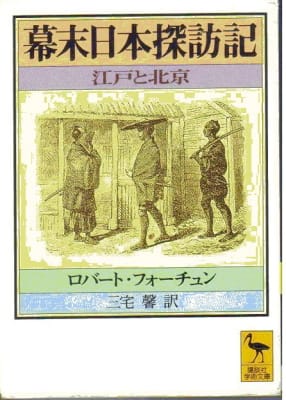その2:
中国・日本のツツジを持っていった英国のプラントハンター:フォーチュン
(写真)セイヨウシャクナゲのつぼみ

「セイヨウシャクナゲ (西洋石楠花)」は、ヒマラヤ周辺を中心とした多数の原種を交配して作出した園芸品種の総称であり、耐寒性に優れ大きな花びらと豊富な花色が特徴だ。アジアの原種が18世紀のヨーロッパに導入され改良が始ったという。
ここには、アジアのツツジ、シャクナゲなどを採取して本国に持ち帰ったヨーロッパのプラントハンター達の活躍がある。
このプラントハンター達を描いてみたいのだが、英国の王立キュー植物園のデータベースには、ツツジ属(Rhododendron)の採取者と採取時期などが登録されているが、採取時期がわかっている最も古いものは、1851年からでありこれ以前がわからない。
また、これから描こうとするプラントハンターの名前が記載されていないのも残念だ。
英国の植物相の貧弱さが珍しい植物へのニーズを創る
1700年代の半ば以降から英国では海外の植物を積極的に導入し始め、組織的に未開拓地の珍しい植物を採りに行き始めた。
もともと緑が少なく、産業革命の進行によるスモッグなどの都市環境の悪化などマイナス面がある一方で、緑を増やそう、都市をデザインしようという動きもあった。
英国の植物がどれだけ貧弱であったかを示す資料がある。1800年前半に活躍した造園家・都市のランドスケープデザイナーで農業・植物に造詣が深いラウダン(Loudon , John Claudius 1783- 1843) は、「英国に自生していた樹木は200種で、そのうちの100種がバラ・イバラ・ヤナギなので品種が少なく貧弱だ。」と述べている。そして、16世紀後半以降の英国人の海外での活動により、アルプス以南の地中海沿岸の植物、北米などの多種多様な植物の美に気づいたという。
ちなみに、日本に自生する樹木の種類は1000種を超えるそうだ。
ラウダンは、1822年に最初の著書として『 The Encyclopedia of Gardening 』など数多くの本を出版し、都市の公園・墓地などの造園、小さな庭に様々な植物を植える美と楽しみを啓蒙し、個人の庭の緑、公園・墓地などの公共の緑、これらが織り成す都市としての景観・ランドスケープの計画を提唱し、小さな庭に海外からの新奇な植物を受け入れるコンセプトを生み出し、プラントハンターの活動を容認し側面から支援した。
プラントハンターの直接的な支援者は、王立キュー植物園、王立エジンバラ植物園などの植物園・博物館、そしてリー&ケネディ商会、ヴィーチ商会などのナーサリーと呼ばれる育種園、そして、産業革命で登場した成功者であり、英国にない植物、他にはない庭を持ちたいという人たちであった。緑が少ない英国だからこそ、珍しい庭とそれを彩る植物がステイタスシンボルとなったのだろう。産業革命の恩恵であるガラス、それを使った温室が英国では育てられない植物の栽培をも可能とした。
19世紀半ば頃まで謎に満ちていた中国と日本
中国清朝と日本の江戸幕府は、それぞれ鎖国政策を採り、貿易は広州、長崎一港に限られていたので、現在的に言えば北朝鮮のように謎の国であった。
この気持ちよい眠りは強引に破られることになるが、中国清朝政府はアヘン戦争後の1842年の南京条約で香港の割譲、広東、厦門、福州、寧波、上海の5港を開港した。
10年ほど遅れるがほぼ同じ時期の日本では、江戸幕府がペリー提督の軍艦と大砲に永い眠りを覚まされ1854年に日米和親条約を結び、1859年には、箱館・横浜・長崎・新潟・神戸の5港を開港した。
鎖国の時は、オランダ東インド会社の医師として長崎出島に来たツンベルク、シーボルト等の日本植物誌によって豊かな日本の植物相が垣間見られ、ヨーロッパで話題になっていた。
この珍しい植物の宝庫と思われていた中国と日本の開国は、プラントハンターにとっても朗報であり、彼らたちの活躍のフィールドが広がった。
開国前で、記録に残っている中国での最初のコレクターは、植物採取のアマチュアのカニンガム(Cuninghame, James 1697‐1719)のようだ。彼は英国東インド会社の医師として雇われ、1698年にアモイに派遣された。1701年の後半に中国のチャサンに航海し、2年以上滞在しこのエリアでの植物の採取を行った。そして、乾燥した標本600種以上を本国に送り、本人も1709年にイングランドに戻った。
確かに日本でも、長崎出島に封じ込められ、植物採取は近隣のところと日本人を使って採取するか植木屋から購入するなど限られていた。ましてやツツジは持ち出し禁止されている植物でもあった。プラントハンター泣かせの国であったことは間違いない。
プラントハンターの偉大な巨人、フォーチュン

この両国の記念すべき開国に立ち会ったプラントハンターが一人いる。スコットランドの園芸家、ロバート・フォーチュン(Fortune、Robert 1812‐1880)で、東インド会社をスポンサーにインド・アッサムに清国からのチャノキを持って行き、この移植栽培に成功させ、イギリスの紅茶産業を発展させた功労者でもある。これは、フォーチュン二回目の中国探検で、1848年に実施された。
フォーチュンが始めて中国に来たのは、1842年、アヘン戦争に敗れた清国が南京条約を結び、香港の割譲、広東など5港の開港をする年だが、この情報を聞きつけたエジンバラ王立園芸協会は、フォーチュンを清国に派遣することにし、採取して欲しい植物の長たらしいリストを渡した。
フォーチュン30歳の時であり、翌1843年2月に英国を出港し、7月に香港に到着し3年間滞在した。この間にフィリピンへ「ラン(Phalaenopsis amabilis)」を採取する短い旅行を行い、エジンバラ園芸協会の要望に見事に答え、アネモネ、キク、ラン、スモモ、スイカズラなど多数の植物を英国に送った。
最も、この時点での中国は、自由に野山を探検旅行することが出来ず、中国人或いは園芸商から購入する以外なかったが、フォーチュンは大胆にもヒゲを伸ばし弁髪になり中国人に変装して禁止されている地域、野山の探索を行ったという。
この現地に溶け込む自在性の情報収集能力が、だまされない目利きとして制約があるなかでの成果に結びついたのだろう。
余談だが、フォーチュンが書いた『江戸と北京』(1863年出版)の本の中では、中国人商人のうそつきとフォーチュンが外出するたびに監視と警護のためにゾロゾロとついて来る日本の小役人のたかり根性を嫌っていたのが印象に残る。最も十分な給料を支払えなかったのでワイロで生計を立てなければならなかったという幕府財政の逼迫があることも否めない。
フォーチュン三回目の中国訪問は、アメリカ合衆国政府をスポンサーに1858年に実施された。アメリカの政府からは、彼が実績のある中国のチャノキの調査であり、あわせてロンドンの育種商スタンディッシュからは珍しい植物の採取をも依頼されていた。
ちょうど、日本の開国の情報を聞き、1860年10月及び1861年4月に再び訪問をする。
フォーチュンは日本の第一印象を「私はこの未知の国の話を沢山読んだり聞いている。・・(略)・・初めて長崎の海岸を見たとき・・(略)・・むしろ自然の庭園そのものであった。」
江戸では、団子坂、王子、染井村など植木屋が密集しているところを探索し、彼が知っている世界で最高の園芸技術と文化を持っていると評価している。
英国人が見た古きよき日本を見直す本としても『江戸と北京』は一読に値する。
フォーチュンが中国・日本から持ち出した植物は、中国からは数多くのツツジ、モモ、シャクヤク、ナンテン、ツバキ、レンギョウ、キク、チャノキなどがあり、日本からはツツジ、ユリ、サザンカ、アオキなど多岐にわたる。
なかでも有名なのは、
ツツジ属の彼の名前がつけられたフォーチュネイ(Rhododendron fortunei) 、
フォーチュンのダブルイエローと名付けられたバラ(Rosa 'Fortune's Double Yellow')が知られている。
フォーチュンは、持ち出し禁止のチャノキを20,000本も“ウオードの箱”に梱包し、インドに送るなどの荒業をやったわりには、観察眼が鋭く文才があったのか、出版物の印税で引退後は豊かにのんびりと暮らしたという。
プラントハンターとして非常に珍しいケースであるがホッとする。夢は荒野を駆けめぐるだけでなく、ベットの上を駆け巡るのも良さそうだ。
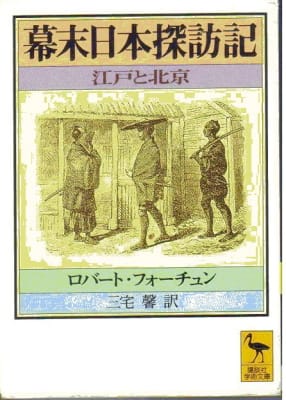
中国・日本のツツジを持っていった英国のプラントハンター:フォーチュン
(写真)セイヨウシャクナゲのつぼみ

「セイヨウシャクナゲ (西洋石楠花)」は、ヒマラヤ周辺を中心とした多数の原種を交配して作出した園芸品種の総称であり、耐寒性に優れ大きな花びらと豊富な花色が特徴だ。アジアの原種が18世紀のヨーロッパに導入され改良が始ったという。
ここには、アジアのツツジ、シャクナゲなどを採取して本国に持ち帰ったヨーロッパのプラントハンター達の活躍がある。
このプラントハンター達を描いてみたいのだが、英国の王立キュー植物園のデータベースには、ツツジ属(Rhododendron)の採取者と採取時期などが登録されているが、採取時期がわかっている最も古いものは、1851年からでありこれ以前がわからない。
また、これから描こうとするプラントハンターの名前が記載されていないのも残念だ。
英国の植物相の貧弱さが珍しい植物へのニーズを創る
1700年代の半ば以降から英国では海外の植物を積極的に導入し始め、組織的に未開拓地の珍しい植物を採りに行き始めた。
もともと緑が少なく、産業革命の進行によるスモッグなどの都市環境の悪化などマイナス面がある一方で、緑を増やそう、都市をデザインしようという動きもあった。
英国の植物がどれだけ貧弱であったかを示す資料がある。1800年前半に活躍した造園家・都市のランドスケープデザイナーで農業・植物に造詣が深いラウダン(Loudon , John Claudius 1783- 1843) は、「英国に自生していた樹木は200種で、そのうちの100種がバラ・イバラ・ヤナギなので品種が少なく貧弱だ。」と述べている。そして、16世紀後半以降の英国人の海外での活動により、アルプス以南の地中海沿岸の植物、北米などの多種多様な植物の美に気づいたという。
ちなみに、日本に自生する樹木の種類は1000種を超えるそうだ。
ラウダンは、1822年に最初の著書として『 The Encyclopedia of Gardening 』など数多くの本を出版し、都市の公園・墓地などの造園、小さな庭に様々な植物を植える美と楽しみを啓蒙し、個人の庭の緑、公園・墓地などの公共の緑、これらが織り成す都市としての景観・ランドスケープの計画を提唱し、小さな庭に海外からの新奇な植物を受け入れるコンセプトを生み出し、プラントハンターの活動を容認し側面から支援した。
プラントハンターの直接的な支援者は、王立キュー植物園、王立エジンバラ植物園などの植物園・博物館、そしてリー&ケネディ商会、ヴィーチ商会などのナーサリーと呼ばれる育種園、そして、産業革命で登場した成功者であり、英国にない植物、他にはない庭を持ちたいという人たちであった。緑が少ない英国だからこそ、珍しい庭とそれを彩る植物がステイタスシンボルとなったのだろう。産業革命の恩恵であるガラス、それを使った温室が英国では育てられない植物の栽培をも可能とした。
19世紀半ば頃まで謎に満ちていた中国と日本
中国清朝と日本の江戸幕府は、それぞれ鎖国政策を採り、貿易は広州、長崎一港に限られていたので、現在的に言えば北朝鮮のように謎の国であった。
この気持ちよい眠りは強引に破られることになるが、中国清朝政府はアヘン戦争後の1842年の南京条約で香港の割譲、広東、厦門、福州、寧波、上海の5港を開港した。
10年ほど遅れるがほぼ同じ時期の日本では、江戸幕府がペリー提督の軍艦と大砲に永い眠りを覚まされ1854年に日米和親条約を結び、1859年には、箱館・横浜・長崎・新潟・神戸の5港を開港した。
鎖国の時は、オランダ東インド会社の医師として長崎出島に来たツンベルク、シーボルト等の日本植物誌によって豊かな日本の植物相が垣間見られ、ヨーロッパで話題になっていた。
この珍しい植物の宝庫と思われていた中国と日本の開国は、プラントハンターにとっても朗報であり、彼らたちの活躍のフィールドが広がった。
開国前で、記録に残っている中国での最初のコレクターは、植物採取のアマチュアのカニンガム(Cuninghame, James 1697‐1719)のようだ。彼は英国東インド会社の医師として雇われ、1698年にアモイに派遣された。1701年の後半に中国のチャサンに航海し、2年以上滞在しこのエリアでの植物の採取を行った。そして、乾燥した標本600種以上を本国に送り、本人も1709年にイングランドに戻った。
確かに日本でも、長崎出島に封じ込められ、植物採取は近隣のところと日本人を使って採取するか植木屋から購入するなど限られていた。ましてやツツジは持ち出し禁止されている植物でもあった。プラントハンター泣かせの国であったことは間違いない。
プラントハンターの偉大な巨人、フォーチュン

この両国の記念すべき開国に立ち会ったプラントハンターが一人いる。スコットランドの園芸家、ロバート・フォーチュン(Fortune、Robert 1812‐1880)で、東インド会社をスポンサーにインド・アッサムに清国からのチャノキを持って行き、この移植栽培に成功させ、イギリスの紅茶産業を発展させた功労者でもある。これは、フォーチュン二回目の中国探検で、1848年に実施された。
フォーチュンが始めて中国に来たのは、1842年、アヘン戦争に敗れた清国が南京条約を結び、香港の割譲、広東など5港の開港をする年だが、この情報を聞きつけたエジンバラ王立園芸協会は、フォーチュンを清国に派遣することにし、採取して欲しい植物の長たらしいリストを渡した。
フォーチュン30歳の時であり、翌1843年2月に英国を出港し、7月に香港に到着し3年間滞在した。この間にフィリピンへ「ラン(Phalaenopsis amabilis)」を採取する短い旅行を行い、エジンバラ園芸協会の要望に見事に答え、アネモネ、キク、ラン、スモモ、スイカズラなど多数の植物を英国に送った。
最も、この時点での中国は、自由に野山を探検旅行することが出来ず、中国人或いは園芸商から購入する以外なかったが、フォーチュンは大胆にもヒゲを伸ばし弁髪になり中国人に変装して禁止されている地域、野山の探索を行ったという。
この現地に溶け込む自在性の情報収集能力が、だまされない目利きとして制約があるなかでの成果に結びついたのだろう。
余談だが、フォーチュンが書いた『江戸と北京』(1863年出版)の本の中では、中国人商人のうそつきとフォーチュンが外出するたびに監視と警護のためにゾロゾロとついて来る日本の小役人のたかり根性を嫌っていたのが印象に残る。最も十分な給料を支払えなかったのでワイロで生計を立てなければならなかったという幕府財政の逼迫があることも否めない。
フォーチュン三回目の中国訪問は、アメリカ合衆国政府をスポンサーに1858年に実施された。アメリカの政府からは、彼が実績のある中国のチャノキの調査であり、あわせてロンドンの育種商スタンディッシュからは珍しい植物の採取をも依頼されていた。
ちょうど、日本の開国の情報を聞き、1860年10月及び1861年4月に再び訪問をする。
フォーチュンは日本の第一印象を「私はこの未知の国の話を沢山読んだり聞いている。・・(略)・・初めて長崎の海岸を見たとき・・(略)・・むしろ自然の庭園そのものであった。」
江戸では、団子坂、王子、染井村など植木屋が密集しているところを探索し、彼が知っている世界で最高の園芸技術と文化を持っていると評価している。
英国人が見た古きよき日本を見直す本としても『江戸と北京』は一読に値する。
フォーチュンが中国・日本から持ち出した植物は、中国からは数多くのツツジ、モモ、シャクヤク、ナンテン、ツバキ、レンギョウ、キク、チャノキなどがあり、日本からはツツジ、ユリ、サザンカ、アオキなど多岐にわたる。
なかでも有名なのは、
ツツジ属の彼の名前がつけられたフォーチュネイ(Rhododendron fortunei) 、
フォーチュンのダブルイエローと名付けられたバラ(Rosa 'Fortune's Double Yellow')が知られている。
フォーチュンは、持ち出し禁止のチャノキを20,000本も“ウオードの箱”に梱包し、インドに送るなどの荒業をやったわりには、観察眼が鋭く文才があったのか、出版物の印税で引退後は豊かにのんびりと暮らしたという。
プラントハンターとして非常に珍しいケースであるがホッとする。夢は荒野を駆けめぐるだけでなく、ベットの上を駆け巡るのも良さそうだ。