先日、幕別町忠類(旧虫類村)にある“ナウマン象記念館”に行ってきた。忠類地区は、人口約1,500人で、牛(乳牛、肉牛)が11,000頭いて、人間1人に対して7頭いる酪農主体の地区である。
この旧虫類村では50年前、太古の動物といわれるナウマン象の化石が、ほぼ原形に近い形で発見された。私の母親の実家があったすぐ近くである。
発見場所は、地質学的に第四紀層と言われる地層の中であった。第四紀層とは、地質年代区分の呼び名にひとつで、古い順に先カンブリア代、古生代、中生代、新生代と呼ばれ、第四紀はこの中の新生代に属する。なお、人類はこの時代に出現したといわれる。
ナウマン象は南方系のマンモスで、マンモスは現生のゾウの類縁であるが、直接の祖先ではないそうだ。ナウマン象は 30~2 万 年前の日本や朝鮮半島、中国などの南方に住んでいた対し、マンモスは 400~1 万年前の ユーラシア大陸北部からアラスカ・カナダ東部にかけての北方に住んでいたという。
ナウマン象がほぼ原形に近い形で発見された理由は、象は重量があるから、湿地帯で動けなくなりそのまま死んでしまった可能性が高いという。発見した偶然性や湿地で死んでいったとみられる偶然性など、奇跡とも思える偶然性が、太古の日本や人類の歴史を解明する手掛かりを与えてくれた。
ナウマンゾウは、明治初期、東大教授をしていたドイツ人「ナウマン」が、日本に存在していた象を研究していたのにちなんで名づけられたそうである。
「十勝の活性化を考える会」会長
注) 忠類ナウマン象記念館
現在、絶滅したナウマン象は、約2〜3万年前の新生代更新世後期まで日本列島や東アジア大陸に生息していたと言われています。
現代のアジア象と比べるとやや小型で体高は2.5m〜3m。氷河期時代の寒冷な気候に順応するため、全身は体毛で覆われていて皮下脂肪が発達していたと伝えられています。
ひとつの偶然が生んだ世紀の発掘・・・
「カチン!」
それは、忠類村(当時)の歴史を大きく変える衝撃の音でした。
日本で初めて全身骨格の復元に成功したナウマン象の化石は、1969(昭和44)年7月、忠類晩成地区の農道工事現場で偶然に発見されました。
側溝掘り作業の際、アルバイトの少年がツルハシを地面に打ち下ろした先に、湯たんぽのような模様がある楕円形の塊(かたまり)が出てきました。少年はそれが理科の教科書に載っているゾウの歯によく似ていることに気づきました。 そして、専門家による調査の結果、その掘り起こされた塊が、なんとナウマン象の臼歯だということが分かったのです。
長い眠りから目覚めた大昔の古代ロマン
その後の発掘調査には、全国から多くの研究者、教師、学生らが参加し、全骨格の70〜80%にあたる計47個の化石を掘り出しました。世紀の発掘に関わった研究者は168人。当時約3千人の静かな村に、村内外からの見物客なども約1万6千人集まり、村を挙げての大発掘となったのです。
(幕別町観光物産協会ホームページより)

















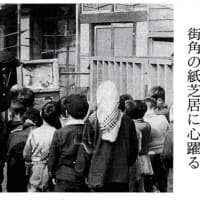


※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます