先日、福島大学教授 工藤雅樹著“古代蝦夷”を読んだ。この本には、蝦夷(エミシ)のことが分かりやすく書かれていた。エミシには、アイヌ説と辺民説がある。辺民とは、辺鄙な所に住んでいる民を意味するので、北海道はむかし、辺鄙なところであったらしい。
日本の歴史を紐解いてみよう。日本列島が、今のように海に囲まれた島国になったのは約2万年前の最終氷河期で、気温が上昇し海水面が約150m上昇して大陸から切り離された。列島となった日本には、旧石器時代後期(縄文時代)から東南アジアから北上してきたモンゴロイドの先住民が住んでいた。
この人々が縄文人で、「縄文文化」が日本列島で生まれたが、その後、中国大陸の揚子江付近に住んでいた人々が、幾度となく渡来してくる。この人々が渡来系弥生人である。弥生人は、稲作文化と金属器文化を持ち、縄文人と混血しながら古代文化の基礎となる「弥生文化」を、さらにその後の「古墳文化」を、九州から西日本で発展させていった。
渡来系弥生人は、混血を繰り返しながら日本人の原型が形成された。だが、弥生文化は東日本まで十分に浸透せず、弥生時代の末期でも東日本や西日本の一部では、縄文文化が色濃く残ったといわれる。やがて、大和に初期大和政権が誕生すると、大和政権は弥生文化を拒否する人々を “隼人”とか”エミシ(蝦夷)”と呼んで差別すると共に、兵を派遣して弥生文化の浸透を図っている。
大和民族が、日本人全体で見た場合のDNAの比率は、縄文人系が約20%、弥生人系が約80%という調査結果もあり、日本民族は縄文人と弥生人とのハーフなのである。縄文人が日本人の起源といわれるが、混血の過程で一部のエミシは新しい文化を受入れ、大和政権の傘下に入り同化していった。
しかし、狩猟採集文化を大切にした別のエミシは混血などを繰り返しながら北へ北へと逃れて、明治時代には北海道(蝦夷地)に住むだけとなった。そうした人々が「アイヌ」とよばれるようになったのである。
一方、本州に残ったエミシ(アイヌ)は和人との混血により、また外見上からもアイヌと呼ばれなくなり、現在に至っているのである。だから言うなれば、民族学者 瀬川拓郎教授が言っているように、アイヌが本家であり和人は分家であると思っている。
生命誌ジャーナルに掲載された神崎秀明氏(国立科学博物館 人類研究部研究員)の “縄文人の核ゲノムから人類の歴史を読み解く”を読むと、人類の歴史が分かってくるので、その図の一部を参考までに載せよう。

図10:縄文人の核ゲノム解析から見えてきた日本列島人の成立ち
先日、樺太アイヌ協会主催のオンライン講座に参加した。その際、樺太アイヌ協会の会長は、樺太アイヌはいるが、アイヌ民族などという“民族”はいないと言っていた。即ち、アイヌには、民族名はないということである。北海道には北海道アイヌはいるが、北海道アイヌ民族はいないということである。私は関西に住んでいたことがある。関西では関西の人を“関西人”というが関西民族とは全くいわないのである。これからはアイヌという表現にも気をつけたいと思っている。
先日、40年年ぶりに「北海道開拓記念館」に行くと、その展示物にはいたるところに、アイヌ民族と書かれていた。北海道人はみんなアイヌであったから、北海道にはむかしアイヌが住んでいたと書くべきだろう。アイヌ民族と書くのは間違いのように感じたのは、私だけではあるまい。
「十勝の活性化を考える会」会員

















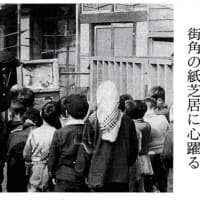


※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます