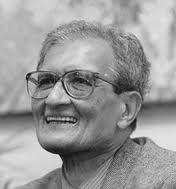
今朝の新聞記事から、思いがどんどん広がってゆく。
まとまりに欠く雑感となるがインドの経済学者アマルティア・センについて書いてみたい。
取っ掛かりは、こういう新聞記事だ。
熊野の山奥の旧小学校校舎に住み、地域に残された高齢者たちと共生する若者がいる。
島根県の高齢者世帯が4割を占める団地(買い物難民の独居世帯が多い)に「軽トラ市」という
近郊の過疎の村から定期的に野菜を訪問販売する試みが成功している。
そんな事例を報告しながら記者は、こう続ける。
生活の豊さは何で決まるのか。持っているお金の量?
それともその人が抱く満足感?
いずれも不十分と考えたのが、インドの経済学者アマルティア・センだ。
所得の不平等や貧困、飢餓の研究で1998年、アジア初のノーベル経済学賞を受けた。
中略
センは個人が実際に選べる生活の「幅」こそが本質だとした。
主流の経済学や政治哲学が、社会が保障すべき「平等」の問題をお金や財などの分配から考えたのに対して、
センは実際のそれらが使われて「機能」が発揮される「場」で考える。
お金の量よりも、お金によってその人が実現できる選択肢の「幅」がどれくらいかを重視した。
中略
団地の住民と農家、都会で疲れた若者と過疎化が進む田舎の間で生まれた緩やかなつながりは、
お互いの生活の「幅」を広げたと考えれば、豊かさを生み出していると言える。
お金やモノを追求することばかりに価値を置かないセンの立ち位置は、
私たちの生きるヒントにもなりそうだ。
ネット検索の結果、色んな人たちの文章を読んだ。
特に印象に残った2つの記事を貼っておきます。
http://1000ya.isis.ne.jp/1344.html
http://purupagi-diary.blog.so-net.ne.jp/2012-11-17
アマルティア・センの唱える民主主義へのアプローチに小熊英二との近似性を覚えた。
なんだ12/22付の新聞のインタヴューで「お任せ民主主義は限界ですか?」という記者の質問に、彼はこう答えている。
「インドの経済学者アマルティア・センの考えでは、民主主義とは投票制度や形式的平等ではない。
誰もが決定に参加できることが民主主義なのです。
その過程で人々が考え発言し潜在能力が上がる。
所得が高くなくとも人生のどのステージでも誰もが承認され、尊重され、能力を高められる。
そんな社会を作ることこそが目的です。
政府の大小や代議制、GDPや株価は、その手段であって目的ではない。
形だけ選挙をやっても、後は全部お任せしかないのでは能力は上がらない。
決定に参加できた実感もない。
だから正統性が上がらず、政治も社会も力強くならないのです。」
アマルティア・センは昨年、福島大学で「東日本大震災からの復興 、人間の安全保障をもとめて」という講演を行っている。

















※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます