↓↓ 二つのサイトの陶芸ランキングに参加してます。バナーをポチッと応援クリックしてね! 人差し指や中指でトントン。
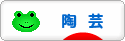 にほんブログ村
にほんブログ村  人気ブログランキング
人気ブログランキング
手びねりでも基本を終えて、熟達してくると回転を入れて成形します。
電動ろくろで成形した作品とほとんど遜色のないものが出来ます。
手びねりの玉づくりで作陶中の恵良さんのスナップです。
この日は、大皿を 1枚、飯碗を 1碗、輪花小鉢を 1個作っていました。
大皿 (30㎝径) を制作中


飯碗を制作中



尚、手びねりの基礎の段階では回転は入れません。
下記のようにコテで小まめに広げて行きます。
これが 「基礎」 です。「基礎」 をつくってから、
次のステップ (中級課程の後半) で回転を入れて成形をします。
ろくろで成形した作品と遜色のない器が作れるようになります。
手びねりの基礎を学んでいる新入会の江島さんの飯碗の作陶です。



飯碗は小さな器ですが、お茶碗の形にしなければなりません。
恵良さんは朝顔型の飯碗です。江島さんはお碗型の飯碗です。
又、飯碗は手に持って使う器ですから軽く作らないといけません。
陶芸を始めたばかりでは、飯碗は作るのが難しいので、
カリキュラムでは中級コースの課程にしています。
ブログに連載中の 「日日是好日」 を終えたら、次は、
「手びねりの基本」 について連載しようと思っています。
さらに、手びねりが終わったら 「ろくろ挽きの基本」 についても
記載して行きたいと思っています。基本を知って欲しいと思っています。
尚、詳細については、アマゾンで売れ筋 No.1 にもなったことがある
拙著 『生活にうるおいを与える食器づくり』 に記述しています。
<追記>
「陶芸の基本 (元祖陶芸?! 目から鱗が落ちる!)」
の連載を2021年1月11日から始めました。下記をクリックするとご覧いただけます。
① 連載1(2021/1/11): 陶芸の基本 (オーソドックスな陶芸)
② 連載2(2021/1/13): 陶芸の基本技法とは
③ 連載3(2021/1/15): 玉づくり (手びねりの基本)
④ 連載4(2021/1/17): 小鉢、中鉢、大鉢づくり
⑤ 連載5(2021/1/19): 中皿、大皿づくり
⑥ 連載6(2021/1/21): 手びねり上級編 (最終目標)
⑦ 連載7(2021/1/23): 手びねりの削り
※ 「ろくろ」 と 「用具」 については追って連載します。
 陶芸ランキング
陶芸ランキング  にほんブログ村
にほんブログ村
↑↑ 励ましのクリックをしてあげてね!! にほんブログ村 陶芸ランキングで 1位、もう一つの陶芸ランキングでも 1位です。
☆ 教室案内 : https://blog.goo.ne.jp/asuka1
☆ 自費出版 : 『生活にうるおいを与える食器づくり』
こういう本があるといい。こういう本が欲しかった。残りは僅か。
アマゾンの陶芸ベストセラーでNo.1 にランクされたこともある実用書。
アマゾンへは、こちら をクリック。定価は1,400円です。
リユース本には、5,000円のプレミアムも付いてます!!
完売御礼
☆ お陰さまで拙著が 10月末で完売しました ☆
尚、通販元によっては、在庫が1、2部ほど残ってるかも知れません。
又、手元には予備が 5部ほどありますので、ご希望の方は教室宛に
書籍代 1,400円と送料 200円を同封のうえご注文願います。
生徒さんも名著を読み返してね。復習になります。
いいことが書いてあるよね! 正統派です。
※ 1月16日から 「いいね」 などの表示ボタンもアップしてみました。
どれをクリックしてもブログ画面は変わりません。
Goo ブロガー以外の方は、ログインが必要になるかも知れませんが、
クリックして見て下さい。
 人気ブログランキング
人気ブログランキング手びねりでも基本を終えて、熟達してくると回転を入れて成形します。
電動ろくろで成形した作品とほとんど遜色のないものが出来ます。
手びねりの玉づくりで作陶中の恵良さんのスナップです。
この日は、大皿を 1枚、飯碗を 1碗、輪花小鉢を 1個作っていました。
大皿 (30㎝径) を制作中


飯碗を制作中



尚、手びねりの基礎の段階では回転は入れません。
下記のようにコテで小まめに広げて行きます。
これが 「基礎」 です。「基礎」 をつくってから、
次のステップ (中級課程の後半) で回転を入れて成形をします。
ろくろで成形した作品と遜色のない器が作れるようになります。
手びねりの基礎を学んでいる新入会の江島さんの飯碗の作陶です。



飯碗は小さな器ですが、お茶碗の形にしなければなりません。
恵良さんは朝顔型の飯碗です。江島さんはお碗型の飯碗です。
又、飯碗は手に持って使う器ですから軽く作らないといけません。
陶芸を始めたばかりでは、飯碗は作るのが難しいので、
カリキュラムでは中級コースの課程にしています。
ブログに連載中の 「日日是好日」 を終えたら、次は、
「手びねりの基本」 について連載しようと思っています。
さらに、手びねりが終わったら 「ろくろ挽きの基本」 についても
記載して行きたいと思っています。基本を知って欲しいと思っています。
尚、詳細については、アマゾンで売れ筋 No.1 にもなったことがある
拙著 『生活にうるおいを与える食器づくり』 に記述しています。
<追記>
「陶芸の基本 (元祖陶芸?! 目から鱗が落ちる!)」
の連載を2021年1月11日から始めました。下記をクリックするとご覧いただけます。
① 連載1(2021/1/11): 陶芸の基本 (オーソドックスな陶芸)
② 連載2(2021/1/13): 陶芸の基本技法とは
③ 連載3(2021/1/15): 玉づくり (手びねりの基本)
④ 連載4(2021/1/17): 小鉢、中鉢、大鉢づくり
⑤ 連載5(2021/1/19): 中皿、大皿づくり
⑥ 連載6(2021/1/21): 手びねり上級編 (最終目標)
⑦ 連載7(2021/1/23): 手びねりの削り
※ 「ろくろ」 と 「用具」 については追って連載します。
 陶芸ランキング
陶芸ランキング ↑↑ 励ましのクリックをしてあげてね!! にほんブログ村 陶芸ランキングで 1位、もう一つの陶芸ランキングでも 1位です。
大分市内にある数少ない 陶芸教室 「夢工房あすか」 です。
意外にも近くにあるのに気付かない人たちが多いですが、
下記の教室案内をご覧下さい。陶芸を基礎からコツコツと学ぼ~う。
電動ろくろもスムーズに習得できます。
意外にも近くにあるのに気付かない人たちが多いですが、
下記の教室案内をご覧下さい。陶芸を基礎からコツコツと学ぼ~う。
電動ろくろもスムーズに習得できます。
☆ 教室案内 : https://blog.goo.ne.jp/asuka1
☆ 自費出版 : 『生活にうるおいを与える食器づくり』
こういう本があるといい。こういう本が欲しかった。残りは僅か。
アマゾンの陶芸ベストセラーでNo.1 にランクされたこともある実用書。
アマゾンへは、こちら をクリック。定価は1,400円です。
リユース本には、5,000円のプレミアムも付いてます!!
完売御礼
☆ お陰さまで拙著が 10月末で完売しました ☆
尚、通販元によっては、在庫が1、2部ほど残ってるかも知れません。
又、手元には予備が 5部ほどありますので、ご希望の方は教室宛に
書籍代 1,400円と送料 200円を同封のうえご注文願います。
生徒さんも名著を読み返してね。復習になります。
いいことが書いてあるよね! 正統派です。
※ 1月16日から 「いいね」 などの表示ボタンもアップしてみました。
どれをクリックしてもブログ画面は変わりません。
Goo ブロガー以外の方は、ログインが必要になるかも知れませんが、
クリックして見て下さい。



























