皆様こんにちは
山三三ツ屋染舗の三ツ屋邦孝です。
いつも当ブログをご覧いただき誠にありがとうございます。
先輩のクリーニング業者から52年前の昭和48年(1973年)発行の「クリーニングの基礎知識」
の本をお借りしました。本を読んで52年前のしみ抜きの事が分かりました。


クリーニングの基礎知識(昭和48年5月発行)

クリーニング基礎知識 目次
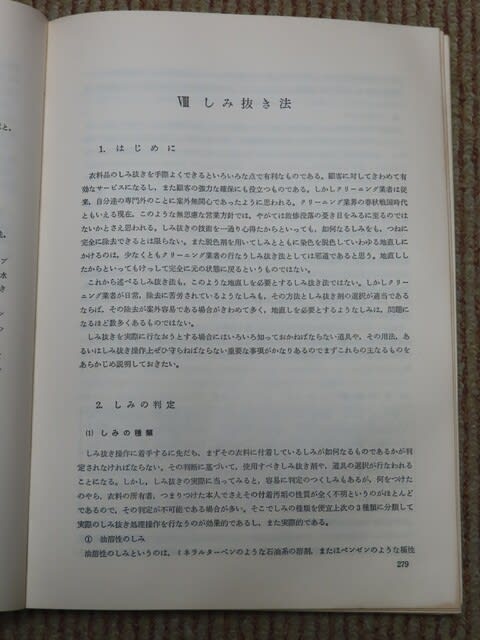
クリーニングの基礎知識 P279
Ⅷ しみ抜き法
1. はじめに
衣料品のしみ抜きを手際よくできるといろいろな点で有効なものである。顧客に対してきわめて
有効なサービスになるし、また顧客の強力な確保にも役立つものである。しかしクリーニング業
者は従来、自分達の専門外のことに案外無関心であったように思われる。クリーニング業界の春
秋時代ともいえる現在、このような無思慮な営業方針では、やがては敗惨没落の憂き目をみるに
至るのではないかとさえ思われる。しみ抜きの技術を一通り心得たからといっても、如何なるしみ
をも、つねに完全に除去できるとは限らない、また脱色剤を用いてしみとともに染色を脱色して
いわゆる地直しにかけるのは、少なくともクリーニング業者の行うしみ抜き法としては邪道である
と思う。地直ししたからといってもけっして完全に元の状態に戻るというものではない。
これから述べるしみ抜き法も、このような地直しを必要とするしみ抜き法ではない。しかし
クリーニング業者が日常、除去に苦労されているようなしみも、その方法としみ抜き剤の選択
が適当であるならば、除去が案外容易である場合がきわめて多く、地直しを必要とするような
しみは、問題になるほど数多くあるものではない。
しみ抜きを実際に行おうする場合にはいろいろ知っておかねばならない道具や、その用法、あるい
はしみ抜き操作上ぜひ守らねばならない重要な事項がかなりあるのでまずこれらの主なるものを
あらかじめ説明しておきたい。


クリーニングの基礎知識 P281~P282
3. しみ抜きに用いられる器具やその用法
(1) 機械法
スチームスポッター機(蒸気しみ抜き機)と登場して間もない超音波洗浄機の事が
書かれています。
この当時はやっと超音波洗浄器やスプレーガンがやっと登場だした頃でまだ十分に機器を
使いこなしていなかった時代ですので、事故も多かったと思います。
これ以前は、和式のしみ抜き道具は水木と呼ばれていたパッキンブラシを使用していましたし
クリーニング業界では濡れタオルで叩く事や下記のブラシやを使用していた為に技術の習得が
困難だった事や、、使用薬品のゆすぎ出しが非常に手間が掛かった事により薬品残留での
経時変化による黄変事故が多発していたと思われます。
私自身修業時代もタオルの下敷きにしてスプレーガンを使用してのしみ抜きを行っていましたが、
師匠から習ったスプレーガンの使用法を学んで使用していた為に記事の穴開きや目開き事故は
有りませんでした。現在は従来のスプレーガンよりも霧の細かいスプレーガンと下敷きのタオルは
バキュームモーターでの吸引に変わって薬剤残留による経時変化が激減しました。

クリーニングの基礎知識 P282
(2) 道具
竹ベラ、しみ抜き用ブラシ、しみ抜き用手鏝の事が書いています。
4.しみ抜きを完了してからの後処理
5.しみ抜き剤
6.しみ抜き操作の実際 P286~P323
37ページにわたってしみ抜きの方法が掲載されています。
この当時どんなしみが多かったかがよくわかります。
(1) 塗料のしみ抜き
(a) ラッカーのしみ
(b) エナメルのしみ
(c) ペンキのしみ
塗料のしみですが、この当時建設ラッシュでしたし、現在は建築現場外部のの足場にテントを
張って養生している事で塗料やペンキのしみは、ほぼ無くなっていると思います。
(2) チューインガムのしみ抜き
次にチューインガムのしみですが、この当時はガムのしみ抜きが多かったのでしょうが、最近は
プロ野球選手が試合中にガムを噛んでいますが、あまりガムを噛んでいる人を見かける事が皆無と
なりました、私自身着物のしみ抜きがメインだった事からガムのしみ抜きをした事がありません。
(3) 血液のしみ抜き
つぎは血液のしみですが、血液のしみは現在でもよくあるしみです。人血や動物の血液や魚の血液も
あります、新しい物であれが、中性洗剤の水溶液で処理しても落ちますが、付着して時間が
経った場合は血液中のたんぱく質の部分が凝固する為の水洗い(水処理)でも落ちない為に
凝固した蛋白質を除去する為にむかしはうぐいすの糞を使用していましたが、現在は高性能な
蛋白分解酵素を使用しています。蛋白分解酵素は湿度(濡れた状態)、温度(温度40℃~45℃)と
時間(30分以上)の条件下でたんぱく質の部分が除去できますが、残った色素は、過酸化水素水や
過炭酸ナトリウムで酸化漂白を行うと除去できますが、酵素処理は時間が掛かる為に水処理後に
酸化漂白を行いしみが残って失敗している事例もよく見ます、蛋白分解酵素処理がとても重要と
なります。
(4) 泥のしみ抜き
① 濃色に染色した羊毛地、又は化繊地に付着した泥のしみ
② 絹地の高級和服に付着した泥のしみ
③ シールやビロードの泥じみ
④ パイルがアセテートのビロードの泥じみ
⑤ 木綿、麻、等のしみ
泥はねのしみもこの当時は道路が悪かった事と撥水加工が普及してなかった事が原因で泥はねの
しみは非常に多かったです。当然修業時代は泥はねのしみ抜きもとても多かったです。
石油系溶剤でブラシングしてから丸洗い(ドライクリーニング)を行いますが、泥はねは
ほとんど落ちない無い為にその後にしみ抜き工程で泥はねしみを除去しました。
泥はねのしみ抜きはスプレーガンを使いでこなす練習に最適なしみでした。
泥はねの部分に油性のしみ抜き剤を付けて、ブラスで叩いた後に、指先でスレが出ないように
やさしく揉んで泥はねに薬剤を浸透させた後に、生地に目依れや穴が開かない圧力調整をして
スプレーガンで油性のしみ抜き用溶剤で洗浄して除去します。この後に落ちない場合は化粧石鹸
を濡らした刷毛で付けて、ブラシで叩いた後に、スプレーガンで水を使用して除去していました。
この工程で舗90%の泥はねは除去できましたが、これでも落ちない場合は、黄変しみ抜きを行い
最後にサビ取り剤を使用するとほとんどの泥はねしみは除去出来ました。
現在はしみ抜き剤の性能の向上したので、油性のしみ抜き剤を付けて指先で揉んだ後にスプレーガン
で油性のしみ抜き溶剤の使用でほぼ100%除去出来ています。
(5) カビのしみ
① 青カビの場合
② 赤カビの場合
カビのしみですが、この本に書いてある時代は白綿地の場合は次亜塩素酸ナトリウムを使用しての
カビ落とします。他の場合は過マンガン酸カリを使用してのカビ落とし行っている事が書かれて
いますが、染色の事を考えると難しい処理になります。
現在は染色に対して影響が少ない過炭酸ナトリウムの登場と過酸化水素水用の高性能助剤が
出てきた為に過マンガン酸カリを使用する事無くなりました。
着物の喪服等に生える白カビは修業時代はブラシング後に石油系溶剤で丸洗いを行ってもあまり落ち
ませんでした。次に油性のスプレーガンで処理していました。
現在は抗菌・防カビ剤入りのドライソープでブラッシング後に同じドライソープの入った石油系
溶剤で必要洗浄時間で洗うと白カビもカビ臭の除去できます。
着物の胴裏や表地全体に生えた黄色いカビは黄変しみと一緒なので、水洗い後に過酸化水素水で
漂白して除去していますし、洋服の場合は過酸化水素水や過炭酸ナトリウムを使用して酸化漂白で
除去していますが、染色との関係があり薬剤に耐えられない場合は作業が出来ませんが過マンガン酸
カリよりも漂白力は弱いですが、染料に対して脱色する事が無い為にしみ抜きや全体漂白に使用でき
ます。
(6) 金属化合物のしみ
① 酸化鉄のしみ
② 銅化合物のしみ
(a) 塩基性炭酸銅(緑青)のしみ
(b)銅の塩化物のしみ
(c)銅のアンモニア塩の水酸化物のしみ
(d)酸化銅のしみ
金属化合物のしみは現在ほとんどはお目に掛かる事ないので、省略します。
(7) 黄褐色のしみの除去
黄褐色しみ(黄変しみ)は以前に記事にしたために下記の記事をご覧下さい。
黄変しみのページ参照 → http://blog.goo.ne.jp/toyo32892/d/20250111
(8) 化粧品類のしみ
①アイシャドウのしみ
②口紅、眉墨、頬紅しみ
③おしろいのしみ
④マニュキュアしみ
⑤コールドクリームしみ
化粧品のしみは現在も多いしみです。
修業時代に日本舞踊で日本手ぬぐいを噛む為に濃い口紅が付いて他の業者に出しても
完全に落ちないけれども、修業先の泉州生洗い本舗おくながでは綺麗に落ちるのは、
どの様なしみ抜きをしているかを問われて、師匠の奥様が企業秘密なので教えられない
と言っていた事を思い出しました。
またみけし洗い小出富勝の先生の講習会でお聞きしましたが、着物に黒いしみが付いていて、
墨のしみかと思い、うぐいすの糞を何度も使ったが除去出来なかったが、黒いしみはアイライン
なので油性のしみ抜き剤を使用して除去した事なども思い起こされます。
マニキュア(ネール)しみはマニキュア除光液の成分にアセトンという成分が入って
いますが、アセトンのみではマニキュアしみが除去できなかった為に、マニキュアしみに
マニキュア除光液で落とした後に油性処理と水処理をして経時変化を防いだ記憶があります。
(9) インクのしみ
①青インクのしみ
②赤インクのしみ
③黒インクのしみ
インクのしみ抜きですが、以前は万年筆をジャケットの内ポケットに入れてインクが漏れて
表地に付着していたしみ抜きを良くやりました。一部解いて、ポケット地、裏地、芯地、
表地の順にしみ抜きしていきます。いきなり表地のしみ抜きするとポケット地に大量のインクが
付いている為に油性処理で取り切るつもりでやらないと完全に除去出来ない為に手間ひまと
忍耐と諦めない心が必要です。
現在は万年筆を使用する事は無くなった為に万年筆インクのしみ抜きもここ10年は行っていません。
その代わりにボールペンや筆ペンや蛍光ペンのしみ抜きは非常に増えました。
現在は非常に高性能なしみ抜き剤が有りますが同じしみ抜き剤を使用しても、綺麗に除去出来る
クリーニング業者が少ないと思います。
取引先のクリーニング業者からポリエステル生地のナース服の胸元に50カ所位のボールペンしみが
付いていて、この業者は低価格大量処理をしているので、ドライクリーニング、またはランドリー
処理をしている為に胸ポケットのボールペンしみが付きっぱなしで納品していました。
ナース服のボールペンしみが落ちるかどうか相談されましたので、15分位掛けてしみ抜きを
行った所、「こんなに綺麗になるんですね」と非常に驚いていました。
(10) 油類のしみ
①機械油のしみ
②植物性油にしみ
③乾性油のしみ
油のしみも多いしみです。
クリーニング業者の中には油のしみはドライクリーニングで落ちていると誤解して入り業者も
多いですが、油のしみはドライクリーニング処理では除去する事は出来ません、断言できます。
亡き小出富勝先生のしみ抜きの講習会でがおしゃっていましたが、現在は使用禁止になっている
溶解力の強いエタン溶剤で7回ドライクリーニングしても除去できない油しみに対して、モノクロール
ベンゼン+ドライソープを付けて指先でやさしく揉んで、超音波洗浄機を使用して石油系溶剤で
ゆすぎ出すと油しみは除去出来たとお聞きしました。大正14年発行の高橋新六著「京染の秘訣」の
なかでしみ抜きを失敗しない為にはまずベンジンから使いなさいと記されています。
小出先生がしみ抜き講習会の最後に油しみと蛋白質しみを正しくと除去するた、大抵のしみは
落ちるとおっしゃっていました。
昭和55年に高等学校卒業後に家業の継承の為、大阪府岸和田市の泉州生洗い本舗おくなが
(師匠奥長昭治)にしみ抜き・色掛けと着物の丸洗い・仕上げ(プレス)の技術の基礎を
3年間の修業で習得しました。実家の山三 三ツ屋染舗に入店して45年間のしみ抜き職人と
仕事に従事して来ました。しみ抜きを行って決して避けて通れないのが黄変しみ(黄褐色しみ)
です。着物の場合着用後にお手入れをしないで、保管している為にいざ着用しようとして初めて
気付く為にほとんどが、付いているしみのほとんどは黄変しみです、掛衿の焼け(黄変しみ)
胸の汗しみ、食べこぼしの黄変しみです。黄変しみ抜きを行うと着物に使用している酸性染料の
青系の染料が脱色する為に必ず色掛け(色修正・染色補正・染直し・部分染・地直し)が必要と
なります、しみ抜き・色掛けの技術の無いクリーニング業者は丸洗い(ドライクリーニング)を
行いますが、しみを残したまま仕上げをしてしみが落ちませんでしたと言って、納品しています。
クリーニング業者としてはドライクリーニングで落ちないしみのしみ抜きを行い生地の脱色や
スレの発生で生地を傷めるよりも、取れませんとお返しする事の方が親切との考えがあります。
お客様はクリーニングに出してしみを落として、また着物を着用しようと考えてクリーニング業者に
出します。お客様はしみだらけの着物を着用したいと考えているのかと思います。
洋服の場合でもクリーニング業者の大命題の低価格で大量処理の為に、溶剤管理が悪くて汚れた
ドライクリーニング溶剤で洗った洋服のしみ抜きを行うとしみ抜きした箇所のみ綺麗になります。
再洗いをするか水洗いをして溶剤の汚れを落とすか、色掛けして綺麗になった箇所を汚すかの
選択肢となります。
しみ抜き法のはじめに書かれていますが、「脱色剤を用いて染色を脱色して色掛け(色修正
・染色補正・染直し・部分染・地直し)を行うしみ抜き法はクリーニング業者の行う
しみ抜き法としては邪道であると思う。色掛け(色修正・染色補正・染直し・部分染・地直し)
を行ってもけっして完全に元の状態には戻というものではない。」と書かれています。
50年前のしみ抜きや色掛け技術を取得していないクリーニング業者が書いた本での意見です。
この本を読んで感じた事はクリーニング業者は誰よりもしみ抜き技術を必要としていますが、
低価格で大量処理の大命題がある為に、脱色する漂白や色掛け(色修正・染色補正・染直し
・部分染・地直し)は邪道だと断言しています。本心は喉から手が出るほど必要ですが、
色掛けを含めたしみ抜き技術を習得する方法が分からない為に根本の問題を見ないようにして
現実を避けていると感じています。
私自身しみ抜きの仕事に携わりは早くも45年が経ちました。
汚れた着物を必死に洗い張りして両親の持っている技術では取れないしみを眺めて悔しそうに
「このしみが落ちればもっと良くなるんだ」としみじみと語っていた父の言葉が今も胸中に
響きます。洗い張り職人として真摯に働いていて、さらなる高みを目指していた事が忍ばれます。
私自身もしみ抜き丸洗い(ドライクリーニング)、しみ抜き、色掛け(染色補正)、洗い張り、
湯通し、水洗い、全体漂白、染め替えとお手入れやメンテナンスを行う技術の選択肢も増えました。
クリーニング業者としては邪道な脱色して、色掛けで補正するしみ抜き方法は染色補正師のしみ抜き
職人としては極当たり前の事ですし、お客様のニーズを叶えることは、職人として当然の事と
思います。しみ抜き屋(染色補正技能士)としては当たり前のクリーニングて引き起こした、脱色した
クレーム品を直す事の出来る邪道な色掛け(色修正・染色補正・染直し・部分染・地直し)で補正を
行っています。クリーニング業者は、しみ抜きを行わない為にお客様からの信用を無くしている、
現実を受け入れないといけないと思います。
現在は黄変しみ抜きを行う為の良い薬剤も登場していますし、何よりお客様は綺麗に
してくれるしみ抜き技術を必要としています。
大東和戦争終戦後今年で80年で昭和100年です、低価格大量処理の大命題が岐路に立っていると
感じます。
着物のお手入れと洋服のメンテナンスは
厚生労働大臣認定一級染色補正技能士と
クリーニング師のいる
山三 三ツ屋染舗にご用命下さい。
〒062-090
札幌市豊平区豊平2条2丁目2番20号
電話011-811-6926 FAX011-811-7126
営業時間 9:00~18:00
休日 日曜・祝日
メール mitsuyasenpo@train.ocn.ne.jp
ブログランキングに参加しています!
皆様の応援がとても励みになりますよろしくお願いいたします。
こちらをポチッポチッと押して下さい。
↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓




































