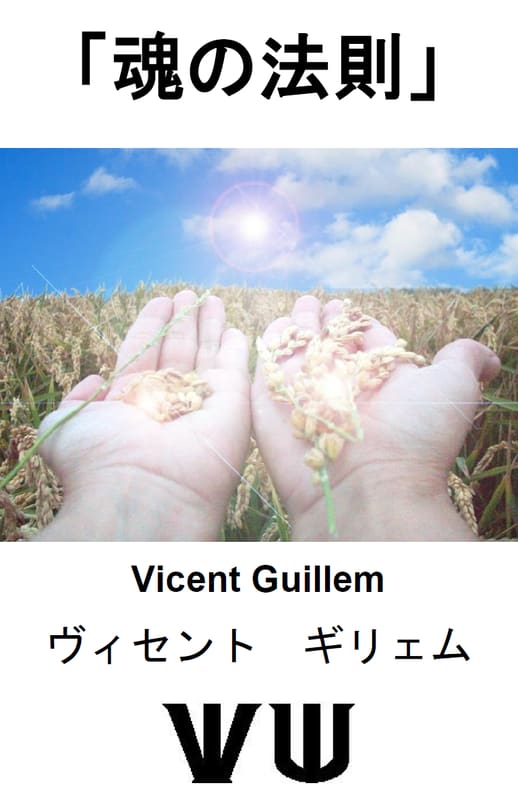少し、細かくかみ砕いていこう!
愛の行使を妨げるもの、
あるいは、
無明、煩悩、に立ち向かう必要がある・・・
立ち向かえば、煩悩即菩提もウソではなくなる!!
無明とは、明かりが無いと書いてある。無い訳ではないだろう。単に曇っているだけだ。曇らすのは、煩悩である。煩悩とは、難しい用語であるが、要するに悩みである。
貪(とん)・瞋(じん)・痴(ち)という、難しい言葉もある。要するに執着である。執着は、肉体人生から生ずる。必然の階梯でもある。それを見つめることは、本然の魂の法則を見つめることにも繋がる。これを煩悩即菩提という。
愛にも多段階の顕現があるように、執着にも階梯がある。一番多いのは、慈悲魔であろう。慈悲魔というのは、愛の押しつけだ。執着を伴った愛であるから、見分けが難しい。執着は執着である。
とは言え、やがては本然の魂の輝きを放つための階梯であると考える。と言うのも、慈悲魔であれ、執着を伴った愛は、実は苦しみなのである。苦しみから脱却しようとして、やがては真実の愛に目覚めるのである。これが、煩悩(苦しみ)即菩提(目覚め)というのであろう。
魂の法則の中でも、重要なことは、知ること、そして、目覚める事である。目覚めることには、実態を見極めることが何よりも重要だ。特に魂に住する心の動きを点検し、無明を拓くことが肝腎だ。
それ以外にない。それが自由意志による魂の願いであろう。自力本願こそ、魂の目覚めの階梯である。
しかし、何と分かり易い指南書が与えられた事であろう。それが、この「魂の法則」その本である。だから、かみ砕いて転載していこうと思う・・・。
尚、全文を読むには、日本語サイト:http://tamashiinohousoku.blogspot.com.esで、ダウンロードできる。
題名: 「魂の法則」
スペイン語原題: “LAS LEYES ESPIRITUALES”
著者: Vicent Guillem Primo ヴィセント ギリェム・プリモ
邦訳: 小坂 真理
知的財産権登録番号 V-2095-08 (Valencia, España)
Copyright © 2008 Vicent Guillem Primo
Japanese Translation Copyright © 2013 Mari Kosaka
ホームページ: http://lasleyesespirituales.blogspot.com.es/
日本語サイト:http://tamashiinohousoku.blogspot.com.es
メールアドレス:tamashiinohousoku@gmail.com
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/deed.es_ES
「魂の法則」 by Vicent Guillem is licensed under aCreative Commons Reconocimiento-NoComercial-SinObraDerivada 3.0 Unported License. Creado a partir de la obra enhttp://lasleyesespirituales.blogspot.com.es/.
本書に修正を加えず営利目的にしない条件で、現在利用可能な全ての媒体によって、本書全体またはその一部の複製を許可するものとする。
【本文転載その⑮開始】
強欲-執着
強欲とは物財の蓄積を過度に熱望することだ。
欲張りな人は、物的には与えられるものを沢山持っているにも関わらず、自分の物だと思っている物を他者と分かち合うことを拒否する。魂の感情認識が進んでも共有ができない場合には、物的な強欲は、霊的な強欲へと変化する。
霊的な強欲とは執着であり、不当に自分の所有物だと考えている人達、例えば子どもやパートナーなどの愛情を分かち合うのが難しい。
執着に苦しむ者は、少数の人しか愛さず、その人達にも同じことを強要する。多くの人が、誤って「愛している」のだと思い込み、相手を強く愛するがために苦しいと言うが、実際には愛着による執着から苦しんでいるのだ。
魂が進歩して初めて、愛と執着との区別がつくようなる。
*愛と執着との違いを説明いただけますか。
人が愛す場合は、愛する人と自分の自由意志を尊重しようと努める。自分がその人と一緒にいられなくても、愛する人が自由で幸せでいられるように尽くすのだ。
執着を患う場合は、愛す人のためになることよりも、自我を満たすことを考える。そのため、愛している筈の人の自由意志を侵害する傾向にあり、その意に反して自分の近くに置こうとしたり、自分のやりたい事を強要したりして、相手と「自分の競争相手」と見なす他の人との関係を最大限妨害しようとする。
本当に愛す者は、愛する人を所有しようとはせず、愛する人が他の人達を愛しても不快に思わない。執着は底をつくかもしれないが、本当の愛・真実の愛は決してなくならない。より沢山の人を愛せるようになっていったとしても、その他への愛が減る訳ではない。しかし執着は、そうだと思い込ませるのだ。他の人達に与えられる愛は、自分から奪われると思わせるのだ。
執着がある者は、感情を要求し強制し強要するのだ。自分がすることの見返りをいつも求める。要求し受け取ることばかりを考え、与える時には利益と引き換えで、最初に自分が頼んだことをしてくれるのが条件だ。執着すると、自分の自由意志すら侵害し、したくないことをするように自己を強要する。
真実の愛を感じる者は、無条件に与え、感情を束縛しない。強制も強要もせず、愛する人に何の見返りも求めず何の要求もしない。
*違いが明らかになる例があればいいのですが。
いいだろう。鳥を愛していると公言する二人が出会ったとしよう。
一人は、冷房の効いた部屋の美しい金のかごの中で鳥を飼っている。高品質のえさをやり、瓶詰めの湧き水を与え、定期的に獣医に連れて行く。もう一人は、単に食べ物を公園に持って行くだけで、鳥が止まればなでてやり、怪我をして飛べない時は世話してやる。
最初の人は、「僕はなんて鳥たちを愛しているんだろう。野生であれば得られない快適さを享受できるように、鳥たちには多額を費やしている! でも直ぐに死んでしまうんだ! いつも病気で、薬や獣医に金を使っても早死にしてしまう。それが酷く辛い! どうしたらいいだろう?」と言う。
二人目は、「僕が世話する鳥たちは、僕のものではない。かごに閉じ込めてはいないし、自然の中で生きている。鳥が僕と一緒にいてくれるのは、かごの格子から出れないためではなく、そうしたいからなので、僕は幸せだ。自由に飛び回り、望むがままに生きているのを見られるので、嬉しい。友よ、君の鳥は自由でないから、悲しみで死んでしまうのだ。好きに羽ばたけるようにかごを開ければ、自由になれて幸せになるので、生き続けるよ」と言う。
最初の者は「かごを開ければ逃げ出して、二度と会えなくなるじゃないか!」と答える。
二人目は、「逃げたとしたら、それは意に反して捕らえられていたからで、隷属した生活から離れたいのだよ。僕の鳥たちは、好きな時に行ったり来たりできると知ってるから、逃げたりしないよ。その反対に、僕が公園に着くのを見ると、直ぐに寄って来て取り囲んでくれて、僕の上に止まるよ」と応じる。
一人目は「それが僕の望みだ。鳥たちに好かれたいんだ」と言う。
二人目は、「強要してでは、絶対に君の望みは叶えられないだろう。君は、彼らが最も切望することの埋め合わせのために、快適さばかりを与えたのだ。鳥は自由に飛びたいのだ。鳥を本当に愛しているのなら、自由に生かしてあげなさい」と返答する。
*愛しているのは誰で、執着しているのは誰ですか。
鳥をかごに入れておきたい人に執着があり、鳥を自由にさせておきたい人が愛しているのだ。
*執着によって他の人の自由意志をどのように侵害してしまうのか、例を示していただけますか。
子どもが大きくなって、恋人ができたからとか、家から離れたところで勉強や仕事をしたいからなどの様々な理由で独立したがる際に、自分のそばに引き留めようとする母親には執着心がある。執着のある母親は、子どもといたいという欲求を押し通そうとし、独立して自分の人生を歩みたいという希望を尊重しようとしない。そして、それが叶わないと感情的に傷つけられた気がして、「子どもは私を愛していない」などの発言に至り、子どもをそばに置こうとする余り、彼らに罪悪感を抱かせるように仕向ける。
「この職業に就きなさい、あの専門を学びなさい」と子どもに要求して、そうしなければ相続権を奪う父親には執着がある。
恋人に着ていい服といけない服や、何時に家から出入りすべきだとか、つき合って良い人と悪い人を指図する人には執着がある。
この偽りの愛が執着であり、それは執着の対象を閉じ込めておく監獄や刑務所のようで、執着に負けた者を牢屋番に変えてしまう。鳥をかごに閉じ込めていた人のように、執着で苦しむ者は、生きることも生かすこともできないのだ。
*執着によって他者の自由意志を踏みにじるというのは理論的ですが、自分自身の自由意志も侵害するかもしれない、ということには驚きました。執着がある時に、どのように自分の自由意志を侵してしまうのか、例を出していただけますか。
いいだろう。例えば、前例の母親が、家族以外の人を支援することなど、自分の心が求めることに時間を割きたいと思っても、そうすると子どもや夫の面倒が見れなくなると考えて、自制してしまう場合だ。
執着を乗り越えなければ、内面を充足させることをする際には罪悪感を覚えるだろうし、その罪の意識によって、そうすることを自分に禁じてしまうかもしれない。
*この例のような執着の顕れ方には驚かされます。家族に尽くす人は、一般的に愛情に満ちた人だと思われていることが多いからです。
それは、執着というものが君たちの文化に深く根づいており、頻繁に愛と混同されているからだ。多くの人は、授かった教育のせいで執着が大層深く、それを自分の個性の一部に同化させてしまっている。
女性には、自分の時間の100%を夫や子どもや仕事に捧げなければ罪悪感を抱かせる。家族以外の人に時間を費やすと、味方である筈の家族からでさえも口さがなく批判され、「自分の家族よりもあの人達の方が大事なの?」とか「一体何でそんな事に関わるんだ? おまえはここに家族と一緒にいるべきだろ」、「人にどう思われるだろうか!」などのコメントで罪を意識させられる。
男性は、慣習的により大きな自由を謳歌してきたが、執着の感情から免がれている訳ではなく、家族でも友達でも同郷(同文化)でもない人に手を貸そうと時間を割くと、特にそれが何の経済的なメリットにもならない場合には、他の人の執着によって非難される。
*でも、家族に専念していても、そこには愛があるのではないですか。
もちろんだ。一方を取ると他方をなくす訳でない。
すでに言ったが繰り返しておこう。真実の愛はなくなることがないのだ。愛す対象が段々と増えていっても、それで家族を愛さなくなる訳ではないのだ。
だが愛の能力が大きいと、大勢の人との約束も多くなるので、自由時間も多くの人と分かち合わねばならない。それが、執着に苦しむ者には、前より少ししか愛してもらえていないと受け取られるのだが、実際にはそうではない。
*人が変わろうと決意すると、家族はどうなるのですか。他者を支援することに時間を割くようになると、自分の家族に手がかけられなくなるのではありませんか。
いいかい、自己変容したいと願い、内面の話ができる他の人達と集まりたいと思う者が出くわす最もきつい障害は、周囲の人達に理解されることがなく、その人達に、家族の義務を果たさないという罪悪感を、弄ばれることだ。
良く観察すれば、誰かが週に一度二時間かけて、おまけにお金も使って、サッカーの観戦やディスコやバーに行っても、その人が家族をないがしろにしているという印象を持つ者はいないと分かるだろう。しかし、同じ人が、自他に役立つように内面に関する話を二時間しに行く場合には、あらゆる難癖をつけられるので、家族を放任してしまったという罪悪感を覚えてしまうのだ。
これは要するに、分かち合うのが困難だという執着のせいだ。執着は愛ではないし、この障害を克服できなければ、君たちは停滞してしまうのだ。
*それでは、家族は霊的進歩の障害となり得るのですか。
いや、障害となるのは、自己成長する気がなく他者にも成長させまいとする魂たちの理解のなさだ。彼らは、進化を願う者を、それが家族のように血の繋がりがある者であっても、手中の全ての武器を駆使して押し留めようと努める。
理解のある家族と暮らす者にとっては、家族が霊的な発展を遂げるための支えとなる。しかし、地上の人類はほとんど成長していないために、霊的な覚醒に取り組もうとする者は少数である。しかも、同じ家族の中に似通った魂がいて、霊的進歩に取り組むつもりであっても、同時に覚醒できることは非常に稀だ。そのため、先陣を切るのが一番難しいのだが、それができる人が、他の者のために道を切り開かないといけない。
かのイエスでさえこれと同じ問題を克服し、執着による家族の理解のなさを乗り越えなければならなかった。イエスの家族は彼を理解できなかったので、霊的事柄に応じるために家の義務を投げ出している、と常にイエスを非難した。気が狂っているとけなし、罪悪感を覚えるように仕向け、ヨセフが亡くなって彼が大家族を養う責任を負う羽目になってからは、特にそれが高じた。だが、それは真実ではない。イエスは、母親と兄弟姉妹が自立できるまで物質的支援をしたのだ。
しかし、彼の使命は、全人類の家族というもっと広範に及ぶものだった。イエスが体験した自分自身の家族の理解の欠如は、福音書の次の一節に反映されている。
そしてイエスは言った、「預言者はどこででも尊敬されるが、自分の郷里と家族の間では敬われない」
*でも、無条件に愛すためには、家族を放棄する必要があるのでしょうか。
霊界が家族の放棄を要求するなど、どうして信じられるのかい? 家族は、魂の最初の感情を刺激する手段として、まさに霊界で創られたのだよ。
夫婦間の愛情や親子間の愛情は、魂が最初に出会う感情で、交配本能や子に対する親の保護本能から発達したものだ。
唯一伝えたいのは、愛において前進するためには、心を開いて分かち合い、家族の概念を広げて、全ての霊的存在がその一部であると考えねばならないということだ。
いいかね、人が愛す時にカテゴリーを設けるとしたら、真の兄弟愛の実現は不可能だろう。自分の家族を一番先にして、同じ故郷・国・人種・文化・宗教の者を優先し、それで残ったものがあれば他者にあげる、となる。
何の見返りも期待しないで与える代わりに、常に何かと引き換えなのは、我欲がカモフラージュされたものなのだ。そのため、与える際にはリストを作成し、最初に自分に沢山くれそうな人を載せ、次にそれ以下の人を記載し、何もくれない人は欄外とするのだ。
このような利己的な態度は、どんなに会員だけの連帯を正当化しようと頑張る人達がいようと、「愛の法則」を侵害している。連帯する権利から誰かを外してしまった瞬間に、連帯という言葉は意味を失うのだ。
このような集団的エゴがどこまでエスカレートできるのかという例は、ナチズムに見ることができる。人種による見せかけの結託を謳い、他の人種や信仰の権利と個人の自由意志を粛清したり排除して、それを捏造したのだ。
*執着は、虚栄の段階にも尊大の段階にも見られると言われましたが、これは克服するのがかなり難しい「エゴ的感情」のようですね。
その通りだ。執着は虚栄の段階に始まり、尊大の段階の最後まで克服されることがない。
*それなら、執着に関しては、虚栄から自尊を経て尊大へと霊的に進化していっても、何の進歩もないのですか。
もちろんあるとも。しかし、進歩は常に緩やかなのだ。
虚栄心の強い者の執着は、自尊心の強い者や尊大な者の執着と同じ強さではないし、同じ要因で増長される訳ではない。虚栄心の強い者は感情が余り発達していないので執着心はずっと強く、他者の自由意志への配慮がなく、甘やかされたり構われたいという思いや進化への意志の弱さなどでそれが増長される。
自尊心の強い者と尊大な者では、執着心は徐々に愛に変化していっているので(愛と執着の両方が混在している)それほど強くないが、愛されないという怖れや愛する者を失う怖れによって増長される。
*強欲と執着は、どう克服するのですか。
強欲の反対は寛大なので、強欲に打ち勝つためには、物的・霊的な寛大さを発展させる必要がある。強欲と執着は、物的面・霊的面で、自分が持っているものを他者と分け合うことで、乗り越えられるのだ。
【本文転載その⑮終了→その⑯に続く】