
斉藤光政、2006年、新人物往来社。新聞の書評でみつけ、買い求めました。著者は青森の地元新聞「東奥日報」の記者。「東日流外三郡誌(つがるそとさんぐんし)」という謎の古文書について、彼が重ねた取材をまとめたものです。
「東日流外三郡誌」中世津軽の歴史と伝承を集め、江戸時代に編纂されたとされています。その物語は遠く古代にまでさかのぼります。日本国主流派の邪馬台国~大和朝廷に対し、東国にて荒覇吐(あらはばき)神をあおぎ「まつろわぬ民」と知られる縄文族の末裔、蝦夷(えみし)の人々と、そのリーダー安倍氏。
日本古代の裏面史とも言える内容になっていて、それはそれで魅力的です。東北の地は中央に対する強いコンプレックスを有し(東北弁は最近まで嘲りの対象であった気がします)、その反面として、宮沢賢治や遠野物語など東北の原日本的な風景は憧憬の対象にもなっています。
『市浦村史資料編』として、まあ公文書として考えて良さそうな(実はそうでもないのですが)、役所発行の村史に収録されるにいたって「外三郡誌」は一定のステータスを得ます。現首相の安倍晋三の父、安倍晋太郎も、蝦夷安倍氏の子孫と持ち上げられ、彼らをまつる石塔山荒覇吐神社を訪問したそうです。
ところがどっこい「外三郡史」は発見者である和田という人物によるでっちあげ、偽書だったと著者は指摘します。その論拠は、筆跡が和田氏と一致すること、古文書の中に用いられる知識、絵図などが明治から甚だしくは戦後のものから引用されていることなど、枚挙にいとまがないようです。荒覇吐神社も彼による建立です。
真書/偽書をめぐって、学者や郷土史家、アマチュア史家、マスコミが喧々愕々の論争を繰り拡げたようです。ただ学者といっても、古田武彦や安本美典といった半アマチュア学者、原田実のようなサブカルライターのような者たちで、その道の権威と呼ばれる人々は黙殺を決め込んでいたようですが。
結局のところ論争は、真の東国縄文文化ともいえる三内丸山遺跡が発見されたことで沈静化したようです。しかし、偽書/贋作のたぐいが受け入れられるのは、それを必要とする人々がいるということだと思います(「外三郡誌」は言わせる人に言わせれば五流の偽書とのことですが)。
誰もが持つ郷土愛、筆者にはまるでそれが薄いのですが、恐ろしいほどに執着する人もいます。それが村おこし町おこしの開発/利権と結びつく時、堂々たる砂上の楼閣が築かれることになるのかもしれません。ところでまた、”国家”も平然と歴史を捏造することがありますね。
「東日流外三郡誌」中世津軽の歴史と伝承を集め、江戸時代に編纂されたとされています。その物語は遠く古代にまでさかのぼります。日本国主流派の邪馬台国~大和朝廷に対し、東国にて荒覇吐(あらはばき)神をあおぎ「まつろわぬ民」と知られる縄文族の末裔、蝦夷(えみし)の人々と、そのリーダー安倍氏。
日本古代の裏面史とも言える内容になっていて、それはそれで魅力的です。東北の地は中央に対する強いコンプレックスを有し(東北弁は最近まで嘲りの対象であった気がします)、その反面として、宮沢賢治や遠野物語など東北の原日本的な風景は憧憬の対象にもなっています。
『市浦村史資料編』として、まあ公文書として考えて良さそうな(実はそうでもないのですが)、役所発行の村史に収録されるにいたって「外三郡誌」は一定のステータスを得ます。現首相の安倍晋三の父、安倍晋太郎も、蝦夷安倍氏の子孫と持ち上げられ、彼らをまつる石塔山荒覇吐神社を訪問したそうです。
ところがどっこい「外三郡史」は発見者である和田という人物によるでっちあげ、偽書だったと著者は指摘します。その論拠は、筆跡が和田氏と一致すること、古文書の中に用いられる知識、絵図などが明治から甚だしくは戦後のものから引用されていることなど、枚挙にいとまがないようです。荒覇吐神社も彼による建立です。
真書/偽書をめぐって、学者や郷土史家、アマチュア史家、マスコミが喧々愕々の論争を繰り拡げたようです。ただ学者といっても、古田武彦や安本美典といった半アマチュア学者、原田実のようなサブカルライターのような者たちで、その道の権威と呼ばれる人々は黙殺を決め込んでいたようですが。
結局のところ論争は、真の東国縄文文化ともいえる三内丸山遺跡が発見されたことで沈静化したようです。しかし、偽書/贋作のたぐいが受け入れられるのは、それを必要とする人々がいるということだと思います(「外三郡誌」は言わせる人に言わせれば五流の偽書とのことですが)。
誰もが持つ郷土愛、筆者にはまるでそれが薄いのですが、恐ろしいほどに執着する人もいます。それが村おこし町おこしの開発/利権と結びつく時、堂々たる砂上の楼閣が築かれることになるのかもしれません。ところでまた、”国家”も平然と歴史を捏造することがありますね。

















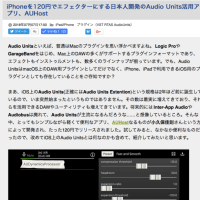

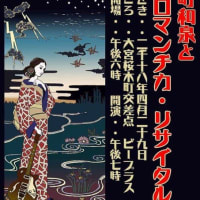
藤村新一の捏造事件は、これもまた縄張り争いのさなか、宙ぶらりんのうちに名が独り歩きの観がありますね。