
著作権法入門。小笠原正仁、明石書店、2001年。著作権関連シリーズ。とはいえ、創造的行為と著作権の関係について、あまり突っ込んだ議論はなされません。芸術大学、音楽大学などに通う学生向けの著作権の手引きでした。すこしがっかり。
しかし若者向けらしく、身近な事例を著作権問題として取り上げてもいて、勉強になりました。漫画において、通説上キャラクターは著作権保護の対象にならないようです。これは文学の考えを敷衍しているらしく、たとえば自分の小説に三毛猫ホームズを登場させても問題にはならず、ストーリーを盗んだ場合のみ著作権侵害となります。それと同様、自分の漫画にハクション大魔王を登場させても今のところ著作権上、問題ありません。
では、ハクション大魔王まくら、なるものを作って販売してよいかと言うと、それは商標法などで規制すべきとのこと。また、キャラクターを使って著しく原作を損なうような漫画を書いた場合、原作者から損害賠償などの訴訟を起こされる可能性もあります。あくまで、著作権という権利にしぼった場合の事例です。もっとも、キャラクターの無断利用は複製権の侵害であるとする判決が出るなど、判例も変化しているようです。
著作権とジャンルの関係も興味深く、業界との力関係によって保護の度合いも異なったりします。映画には、映画会社のみに認められる頒布権という独自の著作財産権が設定されます。音楽では、作詞者作曲者のみが著作者となるわけですが(だからシンガー・ソングライターは儲かります)、歌手や演奏者には著作隣接権という著作権に準ずる権利が発生します。同様、レコード会社には原盤権が与えられます。では、書籍における出版社はどうかといえば、これといった著作権も隣接権も有しません。なんてことだ。
プログラム、データベースといった新著作物、デジタル化の進展とともに進むマルチメディア化、メディアミックス戦略。著作権法は改正を重ねつぎはぎだらけですが、もっと根本的な変革を迫られているように思います。個人的には終章の「表現の自由と自主規制」といったテーマをもっと読みたかったです。
しかし若者向けらしく、身近な事例を著作権問題として取り上げてもいて、勉強になりました。漫画において、通説上キャラクターは著作権保護の対象にならないようです。これは文学の考えを敷衍しているらしく、たとえば自分の小説に三毛猫ホームズを登場させても問題にはならず、ストーリーを盗んだ場合のみ著作権侵害となります。それと同様、自分の漫画にハクション大魔王を登場させても今のところ著作権上、問題ありません。
では、ハクション大魔王まくら、なるものを作って販売してよいかと言うと、それは商標法などで規制すべきとのこと。また、キャラクターを使って著しく原作を損なうような漫画を書いた場合、原作者から損害賠償などの訴訟を起こされる可能性もあります。あくまで、著作権という権利にしぼった場合の事例です。もっとも、キャラクターの無断利用は複製権の侵害であるとする判決が出るなど、判例も変化しているようです。
著作権とジャンルの関係も興味深く、業界との力関係によって保護の度合いも異なったりします。映画には、映画会社のみに認められる頒布権という独自の著作財産権が設定されます。音楽では、作詞者作曲者のみが著作者となるわけですが(だからシンガー・ソングライターは儲かります)、歌手や演奏者には著作隣接権という著作権に準ずる権利が発生します。同様、レコード会社には原盤権が与えられます。では、書籍における出版社はどうかといえば、これといった著作権も隣接権も有しません。なんてことだ。
プログラム、データベースといった新著作物、デジタル化の進展とともに進むマルチメディア化、メディアミックス戦略。著作権法は改正を重ねつぎはぎだらけですが、もっと根本的な変革を迫られているように思います。個人的には終章の「表現の自由と自主規制」といったテーマをもっと読みたかったです。

















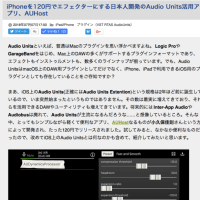

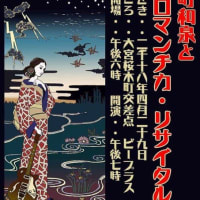
おっしゃるように創作性と著作物性は著作権法の肝ですが、法の原理という観点から見た場合、やはり、経済的引力が強く、法的枠組みであるはずの創作性は新奇性というより、何かを加えた、あるいは切り口を変えたものでもOKというところがあります。
いずれにしろ、芸術は模倣です。複製芸術をどのように位置づけ、文化発展という原理的枠組みを純粋に芸術性というところで語ることは難しいのでしょうか。ということを日々悩んでおります。
いずれにしろ、大きな市場が広がって、それこそフリーの圧力に屈せずに課金・集金していく枠組みは著作権法が根拠ですから、このあたりが正念場と思っています。
著者の方からコメントをいただけるとは大変恐縮しております。全面改訂版、定期的にチェックして上梓された際にはぜひ入手したいと思います。
著作権法と経済的引力のお話は大変興味深く存じます。私事ですが、趣味で音楽をやるにも、仕事で本を作るにも、著作権については常に考えさせられ、またパブリック・ドメインと生活の間で引き裂かれています。
取り急ぎお返事まで。