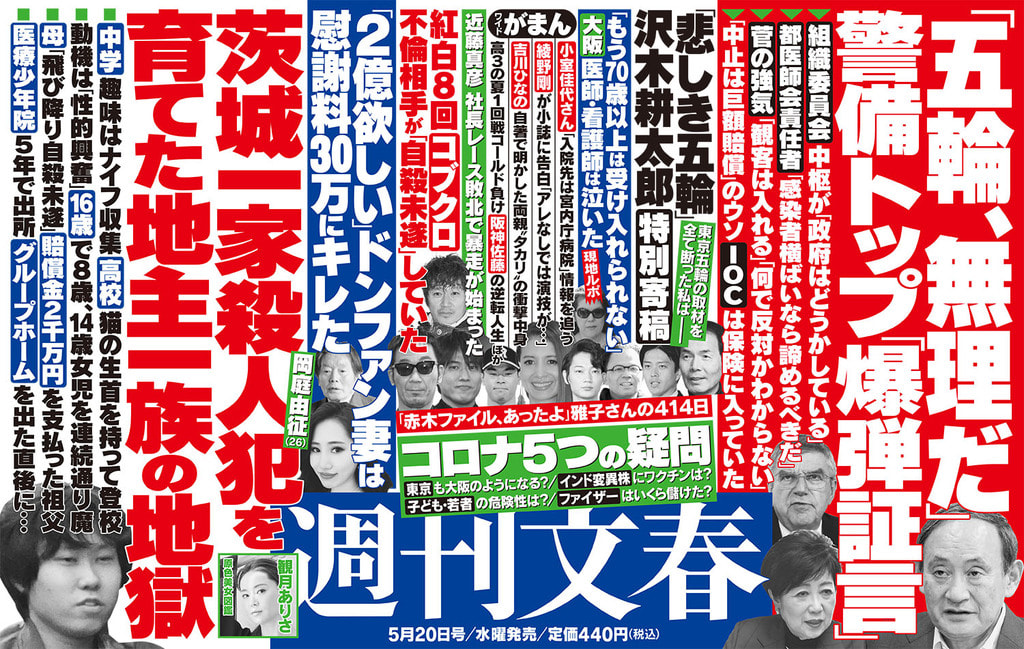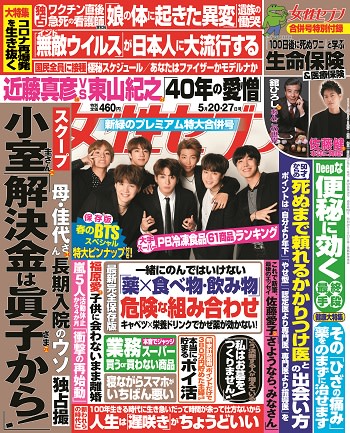小室圭さんが自分の正当性だけを主張して…その結果、起きる宮内庁が最も恐れることは
2021年05月12日 06時02分 デイリー新潮
恐れて居る割には、宮内庁は二人の結婚を後押ししているとしか見えないのだが?
デイリー新潮は4月22日に配信した「小室圭さん文書、弁護士は『法律家の文章に似せようと背伸び』 眞子さまも作成に関与か」の記事中の小田部雄次・静岡福祉大名誉教授のコメントを蒸し返している。
私は今回の記事と小田部教授の見解には少々違和感を感じるところがある。
大手マスコミは世論調査を行う際、長年にわたって「皇室に親しみを感じますか?」との設問を用意してきた。
近年、「親しみを感じる」と回答する割合は、社によっては7割台と高い数値を示している。
天皇陛下の場合は、8割を超えたことさえある。2019年5月に共同通信が実施した調査で、同月1日に即位された陛下に「親しみを感じる」の回答は82.5%に達した。
皇室全体への問いかけでも高率の傾向は変わらない。NHKが同年9月に行った調査によると、「とても親しみを感じている」と「ある程度親しみを感じている」を合わせた「親しみを感じている」は71%を記録した。
だが、小田部名誉教授も指摘しているが、皇室が国民の敬愛を一身に集めるようになったのは、それほど昔の話ではない。
昭和時代までの天皇は親しみを感じる存在ではなく畏敬、尊敬の対象だった。
昭和天皇に接した国民は、皆一様に「素晴らしい威厳」を称えている。
威厳にみちた方がこちらを気遣ってくださるから感激もひとしおになるのでしょう。
親しみ、親しみ、と親近感を前面に打ち出し始めたのは平成以降でしょう。
親しみ路線も悪くは無い。が、親近は往々にして卑近に変化する。
親しむ(…相手を身近な存在と感じる気持ち) は、卑近(…相手を身近でありふれていて、高尚ではないと認識する気持ち)に変化する。
■敗戦と天皇家
1945年8月に日本が敗戦を迎えると、一般庶民でも天皇制の存続に不安を覚える者は少なくなかった。
戦争責任の問題もあり、天皇制に対する批判の声も強かった。1946年5月の「米よこせメーデー」では、以下のような強烈なプラカードを掲げる者もいた。
「ヒロヒト 詔書 曰ク 國体はゴジされたぞ 朕はタラフク食ってるぞ ナンジ人民 飢えて死ね ギョメイギョジ」
掲げた共産党員は不敬罪で起訴され、日本国憲法の公布に伴う大赦で免訴となった。日本史の授業で習った人も少なくないだろう。
一体、いつから皇室に対する敬意は復活したのか、その疑問に答えるのが朝日新聞の世論調査だ。戦後の結果を伝える記事がデータベースに残っているため、パーセンテージの推移をたどることができる。
「皇室に親しみを持つ」、「持たない」という回答が、1959(昭和34)年から、2019(令和元)年までどのように変化したか、折れ線グラフを作成してみた。ご覧いただきたい。
この部分は、どうだろう?
確かに、戦後の一時期共産党系の活動は活発だったが、国民の大部分は皇室への尊敬を失ってはいなかった。
戦後、昭和天皇が全国を行幸された時、国民がどんなに天皇を歓迎したかは記録映像に残っているが、その他にも天皇皇室が人々から敬意を持たれていた資料は多くある。
もちろん、戦争被害者の中には、天皇を恨む者もいたが、全体からみれば少数派と言えるだろう。
小田教授の戦後皇室の敬意が全く失われたところから、昭和天皇、平成の天皇皇后が敬愛を取り戻して行ったという見方には、私は首を傾げる。
1947年広島
セキュリティーへの配慮らしい配慮もなく、素の御姿で大群衆に応えられる昭和天皇。
今では考えられない光景です。
■ミッチーブーム
朝日新聞が20年7月に掲載した「(世論調査のトリセツ)昭和~令和、皇室への親近感は」によると、同紙が「今の皇室に親しみを持っていますか」と最初に質問したのは1959年2月だという。
日本で“ミッチーブーム”が巻き起こったのは58年から56年のことだ。現在の上皇妃・美智子さま(86)が、皇太子妃になられることが発表されたことに端を発する。
お祝いムード一色の世相を反映し、「皇室に親しみを持つ」との回答は60%に達した。一方の「持たない」は26%にとどまった。
だがその後、皇室に対する“支持率”は低迷を続けた。78年と82年の調査では、「持たない」が「持つ」を上回った。担当記者が解説する。
「78年は『持つ』が44%だったのに対し、『持たない』は47%でした。82年は41%と46%を記録し、更に差が開きました。“支持率”低下に大きな影響を与えたのが、20~30代の回答です。朝日新聞によると、当時の60歳以上は76%が親しみを感じていたのに対し、30~20代は6~8割が『持ってない』と回答したそうです」
■“慶事”の影響
当時の30代は、いわゆる「団塊の世代」が含まれ、“全共闘世代”とも重なり合う。20代の場合は「しらけ世代」と呼ばれ、政治的無関心が特徴とされた。
とはいえ両世代とも、現在とは比べものにならないほど左翼思想が活発だった時期に思春期を過ごした。“天皇制”に批判的な考えを持つ回答が多くとも不思議はない。
「86年から日本はバブル景気に突入します。ベルリンの壁が崩壊したのは89年でした。世界トップクラスの好景気と、左翼思想の退潮も後押ししたのか、皇室に『親しみを持つ』という回答は50%台まで回復。『持たない』との回答は30%台に減少しました」(同・記者)
そして今に至るまで、朝日新聞の調査で「持つ」との回答が最高を記録したのは93年の67%だった。
この年、今の天皇皇后両陛下が婚約を発表された。93年1月、外交官だった小和田雅子さん(当時)と皇太子殿下(同)は記者会見を開き、ご結婚の意思を表明されたのだ。
「こうして朝日新聞の世論調査を振り返ると、皇室の慶事が“支持率”上昇に大きな影響を与えていることが分かります。そして眞子さまと小室さんの問題も、慶事を巡っての議論であることは言うまでもありません。だからこそ小室さんや彼の母親に、金銭や遺族年金を巡るトラブルや疑惑が報じられると、今度は“支持率”が下落する可能性があるのではないでしょうか」(同・記者)
親しみを持つ、持たない、だけでなく、日頃関心がある、関心が無い。
天皇皇室について知っているほうか、知らない方か、
も合わせてアンケートを採ったほうが良かったのでは無いか。
慶事に合わせて支持率が上がるのは、俗に言う「勝ち馬心理」奉祝気分に乗って昂揚したいという日本人のお祭り好きが影響しているのかも、です。
奉祝報道で盛り上がる中での、にわか皇室ファン?
だから平常時では、半々、つまりは興味が無いのでしょう。
44%と47%
41%と46%
このようなアンケートの場合、この差は、差と言えるほどの差なのか。
■日本人の心が離れる時
皇室に対する敬意の念を国民が保持しているのは、阪神・淡路大震災を原点として、今の上皇さまと美智子さまが被災地に心を寄せ続けられたことが大きいとされている。
「上皇ご夫妻は、阪神・淡路大震災の発生からわずか2週間後に被災地入りし、兵庫県内の避難所を回って多くの被災者を励ましました。特に国民を驚かせたのは、ご夫妻が避難所で被災者と同じように床にしゃがむ姿勢で、励ましのお言葉をかけられたことです。更に、泣き崩れた被災女性を美智子さまが抱きしめられた一幕もあり、これも大きく報道されました」(同・記者)
むしろ阪神大震災の慰問の成功体験が上皇上皇后を以後足繁く被災地へ赴かせたのではなかったか。
そして、それは「敬意を保った」というより、敬意を薄めていくことになったのではないか。
天皇が膝をついて国民ににじり寄るスタイルは最初こそ衝撃であったが、度重なるにつれて常態化して行く。つまりは、卑近化して行ったように見える。
記事で皇室ジャーナリストの渡辺みどり氏は、次のような“警鐘”を鳴らしている。
《昭和天皇、上皇ご夫妻、そして現在の天皇、皇后両陛下といった方々の並々ならぬご尽力の積み重ねにより、今では世論調査で8割近くが『皇室に親しみを持っている』と回答します。しかし、敬愛を獲得するのには長い時間がかかりますが、失うのは一瞬です。小室さんの問題で、日本人の心が皇室から離れるという可能性もあるのです》
平成、令和のマスコミは、天皇皇室を身近な存在として報道してきた。それは平成の天皇皇后が天皇を国民の身近な存在、国民から親しまれる存在と位置づけたからでしょう。
80%が「親しみを持っている」と回答したアンケート結果を見て、上皇上皇后は満足されたのではないか。
しかし、忘れてはいけない。
親近感は卑近感と極めて近いことを。
天皇、皇室が親近感の対象になったから、小室は臆することなく内親王にプロポーズし、佳代さんは秋篠宮にサポートを要望したのでしょう。
卑近の意味
ありふれた、身近な、高尚で無くわかりやすい。
なんだか、令和の天皇を言っているような。