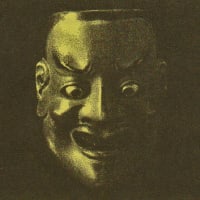(写真は大阪の民族学博物館でうつす))
記録だけ
2008年度 142冊目
『「お墓」の誕生』--死者祭祀(さいし)の民俗学
岩田 重則 著
岩波新書 新赤本 1054
2006年11月25日第1版
210ページ 700円+税
『「お墓」の誕生』--死者祭祀(さいし)の民俗学 を楽しむ。
この本も面白かった。
岩波新書 新赤本の興味のある分野だったので喜楽に読むことができる。
この本を見た子供は、
「おかぁさん、好きだね^^最近、凝り固まってるな。」
だって。
馬鹿にされてるな。(笑み)
ま、大学総合図書で宮田登世界を語るシリーズを二冊借りてきてくれたことだし、多めに見てやるとするか・・・(爆)
興味深かったことの中で、特に印象深い部分だけを記録しておこう。
1.海に向かって・・・が多い静岡などの「送り火」「迎え火」
家では赤飯のお結ぶに長いものをさす
なす馬、キュウリ馬(これは有名)
2.「両墓制」(墓形式)
近畿中心に、遺体埋葬ちと石塔の空間が隔てられている。
3.穴掘り
宮田登氏では清めのために酒・・・と記されていた。
岩田重則氏は、したいがごろごろ
・・・酒でも飲まなければやってられない
4.幽体離脱の話
5.遺体の埋葬は石塔の下では無かった
(山梨など)
これは上出の2にも共通
6.草刈り鎌が添えられる(山梨など)
7.遺体と共に死霊を封鎖
(山犬の掘り返しを避けるためとも言う)
8.「両墓制」と「無墓制」(墓形式)
9.『御伽草子』など、共同幻想としてのお墓
10.嬰児・子供の墓
土饅頭の中心に、鎌立て(山梨など)
11.間引き嬰児遺体葬法
12.靖国問題の問題
まぁ、こんな具合。
わかったのだか、理解できてないのか・・・楽しむだけの わ・た・し。