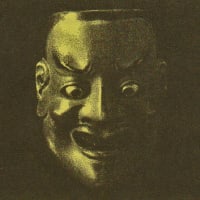(写真は今年二月に行った、中国山西省の博物館で見た版画)
記録だけ
2008年度 76冊目
明治大学公開文化講座 Ⅱ
『ことば・まつり』
発行 明治大学人文科学研究所
風間書房
昭和59年10月5日 第1版発行
1200円+税
『ことば・まつり』も 近隣図書館には無かったため、大阪府立図書館に借りていただいた。
明治大学公開文化講座 Ⅱ『ことば・まつり』を、昨日から今朝にかけて 読む。
明治大学公開文化講座シリーズは『悪』を初めとして、五冊目にあたる。
『ことば・まつり』は、八部構成。
歌舞伎や神楽、能や相撲などの話は何度読んでもわくわくする。
でも、そろそろ宮田登氏に戻る時期か・・・。
五、『古墳祭祀と埴輪の世界』 大塚初重(女)氏 は面白かった。
六、『まつりと演劇』 菅井幸夫氏 のはなしはのめり込んでしまうな。
この本の前半の四講演は「ことば」、後半はまつりに絞られている。
家族は『一、明治文学における・・・云々』大島田人氏の鴎外についてなどを読み、
「これおもしろいわーー。」
といっていたが、
『読みかけの本を途中で取り上げないでよね。』
と内心 家族をしかる。
私としては待ってましたの、後半部 まつりに関する四講演であった(笑)
明治大学公開文化講座は古いものでも内容は濃い。良い講演も多い。
一講演二時間の公開の講演が、自宅で気軽に、しかも無料となると、利用しない理由はない。
一講演最低2千円として・・・、交通費2千円、お茶代千円・・・とすると、締めて5千円。今まで24講演分くらいを読んだので、結構な節約だ。
5千円×28講演=14万円
我ながら、せこい。
『わぁい!14万円の節約だぁ~~。この浮いたお金で、又、芝居をみよう・・・。』
とらぬ『ぬき』 鳥羽ば『た』いて 夢を見る
・・・・・・乱鳥、妄想は尽きぬ。