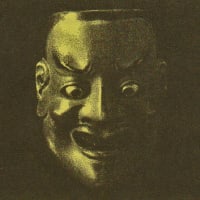(写真は雲崗石窟。中国の山西省。
『宮田登 日本を語る 2 すくいの神とお富士さん』の中の比較民俗学の部分で雲崗石窟が取り上げられていたので、この写真を思う出す。
そういうと、今年は中国に行く予定がないのが、寂しい。
2007.12 )
記録だけ
2009年度 30冊目
『宮田登 日本を語る 2 すくいの神とお富士さん』
宮田登 著
発行所 吉川弘文館
2006年3月10日
225ページ 2730円
本日『宮田登 日本を語る 2 すくいの神とお富士さん』を読了。
江戸時代 6月。
洗いざらしのザンバラ髪に白衣姿の若者が富士に登る。
白雪に くろき若衆や 富士もうで
修行、初詣(6月正月)、成人式云々で山に登り、下山。
赤坂氏の記述によると修行などで山に入り降りた後の込み入った話を踏まえると、これらの若者が富士を下った後も同様と考えるのが妥当だろう。
真の意味での成人式である。
富士参りした若者は、麦わらでつくった蛇を土産にしたという。
この蛇を一年間飾ると、無病息災、火事にならない等と言われたらしい。
ちなみに(白)蛇は「脱皮」という意味合いも大きく、縁起が良い。
成人式の意味合いも含められた富士登山の土産には、ぴったりかも知れない。
138ページの『「非日常時」の民俗学』では 柳田國男氏の『明治大正史 世相編』で示されたモデルは「情念」のようなもの・・・・・・。「知」「情」「意」という意識の問題として、抽出するという独自の方法を持っているがゆえ現代民俗学において、個展として迎入れられる 云々と書かれていた。
これについてゃかねがね、知人や友人が耳にたこができるほどいっていることであり、納得した。
近々、友人に電話を入れることにする。
宮田登氏は若くして亡くなられたが、東アジアにおけるミクロ信仰の研究は、古谷野洋子女史(『ミルクと中国芸能』『比較民俗研究20.2005.10』が性かを出されているとのこと。(佐野賢治氏 解説より)
中国、比較民俗学とあっては 気になる。但し、位置主婦の私に読める内容かどうかの資料が手元にはない。あんちょこだが、何処かの大学図書館やアマゾン等で確かめたいと思う。