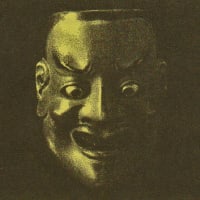赤坂憲雄著の『境界の発生』の記録が長文になってしまったので、手短に書くことにする。
京都の稲荷神社には、お百度の仕方が説明されていた。
写真の図を見てもわかるように、説明では『左まわり』と説明されている。
だが、図を見てわかるとおり、矢印は時計まわりである。
子ども二人が各小学校一年生の頃、いっしょに朝顔観察をした。
教科書には「朝顔の蔓は左まわり」と説明されていた。
納得!
ところが調べてみると、学者にっよっては朝顔の蔓は右まわりと論じられている。
これも納得。
友人の嘘のような話だが、右左が苦手な人がいる。
対象物を中心に考える場合と、自分を中心に考える場合の区別がつきにくいらしい。
右利きの私にはわかりにくいが、彼女は左利きで、親御さんに、
「右はお箸の持つ方。」
だと教えられ、それが後になっても災いしている様子。
但しこの友人の場合はこういった単純な話が、「対象物を中心に考える場合と、自分を中心に考える場合の区別がつきにくい」といった思考の範囲まで入り込み、彼女を悩ましているという。
右まわりと左まわり。
「対象物を中心に考える場合と、自分を中心に考える場合」といった事を考えず、単に対象物を見た場合、どちらまわりかは、必然的に変わる。
こう考えると、たまには時計も「右まわり」とは決めつけず、時計の針とともに歩んで違った見方をするといった遊びも楽しいかも知れない。
其の手始めに、悩みなき人も、一度お百度参りをされて見ては如何でしょうか・・・。


 な~んて。
な~んて。