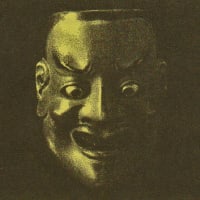(写真は奈良県大和川。コンクリート道の先に見えるのは、車一台がやっとこさ 通ることができる、細い橋。向こう岸にまでかかっている、私のお気に入りの小橋。)
記録だけ 2007年 46冊目
江戸の旅文化
著者 神崎宣武(かんざきのりたけ)
岩波新書 (新赤版)884
2004年3月19日
2253ページ 780円+税
この本を読み始めてまず初めに思い浮かべたのは、カブキの演目である『伊勢音頭こいの寝刃』 ついで思い浮かべたのは、やはりカブキの『江戸みやげ』 どうもこういった江戸の文化 に関する本を読むと、芝居と結び付けてしまうきらいがある。
興味深かった内容も何点かあった。
まずは『伊勢参宮献立道中記』
松阪→石部→石山→京都(4)→宇治→平野→信貴山→奈良→三輪→長谷→阿保→六軒→伊勢(2)といった具合。
京都を例にとってみると、加茂の付け焼きや湯葉などのなじみのお惣菜が食卓に並び、時代冴え違えども、大変に親しみを覚える。何よりも『・・・献立道中記』というだけでの、興味を持ってしまう。
伊勢参り本来の持つ意味や当時盛んだった女性の旅にでるいきさつや湯治、みやげの意味あいなども納得のいく記述。
江戸時代に刷られた道中記(P.113~P.126)の多さにも驚きを隠しえない。
全体を通して、とても楽しく読むことができた。