さて、「良く解らん」「肘木」ですが
よく「社寺建築の工法」を読んでいると
「斗」にも似たような事が有る様で
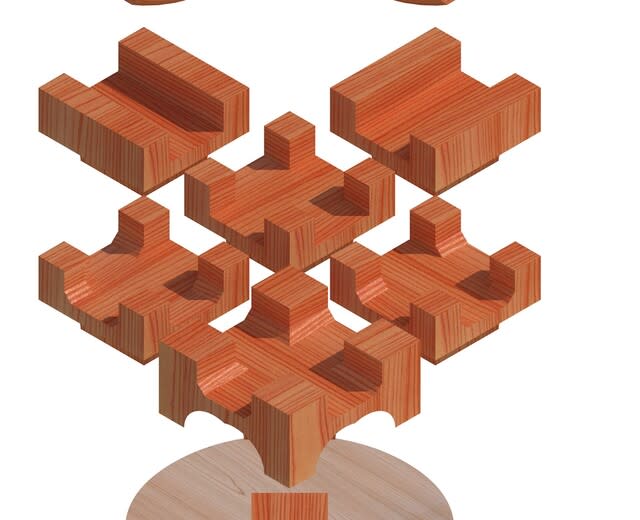
手前、中央は「隅斗」だと説明しましたが
後の物は全部が「巻斗」ではなく
上の左右二つが「巻斗」でその他は
「方斗(ほうと)」と言うらしいです
上に乗って来る「肘木」の通り方で違いが有る様で
上の二つの様に「肘木」が一方向からしか通っていない物を
「巻斗」と言い
「肘木」が二方向から通って、「斗」の上で交差している物を
「方斗」と言うようです
m(__)m
と言う事で、「肘木」の大きさですが
佐藤さん曰く「幅は柱の1/3で背はその1.2倍」だそうですが
どうもこの辺りが又、納得がいかないオヤジでして
基準になっていたのは「枝」じゃないのか?
何で急に「柱」が基準になってんだ・・・とか思いつつ
実は、「柱」の大きさ自体が元を正せば「枝」から
算出された物なんだから・・・「まッえ~~けどな」と
思い直すややこしいオヤジです(肘木だけじゃなくてお前もか!)
そんな事よりも、「肘木」の大きさです。
佐藤さんの言われるように「柱」の大きさの1/3だと
幅は113.3mmで
(たしか3の上に・を打って置けば3が永遠に繰り返されると言う意味に成るとか成らないとか??)
背は135.9mm(9の上に・)と言う事に成るので
この「五重塔」については「肘木」を
113x136mmとして描きました・・・・?
「柱」の大きさって何時決めました?
・・・その話はもう少し後で・・・するのかな?
で、「肘木」の大きさは基本これで、
「雲肘木」も「通し肘木」も「秤肘木」も同じ様ですが

形状によって呼び名が違う物が有って
今回私が描いている様な、下側の角を
面取りして有る様な物を「舟肘木」と呼ぶようです
なので、昨日言ったこの「四つ請秤肘木」は「四つ請舟秤肘木」??
てな事に成るのかもしれません(ややこし~~ッ!?)
以上、「五重塔 肘木の巻」はここまでで勘弁して下さいm(__)m
明日は「大斗」辺りの話になりますが
そうなると、やはり「柱」の大きさから書かなくては・・・・??
又何時か・・・(明日です!)m(__)m































