<2002年12月に書いた以下の文を、一部修正して復刻します。>

1) 相当以前だが、自費出版ブームというのがあった。人間誰しも“自分史”みたいなものを書いてみたいと思うだろうし、それが実現すれば、その人の人生の証しということになる。 また、俳句や短歌などの自費出版も多い。
実は私も、今から20年以上も前に、3冊の本を自費出版したことがある。一つは自伝的小説で、残りの二つは戯曲(史劇)であった。 友人や知人に贈ったり、一部は買ってもらったものもある。
ところで、鮮烈に覚えているのは、自費出版していく「過程」のことである。 なにしろ安く仕上げたいものだから、校正・校閲は勿論のこと、印刷所を見つけて費用の交渉などの全てを、自分一人でやった。
当時は活版印刷が主流だったが、オフセット印刷で安く仕上げ、3冊で100万円はかからなかったと思う。 それにしても、本が出来上がった時の“喜び”は大変なもので、「あ~、俺はもう死んでもいいや」という気分になってしまう。 そして暫くは、法悦に浸ってしまうのだ。
それは、苦労した者でなければ分からない喜びである。 誰でも物を作ることに喜びを感じるだろう。しかし、製作の過程で苦労や障害が多ければ多いほど、出来上がった時の感激、感動、喜び、法悦は大きくなるものだ。 そういう経験を3度もしたことに、やって良かったと今でも思う。
2) 原稿と校正刷りのゲラを照合する作業には、大変な労力がいる。 2時間、3時間とやっているうちに、目が充血してくるのを実感する。目薬を注入しては作業を続けていくのだが、4~5時間もすると、私などは朦朧(もうろう)としてきて、畳の上にひっくり返ってしまう。
こういう作業を、本が出来上がるまでに何回もやるのだ。 その頃は勿論、会社勤めをしていたから、こんな作業は休日でなければ出来ない。 休日に寸暇を惜しんでやり続けるのだ。 やっている間は、どうしてこんなに苦労しなくちゃいかんのかと、つい思ってしまう。
しかし、やがて感動の時を迎える。 新品の本が100冊、200冊と手元に届くと、それまでの苦労は一切忘れて、ただただ“喜び”に浸ることが出来るのだ。 ページを開いて顔を押し付けると、印字の匂いが微かに漂ってきて法悦を味わう。 その気分は、一生忘れることがないだろう。
ところが、出来上がった本を食い入るように読んでいくと、ハッとすることがある。やはり誤字・誤植がいくつかあるのだ。 自分は、あれほど集中して校正したのに・・・もう遅い!! 本は出来上がってしまったのだ。
それから今度は、慌てて「訂正表」を印刷所に発注することになる。 自分はあれほど一所懸命に校正したのに・・・と恨めしく思ってしまう。 全てを“自分の手”で自費出版していると、こういうミスはよく起きるものだ。
人間は完全ではないと、つくづく思ってしまう。思い込みや勘違いは必ずあるものだ。 校正の段階で、国語辞典と首っ引きになっていても、文字の間違いをいくつか見落としてしまうのだ。 喜びの後の、ささやかな悔悟と反省の念が訪れる時である。
3) 私が自費出版した本は、ほとんど反響を呼ばなかった。友人らの中には賞めてくれる人もいたが、半分はお世辞だったろう。 小説は「青春流転」と題するものだが、某出版社の編集長が好意的な手紙を送ってくれただけで、新潮、文藝春秋、講談社、筑摩書房等にはほとんど相手にされなかった。
戯曲の方もほとんど反響がなかったが、「文化大革命」と題する歴史劇には、ある漫画研究家(IJ氏)がわざわざ電話をかけてきて激賞してくれた。 それだけが成果といえば言えるだろう。演劇雑誌にも書評が出たが、それほど芳しいものではなかった。
3冊続けて自費出版したら、相当無理したせいか体調を崩し、仕事にも支障が出るようになった。 本の評判も大したことがなかったので、私はそれ以上の自費出版を諦めてしまった。3冊も出したのだから、とりあえず満足ということである。それから約20年の歳月を経て定年が近づくと、私は無性に「青春流転」の続編が書きたくなった。 焦ることもないので、1年半ぐらいかけて続編を370枚(400字詰め原稿)ほど書いた。定年後に、自費出版してやろうという思惑だったのである。
ところが、書き終えて読み直してみると、内容が極めてエロチックで、他人に見せるのが恥ずかしいような代物になってしまった。 青春の性の“真実”と、恋愛を描き出そうと意気込んで書いたものの、顔が赤らむような出来映えになってしまったのだ。
私にも子供や孫、大勢の親戚がいるので、これではどうかと思い妻に相談すると、どうしても出したいなら「ペンネーム」を使えばいいと言う。 実名で出されたら、親類縁者への体面があると言わんばかりなのだ。 要するに、恥ずかしいということである。
そして、出版社等いろいろ調べたら、今やきちんとした自費出版には相当金がかかることも分かった。 かつて自分がやったように、目を真っ赤にして校正・校閲と格闘する気にはなれない。 結局、金はかかるし内容が自分の恥をさらけ出すようなものだから、出版は諦めてしまった。
しかし、せっかく書いた370枚の原稿は、「オレをどうしてくれるんだ」と言わんばかりに、無言の圧迫を私にかけてくる。「オレを焼却してくれてもいいんだぞ」と脅迫しているのかもしれない。「分かった。俺が死ぬ時、お前も棺桶に入れてやるから、一緒にあの世へ行こうか」と私はつぶやく。 こうして、自費出版用の原稿と私は、際限のない問答を繰り返していくのだ。
4) 自費出版の本というのは、正に“我が子”のようなものである。 まして、手作りのものは余計に愛しい。完全に自分の分身なのだ。 もう一度、自分の目を真っ赤にして校正・校閲に取り組むのが、真実の愛かもしれない。
“我が子”というのは、優秀な子であろうとも、フランケンシュタインのような「出来損ない」であろうとも、可愛いことには変わりがない。 優秀な子は世に認められるから良いが、「出来損ない」は無視されたり嫌われたりするから、親にとっては一層“不憫”である。
いま「出来損ない」の我が子を抱えた私は、この子をどうしたら良いのか迷っているのだ。 いっそのこと、親子心中(焼却処分)してしまえばスッキリするかもしれないが、「出来損ない」への愛着は、そうもさせてくれない。 結局、我が子との問答は死ぬまで続くのだろうか。
このように、私の煩悩というのは“自費出版”なのである。 優秀で立派な子供なら、無理をしてでも世に出したいが、フランケンシュタインのようなエロスの「お化け」だったら、世に出すことも憚られる。
とんでもない「出来の悪い子」を抱えた私は、その子の処理についてこれからも悩むだろう。 これは、自費出版に魅せられた私の“業”なのかもしれない。我が子の処理や処分を忘れている時が、最も気楽で平和な一時なのだ。 (2002年12月22日)










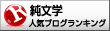

















恥ずかしながら、私も1冊だけ自費出版したことが会います、きっかけはうつ病を克服したての頃、どうしても本を出したくて、老後の資金を出して作りました、それで今は節約の日々です。
出した直後は涙を流しながら読みましたが、ある日突然とても恥ずかしくなり読めなくなり眼のつかないようにしまっています、けれど、あれを出したことでうつ病の克復には執拗だったのだと最近は思えるようになりました。
どんな無駄な事と思える事もとても大事な事と、今は思います。
10年以上前に書いた記事ですが、思いは変わっていません。それよりも何よりも、自分の「存在」を立証してくれるものではないでしょうか。
これは自分の存在の証だと思えば、無いよりはずっとマシだと考えられるでしょう。