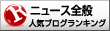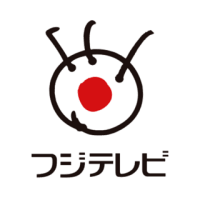かぐや姫が宮仕えを拒否したことで、帝(みかど)の姫への好奇心はますます高まりました。こうなったら、意地でも姫に会わねばなりません。帝の権威、面子から言ってもこのまま引き下がるわけにはいかないのです。
帝はいろいろ考えました。そして、出た結論としては、狩の行幸をする振りをしてかぐや姫の館に立ち寄れないかというものでした。これならばごく自然に、大げさでなく姫に会えるかもしれません。さっそく、竹取の翁を呼んで相談してみると、その方がかぐや姫も不意を衝かれ、会わざるを得なくなるだろうということでした。
そして数日後、帝は急に思い立ったように狩をして、帰りに竹取の翁の館を訪れました。大成功です。かぐや姫はぼんやりとした風情で物思いに耽っていました。初めて見る彼女は光り輝いていて、この世の人とは思えない美しさに溢れていました。そして、姫の周りには何とも言えない芳しい香りが漂っているのです。
あまりの美しさと気品に、帝はしばし茫然と佇んでいました。やがて姫の袖を捕らえると、一緒に御所へ参ろうと促したのです。帝はもうかぐや姫に夢中でした。神輿(みこし)まで用意させ連れて行こうとすると、彼女はなお抵抗していましたが、そのうちに不思議なことが起きました。かぐや姫が急に姿を消して“影”になってしまったのです。
これには帝もなす術がありません。結局、姫を連れて行くのを諦め「元の姿に戻りなさい」と言うと、かぐや姫が元通りの姿に戻ったのです。帝は彼女を館に残したまま御所へ帰っていきました。
この日以来、帝はかぐや姫を思わない日はなくなりました。しかし、彼女を宮中に召し出すことはできないので、せっせと愛の歌をお詠みになり、歌のやり取りをするようになったのです。
こうして、帝(みかど)とかぐや姫の交友関係が続くのですが、姫を恋しく思う帝の心は変わりませんでした。また、かぐや姫の方も帝を慕っていたのですが、宮中への出仕がないまま、3年という月日が経っていきました。
かぐや姫の周りには何人かの召使いがいましたが、ほとんどが下女でした。下男でいつも奉公していたのは藤吉(とうきち)だけで、これは姫や竹取の翁の信頼が厚かったからでしょう。
前にも言いましたが、藤吉の父は竹取の翁の親友で、2人とも大友皇子(おおとものみこ)に仕えていました。ところが、壬申(じんしん)の乱が起き大友皇子は敗れて自殺し、臣下であった2人とも没落したのです。そして、藤吉の父は悲嘆に暮れながら亡くなったのですが、金回りが良くなった竹取の翁が彼の面倒を見るようになりました。
その辺の事情はすでに述べましたが、翁夫妻は藤吉を実の息子のように可愛がり、彼がかぐや姫と親しくするのを大目に見ていたのです。翁夫妻は本当は藤吉を養子に迎え入れ、良き伴侶を宛がおうと考えていたのかもしれません。あるいは、かぐや姫の婿にもと思ったかもしれません。 ところが、成長するにつれて彼女は絶世の美人となり、世の中の人が姫を放っておかなくなったため、藤吉の婿養子などの話は立ち消えになったのです。
しかし、かぐや姫が5人の貴公子に無理難題を押しつけたり、帝への御奉公を断ったため事情は変わってきました。藤吉の婿養子の話などがまた浮上してきたのです。この背景には、竹取の翁と嫗(おうな)が年を取ってきたことがあります。ある日、翁夫妻はかぐや姫に問い質しました。
「われわれ夫婦は年老いて、いつ死ぬかもしれない。ところが、お前は求婚者たちの切なる願いを断ったりして、全く結婚しようとはしない。このままで良いのか。
もし“殿上人”と結婚しないのなら、藤吉のような地下人(じげにん)でも構わないではないか。いったい、自分のことをどう考えているのか。教えてほしい」 これに対して、かぐや姫は驚くような答えをしたのでした。
「私はこの国の人ではなく、月の都の人なのです。前世からの約束があってこの世界に参りましたが、いずれ近いうちに帰らなければなりません。だから、この世界の人とは結婚できないのです。また、宮仕えをしても全く意味がありません。
お爺様、お婆様には、私を育てて頂きいろいろお世話になりましたが、何の御礼も恩返しもできず、近いうちに別れなければならないとは、まことに心苦しく思っております。どうぞ、この“親不孝者”をお許しください。私がいま話せることはこれまでですが、いずれ全てのことをお話しできると思いますので、どうぞそれまでお待ちください」
かぐや姫はそう言うと、竹取の翁と嫗に深々と頭を下げました。翁夫妻はしばらくの間、返事をすることができません。あまりにもショックが大きかったのです。手塩にかけて育ててきた姫がこの世の人ではなく、近いうちに月の世界に帰るなど信じられないことです。夫妻はしばらく返事もできませんでしたが、ようやく翁が口を開きました。
「姫よ、いまの話はにわかに信じられず、私も嫗も仰天している。召使たちもびっくりしているだろう。また、この話が帝の耳に入ったら、何と思われるか分かったものではない。このことは、しばらくの間伏せておこう。決して他言しないように」
翁はこう言うと、その場に控えていた主な召使いたちにも他言を禁じました。そこには藤吉(とうきち)もいましたが、彼もかぐや姫の告白に驚きました。竹取の翁はいずれ朝廷に報告しなければと思いましたが、事が重大なだけにしばらく口外しないことにしたのです。
近いうちに月の世界に帰ると聞いても、藤吉はもちろん半信半疑でした。せっかく親しくさせてもらっているかぐや姫が、この世から姿を消すなど考えられないことです。いずれにしろ、この日を境に藤吉の人生観が大きく変わろうとしていることに、本人もまだ気づいていないようでした。
やがて、竹取の翁がかぐや姫のことで帝(みかど)に報告する日がきました。翁にしてみれば帝の力を借りるなどして、何としてもかぐや姫をこの世につなぎ止めておきたい一心です。彼女が“月の都の人”で、近いうちに月に帰ると聞いて帝も驚きました。
「竹取の翁よ、それは信じられないことだ。かぐや姫はどんなことがあっても、この世にいてもらわなければならない。朝廷としてもできる限りのことをするので、何かあったら必ず知らせてほしい」 帝から心強いお言葉があったので、竹取の翁は少し安心して退席しました。この日から、翁は逐一 朝廷に報告するようになったのです。
ところが、ちょうどその頃からかぐや姫の様子がおかしくなりました。毎晩、月を見てはらはらと涙をこぼすようになったのです。竹取の翁や嫗が心配して、一体どうしたのかと尋ねると姫はこう答えました。
「月を見ていると、何もかも心細く悲しく感じられるのです。それに私は、いずれあの月に帰らねばなりません。この世の人とお別れしなければと思うと、ただただ悲しくなってくるのです」
姫の答えに翁夫妻はもう驚きませんでしたが、いよいよ決定的な“その日”がやって来るような予感がしたのです。しかし、かぐや姫の月への帰還を何としても阻止しなければなりません。朝廷の方は何かやってくれそうですが、翁の館もいろいろ努力しなければなりません。 そこで、竹取の翁は藤吉(とうきち)を呼んでこう下知したのです。
「藤吉よ、わしはお前を最も信頼しているが、いよいよ決定的な日が近づいてきたようだ。この頃のかぐや姫の様子は全くおかしい。お前は姫から目を離すことなく、いつも気をつけてほしい。姫に何か起きれば、その責任はまずお前が取らねばならないのだ」 翁が強い調子で命じたので、藤吉は緊張して聞き入っていました。
その後も、かぐや姫は月を眺めて泣くので、竹取の翁夫妻はあまり月を見ないように注意しました。しかし、かぐや姫は「どうして月を見ずにいられましょうか」と言って、その挙動が全く変わりません。翁夫妻はとうとう諦めてしまい、何か不測なことが起きない限り放っておくことにしました。その代わり、藤吉(とうきち)に姫の監視を十分にするようさせたのです。
藤吉の役目はだんだん重くなりました。彼はほとんど竹取の翁の館から離れられなくなり、特に月がよく見える晩は、かぐや姫が嘆き悲しむので夜もおちおち眠れません。そして朝になると、睡眠不足でぐったりと疲れ切ってしまうのです。たまに藤吉に代わって、何人かの下男下女が交代でかぐや姫の“見張り番”をしますが、もし不測の事態にでもなれば藤吉が責任を負わねばなりません。このため、彼は精神的疲労もあって少しやせ細ってきました。
ある晩、かぐや姫が見かねたのか、藤吉をはじめて塗籠(ぬりごめ)の中に招き入れました。塗籠とは周囲を壁で塗り籠めた部屋で、ふだんは姫の寝室となっている閉鎖的な部屋です。この“密室”に呼ばれて、藤吉は緊張し入室をためらいました。当然でしょう。下男ごときがたとえお許しがあっても、姫の寝室には入れません。普通は部屋に入らず、妻戸の外で待っているのです。
しかし、かぐや姫はその晩は違いました。躊躇する藤吉を促し塗籠の中に招き入れたのです。夜も遅かったので、姫と藤吉以外には館で起きている人はいません。そうでなければ、いかに招かれたとはいえ下男の分際で姫の寝室には入れないでしょう。
「入っても宜しいですか?」「ええ、どうぞ」 二人は低い声で言葉を交わしました。誰も起きていないことは分かっていても、ひそひそ話にならざるを得ません。藤吉は意を決して塗籠の中に入りました。すると・・・なんとも芳しい香りが漂ってきて、藤吉は陶然とした気分になりました。目の前にかぐや姫がいます。こんなに近いところから、藤吉は姫を見たことがありません。
かぐや姫は少し青白い顔色をしていましたが、さすがに“絶世の美人”と言われるだけに神々(こうごう)しい美しさに輝いていました。藤吉はただ息を呑むだけで言葉になりません。姫の前で畏まっていると、やがて彼女が口を開きました。
「藤吉殿、毎晩ご苦労さまです。そこで率直に申しますが、今夜二人きりになったのには訳があります。単刀直入に聞きますが、あなたの父上は故大友皇子(おおとものみこ)様の家臣だったのですか?」
かぐや姫はようやくその時が来たとばかりに、率直に藤吉に問い質してきました。彼の亡父が大友皇子の家臣だったことは既に竹取の翁から聞いて知っていたのですが、改めて挨拶代わりに聞いてきたのです。藤吉は亡父のことを簡単に語り、さらに亡父の友人であった竹取の翁に世話になっている経緯を説明しました。
かぐや姫はなおも幾つか問い質しましたが、藤吉が包み隠さず正直に答えるので満足した様子です。二人は相当に打ち解けた雰囲気になり、姫と下男という立場の相違を忘れた感じになりました。夜の静寂(しじま)の中に二人の息吹だけが息づいているようです。
どのくらい時間が経ったでしょうか。かぐや姫はこんなに親身になって他人と話し合ったことがありません。藤吉との対話に安堵したのか、彼女は次に思いも寄らないことを言いました。
「藤吉殿、私は今までこんなに打ち解けて人と話し合ったことがありません。どうやら、あなたとは過去の境遇や生き方が似ていますね。実を言うと、私は“前世”において大友皇子様の妃(きさき)の一人だったのです」
この言葉に藤吉はびっくりしました。かぐや姫には何か秘密があると藤吉は察していましたが、まさか大友皇子の妃の一人だったとは・・・
「皇子様との関係でいま詳しいことは言えませんが、あなたと私は“同憂の士”ということになります。私がなぜ現世に来たのか、これからゆっくりとお話ししましょう」 かぐや姫はこう言うと、藤吉に向かってにっこりと微笑みました。
月を見ては嘆き悲しんでいたかぐや姫が、人に微笑みかけるとは余程のことでしょう。彼女は明らかに藤吉(とうきち)に好意を抱いていました。だから大友皇子の妃であったことも打ち明けたのです。
かぐや姫は月の都からこの世に降りてきた理由として、彼女なりに“けじめ”を付けたかったからだと語りました。しかし、具体的な話はまた後日にするとして、この際、藤吉にぜひ頼みたいことが二つあると述べました。
「ぜひ頼みたいこととは何でしょうか?」
「藤吉殿、これはたってのお願いですが、私が月に帰った後、竹取の翁様と嫗(おうな)様のお世話をぜひともお願いしたいのです」
「それならば、どうぞご心配なく。私は翁様ご夫妻には大恩があります。それより、姫様はどうして月に帰ると言うのですか? 私には理解できません。せっかくこの世に戻ってきたというのに、その若さでお別れしなければならないとは残念至極です。できることなら、考え直してくれませんか」
「その件はもうお爺様、お婆様に言ってあります。やむを得ないことなのです。それよりも藤吉殿、もう一つの頼みごととは、あなたに全ての出来事を後の世の人に伝えてほしいということです。あなたは文字を習っているそうですね。お爺様からそう聞きました。後世の人にぜひ伝えてくれませんか」
「はい、翁様に言われて仮名(かな)を習い始めたばかりです。全ての出来事とはこれまでの話などでしょうか」
「これまでの話と、これから起きる出来事など全てです。いえ、これ以上はもう申しません。やがて、あなたに最後のお願いをする時が必ず来ると思っていますから」
かぐや姫はそこで言葉を切り、遠くに視線を向ける仕草をしました。この話はもう終わりという合図なのでしょう。藤吉は幾つも疑問がありましたが、それ以上は質しませんでした。塗籠(ぬりごめ)の中にいるのでよく分かりませんが、夜が白々と明けてくる気配がしたのです。
藤吉が仮名文字を習い始めたのは、竹取の翁が彼の能力と将来性に期待したからです。近くの“貧乏貴族”のもとへ藤吉は通いましたが、なかなか物覚えが良く竹取の翁を喜ばせました。翁としては藤吉に高い学力を付けてもらい、立派な大人に成長してほしかったのです。
さて、かぐや姫は相変わらず月を眺めては嘆き悲しんでいましたが、藤吉と会っている時だけ嬉しそうな素振りをするのです。それは翁夫妻も気が付きましたが、こうなると彼にいつも姫の傍にいてもらおうということになりました。今はかぐや姫の御機嫌が第一です。藤吉は貴族の家で仮名文字の猛勉強をした後、かぐや姫の相手になったり彼女の世話をする毎日でした。
そして7月のある晩、藤吉がかぐや姫の部屋に呼ばれると、彼女は激しくむせび泣いていました。酷い泣き方です。藤吉が心配して聞きました。
「今夜はどうされたのですか。あまり泣くと体に良くありません。一体、何がそんなに悲しいのですか?」 月がよく輝く晩は、かぐや姫は特に嘆き悲しむのですが、今夜はちょっと普通ではありません。
「藤吉殿、私は悪いことをしました。悪い女です、悪い女です・・・」
「えっ、何か悪いことをしましたか。姫様は少しも悪いことをしていないでしょう」
「それはあなた方が気が付かないだけです。私は大変悪いことをしました」
かぐや姫はそう前置きすると、以前、石作皇子(いしづくりのみこ)や車持皇子(くらもちのみこ)ら5人の求婚者に無理難題を押しつけ、大伴御行(おおとものみゆき)や石上麻呂(いそのかみのまろ)は死に至った話をしました。それは藤吉もよく覚えています。あの頃は一時、かぐや姫は“魔女”ではないかとの噂も立ちましたね。
「そんな話はもう昔のことです。お忘れになった方がいいでしょう」
「いえ、もう古い話ですが、私は月に帰る前に真実を明かさねばなりません。特に藤吉殿には、何もかも正直に話します。私は大友皇子様の仇を討ったのです。怨みを晴らしたのです!」