司馬遼太郎
【ワイド版】
『街道をゆく 33 白河・会津のみち、赤坂散歩』★★★★
http://publications.asahi.com/kaidou/33/index.shtml
やっとここまで来たのねとうれしさひとしお。
浜通り、中通り、会津地方 そうそう
---
福島県地図をみていると、つい漢字の「列」という字画を思いうかべる。
相馬など太平洋岸(浜通り)は、ツクリの立刀の右側の線である。東北にしはめずらしく暖地性の照葉樹林がみられるという。
この白河のある中通りは、立刀の左側の線である。ここはタテ長の盆地だけに、寒暖の差がはげしい。
最後に偏である会津地方である。古代以来もっとも早く稲作文化のひらけたところながら、会津盆地のまわりは大きな山にかこまれ、しかも気候の面では同県ながら立刀はとがい 、西のほうの越後(新潟県)の影響をうけ、冬は豪雪地帯になる。
「会津は東北じゃないんです」
私はそうきいたとき、江戸時代、会津藩が、教養の上で、三百大名のなかでももっとも精密だったことを思いかさねて、会津はどこか東北農民型の民俗性が薄いのだろうかとひとり合点してみたが、あるいは単に気候が越後圏だということだけのことかもしれない。
そういう三つの要素が、福島県という大県を構成している。
山脈でいうと、立刀の部分は、山脈が南北タテに走っている。阿武隈山脈が浜通りと中通りをへだて、県の中央に奥羽山脈が大きく盛りあがって、中通りを渓谷低地にしている。
会津地方は、山なみが入りくんでおり、ヨコに横たわるか、ナナメに走る かである。つまり北部は吾妻山の山地が一の字をなし、只見ダムのある越後山脈が南西を走る。それと併行して帝釈山地が、おなじく南西に走っているのである。まさに列の偏といっていい。列の偏は、立刀よりどこか優越感をもっている。
(一部変更)
---
戊辰戦争は、日本史がしばしばくりかえしてきた、“東西戦争”の最後の戦争といっていい。
古代はさておき、日本社会がほぼこんにちの原型として形成されはじめた平安末期に、西方の平家政権が勃興した。当然ながら、東方はその隷下に入った。
それをほろぼした東方の鎌倉幕府が、西方を従え、関東の御家人が、山陰山陽から九州にかけての西方の諸国諸郷に守護・地頭として西人の上に君 臨した。
南北朝時代は、律令政治を再興しようとした後醍醐天皇(南朝)が、いったんは関東の北条執権をほろぼしたから、一時的に“西”が高くなったが、結局は北朝を擁する関東出身の足利尊氏が世を制した。東方の勝利といえる。
織田・豊臣氏は西方政権であった。しかしそれらのあと、家康によって江戸幕府がひらかれ、圧倒的に東方の時代になった。
戊辰戦争は、西方(薩摩・長州など)東方を圧倒した。
しかしながら新政府は東京に首都を置き、東京都もって文明開化の吸収機関とし、同時にそれを地方に配分する配電盤(デストリビューター)としたから、明治後も東の時代といっていい。
――東北は、そういう“東”じゃありませんよ。
というむきもあるかもしれな いが、奥州は、源頼朝以後、関東の後背地としてやってきたから、右の図式でいう“東”に属すると私はおもっている。
――そうじゃなくて、東北は第三の一点です。“東”じゃないんです。
というような力み方が、東北にある。これはひょっとすると東北人のひそかな楽しみのひとつである自虐性――もしくは高度な文学性から出た自家製の幻想かもしれない。
“西方”には、そういう幻想はない。たとえば、西方のなかの四国だけが“私どもは南方で、西方じゃありません“と拗ねていうようなことは、まずありえない。
そこへゆくと、東北、ことに会津はちがう。
戊辰への感情については、白河はすこしちがう。
「戦場を貸しただけです」
と、白河人はよくいう。
---
いまは、世界の多くの部分が、一つのルールで動いている。だたソ連だけが、印象として“最後の外国”のようである。
その印象のもとは、ソ連における閉鎖性、史上最大の軍事力、さらには社会主義的価値観と岩牢のような官僚制といったものがあげられるかもしれない。
---
時代を感じる・・
今は北朝鮮が孤立し暴走している。
---
白河基監(ハリストス)正教会聖堂
小さな聖堂のなかは、彩光がみごとで、光にあふれている。正面に多くのイコンが美しく構成されていて、異教徒の私にも荘厳な光の国にいることが感じられた。
「平面」
というのが、日本画でもイコンでも重要な要素なのである 。
---
大内の小盆地に入ったとき、景色のすがすがしさにおどろいた。
まわりを、標高千メートルほどの峰々がかこんでいる。北に六石山(大内峠)、東に小野岳・西に烏帽子岳(檜和田峠)、神籠ヶ岳などといった山々で、私どもは南から入った。大内という在所だけが、うそのように平坦だった。
そのなかにひと筋の古街道がとおっていて、その古街道の両側に、大型の草ぶき屋敷が、幾棟も幾棟も、棟をむきあわせてならんでいるのである。
「これは、すばらしい村です」
須田画伯が、肝をつぶしたような声をあげた。江戸時代そのままのたたずまいだった。
残っている規模が大きく、戸数五十四戸が、整然とならんでおり、どの家もよく手入 れされていて、たったいま会津若松城下から、松平候の参勤交代の行列が入ってきても、すこしもおかしくない。
それにしても、この大内(福島県南会津郡下郷町大字大内)のひとびとは、見上げたものといわざるをえない。
江戸時代が去り、もはや参勤交代の行列がやって来なくなっても――さらには新街道がべつのほうに付いて山間に置きすてられてしまっても――住居や村を変えようとはしなかったというのは、遠いむかしからの日本人の心だったというべきだろう。
---
大いなる会津人
奈良朝や平安朝の都びとにとって、文明という太陽は、平城京や平安京という都だけに照っていた。
田舎のことを鄙といった。ひなということばに 当てられる漢字は夷もあり、戒夷もあり、その字のように草深く野蛮で、文化どころか、言語さえ通じない世界だとおもわれていた。
ところが、徳一(とくいつ)が存在した。
奈良朝末・平安初期の会津に徳一という日本最高の法相学者がいたというふしぎさを、たれもが十分には説明できない。
---
私には初耳で・・無知がはずかしい・・
---
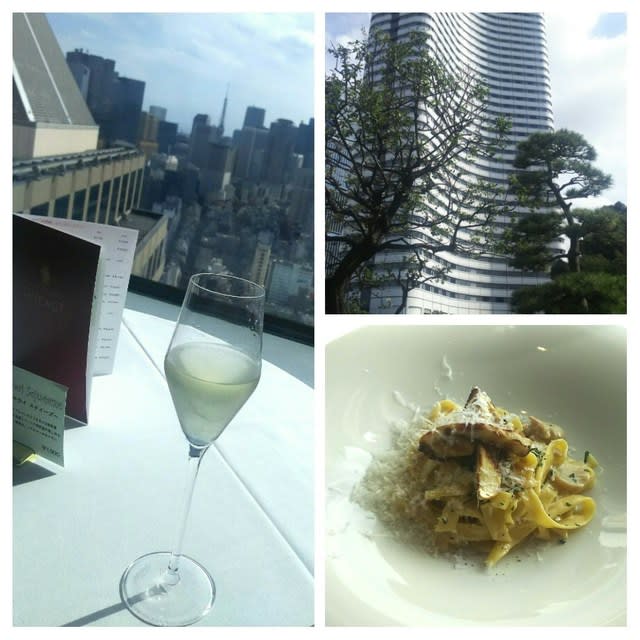
おもしろいことにこちらもちょうど赤坂
雨続きで明日も雨予報・・週末台風「お天気当てたね!」
付き合ってもらってリアルタイムに寄り道散歩
---
清水谷界隈
清水谷公園は小規模ながら、樹蔭が多く、それに湧水がつくる小堀の水もあり、石橋もかかっていて、水面を見ることのすくない赤坂界隈では、貴重な空間といっていい。


---
お奉行と稲荷
いまもそうだが、江戸には稲荷社が多かった(もっとも、全国の神社の四割がお稲荷さんだという説がある)
赤坂に、高名な豊川稲荷がある。
豊川稲荷の境内に入ると、赤提灯や赤幟の列がいかにもお稲荷さんで、香煙がたちのぼっているあたりだけが、神社と異なっている。それに、神社のように余白を重んずることがなく、お堂やらなにやらが建てこんでいる。
お堂には、
「荼枳尼真天」
という扁額がかかっている。


着信にショックを受け愕然としていたら、
わんこがそれを察知したのか首をかしげてぺろりと顔を舐めてきた。
あまりの自分の不甲斐なさに涙がぽろり。。
今月の有給は なし だね。


















