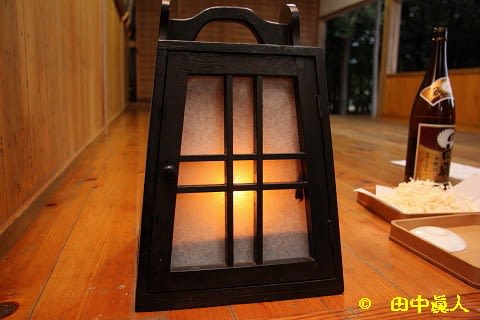おふくろの診察時間を利用して車を走らせる。
畠中医院から西へ少し。
信号の向こう側にある線路はチンチン電車。
子どものころはその呼び名でも、あるいは駅名が我孫子道駅だから我孫子電車とも呼んでいた。
子どものころの風景とはまったく違うから、何十年も離れて戻ってきたら、すごく違和感をもつだろう。
信号がある左右の道は南北を往来する古道である。
北へ向かう道は安立商店街。

アーケードに「一休法師ゆかりの安立町」とある。
安立町は大阪市住之江区の安立(あんりゅう)町。
今の今まで、そんなことを知らずに育ってきた。
ネットをぐぐってみれば「一寸法師は安立の地で生まれた。針の刀をもって、京を目指した。かつて安立に多くの針屋があった。そのようなことで生まれたお伽噺」と書いてあるブログがあったが・・・。
へぇー、そうなんだというのが実感だが、安立は万葉集にも登場する地。
時代的には合致しそうだが、直接的なもののない由来は後付けどころか宣伝だった。
近世の安立に三栖屋(みすや)新右衛門など針商人が多くの店を構えていた。
そこでちょいと利用したお伽噺一寸法師の鬼退治伝説であった。
安立本通商店街振興組合が伝える由来である。
組合でなくとも誰しも知っているお伽噺。
「子宝に恵まれない夫婦が住吉大社に願をかけたら一寸法師が生まれた。お椀の舟に乗って川を上り京の都に向かった。なぜかそこにお姫さんがいた。姫を襲っていた鬼は針の刀で退治した。そして打ち出の小槌を振ったら大人になったで、姫と結ばれた」である。
組合が云う由来の原文は次の通りである。
「江戸時代、針の製造販売は安立の地場産業だった。針を扱う行商人たちが、一寸法師の物語を販売促進に引用しながら、安立の針を全国に広めたと考える」であるが、これもまた・・。
江戸時代に針の地場産業だったことを示す史料はどのようなものであったのか。
行商人はどこから来ていたのか。
行商人が運んでいたなら、製造元は安立ではない。
販売だけの商人の町。
かつて紀州街道を往来する人たちにもうけさせてもらった「市」であろう。
紀州街道は大坂と和歌山を結ぶ紀州徳川家の参勤交代路として整備された街道。
その街道に宿場町や市が発達したに違いない。
ところで伝承はどのように形成されて物語化したのか。
実証を知りたいものだが、そこはロマンである。
看板は「一休法師ゆかりの安立町」。
所縁は“針”でしかならない。
さて、そこより反対側の南に向かって歩けば京都知恩院派の浄土宗・正音山阿弥陀寺がある。
文禄三年(1594)、旭蓮社播譽空智大和尚によって中興された寺院。
豊臣秀吉の五奉行の一人。
浅野長政ゆかりの寺である。
お寺の門扉前に石標が建っていた。

古い形式でもない石標に「十三まいり」とある。
「十三まいり」に関連する仏さんは虚空蔵菩薩。
阿弥陀寺のご本尊は阿弥陀如来仏。
どういう関係にあるのだろうか。
その「十三まいり」石標右横にある小堂。
椅子に座る弘法大師像もあれば観音菩薩立像に地蔵石仏、修験像なども。
正面に据えた仏像は赤ら顔の坐像。

どこやらのお寺の回廊で見た像と同じような表情をもつ特徴のある真っ赤なお顔の仏像は赤い涎掛けをしている。
思い出した坐像はびんずる尊者坐像だった。
びんずる(賓頭盧)尊者はお釈迦さんの弟子。
特に優れた代表的な16人は十六羅漢さんのうちのお一人。
酒が大好きなびんずる尊者はお釈迦さんから見えないところに隠れて酒浸り。
見つかった尊者はたしなめられて禁酒を決意するが・・・誘惑に負けた。
そういうことで許さないお釈迦さんは遠くへ放りだされた。
反省の上、修行に励んだと伝えられる尊者であるが、酒飲み。
そういうわけでの赤ら顔、ということだ。
ちなみに小堂奥の仏画はたぶんに地蔵菩薩の来迎降臨図であろう。
ここよりさらに南下すれば堺市との境界になる大和川が流れる。
奈良大和盆地から流れてきた水は大河となって大阪湾に流れ着く。
かつての大和川は当地を流れていなかった。
古くは奈良・飛鳥時代から洪水の記録がある大和川。
延暦七年(788)、和気清麻呂が河内川(おそらく現在の平野川)を今の天王寺公園北側より大阪湾へと普請するはずだったが、技術的或いは資金繰りで和えなく断念した経緯があるそうだ。
飛鳥時代の河内平野を流れる川は奈良から流れてきた大和川と大阪・柏原で合流する石川の水は北へ流れていた。
恩智川、玉櫛川、久宝寺川に平野川に分かれて上町台地北を迂回、西に折れて茅渟の海へ、であった。
大雨、決壊、土砂による天井川、そして護岸工事。
さまざまな工事を経てきたが、抜本的な対策ではなかったようだ。
状況を克服しようと、万治二年(1659)のころから大阪・河内地域の住民たちが出した改革案は「大和川を西に向けて、直接に大阪・住吉/堺の海に流れこむように」した大規模改革案であった。
やがて今米村(現在の東大阪市)に住む中甚兵衛らが中心となって付け替え運動を展開してからのことである。
付け替えに際して検分が行われた時期は万治三年(1660)から元禄十六年(1703)に至るまでの44年間である。
新・大和川の大規模付け替え工事が決定された元禄十六年十月。
翌年の元禄十七年二月に工事が始まって、完成したのは宝永元年(1704)十月十三日。
なんと、たったの8ケ月間足らずの期間に完成したというから凄いとしか言いようがない。
大和川の壮大なる記録は、大阪・柏原市が纏めたものがあるので、参考にしていただきたい。
なにが云いたいかといえば、住吉大社の一大行事である。
堺市・宿院の頓宮(※お旅所)まで向かう神輿の道に紀州街道を行く。
大和川に架かる大橋を渡るのではなく、大和川の水に浸かって渡る川渡御神輿巡行路である。
7月31日は堺渡御がある住吉祭。
明治14年7月31日に奉納された大神輿。
新調奉納のきっかけになったのは明治11年から明治12年にかけて行われた式年遷宮である。
その奉祝に新調された大神輿は明治、大正、昭和16年、戦争勃発まで続けていた。
戦後、復活の願いもあったが、昭和36年以降は渡御そのものが車両による形に移り替わったのである。
長年に亘って途絶えていた人足担ぎの大神輿が修繕・復活したのは平成17年のことである。
安立・紀州街道の文化財を伝えるリーフレットがある。
PDF版で公開している大阪あそ歩-岸の辺の道・安立を越えて-である。
住吉大神を大神輿に遷しまして渡御するようになったのは、明治14年からである。
それより以前はどういう形式でされていたのだろうか。
平成28年に行われた第43回の堺まつりの特別史料にあった400年前の渡御の情景である。
大和川の付け替え工事が終わったのは今から315年前のこと。
その時代の紀州街道には大和川はない。
たぶんに細い川であった狭間川に架かる橋を渡っていたのである。
そのことを示す史料は堺市博物館所蔵の「住吉祭礼図屏風」の左半分に住吉大社から出発した神輿など、神事の行列を描いているそうだ。
堺渡御はいつの時代から始まったのだろうか。
定かでないが、和泉国南庄の氏神である開口神社付近にあった海会寺住職が書き記した『蔗軒日録(しゃけんんもくろく)』の文明十六年(1484)6月29日の条に「住吉大明神・・・、午後馬騎百人ばかり、神輿を送り、宿井の松原(※河内松原であろうか)に至る」がある。
永禄五年(1562)、イエズス会宣教師フロイスによる記事に「住吉社は堺の郊外約半里のところで、市の人々の行楽地となっている広野にあり、堺のまちに神輿が来ていた」とある。
興味を惹かれた「住吉祭礼図屏風」にはその当時の安立集落が描かれている。
拝見する機会があれば、是非見ておきたい屏風図である。
ちなみにこの日に昼飯させてもらった食事処の外壁に一枚のお願いが貼ってあった。

お願い文は、住吉大社の「神輿担ぎ手募集」である。
お願いしているのは安立神興会。
担ぎ手の申し込みは各町会長まで、ということだから、街道沿いの町内会に貼りだしているように思える。
なお、現在の大神輿渡御は8月1日の午後2時より。
住吉大社を出発して安立を通って大和川までの行程を担う。
渡御が境に入れば宿院頓宮堺神興会・若松神社の若衆会の手に移るそうだ。
(H30. 4.16 SB932SH撮影)
畠中医院から西へ少し。
信号の向こう側にある線路はチンチン電車。
子どものころはその呼び名でも、あるいは駅名が我孫子道駅だから我孫子電車とも呼んでいた。
子どものころの風景とはまったく違うから、何十年も離れて戻ってきたら、すごく違和感をもつだろう。
信号がある左右の道は南北を往来する古道である。
北へ向かう道は安立商店街。

アーケードに「一休法師ゆかりの安立町」とある。
安立町は大阪市住之江区の安立(あんりゅう)町。
今の今まで、そんなことを知らずに育ってきた。
ネットをぐぐってみれば「一寸法師は安立の地で生まれた。針の刀をもって、京を目指した。かつて安立に多くの針屋があった。そのようなことで生まれたお伽噺」と書いてあるブログがあったが・・・。
へぇー、そうなんだというのが実感だが、安立は万葉集にも登場する地。
時代的には合致しそうだが、直接的なもののない由来は後付けどころか宣伝だった。
近世の安立に三栖屋(みすや)新右衛門など針商人が多くの店を構えていた。
そこでちょいと利用したお伽噺一寸法師の鬼退治伝説であった。
安立本通商店街振興組合が伝える由来である。
組合でなくとも誰しも知っているお伽噺。
「子宝に恵まれない夫婦が住吉大社に願をかけたら一寸法師が生まれた。お椀の舟に乗って川を上り京の都に向かった。なぜかそこにお姫さんがいた。姫を襲っていた鬼は針の刀で退治した。そして打ち出の小槌を振ったら大人になったで、姫と結ばれた」である。
組合が云う由来の原文は次の通りである。
「江戸時代、針の製造販売は安立の地場産業だった。針を扱う行商人たちが、一寸法師の物語を販売促進に引用しながら、安立の針を全国に広めたと考える」であるが、これもまた・・。
江戸時代に針の地場産業だったことを示す史料はどのようなものであったのか。
行商人はどこから来ていたのか。
行商人が運んでいたなら、製造元は安立ではない。
販売だけの商人の町。
かつて紀州街道を往来する人たちにもうけさせてもらった「市」であろう。
紀州街道は大坂と和歌山を結ぶ紀州徳川家の参勤交代路として整備された街道。
その街道に宿場町や市が発達したに違いない。
ところで伝承はどのように形成されて物語化したのか。
実証を知りたいものだが、そこはロマンである。
看板は「一休法師ゆかりの安立町」。
所縁は“針”でしかならない。
さて、そこより反対側の南に向かって歩けば京都知恩院派の浄土宗・正音山阿弥陀寺がある。
文禄三年(1594)、旭蓮社播譽空智大和尚によって中興された寺院。
豊臣秀吉の五奉行の一人。
浅野長政ゆかりの寺である。
お寺の門扉前に石標が建っていた。

古い形式でもない石標に「十三まいり」とある。
「十三まいり」に関連する仏さんは虚空蔵菩薩。
阿弥陀寺のご本尊は阿弥陀如来仏。
どういう関係にあるのだろうか。
その「十三まいり」石標右横にある小堂。
椅子に座る弘法大師像もあれば観音菩薩立像に地蔵石仏、修験像なども。
正面に据えた仏像は赤ら顔の坐像。

どこやらのお寺の回廊で見た像と同じような表情をもつ特徴のある真っ赤なお顔の仏像は赤い涎掛けをしている。
思い出した坐像はびんずる尊者坐像だった。
びんずる(賓頭盧)尊者はお釈迦さんの弟子。
特に優れた代表的な16人は十六羅漢さんのうちのお一人。
酒が大好きなびんずる尊者はお釈迦さんから見えないところに隠れて酒浸り。
見つかった尊者はたしなめられて禁酒を決意するが・・・誘惑に負けた。
そういうことで許さないお釈迦さんは遠くへ放りだされた。
反省の上、修行に励んだと伝えられる尊者であるが、酒飲み。
そういうわけでの赤ら顔、ということだ。
ちなみに小堂奥の仏画はたぶんに地蔵菩薩の来迎降臨図であろう。
ここよりさらに南下すれば堺市との境界になる大和川が流れる。
奈良大和盆地から流れてきた水は大河となって大阪湾に流れ着く。
かつての大和川は当地を流れていなかった。
古くは奈良・飛鳥時代から洪水の記録がある大和川。
延暦七年(788)、和気清麻呂が河内川(おそらく現在の平野川)を今の天王寺公園北側より大阪湾へと普請するはずだったが、技術的或いは資金繰りで和えなく断念した経緯があるそうだ。
飛鳥時代の河内平野を流れる川は奈良から流れてきた大和川と大阪・柏原で合流する石川の水は北へ流れていた。
恩智川、玉櫛川、久宝寺川に平野川に分かれて上町台地北を迂回、西に折れて茅渟の海へ、であった。
大雨、決壊、土砂による天井川、そして護岸工事。
さまざまな工事を経てきたが、抜本的な対策ではなかったようだ。
状況を克服しようと、万治二年(1659)のころから大阪・河内地域の住民たちが出した改革案は「大和川を西に向けて、直接に大阪・住吉/堺の海に流れこむように」した大規模改革案であった。
やがて今米村(現在の東大阪市)に住む中甚兵衛らが中心となって付け替え運動を展開してからのことである。
付け替えに際して検分が行われた時期は万治三年(1660)から元禄十六年(1703)に至るまでの44年間である。
新・大和川の大規模付け替え工事が決定された元禄十六年十月。
翌年の元禄十七年二月に工事が始まって、完成したのは宝永元年(1704)十月十三日。
なんと、たったの8ケ月間足らずの期間に完成したというから凄いとしか言いようがない。
大和川の壮大なる記録は、大阪・柏原市が纏めたものがあるので、参考にしていただきたい。
なにが云いたいかといえば、住吉大社の一大行事である。
堺市・宿院の頓宮(※お旅所)まで向かう神輿の道に紀州街道を行く。
大和川に架かる大橋を渡るのではなく、大和川の水に浸かって渡る川渡御神輿巡行路である。
7月31日は堺渡御がある住吉祭。
明治14年7月31日に奉納された大神輿。
新調奉納のきっかけになったのは明治11年から明治12年にかけて行われた式年遷宮である。
その奉祝に新調された大神輿は明治、大正、昭和16年、戦争勃発まで続けていた。
戦後、復活の願いもあったが、昭和36年以降は渡御そのものが車両による形に移り替わったのである。
長年に亘って途絶えていた人足担ぎの大神輿が修繕・復活したのは平成17年のことである。
安立・紀州街道の文化財を伝えるリーフレットがある。
PDF版で公開している大阪あそ歩-岸の辺の道・安立を越えて-である。
住吉大神を大神輿に遷しまして渡御するようになったのは、明治14年からである。
それより以前はどういう形式でされていたのだろうか。
平成28年に行われた第43回の堺まつりの特別史料にあった400年前の渡御の情景である。
大和川の付け替え工事が終わったのは今から315年前のこと。
その時代の紀州街道には大和川はない。
たぶんに細い川であった狭間川に架かる橋を渡っていたのである。
そのことを示す史料は堺市博物館所蔵の「住吉祭礼図屏風」の左半分に住吉大社から出発した神輿など、神事の行列を描いているそうだ。
堺渡御はいつの時代から始まったのだろうか。
定かでないが、和泉国南庄の氏神である開口神社付近にあった海会寺住職が書き記した『蔗軒日録(しゃけんんもくろく)』の文明十六年(1484)6月29日の条に「住吉大明神・・・、午後馬騎百人ばかり、神輿を送り、宿井の松原(※河内松原であろうか)に至る」がある。
永禄五年(1562)、イエズス会宣教師フロイスによる記事に「住吉社は堺の郊外約半里のところで、市の人々の行楽地となっている広野にあり、堺のまちに神輿が来ていた」とある。
興味を惹かれた「住吉祭礼図屏風」にはその当時の安立集落が描かれている。
拝見する機会があれば、是非見ておきたい屏風図である。
ちなみにこの日に昼飯させてもらった食事処の外壁に一枚のお願いが貼ってあった。

お願い文は、住吉大社の「神輿担ぎ手募集」である。
お願いしているのは安立神興会。
担ぎ手の申し込みは各町会長まで、ということだから、街道沿いの町内会に貼りだしているように思える。
なお、現在の大神輿渡御は8月1日の午後2時より。
住吉大社を出発して安立を通って大和川までの行程を担う。
渡御が境に入れば宿院頓宮堺神興会・若松神社の若衆会の手に移るそうだ。
(H30. 4.16 SB932SH撮影)