朝方は強い雨でしたが、お昼前から小康状態
 湿度が高くてジメジメ~と・・・
湿度が高くてジメジメ~と・・・
「津山城跡」~旧出雲街道沿いの町並み保存地区へ・・・
 院庄IC を出るとき。ETCが故障しているのか、ETCカード手渡しして決済。
院庄IC を出るとき。ETCが故障しているのか、ETCカード手渡しして決済。
「津山城(鶴山公園 かくざんこうえん)」の駐車場から
表門入口へ
マンホールのふた 可愛い~
可愛い~
細くて長い坂道~「千石坂」


「日本100名城」「日本さくら名所100選」に選ばれている津山市のシンボル。本能寺の変で討死した森蘭丸の弟、森忠政が1616年に築城しました。明治の廃城令によって建造物はすべて取り壊されましたが、2005年に築城400周年を記念して備中櫓(びっちゅうやぐら)が復元。約45mの高さを誇る石垣とともに新たな人気スポットとなっています。また、県内でも1、2を争う桜の名所として知られ、約1,000本の桜が咲き誇る景観は見事です。石垣の上から眺めるライトアップされた桜も圧巻です。(岡山観光WEBより)

「入場券売場」



石段は上がらずに
アジサイまだ愉しめます~
左の石段から


真ん中に見えているのが入口から正面の石段です。
改修工事中のようで邪魔にならないようにカシャ


堅固な石垣
津山城は、室町時代に山中忠正が高さ50mの鶴山に鶴山城を築いたことが始まりで、応仁・文明の乱で廃城となったが、関ヶ原の戦功により1603年(慶長8)に入った森忠政(本能寺の変で討死した森蘭丸の弟)が、鶴山を津山と改名し13年かけて津山城を大規模な近世城郭として完成させる。城は鶴山全体を10mを超える高石垣で囲み、さらに雛壇状に三の丸、二の丸、本丸と曲輪を積み上げ、最上段の天守曲輪には藤堂高虎によって考案された層塔型(下の階から上の階へ規則的に小さくなる様式)で、小倉城を参考にした五重天守が建ち、これを取り囲むように多くの櫓と門が林立した強固な防御網を誇った平山城であったが、明治初期に城内の建物は全て取壊された。2005年(平成17)築城400年の記念行事として、城内最大の櫓で「全室畳敷きで御殿の一部として使用されていた」という備中櫓が復元され、2006(平成18)には天守台南側に太鼓塀が復元された。(日本100名城よりお借りしました)

「鶴山館」


「備中櫓」が望めます~


「表中門」へ




足場が組まれてます~
「二の丸」から

本丸(備中櫓)へはこの先です
前日の曇り空から、この日は快晴!ギラギラ☀太陽

 暑さに弱い~
暑さに弱い~
櫓へは上がらず「裏門」から出ます~
おふろのような入口の暖簾


地面を這うような桜の枝
サクラ 素晴らしそう~
素晴らしそう~

青もみじも素敵~


「裏門」が見えています!
が、結構距離が!
石段も!



裏門からでます
「厩堀」から

「津山観光センター」へ立ち寄り
城下町城東界隈へ・・・つづきます~



































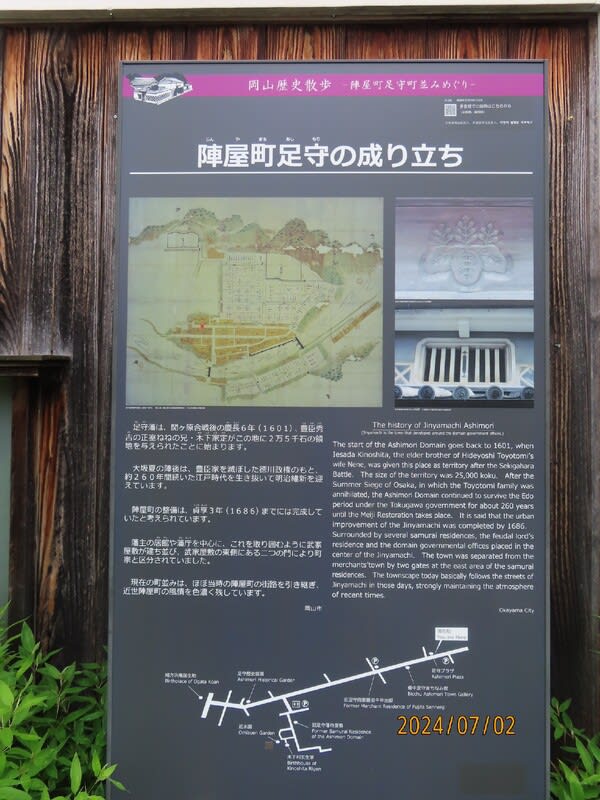

 宿舎へ・・・
宿舎へ・・・

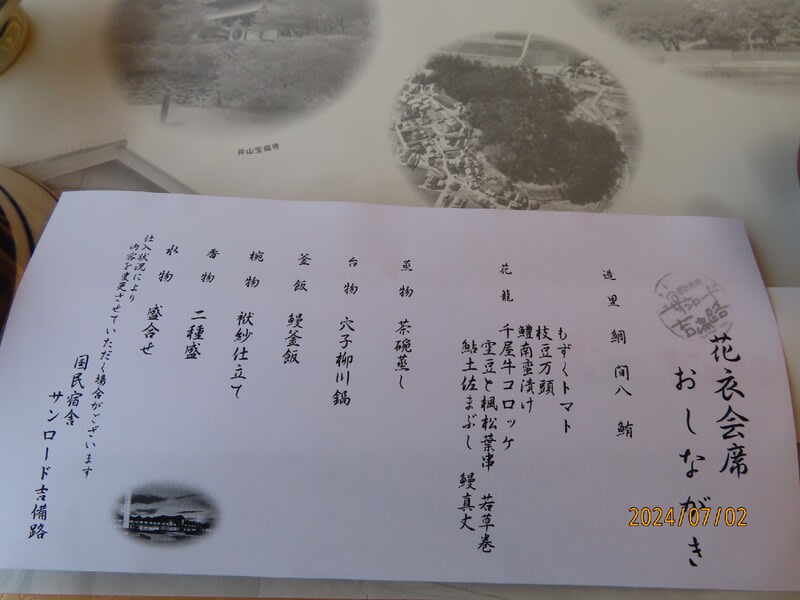



























































 うっかりしては立ち寄らず
うっかりしては立ち寄らず 残念なことをしました、、、
残念なことをしました、、、


 (前回は2022年12月・境内の様子は詳しく載せてます)
(前回は2022年12月・境内の様子は詳しく載せてます)


















































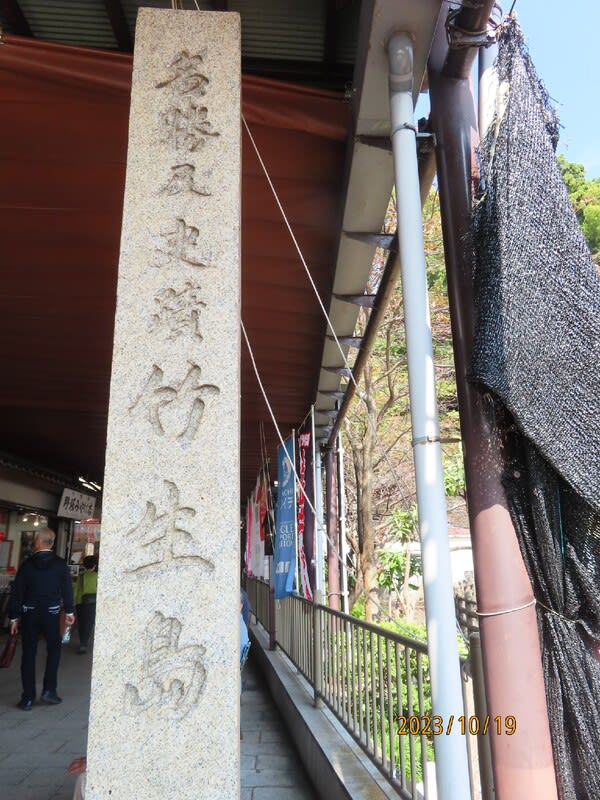




















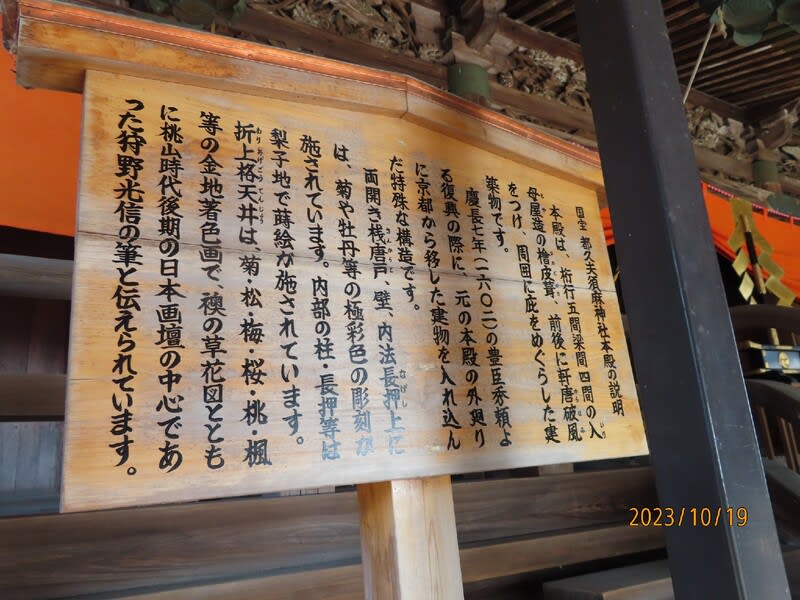






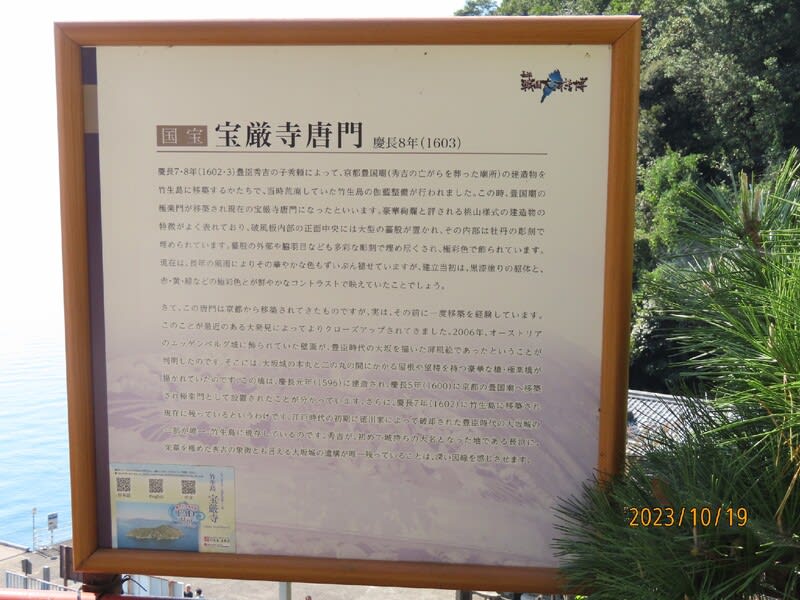
 この先から
この先から















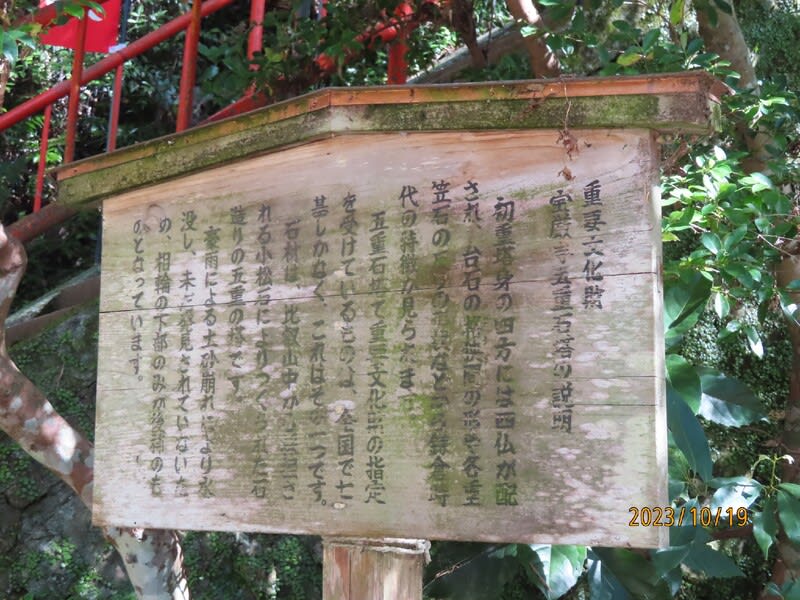







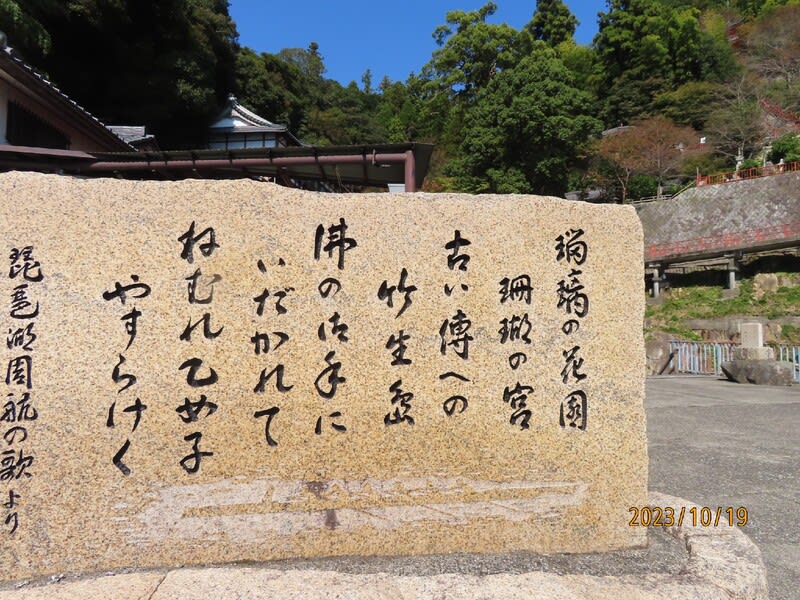
 )
)


