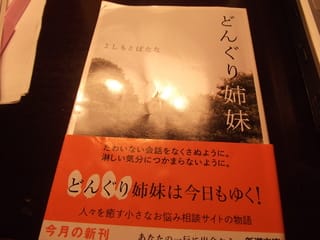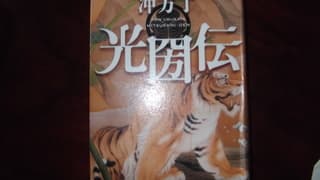「生きとし生けるもの、末永く元気で、さようなら」という言葉を残して
息子さんは亡くなった。・・それから1年後3・11が起きる。
「原発事故という惨事を招いたシステムと人脈が息を吹き返し、
我こそ「改革者」とばかりに戦後の幕引きを図ろうとしている。」
「この2年は、あの関東大震災から昭和恐慌、世界恐慌、そして満州事変と続く
時代の暗転劇のようで、今や戦後の終わりが始まろうとしているのかもしれない」
「不安を感じながらなす術もなく見守らざるを得ない人々にとって、
本書がささやかな励みになってほしいと願う」・・作者の言葉
この本は、「アエラ」に連載されたコラムを収録されたもの。
ひとつひとつのコラムの中味が濃く、読み飛ばしてしまうのは惜しい。