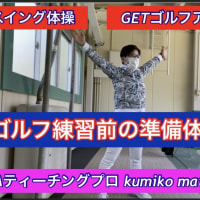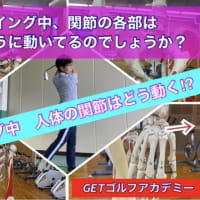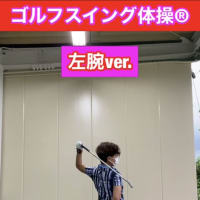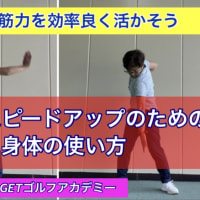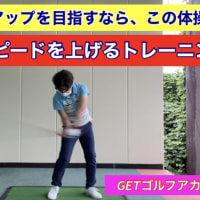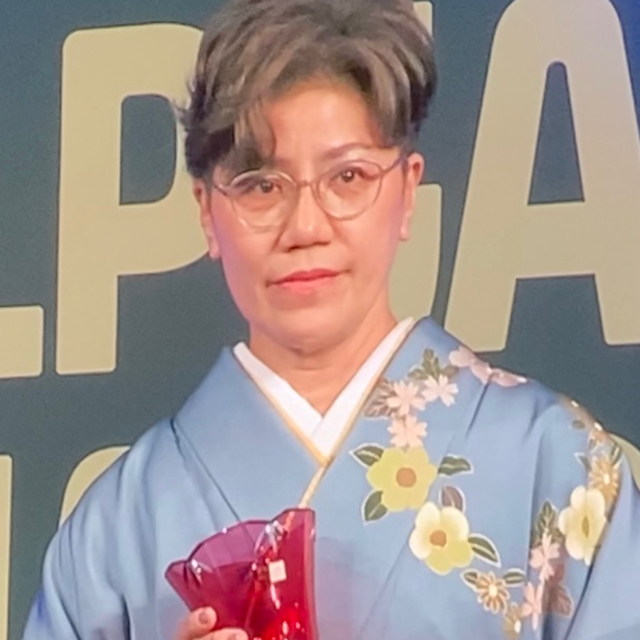一昨日、昨日のblogの続きです…。
よく動くが、その分、安定性にも乏しい機能的な特徴を持っている『肩甲上腕関節』、
肩甲棘と上腕の骨がまっすぐ一直線になる位置で、肩甲上腕関節が最も安定する『肩のゼロポジション』、
上腕骨の骨頭をかかえ込んで、肩甲上腕関節を安定させるはたらきのある『ローテーターカフ(回旋筋腱板)』。
“ここ”を知り、“ここ”の動きを良くして行くことは、よく「スイング中、両肩と両腕を結ぶ、二等辺三角形を崩さずに振る」と言われる理論をご理解いただくことにも繋がる…と思っています。
特に、インパクトの瞬間に、この二等辺三角形が崩れていなければ…、
「構えた通りのインパクトになりやすい(アドレス時にフェースが正しくターゲット方向を向いていれば、インパクトでも、フェースはターゲット方向に向くので、そのまま、ターゲット方向に向かってボールが飛び出しやすくなる)」
「身体の中心でボールをとらえることができる(全身のパワーをロス無くボールに伝えることができる)」
…ので、ゴルフスイングを作る上では、どうしてもこだわりたいところ。
なので、巷には、この二等辺三角形を崩さずに振れるようになるための練習器具が、あふれ返っている…(~_~;)。
両腕の間を縛るゴム製のもの、両腕の間にはさめるプラスチック製のもの、などなど多種多様…。
私も、レッスンに、両肘の間にはさめるくらいの大きさのビニールボールを使用したりするが…(^_^;)
でも、「二等辺三角形を崩さずに振る」と言っても、ただ単に、両肘を締めれば良いだけではない。
締めただけでは、スイングは“小さく”、そして、動きも“窮屈”になる。
両肩、すなわち肩甲骨と、両腕が、共に動き、さらに、その動きが一致して、はじめて、「二等辺三角形を崩さずに振る」ができるのだ。
これを考えると、スイング中、両肘の間にボールをはさんだまま打てないとか、落とさずに振ろうと思えば、とても窮屈に感じられる方は、両腕の動きに伴う肩甲骨の動きが少ない、あるいは、連動していないと言う事になるのだが…。
でも、肩と腕の動きを連動させるって、難しいですよね…(^_^;)
肩甲骨の動きって、感知しにくいし、
肩甲骨周辺の柔軟性も必要だし、
肩甲上腕関節の動きは、安定性に乏しいし…(~_~;)
だからこそ、『肩のゼロポジション』を知って、『ローテーターカフ(回旋筋腱板)』の存在をそれとなく感じ、“二等辺三角形”を崩さないまま、一旦、身体の前で、大きな円を描く練習を行なっていただいて…、
上腕骨と肩甲骨の動きを一致させて行く練習が必要…だと思うのです。
レッスンでは、毎回、全身の筋肉をほぐすストレッチと、この“円月殺法素振り”は、欠かさずに行なって頂いていますが…。
これらを行なう事によって、目指して行きたい、主な目標は…、
スイング理論として、当たり前のように言われている「両肩と両腕を結ぶ二等辺三角形を崩さずに振る」です…。
『肩のゼロポジション』とか『ローテーターカフ(回旋筋腱板)』とか、聞き慣れない言葉を出してきて、ややこしいことを言っているようでも…(^_^;)
この当たり前のように言われているスイング理論も、実は、肩甲骨と上腕骨の動きの連動がなされていなければ、できないことなのだとご理解いただいた上で…、
当たり前と言われているスイングに近付けて行けるように…との試みだと思っていて下さいね…(^^)
これは、続けてやって行くのと、あまりやらないのとでは、積み重なれば、やがて、大きな差になる…と、私は、思っています。
よく動くが、その分、安定性にも乏しい機能的な特徴を持っている『肩甲上腕関節』、
肩甲棘と上腕の骨がまっすぐ一直線になる位置で、肩甲上腕関節が最も安定する『肩のゼロポジション』、
上腕骨の骨頭をかかえ込んで、肩甲上腕関節を安定させるはたらきのある『ローテーターカフ(回旋筋腱板)』。
“ここ”を知り、“ここ”の動きを良くして行くことは、よく「スイング中、両肩と両腕を結ぶ、二等辺三角形を崩さずに振る」と言われる理論をご理解いただくことにも繋がる…と思っています。
特に、インパクトの瞬間に、この二等辺三角形が崩れていなければ…、
「構えた通りのインパクトになりやすい(アドレス時にフェースが正しくターゲット方向を向いていれば、インパクトでも、フェースはターゲット方向に向くので、そのまま、ターゲット方向に向かってボールが飛び出しやすくなる)」
「身体の中心でボールをとらえることができる(全身のパワーをロス無くボールに伝えることができる)」
…ので、ゴルフスイングを作る上では、どうしてもこだわりたいところ。
なので、巷には、この二等辺三角形を崩さずに振れるようになるための練習器具が、あふれ返っている…(~_~;)。
両腕の間を縛るゴム製のもの、両腕の間にはさめるプラスチック製のもの、などなど多種多様…。
私も、レッスンに、両肘の間にはさめるくらいの大きさのビニールボールを使用したりするが…(^_^;)
でも、「二等辺三角形を崩さずに振る」と言っても、ただ単に、両肘を締めれば良いだけではない。
締めただけでは、スイングは“小さく”、そして、動きも“窮屈”になる。
両肩、すなわち肩甲骨と、両腕が、共に動き、さらに、その動きが一致して、はじめて、「二等辺三角形を崩さずに振る」ができるのだ。
これを考えると、スイング中、両肘の間にボールをはさんだまま打てないとか、落とさずに振ろうと思えば、とても窮屈に感じられる方は、両腕の動きに伴う肩甲骨の動きが少ない、あるいは、連動していないと言う事になるのだが…。
でも、肩と腕の動きを連動させるって、難しいですよね…(^_^;)
肩甲骨の動きって、感知しにくいし、
肩甲骨周辺の柔軟性も必要だし、
肩甲上腕関節の動きは、安定性に乏しいし…(~_~;)
だからこそ、『肩のゼロポジション』を知って、『ローテーターカフ(回旋筋腱板)』の存在をそれとなく感じ、“二等辺三角形”を崩さないまま、一旦、身体の前で、大きな円を描く練習を行なっていただいて…、
上腕骨と肩甲骨の動きを一致させて行く練習が必要…だと思うのです。
レッスンでは、毎回、全身の筋肉をほぐすストレッチと、この“円月殺法素振り”は、欠かさずに行なって頂いていますが…。
これらを行なう事によって、目指して行きたい、主な目標は…、
スイング理論として、当たり前のように言われている「両肩と両腕を結ぶ二等辺三角形を崩さずに振る」です…。
『肩のゼロポジション』とか『ローテーターカフ(回旋筋腱板)』とか、聞き慣れない言葉を出してきて、ややこしいことを言っているようでも…(^_^;)
この当たり前のように言われているスイング理論も、実は、肩甲骨と上腕骨の動きの連動がなされていなければ、できないことなのだとご理解いただいた上で…、
当たり前と言われているスイングに近付けて行けるように…との試みだと思っていて下さいね…(^^)
これは、続けてやって行くのと、あまりやらないのとでは、積み重なれば、やがて、大きな差になる…と、私は、思っています。