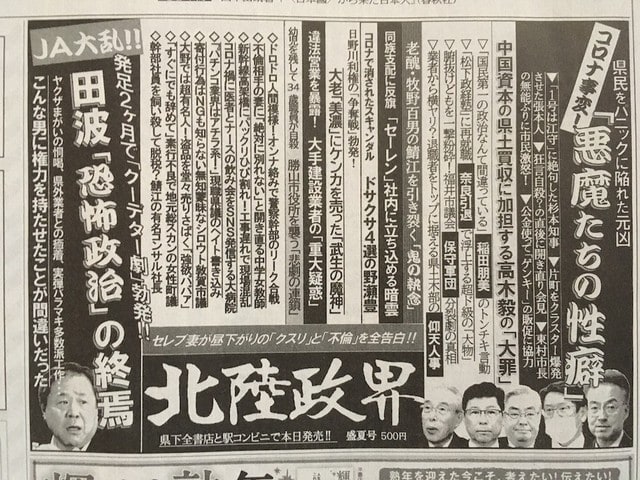地主A:80歳、独り暮らし(家族は神戸)田面積6.5反 農家組合長 村八分的存在 退職サラリーマン 孤独な変人
地主B:80歳、村の先生、ほぼ独り暮らし(時々、街に住む奥さんが車でやってきて、畑をしている。最近、先生が免許を返納したので、日数が多くなった。息子は医者)田面積約4反 変人
地主C:85歳、一昨年より急に歩行困難。息子夫婦は廊下で繋がった敷地内別家屋で同居。夫人は元気。息子はサラリーマンで農業は一切タッチしない。田んぼ面積3反
地主D:75歳、村で一番農作業に詳しく、よく働いたが、近年椎間板ヘルニアで歩行困難。家族同居だが、息子は遠隔地で就職。家の前の小さな畑だけ、夫婦でしている。田面積1.5反
さあ、この1.5町歩ほどの小さな田んぼは、農業法人アベベ(仮称)に依頼して(その主導は全て地主A)、完全放置。年間反あたり五千円の地主地代をもらっている。1番の大地主でも年間、3万5千円程度。
で、農家組合の決算では、用水ポンプの電気代だけでも年間10万円ほどかかる。これを地主は当然負担できない。負担すれば赤字になる。それは耕作を委託された農業法人が負担している。無論、だから、用水の管理もお任せだが、用水ポンプは村の所有物であり、これが年代物だから、壊れた時どーすんの? と私は用水の泥上げ作業で、スコップいっぱいさえ作業したことのない農家組合長、つまり1番の田んぼ面積所有者Aに突きつけ、挙句、あんたが一番金をださんとあかんやろ、と村の葬儀に香典の千円も出さない彼には頭痛の種を植え付ける。
用水ポンプを交換すれば、100万円や200万円の金がかかる。今、その用水は県道の下を古い鉄管パイプで通過している。大型車両が激しく通行する。いつ、壊れても不思議ではない。
将来の問題として、日野川の増水時に水に沈むポンプ小屋。算盤の合わない電気代を使って、その用水に水を流して稲作しても年間7、8万円の不労所得。その不労所得を稼ぐために、あれこれ言い訳しているが、さあ、泥水で水の吸い上げが不能になった。先週は、連日たっぷり水が流れていた用水はカラカラになってきた。
誰が、役所に泣きつくのだろう? そして、役所はどういう判断をするのだろう?
近い将来が、実に楽しみだ。