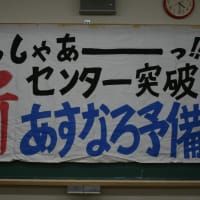千鳥格子のジャケットの胸元に鼈甲のループタイ、ジャケットと同系色のハンチングをかぶってピシッとプレスの効いたパンツに磨き上げた赤茶の牛革の靴を履いて、竹のステッキを小脇に抱え込んで少し早足に矍鑠と闊歩する。商都大阪で文具店を営んでいた弥乃輔(やのすけ)爺さんである。いつだって外出時の身なりには気を使う弥乃輔爺さんはジャケットのことを「ジャケツ」と云う。若いころは京阪神の繁華なあたりで「ブイブイ」いわせていた『モボ』だったとも聞く。細かい関係はわからないがとにかく親類にあたって、小さいころからよくかわいがってもらっていた。
幼稚園に上がるか上がらないか、はっきりとしないがまだほんの小さかった頃。その当時アーモンドチョコを食べたことも見たこともなかった。爺さんのところに行くと口の中で何かをオネオネと舐っている。それは何だと尋ねても質問に答える代わりにチョコの箱を指差したなりこちらの顔を見据えながら暫くの間オネオネオネオネ、『お!』という顔をして口から何かを取り出した。当時の自分にとってはチョコはチョコ、中までチョコの塊で、中にチョコ以外のものが入っているなど思いもよらない。
「チョコのタネや」
そう言ってニヤッと笑って見せる。「わ!」そのままちり紙に包んでもらったのを後生大事に自宅に持ち帰って庭に植えた。毎朝水をやり、それは一生懸命に世話をしたものである。なのに一向に芽を出さない。当たり前だ、チョコレートの中に封入された加工済みのアーモンドが芽吹くほうがどうかしている。毎年秋には鳥取の梨を送っていたのだが、そのお礼の電話がかかってきたときに「おじいちゃん、芽が出ん」と訴えてみた。そのときに真相を知らされて泣き寝入りした。しょっちゅう大阪に行っていろんなところに連れて行ってもらって、いろんなことをしている写真も残っているのだが、小学校の低学年くらいまでの大阪にまつわる記憶はそれだけしか残っていない。
大学に入って京都に住むようになり、最初の夏休みが始まって帰省する前、その時期は弥乃輔爺さんの最晩年にあたるのだけれど、ちょっと顔を出してみた。訪ねていったのがお昼前で、爺さんはステテコ姿で昼寝をしていた。一歩家を出るときはいくら暑くても必ずジャケツを着込んで出かける洒落者だが、自宅待機中はラフな格好で快適に過ごすようである。よくきたねぇ、と迎えてくれたおばさん、弥乃輔爺さんにとっては長男の嫁、によるとほんの数日前隣家の玄関を開けて「ただいまぁ」と声をかけたのだそうで、そこの若奥さんが「え? 隣のお爺ちゃん…」と驚いている様子を見て楽しそうに「いや大丈夫大丈夫、ちゃんとわかってるがナ」と言い残して帰宅したという。隣の奥さんからその話を聞いてどうしてそんなことをするかと詰問したところ、しれっと「いつボケたかわからんようにしたろ思て」と言ってのけたらしい。いかにも爺さんらしいと笑っていると「たまにやったらええケド、こんなん毎日やったらたまらんよぉ」と深い息をつく。
「よぉ来たな」
「久しぶりやし、晩御飯食べてゆっくりしていきぃ」と楽しそうに言ってくれているおばさんの横手から弥乃輔爺さんが入ってきた。すでに外出用の身なりを整えている。
「あれ、お爺ちゃんどっか行かはんの」
「うん、ちょっとこいつと蕎麦食い行こか思てな、昼はそれで済ませるわ」
あんまり過ぎたらあかんよぉ、と送り出され、千鳥格子のジャケツの胸元に鼈甲のループタイ、ジャケツと同系色のハンチングをかぶってピシッとプレスの効いたパンツに磨き上げた赤茶の牛革の靴を履いて、竹のステッキを小脇に抱え込んで少し早足に矍鑠と闊歩する。途中で行き交う顔見知りと一言二言声を掛け合い、古い蕎麦屋の暖簾を潜る。「おぉ、爺ちゃん毎度」という若い大将のお愛想に「ご機嫌さん、邪魔すんでぇ」と答えて衝立に隠れたテーブル席に座る。
「お銚子、こそばそか」
席に着くなりにんまりとこう切り出した。「何だそれ」と尋ね終わらないうちにカウンターの向こうに「お、一本付けたってぇ」と声をかけた。天ざるの台抜きに出汁巻と板わさ、それをつまみに燗酒を煽る。「かーっ、昼間の酒は効っきょんなぁ!」カウンターに知り合いらしいおじさんが座っていて、「弥乃さん、こんな孫おったんかいな」「あぁ、孫ちがう、弟子みたいなもんやな」弟子入りした覚えはないのだが。
一合徳利で三本、酔うというほどでもなくちょうどふわっとなりかけた好い頃合いで盛りを一枚。「ほななぁ」と言って店を出るとちょっと足元がおぼつかなくなっている。相当の酒豪だと話には聞いていたのだけれど、寄る年波というやつだろう。来しなには小脇に抱えていたステッキを突き突き気持ちよさそうに揺らぎながら歩いている。途中の酒屋に寄って店主と二言三言、奥に引っ込んだ店主が持ってきた酒を買って「これ旨いんやでぇ」と嬉しそうである。
帰って上着を脱ぐなり大の字になってそのままゴワゴワと高鼾。おばさんはタオルケットを掛けながら「こんなに酔うのん珍しいネェ」と言ってもうすぐみんな帰ってくるから、軽く汗流しといで、と浴衣を出してくれた。シャワーを借りて爺さんの寝顔を眺めつつ出された麦茶で涼んでいるとおじさんと短大に通う孫娘も帰ってきた。「久しぶりやねぇ」起きだしてきた弥乃輔爺さんも加わって酒盛りが始まって、おじさんによると爺さんは「ここ何年かついぞなかった」というほどたくさん量を過ごしている。結局何時にどうなったかわからないけれど、目が覚めたら明るくなっていて全員が軽い頭痛を抱えつつおかゆをすすった。
結局弥乃輔爺さんとはそれが最後になってしまったけれど、後におじさんとおばさんから「あの時はよっぽど嬉しかったんやねぇ」と言ってもらって、そう言ってもらったのが嬉しかった。
せめて大学を卒業するまでは旨いお酒を一緒に酌み交わしたかったのだけど、わが師と仰ぎたくなるような、飄然とした生きざまのなんとも素敵な爺さんでした。
幼稚園に上がるか上がらないか、はっきりとしないがまだほんの小さかった頃。その当時アーモンドチョコを食べたことも見たこともなかった。爺さんのところに行くと口の中で何かをオネオネと舐っている。それは何だと尋ねても質問に答える代わりにチョコの箱を指差したなりこちらの顔を見据えながら暫くの間オネオネオネオネ、『お!』という顔をして口から何かを取り出した。当時の自分にとってはチョコはチョコ、中までチョコの塊で、中にチョコ以外のものが入っているなど思いもよらない。
「チョコのタネや」
そう言ってニヤッと笑って見せる。「わ!」そのままちり紙に包んでもらったのを後生大事に自宅に持ち帰って庭に植えた。毎朝水をやり、それは一生懸命に世話をしたものである。なのに一向に芽を出さない。当たり前だ、チョコレートの中に封入された加工済みのアーモンドが芽吹くほうがどうかしている。毎年秋には鳥取の梨を送っていたのだが、そのお礼の電話がかかってきたときに「おじいちゃん、芽が出ん」と訴えてみた。そのときに真相を知らされて泣き寝入りした。しょっちゅう大阪に行っていろんなところに連れて行ってもらって、いろんなことをしている写真も残っているのだが、小学校の低学年くらいまでの大阪にまつわる記憶はそれだけしか残っていない。
大学に入って京都に住むようになり、最初の夏休みが始まって帰省する前、その時期は弥乃輔爺さんの最晩年にあたるのだけれど、ちょっと顔を出してみた。訪ねていったのがお昼前で、爺さんはステテコ姿で昼寝をしていた。一歩家を出るときはいくら暑くても必ずジャケツを着込んで出かける洒落者だが、自宅待機中はラフな格好で快適に過ごすようである。よくきたねぇ、と迎えてくれたおばさん、弥乃輔爺さんにとっては長男の嫁、によるとほんの数日前隣家の玄関を開けて「ただいまぁ」と声をかけたのだそうで、そこの若奥さんが「え? 隣のお爺ちゃん…」と驚いている様子を見て楽しそうに「いや大丈夫大丈夫、ちゃんとわかってるがナ」と言い残して帰宅したという。隣の奥さんからその話を聞いてどうしてそんなことをするかと詰問したところ、しれっと「いつボケたかわからんようにしたろ思て」と言ってのけたらしい。いかにも爺さんらしいと笑っていると「たまにやったらええケド、こんなん毎日やったらたまらんよぉ」と深い息をつく。
「よぉ来たな」
「久しぶりやし、晩御飯食べてゆっくりしていきぃ」と楽しそうに言ってくれているおばさんの横手から弥乃輔爺さんが入ってきた。すでに外出用の身なりを整えている。
「あれ、お爺ちゃんどっか行かはんの」
「うん、ちょっとこいつと蕎麦食い行こか思てな、昼はそれで済ませるわ」
あんまり過ぎたらあかんよぉ、と送り出され、千鳥格子のジャケツの胸元に鼈甲のループタイ、ジャケツと同系色のハンチングをかぶってピシッとプレスの効いたパンツに磨き上げた赤茶の牛革の靴を履いて、竹のステッキを小脇に抱え込んで少し早足に矍鑠と闊歩する。途中で行き交う顔見知りと一言二言声を掛け合い、古い蕎麦屋の暖簾を潜る。「おぉ、爺ちゃん毎度」という若い大将のお愛想に「ご機嫌さん、邪魔すんでぇ」と答えて衝立に隠れたテーブル席に座る。
「お銚子、こそばそか」
席に着くなりにんまりとこう切り出した。「何だそれ」と尋ね終わらないうちにカウンターの向こうに「お、一本付けたってぇ」と声をかけた。天ざるの台抜きに出汁巻と板わさ、それをつまみに燗酒を煽る。「かーっ、昼間の酒は効っきょんなぁ!」カウンターに知り合いらしいおじさんが座っていて、「弥乃さん、こんな孫おったんかいな」「あぁ、孫ちがう、弟子みたいなもんやな」弟子入りした覚えはないのだが。
一合徳利で三本、酔うというほどでもなくちょうどふわっとなりかけた好い頃合いで盛りを一枚。「ほななぁ」と言って店を出るとちょっと足元がおぼつかなくなっている。相当の酒豪だと話には聞いていたのだけれど、寄る年波というやつだろう。来しなには小脇に抱えていたステッキを突き突き気持ちよさそうに揺らぎながら歩いている。途中の酒屋に寄って店主と二言三言、奥に引っ込んだ店主が持ってきた酒を買って「これ旨いんやでぇ」と嬉しそうである。
帰って上着を脱ぐなり大の字になってそのままゴワゴワと高鼾。おばさんはタオルケットを掛けながら「こんなに酔うのん珍しいネェ」と言ってもうすぐみんな帰ってくるから、軽く汗流しといで、と浴衣を出してくれた。シャワーを借りて爺さんの寝顔を眺めつつ出された麦茶で涼んでいるとおじさんと短大に通う孫娘も帰ってきた。「久しぶりやねぇ」起きだしてきた弥乃輔爺さんも加わって酒盛りが始まって、おじさんによると爺さんは「ここ何年かついぞなかった」というほどたくさん量を過ごしている。結局何時にどうなったかわからないけれど、目が覚めたら明るくなっていて全員が軽い頭痛を抱えつつおかゆをすすった。
結局弥乃輔爺さんとはそれが最後になってしまったけれど、後におじさんとおばさんから「あの時はよっぽど嬉しかったんやねぇ」と言ってもらって、そう言ってもらったのが嬉しかった。
せめて大学を卒業するまでは旨いお酒を一緒に酌み交わしたかったのだけど、わが師と仰ぎたくなるような、飄然とした生きざまのなんとも素敵な爺さんでした。