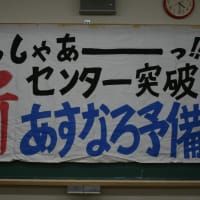七月になると祇園祭を間近に控えた京都の町の色めき立つ、のだそうで。コンコンチキチンの祇園囃子も賑やかに山鉾の巡行する十七日をクライマックスとして、十日ごろには山・鉾の組み立てが始まり十四日の宵々々山(よいよいよいやま)から前夜祭にあたる十六日の宵山(よいやま)の深更に及ぶまで出店や夜店も出されてそれはもう大変な盛り上がりを見せる、のだそうで。
伝聞調になっているのは伝聞でしかないからなのだが、実を申さばただでさえ蒸し蒸しと不快指数が天井知らずに鰻昇ってしまうこの時期に犇く人のいきれの中にわざわざ赴こうかなどという酔狂な気分にもなれず、毎年新聞、テレビのローカルニュースで報道される祭りの様子を疑似体験するに留まっていた。そもそも十四日の宵々々山は毎年大学の前期試験の初日に当たっていたのでそれどころではない。それでも祭りの雰囲気に便乗したくもあったりするので7月に入ると宵々々々々…と指折り数えて宵を十六個連ねた山、から一日ひとつずつ々を取ってカウントダウンをしながら、賑う八坂さん周辺から遠く離れた大学辺で講義ノートを求めて奔走し、迫る締め切りも目白押しな数多のレポートを作成する傍ら酒を呑んだり呑まなかったりと忙しい明け暮れを過ごしていた。前期テストの直前に当たるこの時期には見ず知らずの友人が増える。これには知らない奴を友達呼ばわりする場合と知らない奴に友達呼ばわりされる場合とがあって、ノートのコピーが終わってしまえばその関係も清算されるという後腐れのない一期一会な出会いとなるのだが、そのような出会いを経た者たちによって学内に数台あるコピー機の前は黒山の人だかりとなり、東門を出た外にあるいつもは開いているのかいないのかよくわからない、買い物をするのが躊躇されるような小さなパン屋の店頭には湿式ブルーコピーによって量産された講義ノートが一冊800円程度から並べられ、そこそこの値段がする割にモノによっては当たりはずれが大きいと聞いていたので自分で利用することはなかったが、前・後期の各試験前にあたる年に2回の書き入れ時の一つを迎えたその店も学生たちの喧騒に取り囲まれる。大学で滅多に顔を合わせたことのない奴を見かけるのもこの時期で、そんな奴と出くわすといかにも不断とは違う「ハレ」な感慨を味わって、何かいいことがありそうな気分になる。そんなこんなで「碁盤の目」の北西のはずれにある大学周辺もそわそわ、ざわざわと浮き足立ったようになり、祭りの現場もかくやという盛況ッぷりを呈する。
京都で迎える初めての七月、いくつか締め切りの迫ったレポートを抱えており、なにしろ携帯電話はおろかパソコンですら普及していなかった時分の話なのですべて手書きしなければならない。資料を調べる都合もあって、週末をはさんだ何日間か日中は京都市中央図書館に篭って書いては推敲、を繰り返していた。初めてのことなのでそれはもう莫迦正直に真面目に取り組んでいたのである。中央図書館のある丸太町七本松は下宿からだと大学よりも近い上に、知り合いに出くわすこともそう多くないので煩わしさもない。下宿から見て大学の反対方向に当たるのでその間は大学に顔を出さずに済ませていたが、翌日締め切りの一つを残して風呂上りにぼんやりと煙草を吸いながら晩飯について考えていると古邑さんから電話がかかってきた。
「お前なにしとん?」
特になにも。晩飯のことを考えながら煙草を吸っとりますが。
「呑もけ?」いや明日締め切りのレポートがね。
「お前んちに行くわ、呑みながら書いとったらええぞ」呑みながらてあんた… 明確な返事を待たないままいつものメンバーが大挙して押し寄せてきて、レポートどころではなくなって、それ見たことかと思ったところで後の祭りもいいところで。
「松田心配スンナ、『助詞を変えたら僕の文』だから」古邑さんがおかしなことを言い出した。何です? 「『何何は』の『は』を『が』に換えるとか、それでもうオリジナルよ」いわゆる『コピペ』を勧められているようなのだが、なりますかいな、そんなもん。「大丈夫や、イザとなったらばあちゃん死なしといたらええど」松須さんがさらにおかしなことを言い出した。何です! 「田舎のばぁさんが亡くなったちゅうことにして締め切り延ばしてもらうねん、たいがい信じよるぞ」それはちょっと…「死なすのがいややったら危篤やとか言うとけ、ワシ祖母さん何人居てんねんいうくらい死んでもろてるからなぁ、そろそろ通用せんやろなぁ」松須さんやなかったらできませんよそんなマネ…「お、松田、話半分に聞いとけよ」とは石地さんからの有難い助言である。はい、わかってます。「まぁレポートの一つやふたつ、どぉちゅうことないわい」と松須さんは勢いよく言ってのける。酒を呑んでいるうちにそんな気がしてくるから始末に負えない。
「ポチ何してんの!」という会津さんの声にふと見ると古邑さんは袋から取り出したソーセージを生のままポリポリと齧っている。「ん? 普通ナマで食わん?」
古邑さんからソーセージの袋をもぎ取った石地さんのひと言で鍋を下げて炊事場へ、沸き立つ湯玉にくるくると踊るソーセージを眺めながら自らの来し方行く末にぼんやりと思いいたそうとしているところに「大丈夫?」という声。会津さんが様子を見に来てくれたようである。「みんな好き勝手言うからねぇ。だいたい、松田もヒトが好すぎるんだよ」と、妙に残る一言を言われた。
翌朝無理やり早起きをして慌てふためいて書き上げたレポートの推敲もないまま学部事務室へと駆け込みどうにか間に合わせることができた。Boxに顔を出すと前夜下宿に来て呑んでいたひとりずつから「大丈夫だったか/間に合ったか」と尋ねられた。なんだかんだ言って心配してくれているのが嬉しくもあり可笑しくもあり、とはいえ大変スリリングでしたよ。
その年は山矛巡行の十七日がその次の日曜に当たっていて、ときどきお酒に誘ってくれていた4回生の先輩から見物に行かないかと声をかけてもらった。四条河原町の百貨店前で待ち合わせをして、祇園祭の京都を経験したことがないので普段なら十分間に合う時間に下宿を出たら、バスが動かない上に途中までしか行かない、降りてみたところで人、人、人で思うように身動きできない、そんな状態なので汗だくになって待ち合わせ場所に着いたのは約束の時間から2時間近くも経った後だった。百貨店入り口脇の壁にもたれて退屈そうな表情を浮かべながら、それでも待っていてくれた先輩は「早めに出るように言っとけばよかったね」と笑ってくれた。その日のことはその表情しか覚えていない。
かくして大学での初レポートも京都での初祇園祭もドタバタとあまり好い印象のないまま過ごしてしまい、それ以降祇園祭には伝聞でしか関わったことがない。
伝聞調になっているのは伝聞でしかないからなのだが、実を申さばただでさえ蒸し蒸しと不快指数が天井知らずに鰻昇ってしまうこの時期に犇く人のいきれの中にわざわざ赴こうかなどという酔狂な気分にもなれず、毎年新聞、テレビのローカルニュースで報道される祭りの様子を疑似体験するに留まっていた。そもそも十四日の宵々々山は毎年大学の前期試験の初日に当たっていたのでそれどころではない。それでも祭りの雰囲気に便乗したくもあったりするので7月に入ると宵々々々々…と指折り数えて宵を十六個連ねた山、から一日ひとつずつ々を取ってカウントダウンをしながら、賑う八坂さん周辺から遠く離れた大学辺で講義ノートを求めて奔走し、迫る締め切りも目白押しな数多のレポートを作成する傍ら酒を呑んだり呑まなかったりと忙しい明け暮れを過ごしていた。前期テストの直前に当たるこの時期には見ず知らずの友人が増える。これには知らない奴を友達呼ばわりする場合と知らない奴に友達呼ばわりされる場合とがあって、ノートのコピーが終わってしまえばその関係も清算されるという後腐れのない一期一会な出会いとなるのだが、そのような出会いを経た者たちによって学内に数台あるコピー機の前は黒山の人だかりとなり、東門を出た外にあるいつもは開いているのかいないのかよくわからない、買い物をするのが躊躇されるような小さなパン屋の店頭には湿式ブルーコピーによって量産された講義ノートが一冊800円程度から並べられ、そこそこの値段がする割にモノによっては当たりはずれが大きいと聞いていたので自分で利用することはなかったが、前・後期の各試験前にあたる年に2回の書き入れ時の一つを迎えたその店も学生たちの喧騒に取り囲まれる。大学で滅多に顔を合わせたことのない奴を見かけるのもこの時期で、そんな奴と出くわすといかにも不断とは違う「ハレ」な感慨を味わって、何かいいことがありそうな気分になる。そんなこんなで「碁盤の目」の北西のはずれにある大学周辺もそわそわ、ざわざわと浮き足立ったようになり、祭りの現場もかくやという盛況ッぷりを呈する。
京都で迎える初めての七月、いくつか締め切りの迫ったレポートを抱えており、なにしろ携帯電話はおろかパソコンですら普及していなかった時分の話なのですべて手書きしなければならない。資料を調べる都合もあって、週末をはさんだ何日間か日中は京都市中央図書館に篭って書いては推敲、を繰り返していた。初めてのことなのでそれはもう莫迦正直に真面目に取り組んでいたのである。中央図書館のある丸太町七本松は下宿からだと大学よりも近い上に、知り合いに出くわすこともそう多くないので煩わしさもない。下宿から見て大学の反対方向に当たるのでその間は大学に顔を出さずに済ませていたが、翌日締め切りの一つを残して風呂上りにぼんやりと煙草を吸いながら晩飯について考えていると古邑さんから電話がかかってきた。
「お前なにしとん?」
特になにも。晩飯のことを考えながら煙草を吸っとりますが。
「呑もけ?」いや明日締め切りのレポートがね。
「お前んちに行くわ、呑みながら書いとったらええぞ」呑みながらてあんた… 明確な返事を待たないままいつものメンバーが大挙して押し寄せてきて、レポートどころではなくなって、それ見たことかと思ったところで後の祭りもいいところで。
「松田心配スンナ、『助詞を変えたら僕の文』だから」古邑さんがおかしなことを言い出した。何です? 「『何何は』の『は』を『が』に換えるとか、それでもうオリジナルよ」いわゆる『コピペ』を勧められているようなのだが、なりますかいな、そんなもん。「大丈夫や、イザとなったらばあちゃん死なしといたらええど」松須さんがさらにおかしなことを言い出した。何です! 「田舎のばぁさんが亡くなったちゅうことにして締め切り延ばしてもらうねん、たいがい信じよるぞ」それはちょっと…「死なすのがいややったら危篤やとか言うとけ、ワシ祖母さん何人居てんねんいうくらい死んでもろてるからなぁ、そろそろ通用せんやろなぁ」松須さんやなかったらできませんよそんなマネ…「お、松田、話半分に聞いとけよ」とは石地さんからの有難い助言である。はい、わかってます。「まぁレポートの一つやふたつ、どぉちゅうことないわい」と松須さんは勢いよく言ってのける。酒を呑んでいるうちにそんな気がしてくるから始末に負えない。
「ポチ何してんの!」という会津さんの声にふと見ると古邑さんは袋から取り出したソーセージを生のままポリポリと齧っている。「ん? 普通ナマで食わん?」
「加熱して来い」
古邑さんからソーセージの袋をもぎ取った石地さんのひと言で鍋を下げて炊事場へ、沸き立つ湯玉にくるくると踊るソーセージを眺めながら自らの来し方行く末にぼんやりと思いいたそうとしているところに「大丈夫?」という声。会津さんが様子を見に来てくれたようである。「みんな好き勝手言うからねぇ。だいたい、松田もヒトが好すぎるんだよ」と、妙に残る一言を言われた。
翌朝無理やり早起きをして慌てふためいて書き上げたレポートの推敲もないまま学部事務室へと駆け込みどうにか間に合わせることができた。Boxに顔を出すと前夜下宿に来て呑んでいたひとりずつから「大丈夫だったか/間に合ったか」と尋ねられた。なんだかんだ言って心配してくれているのが嬉しくもあり可笑しくもあり、とはいえ大変スリリングでしたよ。
その年は山矛巡行の十七日がその次の日曜に当たっていて、ときどきお酒に誘ってくれていた4回生の先輩から見物に行かないかと声をかけてもらった。四条河原町の百貨店前で待ち合わせをして、祇園祭の京都を経験したことがないので普段なら十分間に合う時間に下宿を出たら、バスが動かない上に途中までしか行かない、降りてみたところで人、人、人で思うように身動きできない、そんな状態なので汗だくになって待ち合わせ場所に着いたのは約束の時間から2時間近くも経った後だった。百貨店入り口脇の壁にもたれて退屈そうな表情を浮かべながら、それでも待っていてくれた先輩は「早めに出るように言っとけばよかったね」と笑ってくれた。その日のことはその表情しか覚えていない。
かくして大学での初レポートも京都での初祇園祭もドタバタとあまり好い印象のないまま過ごしてしまい、それ以降祇園祭には伝聞でしか関わったことがない。