イスラム教のラマダーンの変更から、
まずは、WEBで断食として検索をすると下記の考察が出て来たので、これから話をしたい。
平成 24 年度公開教学講座「信仰を生きる」:『逸話篇』に学ぶ(1)
第2講:25「七十五日の断食」 おやさと研究所教授
堀内 みどり Midori Horiuchi
これの、はじめの部分は、イスラムやキリスト教、仏教での断食についての考察で、後半部分が本教での教祖の断食についての考察である。

この記事を読むと、ラマダンの断食は、神の守護をありがたく思うためにする事のようである。しかし、ニュースで流れる現在のラマダンは、昼間断食をすることよりも、実家に家族が集まり飲み食いする宴会をする事に重点があるように感じて、教義にある神の思いと人間の理解の差を感じた。
そして教祖の行われている断食については、他の宗教で行われる断食とは異なり、「教祖が神であることを証明するための断食であること」を、その当時に行われた事柄から書かれている。
その部分だけ以下にコピペして、天理教事典の年表も添付しておく。
・・・・・・・
教祖の断食
『稿本天理教教祖伝』によると、教祖が断食された時期として、①慶応元(1865)年(68 歳)9月 20 日頃から約 30 日間、②明治2(1869)年(72 歳)4月末から6月初めにかけての 38日間、③明治5(1872)年(75 歳)6月初め頃から 75 日間(8月中頃まで)、④明治 15(1882)年(85 歳)10 月 29 日から11 月9日の奈良監獄署、⑤明治 19(1886)年(89 歳)2月、櫟本分署での 12 日間が記されています(④⑤は「出されたものは召し上がらなかった」(「別火別鍋」)ということでここでの考察外とする)。①②③のとき、教祖は、水、味醂、(生)野菜を食され、穀物、煮たものは食べられませんでした。いわゆる「断ちもの」というかたちの断食でした。「水さえ飲んで居れば、痩せもせぬ。弱りもせぬ」(『教祖伝』64 頁)といわれ、辻先生御咄として「みりんと、いものさいと、少しづゝめし上がって被下と頼んで食していただきしなりと。他のものを差上げ、御自身の手にて御口の側まで御もちになれば、手自然とはねかえして口中に入るゝ事あたはざりし」『正文遺韻抄』58 頁)という話が伝えられます。

断食前後の出来事をみてみますと、まず、①の時期には、僧侶らの論難や守屋筑前守が教祖と面談し公許をすすめるということがあり、はるの懐妊中には「真柱の眞之亮やで」と仰せられ、10月には針ケ別所に赴かれて、いわゆる異説を唱える今井助造を説諭されました。翌慶応2年秋頃には小泉村不動院の山伏が論難に来て乱暴し、芝村、高取、郡山などの武士の参詣人が増加し、村人たちは参詣人多数につき迷惑と苦情を申し立てました。しかし、教祖はこの年から「みかぐらうた」第1節の歌と手振りを教えられ、5月7日には眞之亮が誕生しました。一方、慶応3年、秀司が京都吉田神祇官領に公認出願(7月 23 日認可)しました。

②の時期には、「おふでさき」第1号(正月)、第2号(3月)の執筆が始まります。この頃、はったい粉を御供として渡されるようになり、秀司の縁談につき、平等時村小東家にも赴かれました。教えは、河内、摂津、山城、伊賀へ広がっていき、明治5年には「別火別鍋」といわれ、6年飯降伊蔵に簡単な「かんろだい」の模型を作らせ、翌年は「おふでさき」執筆が続き、6月にかぐら面を受け取り、「証拠守り」を下付、10 月には仲田、松尾に命じて「大和神社」での「神祇問答」をさせました。これによって教祖は山村御殿で取り調べを受けることになりますが「高山布教」ともなりました。12 月には赤衣を召され、仲田、松尾、辻、桝井にさづけを渡され、翌年は「おふでさき」の執筆がさらに続き、「ぢば定め」があり、「みかぐらうた」の歌と手振りが教え終わります。
こうした状況から、教祖はつとめの完成(世界たすけ)のために「みかぐらうた」を教え、「おふでさき」を執筆し、かんろだいを試作し、かぐら面を作成し、ぢばを定められ、そして何より、教祖御自身が「月日のやしろ」であることを「赤衣」「別火別鍋」「さづけの授与」などによっても、人々の目に分かり、心に納得できるようにされたといえます。
「七十五日の断食」
人間では到底できない長期間の「断食」は端的に「月日のやしろ」を明示し、神様の思召しに従った断食は神に凭れ沿い切った行為であることを、自らを「ためし」として人々に理解させようとされました。一方、教祖を「ひながたの親」として慕う信者には「この道は、身体を苦しめる道やない」と「かしもの」の身上の尊さを説かれています。また、「教祖のことを思えば、我々、三日や五日食べずにいるとも、いとわぬ。」というような真実に心を定める信者の心情は、をやを慕い沿い切る心として受け取られているように思われます。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
そこで、この断食を行われた期間中に何があったかについて、資料を探すと、①については異端を唱えた「針ケ別所事件」②と③については、若井村の松尾市兵衛に関する事が見つかった。
その資料を表示して、思えることを次に書いてみたいと思う。
どうぞ、親神様、大難は小難にとお導き下さい。










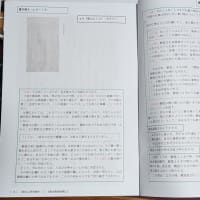















※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます