
(添付画像:光陽展広島展・「鱸 群」)
<作品画像紹介>
作品番号: 96
作者氏名: 磯 貝 文 利
作品題名: 『鱸 群』
受賞名: 新人優秀賞
住 所: 愛 知
*人気ブログランキング参加中! 人気blogランキングへ・・・)
人気blogランキングへ・・・)
読者諸兄におけれましては既に著名なる「悠々さん」。光陽会の会員でいらっしゃる。先の記事にてご紹介したとおり、恐れ多くも「広島展の招待券」をお贈り頂き、6月3日(土曜日)に『光陽展広島展』に赴く。さすが、すばらしい作品の数々を鑑賞し、たいへん満足した。かくして本日、引き続き展覧会鑑賞感想文を書いてみたい。
(前回掲載「光陽展」鑑賞感想記事はこちらから入れます。)
まさかこの絵画、新人優秀賞受賞作品とは!つゆ知らず、多いに気に留まる「作品」なので、真面目にデジカメ記録した。
展覧会会場にて、作者氏名住所等々、可能な限り「こだわり」や「色眼鏡」等はかなぐり捨てること心がけて鑑賞した。
帰宅し、その夜になってデジカメ記録を整理しつつ、出展作品一覧と照合し、はじめて出処詳細、判明。この作品は「魚群」を描かれているのであるにもかかわらず、魚の名前は「辞書を引く」迄、(恥ずかしながら我輩)読めなかった。
読み方及び発音は、「スズキ」!
知らなかった・・・
サラリーマン現役時代、山陰(松江市)に3年いた事、以前、記事に書いた。もう、25年も以前になるか。たしかその時、「スズキノホウショヤキ(鱸の奉書焼)」なるもの、松江「宍道湖の七珍」(地元の言葉で、「シッチン」、と発音する。宍道湖で採れた「山湖の珍味」、すなわち神懸りなる?の、珍味美味の意味?)の一つとして、聞き及んでいた事思い出した。なぜスズキが宍道湖で採れるのか?宍道湖でなぜに海の魚?が採れるのか?汽水だから海の魚が遡上してくるのか、それとも全く我輩の聞き間違い記憶間違いなのであるか?
そういえば「宍道湖のしじみ貝」は、殻が沫白く粒が多く、確かに美味であった記憶などなど、蘇ってきた。
しかし、この作品を拝見した時、直ちに思ったのは、、、
1)描かれている「魚の種類」は、何か分からない。が、問題ではない、、、。
2)こんな大きな画面に、何処のどなたがこんなに「たくさんの魚」をご覧になり、こんなに生臭く雑然とした対象を、「作品として描こう!」と、決められたのか。
3)そして、これだけきめ細かく観察され、結果、微細に詳細に緻密に、加えて超観察力にて極色彩に描かれるか?
4)作品完成するまでにどのくらいの歳月が掛かったのか?何千時間か?よくもここまで根気を継続させる精神力の持ち主とは?
5)精神力だけで描かれていはいない。私は絵を描かないから、想像からの発想発言である。が、作品から発せられるオーラがある。発せられるオーラからは、(オーラの一部分ではあるが)如何にもこの作品の作者をして「天から授けられたもの」、すなわち「かみわざ」有り、よほど絵画制作技巧の優れた方か!
6)さらに、製作過程の作品に立ち向かわれている「その時」を想像する。緻密な作品の製作過程には、寸分の息抜きされた形跡はない。ならば作品完成寸前まで、強固な精神力をもって緊張感を維持してこられたものか!精神力と感性の持続力に感銘感嘆する!
作品は、どの距離から観ても、すばらしい!
近くから見れば、驚くべき緻密な筆のタッチが伺えるし、遠くから見れば、魚群すなわち「鱸群」の群像は、それぞれの魚の形状は、微細に違っているものの「一枚の連続した押絵」、もって着物の原材料・反物にも見えてくる。それほど美しく色彩感覚と感性の優れ輝く作品なり。
これらの印象、添付画像は解像度を落としているから十分に伝わってこなくなっているが、ホンモノの絵を今一度拝見したい。
「光陽会」(会本部ホームページはこちらから入れます。ホームページ内には、今回展覧会作品の受賞作等、もっと上質な画像をご覧になれます)
<・続く・・>(6月14日水曜日投稿予定)
愛知の磯貝さま作品!是非、皆様の「賞賛」をお送り願いたく、
是非、左記ランキングバークリック応援してください! (人気ブログランキング)
(人気ブログランキング)
---------------------------------------------------
<添付>:『参考資料』
スズキ (魚)
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』(鱸 から転送)
分類
界: 動物界Animalia
門: 脊索動物門 Chordata
亜門: 脊椎動物亜門 Vertebrata
上綱: 魚上綱 Pisciformes
綱: 硬骨魚綱 Osteichthyes
目: スズキ目 Perciformes
亜目: スズキ亜目 Percoidei
科: スズキ科 Percichthyidae
属: スズキ属 Lateolabrax
種: スズキ L. japonicus
学名
Lateolabrax japonicus
(Cuvier et Valenciennes, 1828)
英名
Japanese seabass
Japanese seaperch
スズキ(鱸) Lateolabrax japonicus は、スズキ目・スズキ亜目・スズキ科に分類される魚。海岸近くに生息する大型の肉食魚で、食用や釣りの対象魚として人気がある。成長につれて呼び名が変わる出世魚でもある。
目次
1 生物的特徴
1.1 分類
1.2 近縁種
2 水産・漁業
2.1 陸揚げ漁港
3 食材
4 釣り
5 関連項目
生物的特徴
全長は最大で1mを超える。体は細長くて上下に平たい。口は大きくて吻が前方に突き出ており、下あごが上あごより前に出る。体色は背中側が緑黒色-灰緑色、体側から腹部にかけて銀白色をしている。尾びれはハート型に切れこむ。若い個体は背中側の皮膚や背びれに小さな黒点が散らばっており、成長とともに消えるが、背びれの黒点は大きくなっても残ることがある。
日本から朝鮮半島南部に分布する。冬は深場で産卵と越冬をおこなうが、春から秋はおもに内湾の海岸近くで生活する。昼間はあまり動かないが夜になると動きだす。食性は肉食性で、小魚や甲殻類などを大きな口で捕食する。
産卵期は冬で、春になると沿岸部や河口付近の汽水域で幼魚が見られる。中には川を遡上し淡水域で過ごすものもいる。幼魚は端脚類やアミなどの動物プランクトンを捕食して成長する。
分類
スズキ属の上の区分「科」の分類は一定していない。日本での代表種であるスズキの名をつけて、和名では「スズキ科」という名を用いる場合が多いが、これの意味するところは場合により異なる。
ペルキクティス類(温帯性スズキ類)と呼ばれる主にオーストラリア産のスズキ類と一緒にして、スズキ科( Percichthyidae ペルキクティス科)と呼ぶ場合
モロネ類(温帯性シーバス類)と呼ばれるヨーロッパやアメリカ大陸産のシーバス、スズキ類と一緒にして、スズキ科( Moronidae モロネ科)と呼ぶ場合
スズキ属だけを含む単独のスズキ科 (Lateolabracidae) を設定する場合
がある。ここでは 1. に従っている。スズキ亜目にも関連記事。
近縁種
日本近海に分布するスズキの近縁種は2種が知られ、どちらもスズキと同じように食用に利用される。
ヒラスズキ Lateolabrax latus Katayama, 1957
全長1mほど。スズキによく似ているが和名のとおり体高が高くて平たい体をしている。他には吻がやや長くて下あごの下面に鱗があること、尾びれのつけ根が太くて切れこみも浅いことなどで区別できる。関東地方以西の太平洋岸と九州地方沿岸に分布する。外洋に面した岩礁域に多く生息し、内湾にはあまり侵入しない。メジナやイシダイなどと共に磯釣りの対象として人気がある。
タイリクスズキ Lateolabrax maculatus Lee et Yang, 2002
全長1mほど。これもスズキによく似ているが、体側やひれにある黒い点が鱗1枚分よりも大きいのでスズキやヒラスズキと区別できる。黒い点が目立つため「ホシスズキ」とも呼ばれる。もとは中国沿岸や朝鮮半島西岸に分布し、日本沿岸には分布していなかったが、養殖用に輸入した個体が逃げ出して野生化した外来種である。
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』(鱸 から転送)続きを読みたい方は、こちらから入れます。
*人気ブログランキング参加中! 人気blogランキングへ
人気blogランキングへ
<作品画像紹介>
作品番号: 96
作者氏名: 磯 貝 文 利
作品題名: 『鱸 群』
受賞名: 新人優秀賞
住 所: 愛 知
*人気ブログランキング参加中!
 人気blogランキングへ・・・)
人気blogランキングへ・・・)読者諸兄におけれましては既に著名なる「悠々さん」。光陽会の会員でいらっしゃる。先の記事にてご紹介したとおり、恐れ多くも「広島展の招待券」をお贈り頂き、6月3日(土曜日)に『光陽展広島展』に赴く。さすが、すばらしい作品の数々を鑑賞し、たいへん満足した。かくして本日、引き続き展覧会鑑賞感想文を書いてみたい。
(前回掲載「光陽展」鑑賞感想記事はこちらから入れます。)
まさかこの絵画、新人優秀賞受賞作品とは!つゆ知らず、多いに気に留まる「作品」なので、真面目にデジカメ記録した。
展覧会会場にて、作者氏名住所等々、可能な限り「こだわり」や「色眼鏡」等はかなぐり捨てること心がけて鑑賞した。
帰宅し、その夜になってデジカメ記録を整理しつつ、出展作品一覧と照合し、はじめて出処詳細、判明。この作品は「魚群」を描かれているのであるにもかかわらず、魚の名前は「辞書を引く」迄、(恥ずかしながら我輩)読めなかった。
読み方及び発音は、「スズキ」!
知らなかった・・・
サラリーマン現役時代、山陰(松江市)に3年いた事、以前、記事に書いた。もう、25年も以前になるか。たしかその時、「スズキノホウショヤキ(鱸の奉書焼)」なるもの、松江「宍道湖の七珍」(地元の言葉で、「シッチン」、と発音する。宍道湖で採れた「山湖の珍味」、すなわち神懸りなる?の、珍味美味の意味?)の一つとして、聞き及んでいた事思い出した。なぜスズキが宍道湖で採れるのか?宍道湖でなぜに海の魚?が採れるのか?汽水だから海の魚が遡上してくるのか、それとも全く我輩の聞き間違い記憶間違いなのであるか?
そういえば「宍道湖のしじみ貝」は、殻が沫白く粒が多く、確かに美味であった記憶などなど、蘇ってきた。
しかし、この作品を拝見した時、直ちに思ったのは、、、
1)描かれている「魚の種類」は、何か分からない。が、問題ではない、、、。
2)こんな大きな画面に、何処のどなたがこんなに「たくさんの魚」をご覧になり、こんなに生臭く雑然とした対象を、「作品として描こう!」と、決められたのか。
3)そして、これだけきめ細かく観察され、結果、微細に詳細に緻密に、加えて超観察力にて極色彩に描かれるか?
4)作品完成するまでにどのくらいの歳月が掛かったのか?何千時間か?よくもここまで根気を継続させる精神力の持ち主とは?
5)精神力だけで描かれていはいない。私は絵を描かないから、想像からの発想発言である。が、作品から発せられるオーラがある。発せられるオーラからは、(オーラの一部分ではあるが)如何にもこの作品の作者をして「天から授けられたもの」、すなわち「かみわざ」有り、よほど絵画制作技巧の優れた方か!
6)さらに、製作過程の作品に立ち向かわれている「その時」を想像する。緻密な作品の製作過程には、寸分の息抜きされた形跡はない。ならば作品完成寸前まで、強固な精神力をもって緊張感を維持してこられたものか!精神力と感性の持続力に感銘感嘆する!
作品は、どの距離から観ても、すばらしい!
近くから見れば、驚くべき緻密な筆のタッチが伺えるし、遠くから見れば、魚群すなわち「鱸群」の群像は、それぞれの魚の形状は、微細に違っているものの「一枚の連続した押絵」、もって着物の原材料・反物にも見えてくる。それほど美しく色彩感覚と感性の優れ輝く作品なり。
これらの印象、添付画像は解像度を落としているから十分に伝わってこなくなっているが、ホンモノの絵を今一度拝見したい。
「光陽会」(会本部ホームページはこちらから入れます。ホームページ内には、今回展覧会作品の受賞作等、もっと上質な画像をご覧になれます)
<・続く・・>(6月14日水曜日投稿予定)
愛知の磯貝さま作品!是非、皆様の「賞賛」をお送り願いたく、
是非、左記ランキングバークリック応援してください!
 (人気ブログランキング)
(人気ブログランキング)---------------------------------------------------
<添付>:『参考資料』
スズキ (魚)
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』(鱸 から転送)
分類
界: 動物界Animalia
門: 脊索動物門 Chordata
亜門: 脊椎動物亜門 Vertebrata
上綱: 魚上綱 Pisciformes
綱: 硬骨魚綱 Osteichthyes
目: スズキ目 Perciformes
亜目: スズキ亜目 Percoidei
科: スズキ科 Percichthyidae
属: スズキ属 Lateolabrax
種: スズキ L. japonicus
学名
Lateolabrax japonicus
(Cuvier et Valenciennes, 1828)
英名
Japanese seabass
Japanese seaperch
スズキ(鱸) Lateolabrax japonicus は、スズキ目・スズキ亜目・スズキ科に分類される魚。海岸近くに生息する大型の肉食魚で、食用や釣りの対象魚として人気がある。成長につれて呼び名が変わる出世魚でもある。
目次
1 生物的特徴
1.1 分類
1.2 近縁種
2 水産・漁業
2.1 陸揚げ漁港
3 食材
4 釣り
5 関連項目
生物的特徴
全長は最大で1mを超える。体は細長くて上下に平たい。口は大きくて吻が前方に突き出ており、下あごが上あごより前に出る。体色は背中側が緑黒色-灰緑色、体側から腹部にかけて銀白色をしている。尾びれはハート型に切れこむ。若い個体は背中側の皮膚や背びれに小さな黒点が散らばっており、成長とともに消えるが、背びれの黒点は大きくなっても残ることがある。
日本から朝鮮半島南部に分布する。冬は深場で産卵と越冬をおこなうが、春から秋はおもに内湾の海岸近くで生活する。昼間はあまり動かないが夜になると動きだす。食性は肉食性で、小魚や甲殻類などを大きな口で捕食する。
産卵期は冬で、春になると沿岸部や河口付近の汽水域で幼魚が見られる。中には川を遡上し淡水域で過ごすものもいる。幼魚は端脚類やアミなどの動物プランクトンを捕食して成長する。
分類
スズキ属の上の区分「科」の分類は一定していない。日本での代表種であるスズキの名をつけて、和名では「スズキ科」という名を用いる場合が多いが、これの意味するところは場合により異なる。
ペルキクティス類(温帯性スズキ類)と呼ばれる主にオーストラリア産のスズキ類と一緒にして、スズキ科( Percichthyidae ペルキクティス科)と呼ぶ場合
モロネ類(温帯性シーバス類)と呼ばれるヨーロッパやアメリカ大陸産のシーバス、スズキ類と一緒にして、スズキ科( Moronidae モロネ科)と呼ぶ場合
スズキ属だけを含む単独のスズキ科 (Lateolabracidae) を設定する場合
がある。ここでは 1. に従っている。スズキ亜目にも関連記事。
近縁種
日本近海に分布するスズキの近縁種は2種が知られ、どちらもスズキと同じように食用に利用される。
ヒラスズキ Lateolabrax latus Katayama, 1957
全長1mほど。スズキによく似ているが和名のとおり体高が高くて平たい体をしている。他には吻がやや長くて下あごの下面に鱗があること、尾びれのつけ根が太くて切れこみも浅いことなどで区別できる。関東地方以西の太平洋岸と九州地方沿岸に分布する。外洋に面した岩礁域に多く生息し、内湾にはあまり侵入しない。メジナやイシダイなどと共に磯釣りの対象として人気がある。
タイリクスズキ Lateolabrax maculatus Lee et Yang, 2002
全長1mほど。これもスズキによく似ているが、体側やひれにある黒い点が鱗1枚分よりも大きいのでスズキやヒラスズキと区別できる。黒い点が目立つため「ホシスズキ」とも呼ばれる。もとは中国沿岸や朝鮮半島西岸に分布し、日本沿岸には分布していなかったが、養殖用に輸入した個体が逃げ出して野生化した外来種である。
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』(鱸 から転送)続きを読みたい方は、こちらから入れます。
*人気ブログランキング参加中!
 人気blogランキングへ
人気blogランキングへ 









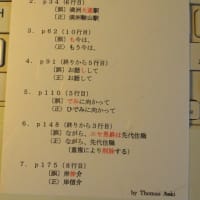
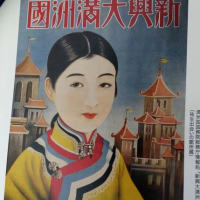

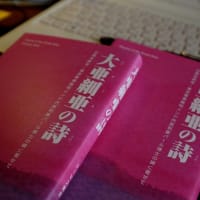
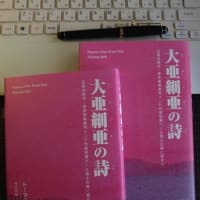


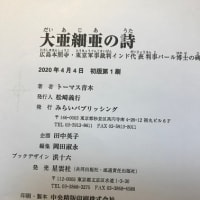
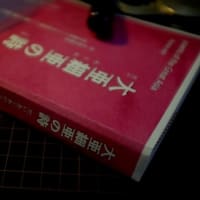

まず“鱸”の読み方を調べました。
『恥ずかしい…』と思いつつ、
文章を読んでいくと、
男爵様も読めなかったとのこと。
密かに安心?し、最後まで読み終え、
結局『絵については何とコメントしてよいかわからない』という結論に落ち着いてしまいました(泣)
語れない美しさでした。
水族館の大水層を泳ぐ鰯の群れもきらきらと筆舌に尽くせぬ色・輝きですよね。
この絵は、
その色・輝きを「筆に尽くしてしまった」ような感じです。
この感じは、ある意味写真では出ない「リアリティ」すら感じます。
人の感性を経由して描かれた分、人にはそう映るのでしょうか?
私には、ただただ驚きです。
因みに私も鱸は読めませんでした。
あほん鱈なら読めるのですが。。
関東ではセイゴ→フッコ→スズキと呼ばれます。
最近ではスズキのダイナミックな引きから海のブラックバス、シーバスとも呼ばれスズキを専門でルアーで狙う釣り人も多いです。
エラは剃刀のようでキュウリなど簡単に切れてしい扱いには注意が必要です。
以前(今もいますが)は東京湾でもかなり生息してたスズキ。
昔はボラと同様食用としてはあまり出回ってなかったと記憶しております。
しかし最近ではスーパーでも並んでいるのを見かけます。
PS:後ほど売春の記事にレス入れます。
はじめ写真と思ったからです。
小生も
こんなにたくさんの魚形をよく描いたと思いました。
わたしのお世話になった方に鱸さんという方がおりました。
済
すごいですね。
昨晩は辛かった。
もう苦しまないで、早く帰っておいで
という感じですね。
日本人に乗馬やクロカンがダメなように
民族による向き不向きがあるのでしょう。
鹿児島の水族館
ここで、このような魚の群れを見ました。
みんな口を大きくあけて泳いでいたのは
異様でした
と思いましたが「スズキ」だったんですね。
実は私、スズキという魚は食べた事も無いし
実際に見た事がないんです ^_^;
多分、白身の魚なんでしょうね。
ぽちっ♪
たいていは「山勘(ヤマカン)」で、てきとうなよみをいれるとそれなり漢字が出てくるのですが、この度は「お手上げ!」・・・
寿司屋好きの「食わず嫌い」にて、この手の漢字には弱いのです。つまり、鮨は大好きですが、食べるものが決まっているのでして、、、。
スズキは、瀬戸内海で実物を一度実物を見たことあります。
昼間に船釣りやっていて、誰か仲間内の一人が「弱って浮遊しているスズキ」を見つけ、網ですくったのを今、思い出しました。体長(魚長)70cm位だった。銀色の鱗のきれいな「魚体」であった・・・
でも、なぜふらるら泳いでいたか、すでに老衰か、病気であったか?
そのあたり、救い上げた友人が語っていた話、これが思い出せないのです。
食べたこともあります。
山陰で、松江で、ホウショヤキの類いを・・・
でも、
味は覚えていない。
白身の、淡白な味?の魚であったという、おぼろげな記憶、かすかに残っています。
そして殿下の本日・・・
またまた度重なる「美術評論」の冴え。。。
脱帽です。
おっしゃるとおり、
写真撮影では「表現不可能」なる絵筆の技!
>この感じは、ある意味写真では出ない「リアリティ」すら感じます。・・・
>人の感性を経由して描かれた分、人にはそう映るのでしょうか?・・・
>私には、ただただ驚きです。・・・
この3行!!!!!
三行誌、これにて表現しつくされ、すべて終了!です。
言葉少なく、如何に多くを表現するか、いかに大切なポイントを抽出するか!
これ、
モノカキの「極意」なのです。が、、、。
確かにtonoさん!
一流高級なお寿司屋さんで、一流の職人が超一級品の刺身包丁で「調理」した如く、
表現の切り口が見事、きれいです、正確です、科学的想像力が付加されます。だから、すばらしいのです。