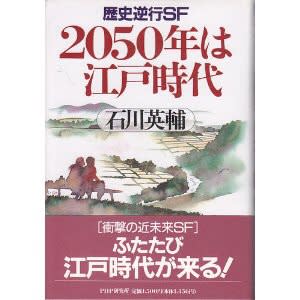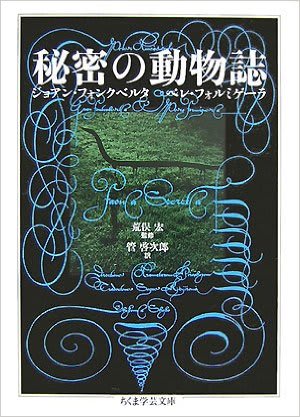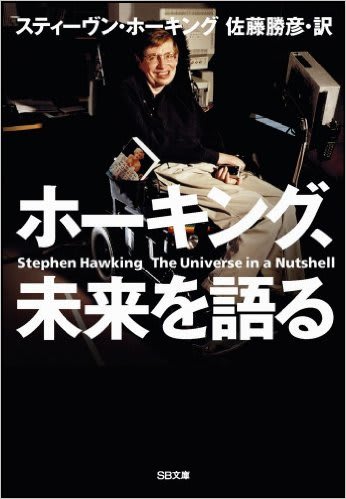今、日本でヒットしているこの本。タイトルだけ読んでも、一体なんのことかと思いますが、あの
ナイキの話を書いた本。ShoeDog とは靴バカと言って良い言葉。要するに、靴の事しか考えていない人達の事です。ナイキ創業者の方達も靴バカだったという事で、ナイキが如何に世界的な企業になったのかという事が書かれています。
それも創業から上場するまでの間の事で、ナイキが成長できた影には日本企業の働きがあった事が書かれてあり、それが日本でヒットした一つの理由かもしれません。この事は日本でもあまり知られていないのではないでしょうか❓私は初めて知りました。
また、主人公の
フィル・ナイトの行動やほかの創業者の皆さんの行動が会社を経営するにはあまりにもお笑いすぎるし、また、次から次へといろんな災難が降りかかるので、次はどうなるのだろうと思いつつドンドンと読み進んでしまいました。

世の中に自分の足跡を残したい、日本のスポーツシューズは性能が良いので、アメリカでも売れるのではないかと思いたち、なんのツテもないのにアジア旅行に出発。そして神戸にある
オニツカまで交渉に出かけます。時は1962年。戦後まだ17年。
そんなどこの馬の骨ともわからないアメリカ人にオニツカ側も良く面接した、と不思議に思いますが、当時オニツカもアメリカにシューズを販売したいと思っていたようなのです。
そしてその面接の時に「どこの会社❓」と聞かれたフィル。当時はまだ会社なんてないのにどう答えるのかと思ったら、自分の部屋にあったブルーリボンを思い出し「
ブルーリボンです。」と答えてしまうんですね。
これって詐欺じゃないの❓
と思ってしまう。
そんなハッタリをかましつつ、その後の会社の発展に邁進していく訳です。あるのは最初の信念のみって、よくよく考えれば怖い事。
でも創業に関わった4人の男どもはみんなフィルと同じような考えだったようです。

右端がフィル。
オニツカ社長はこの信念をフィルの中に見ていたのではないでしょうか。オニツカ社長も創業当初はシューズを売り歩いていたようで、フィルもポートランド近辺でツテを使って売り歩いていました。

最初は自宅の地下室で始まったフィルの会社。それが今では売り上げ世界一❗️
その間に何度も倒産の危機に見舞われましたが、
日商岩井のお陰で復活。
なんてたって当時一億9千万円ものナイキの借金を肩代わりしちゃうんだから。今では双日(日商岩井)の中でも伝説となっているこの話。ナイキのキーマンになった皇さんや伊藤さんはナイキに物凄い将来性を感じていたのでしょう。それもフィルの信念がなせる技だったのかもしれません。
このあたりの事は、NHK BSで4月に放送された「
ナイキを育てた男たち」でより詳しく描かれてます。
この番組とこの本を読むとナイキと日商岩井の関係をより理解できると思います。
フィルは創業当初の事それに皇さんや伊藤さんの存在を知ってほしくてこの本を書いたようです。


そんな日本人が登場するお話なんですが、どういう映画になるのでしょうか。日本人の俳優さんも出演するのかしら❓ケンワタナベ❓NHK の番組ではナレーションをしていた小栗旬❓
そういう事を考えると楽しみでもあります。
それにしても、ナイキってこんなに若い会社だったんだという事と最初からシューズを作って販売していたわけではない、という事が一番の驚き❗️でした。
とにかく笑って読めて元気が貰える内容です。